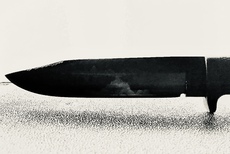2024年01月20日
キャンピングムーンのグリルベース

*キャンピングムーン・ファイヤーグリルベース 帆布ケース付
こんにちは、ponio です。
アタシはキャンプの際に焚き火台と七輪、それに組み立て式のウッドストーブを持っていきます。そんなに熱源ばかり持っていってもと思われるでしょうね。はい、その通りです。いろいろ手間暇がかかります。ではなぜ?



焚き火台はそのまま焚き火のため。これは火付盗賊と呼ばれるうちの奥さんの焚き火欲を満たすためが最大の理由です。七輪は純粋なる調理用熱源です。残るウッドストーブは、、これはアタシの趣味嗜好です。

このウッドストーブですが、 SOLO STOVE を除いてほぼ全ての機種に灰の問題が付きまといます。底板や底網、吸気口から落ちる灰の中には小さな熾も含まれます。キャンプ場の下草を焼いたり、そこら中に灰が飛散することもあります。ウッドストーブによってはアッシュパンと呼ばれる灰受けを持つ物もありますが、無いよりマシという程度のものばかりです。海外の様に灰をそのまま地面に撒いて火の始末をして埋め戻すことが出来る場所ならその必要も無いのですがね。

そこで以前から考えていたのが金属製の焚き火台ベースです。テンマクさんやキャプテンスタッグさんから出ている様な四方に縁の付いた小さなテーブルです。その殆どの物が脚付きですので地べたよりも少し高い位置で火を扱えます。この地面より少し高いことで腰痛も防げるという一挙両得なアイテムです。

そんな焚き火台ベースの中から実際に使う場面を想定して選んだのが今回ご紹介しますキャンピングムーンさんのファイアグリルベースです。

キャンピングムーンのファイヤーグリルベース MT-6-LT。FIRE BOX Freestyle のフルセットが収まります。


こうして見るとなんだかフライや天ぷらなどの揚げ物に使うステンレスパットと油切りみたい。実際、使えると思う。

見ての通り火床となるロストルから本体の底までは2センチに満たない浅さである。左右の空気の取り入れ口はロストルと同じ高さで七輪の様な下方からの吸気は出来ない。もし、下方からの吸気で火力を上げたければロストルを左右の空気取り入れ口より高くすることだ。
一方で炭を並べた場合、上に置く五徳やスタンドの高さによって遠火から極近火まで使い分けられる。このベースを焚き火台やコンロとして使う場合はクッカーや焼き網を乗せるスタンド(五徳)が必要。

クッカーを乗せる。ユニフレームの旧・タフ五徳は前後左右共に長さが足りません。写真は前後に脚を掛けた状態です。これも安定せず傾く恐れがあります。

グリルベースの脚を畳んで正面から奥に向かってタフ五徳を置くと設置可能です。

灰受けとして使う。G2 /5" Firebox Stove は余裕あり過ぎです。使うなら Firebox Nano やB-6君と並べて使うでしょうね。

笑's の B-6君も余裕のヨッちゃん。このためだけにファイヤーグリルベースを持って行くのは勿体無い使い方なのでやらないと思いますが。

FIRE BOX Freestyle の8パネル 横型。ギリギリ収まります。ひとつだけ、、

8パネル の横型にした場合、ストーブ本体の左右に開いたサイドフィードポートとファイヤーグリルベースの空気の取り込み口がちょうど重なります。灰がこぼれるとしたらここです。そこで、このスタイルの場合はストーブ本体左右のポートを例のステンレス板で塞ごうと思います。

FIRE BOX Freestyle の8パネル ファイアーピット スタイル。わが家ではこのスタイルが一番使われる様なのでこれが収まれば大収穫です。ファイヤーグリルベースの左右に開けられた空気の取り入れ口は直線的なので適当なステンレスかアルミ板ででも塞ぐことが可能です。

このMT-6-LTというグリルベースを単体で使うとすれば、オガ炭(短く切り割った物)を適当に並べて焼き網を乗せ耐熱テーブルの上でBBQコンロの様にして使うか、鍋物でしょう。その場合はテーブルの脚を畳んで低くして使えば高すぎず低すぎずで使えるかもね。
コレ予定は未定ですが次のキャンプ(キャンプ 如月)でデビューさせようと思います。


ウッドストーブの灰問題はこれにて解決!