2025年03月05日
弥生の雑記・時々追記

弥生三月は雨から始まり。
写真は2024年度版の新富士バーナーカタログ、新年度直前だというのに、、これについてはのちほど。

三月最初の日曜は予報通りの雨・雨・雨。毎年訪れる太宰府政庁跡から『歴史の道』を散策。今年はほぼ一日雨でした。雨やどりをしながら約7時間の散策を終え奥さんと合流したのが16時すぎ。春になったらまた来まひょ。

TOAKS TITAN POT 1100

軽い以外は取り立てて特筆することが無さそうな普通のクッカーです。TOAKS といえばアメリカのブランドですが製造は中国。今や雨後の筍か無限分身の如く出現し続ける China made TITAN の先駆け的な存在でした。現在市場に溢れる類似製品と比べると価格的にもワンランク高かったのですがここにきてほぼ同価格となってきました。やはりネームバリューだけでは売れないということでしょうね。

この三つ、すべて1100ml、1.1Lの満水容量です。
左から MSR(seagull)のストアウェイポット、真ん中が GSI ソロイスト、右 TOAKS です。この1.1Lという満水容量は現実的に沸騰時の吹きこぼれや溢さず注げる限界を考慮すると約2割減の 800〜900ml あたりが最大適量とわかります。MSR のストアウェイポットは調理上手で注ぎ下手、GSI のソロイストは三層のコーティングで抜群の水切れと注ぎ上手、

では TOAKSは? それは無垢の強さでしょう。コーティングが施されていないので金属製のカップやカトラリー、ストーブバーナーなどをそのままガチャ入れてきるし、水道水による変色や傷も気にならない。ただ、一点気をつけるべきはその薄さと剛性です。持ち運ぶ際には他の荷物で潰されない様に注意すべきです。チタンは丈夫だからはあくまで素材のお話で、この薄さとなると蓋が収まる開口部は簡単に変形します。中にスタッキングできるものを詰め込むのも策です。

TITAN POT 1100 に付属のリッドはあたしが9年前に買った同社のチタンリッドと同一のもの。9年前に買ったリッドは GSI ソロイスト用として無理矢理使われています。今回のチタンは水がシミにならず玉のようになります。EPIのチタンは水分が表面に広がるようにしみていました。

KUPILKA のカップ。ティーパックを淹れる時はこの様にハンドルの穴に紙タグを通しておきます。



3年前の今日(3/6)はあるお宅の橙を収穫していた様です。FISKARS のギアプルーナーで切り落とし収穫のあとは余った橙を Queen のナイフで半分に切って庭木の枝先に突き刺してメジロやヒヨドリの餌にしていました。今はもうこのお宅も庭も橙もありません。
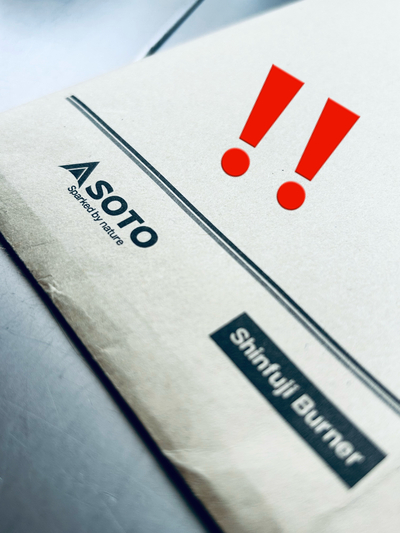
「これか?!」とはアタシの内なる叫び、、
先月二度にわたって見知らぬ市外局番からの着信がありその番号を調べてみると、、なんと新富士バーナーさんからではないか!アタシが日頃から家でも出先でもキャンプやドライブでも持ち出して使っている【SOTO 】さんからの着信。結局こちらから問い合わせてみたところ「間違いだと思います。」との返答。それがだ、またもや同じ番号から着信があり今度は「モスモス?」と出まして候。すると〜「当社のホームページから無料カタログの送付をご希望されておりますが宛先に訪ねあたりませんと戻ってまいりました」ちゅーことで、こりやぁーアタシが忘れていただけ?なーーぁんだ!そうだったのかー!こりゃまた失礼こきました!

来月、法事のため長崎の離島に行くにあたっていつもの毎度お馴染みの湯沸かしセットを考察中です。上の写真は Trangia のストームクッカー 27(DUOSSAL)からフライパンとソースパン(インナー)を抜いたセットアップです。目的は朝のひげ剃りと義姉に淹れるコーヒーのためです。離島は風が強い日が多く昨年正月と夏の訪問時は風を遮るのにひと苦労しました。今回は一泊なので MSR のウインドバーナーが最有力ですがあれこれと考えるのも好きなアタシです。現実的にはこれにアルコール燃料を加えると重量増しとなるのでたぶんウインドバーナーになるでしょう。ただね、ストームクッカーの安心感に勝るもの無しと実感もしております。

身近な道具たち
SOTO SOD-331 は南向きの窓に面して置かれたキャンプテーブルの脇にいつもある。気が向いた時に OD缶をつなぎ適当なクッカーやケトルを乗っけて湯沸かしをする。小さなケトルやクッカーの場合は常に OD缶と接続されている SOD-310 がサッとお湯を沸かしてくれる。

珈琲一杯ならこれで済む。SOTO SOD-310。

身近な道具たち。Trangia の『グルメフライパン』。わが家にたった二つだけ残るノンスティックフライパンのひとつ。もう一つはティファールのパンケーキ用。Trangia の方はアタシしか使わない。奥さんは「強火魔王」なのでコーティングがぶっ飛んでしまうから。一人分のパスタやリゾット、写真の様にパンを軽く炙り焼きする時などに登場する。

身近な道具たち。100均のメモ帳とボールペン、そして革製のシースに収められた CASE 社のナイフ(Sowbelly)。南向きに置かれたキャンプテーブルの右の隅にいつもあって仕事の電話もここで取るし、書き物や読み物もここでする。キレモノはズボンの右ポケットにクリップされているが目の前にあるこちらを使うことも多い。身近に置いておく物ほど愛着があって使いやすい。

母親の月命日にご飯を炊く。一合の米をたく。

アルコールバーナーははじめ強火でのち弱火

分厚いアルミの蓋が微かに持ちあがりパフゥ〜と蒸気を吐き出す。耳をすませ沸々と米が炊ける音に集中する。おおよその時間がきたらバーナーを強火に戻して10秒ほど炊く。

10分蒸らして出来上がり。仏様にあげたら残りはおむすびにしておく。

三月第二日曜はすっきりと晴れ渡り風が吹けばほんのちょっぴり肌寒いだけのお出かけ日和。寒さも緩んだせいか街にはどっと人が出ている。東西にのびる主要な幹線道路は軒並み長い車列ができている。

アタシはというと本日仕事の奥さんに頼まれ野菜の買い出しに自転車走らせる。買い物を済ませ仕事で時折訪れる近くの昼飯スポットに立ち寄る。と言っても飲食店でもカフェでもない。ここはアタシが外飯を食う場所の一つで河川敷。朽ちたベンチが置かれ景観は冬枯れの雑木と緩〜く流れる川面だけ。そのせいかあまり人とバッティングせずのんびりできる。先ずは湯沸かし、Trangia トライアングルに TOAKS のアルコールストーブ、小さなウインドスクリーン、そして500ml の水を入れた mont-bell のクッカー。

TOAKS のアルコールストーブは燃料を燃やし尽くさなければ消火できないのでアルコール燃料は多過ぎず少な過ぎずの目分量。今日の気温を考えれば 500ml の湯が沸くまで6〜7分、それだけ燃えてくれれば良い。時間を測ったわけではないが沸騰後10秒ほどで火が消えたのでそんなとこだろう。

朝握ったおむすびとカップで食べるチキンラーメンが今日の昼飯。

コーヒーはドリップパックで湯が沸いたら最初に淹れておく。保温タンブラーは作り置きができるので外飯には最適だ。飯の後でも熱々を啜れる。塩ミルクキャラメルはコーヒーのお供。これを一粒口に入れてコーヒーを飲むとなんとも言えない香ばしさ。


自宅に戻り買ってきた野菜から先ずはブロッコリーを茹でる。カリフラワーはレンジで3分チンしておく。

今夜はイワシのフライ、つけ添えにブロッコリーとカリフラワー、これに半熟ゆで卵を加えてサラダにする。

仏様のご飯を炊いた SOTO の角いクッカー。他のアルミクッカーと違い分厚く作られているので炊飯時の火加減はやや強め、時間もやや多めにとる。シンプルで何かと使えるクッカーです。

先月末の厳冬キャンプで一瞬だけ使われた G2 /5" Firebox Stove 。このウッドストーブはチタン製で軽く扱い易いが使用しているうちに熱による軽微な変形を起こす。もう一つあるステンレス製の方は奥さんのガンガン焚きにもびくともしない強さを誇っている。今日はこのチタン製の FIRE BOX STOVE を手曲げで矯正してやりました。

本日もいつもの河岸にて昼メシざんす。天気は上々、陽射しがジリジリと熱い。この時期にこの暑さは夏が思いやられる。

引退箱で暮らすこと10年余り、Esbit 585 ポットの再登城(家臣か)です。今の仕事を始めたばかりの頃に買って仕事先にてこれで湯を沸かしカップラーメン作ったりコーヒー淹れたり。蓋が外れて手に火傷をしたのもいまや昔の話。今日はカップ一杯分の湯を沸かすだけなので久しぶりにこれを持ち出しました。ポンコツな蓋は使わず TOAKS のチタンリッドを代用しています。

熱源はこの方、SOTO SOD-310 Wind Master stove です。ポットが小さいので付属のトライフレックスできました。風は微風でしたが吹くたびに燃焼炎が流される音がします。“風に強い” は立ち消えしないというだけでそのまま風防要らずではありません。たとえ Wind Master stove といえど風のある環境下では何らかの風防は必要だと思います。風に煽られて必要以上に燃料を消費するのは明らかですから。

お湯が沸くまで2分ほど、ポンコツ蓋の代わりに持ってきた TOAKS なチタンリッドを外してニョロニョロとドリップパックに注ぎます。

本日は自宅で作ってきた蒸しパンをシートゥーサミットのデルタボウルに密封してきました。食べ終えたらこれにゴミを入れて密封して帰ります。デルタボウルは蓋をちゃんと閉めると水の運搬も可能です。

Esbit のポットと共に引退箱に押し込まれていた A&F のチタンカップです。これも長いこと使われてきました。しかし何を飲んでも美味く感じない、甘いもの苦いもの、コーヒーもカフェオレもココアもただのフレーバーなお湯にしか感じられない不思議なカップです。今日もドリップパックのコーヒーがコーヒー風味のお湯に感じられました。

「カップで食べるチキンラーメン」を二つ食べる。二つと言ってもこの量だから満腹にはならない。ただね、スープが濃いので後味は満腹です。外で食べる時は殆どの場合、それは仕事の合間なので後の仕事を考え満腹を避けています。


今日も外メシ、いつもの河川敷、しかし寒かったー!
風もあって体感温度は10℃を下回っていました、これには流石に鼻水出ましたわ。ウインドスクリーンは 360度囲い、それでも 600ml の水が沸騰するまでかなりかかりました。

アタシのお気に入りパン(6個入り)も小さくなっちまって、、くぅー泣けてきます。

いつも持ち歩くシリアル。100均で買った何種類かをミックスしてある。これも大切な行動食。


雨の福岡、人の気配無き総合図書館で気になっていた本を読み終える。外は雨、雨、夕方からは「呑み会」ざんす。

アタシは新しい道具(焚き火台やテント・タープ以外)を手に入れたら先ずは自宅で使ってみる。それからキャンプやデイハイク、日常で実際に使って一応の結論を出す。自分の中で結論が出るとそれからは滅多に実験などしない。しかし、実際に使っても「うーむ、、いまひとつわからん」という物もある。その一つが SOTO SOD-331 フュージョントレックなのです。


SOTO SOD-331 は主に湯沸かしを担当しています。ちゃんと使ってるんです。自宅でも外でも。キャンプにも持ち出して。その都度ちゃんと働いてくれるんです。数年前の極寒キャンプで湯たんぽ用のお湯を沸かそうとして沸かしきれず(あまりの寒さに待ちきれず)同社の SOD-372 にバトンタッチしたことを除けば持ち出した先では「普通」に使えてるんです、コレ。

ただね、このストーブの売りである低温下や連続使用に効果を発揮するマイクロレギュレーター機能や風に強いすり鉢型バーナーヘッド、安定感のある分離型(最近はリモートというらしい)、冬季用ガスなども豊富なOD缶仕様、とこれだけ聞けば「完璧やん!」と言いたくなりますが、、実はアタシこのストーブの実力を実感したことがありません。
かと言って「え?ホンマは大したことない?」とはならない摩訶不思議なストーブなのです。購入から数年、実際に使っての感想は、春夏は当たり前に調子が良く、では秋冬は寒さに強いかと言えば「強い、かな?うーむ、普通」とそんな感じ。アタシにとってこの SOD-331 は『普通』なのです。同じ OD缶+マイクロレギュレーター機能を持った SOD-310(Wind Master stove)ほどのコンパクトさも無く、SOD-372 の様なギミックやガソリンモードの癖や力強さも無く、自宅で2L以上の湯沸かしを担当している ST-310 ほどの盤石性も感じられず、、果たしてこれ(SOD-331)ってどうなの?とモヤモヤしとりました。

今日は雨でとても寒い、福岡は北の風6メートル前後で気温8℃、ガスキャニスターストーブにとっては一番悪い条件ざんす。そこで滅多にやらない実験をSOTO SOD-331 にやらせてみました。風は建物の反対方向から回り込むような吹き方で2〜3メートルくらいか。アルミの風防を風上側に立てます。エバニューの2.8L満水クッカーに2.5Lの水を入れお湯を沸かして麦茶を煮出します。

ガスは純正のトリプルミックスではなく冬季用として長年使っているキャプテンスタッグのPX。今回実際に使ったのは昨年末からの年越しキャンプと2月末の厳冬キャンプの2回に持ち出してかなりのお湯を沸かした「使いかけ」です。

点火直後からバルブ全開。豪快な燃焼音をたてて最大火力を発揮。社外品のチタン風防は真っ赤っかです。クッカーの中の水も短時間で沸々し出しました。

結果からいうと点火から12分ほどで2.5Lが沸騰状態になりました。これは室温20℃の屋内で ST-310を使って沸かす時にかかる時間とほぼ同じです。ちなみに自宅キッチンのガスレンジでは火力をやや絞って10分です。低い気温、風防越しの横風という条件の悪さを加味しても室内での沸騰時間と変わりない、これってやはり凄いのか。これが ST-310 なら更に多くの時間を要したでしょう。

更に細かくみると、点火から3分半ほどで力強い燃焼音がやや落ち着き気味に。その後は時間をを追う毎に更に燃焼音は小さく、赤化したチタン風防の色もやや薄くなりました。点火から5分ほどでOD缶の表面が曇り始め8分が経つころには結露が霜って白くなり出します。そこから沸騰までが長くかかった印象です。10分を回る頃でもクッカーの中は比較的おとなしく直ぐには沸騰しそうにありませんでした。

点火から12分ほどで蓋の隙間から白い蒸気が出始めその後ちょっとで沸騰状態に。ただ、グツグツ煮立ってる感じはなく大人しく沸騰している感じでした。OD缶は白く冷たく結露ってこれ以上はちょっと無理な状態でした。
さて、麦茶沸かしという名目で行った今回の実験では気温8℃、風2〜3メートルで風防ありという条件で2.5Lの水を12分で沸騰させてくれました。

今回使ったOD缶が未使用の純正トリプルミックスの新品だったらもう少し最大火力が続いたかもしれません。逆に風防無しでは更に多くの時間がかかり沸かしきれなかった可能性もあります。風に強いは「立ち消え」しにくいだけで風をまともに浴びても常に同じ性能を発揮できるわけではないことを理解しなければなりません。
気温8℃ 横風3メートル前後、この条件下で使いかけのガスを使い点火から最大火力が3分半ほど続くなら一人分、たとえば500ml程度の湯沸かしは楽勝だと思います。

実際に同日のほぼ同じ条件でやった500mlの湯沸かし(クッカーはmont-bell スクエア900ml)では上の数値でした。燃焼音を聞いた感じでは点火から沸騰まで落ちることなくほぼ最大火力でした。

外に持ち出しては毎回一人分5〜600ml(多くても900ml程度)の湯沸かしを火力の低下無く済ませてしまう SOD-331 の当たり前さ、それこそアタシがこのストーブに感じる『普通』なのかもしれません。

友人とSNSでコーシー談義しつつ『煮出し』コッシーを淹れる。350ml ほどの湯を沸かし残り豆を挽いたミルを蒸気に晒す。わかる人はわかるよね。静電気防止ね。それから挽いた豆をぶち込み煮立てるが時折りケトルを持ち上げ沸々を落ち着かせる。最後に蓋をして一瞬強火に。あとは忘れるくらい放っておき気がついたらケトルをコンコン叩いて上澄をカップに注ぐ。結果は「うーん、、なんともビミョーな旨さ也」


春のお彼岸、中日に奥さんが「ぼたもち」を作る。
仏様に供え翌日にはそれすら食い尽くされた、わたしに。

サァーと雨が降った後の晴天下、久しぶりのドライブランチはわが家がよく行く菜の花と桜の名所。流石に殆どの桜はまだ咲いていなかったけど菜の花は満開、桜の開花前なので人もおらずほぼ貸し切り也。

ひと通り菜の花を愛でた後、いつもの草地にシートを広げランチを食う。コーヒーはドリップパック、豆ゴリドリップは家だけで十分だ。これに奥さん手作りのフルーツサンドとアタシ作のサラダを加えてモリモリ食う。

昨日買ってきた菜の花はお決まりの「菜の花パスタ」になりました。




今から20年近く前に中古で買った RICOH GR1/35mm。最後に使ったのは16年前の身内の結婚式。これが流石の写り具合で我ながらスンバラスィー出来でした。その後、フィルムと電池を抜かれた状態で壁に飾られ今は玄関の置き物になっています。果たしてまだ使えるか。液晶が生きていればまた写してみたいカメラです。

キャンピングムーンのシェラリッド・ケトルレスを GSI ソロイストに取り付ける。少し前に自宅使いのシェラカップに TOAKS のチタンリッド 110mmを乗せたら微妙に大きく使えなくはないがフィットせずだった。??これって、、アタシの GSI ソロイスト と同じやん!純正のリッドを失くしてからずっと微妙に大きな TOAKS のリッドを乗せていたソロイストとサイズ感同じ。ということは一般的なシェラカップとソロイストは同じ径か?とケトルレスリッドを取り付けたら見事にフィットいたしました。ただね、GSI ソロイストはこのリッドを取り付けなくてもニョロニョロ注ぎが出来るのであまり意味がないかも知れませんが、、ちょっと多めのコーヒーを淹れる時などは良いかも。それと、アタシの持っている TOAKS のチタンポット1100 にもピッタンコでありました。

一気に咲きました




ほんと思い出した様に巻いてみる時計。大阪時代に仕事で渡韓する友人に買ってきてもらった中古のオメガ・シーマスター。オートマチックで手巻きもOK。デイ・デイトとも呼ばれる曜日付きカレンダーモデル。70年代の代物と思われざっと考えても50年は経っているかも。現在は手巻きにて正確に駆動している。放ったらかしだったが思い出した様に引っ張り出して3Mのスーパーファイン研磨パッドで磨いておく。アタシは何につけてもコレクターではないし転売など考えもしないので使って磨いてを繰り返してきた。これを中古で買ったのが90年代だからそれからでも30年以上にはなる。防水性など無いに等しくいずれは動かなくなる機械式時計、その日まで使ってあげましょう。
三月も今日で終わりざんす。ここ福岡は花冷えなれど桜満開ざんす。
またのお越しを。
2025年02月26日
厳冬キャンプ 2025年 2月





これらの写真が今回のキャンプを如実に物語っています。今年度最後(?)の「雪景色」。予報(北西)に反して反対方向(南東)からビュービューと吹きつける強い風と大粒の雪にこれはとても焚き火ができる状況ではないと早々に判断、冬キャンプを始めて11年、初めて焚き火を諦め、初めて石油ストーブに頼りました。

結局、こうなりまして候。今回は自宅で廃棄寸前だった古いトヨトミの石油ストーブをメンテナンスし直して持ち込んでいました。キャンプ場に着いたのが予定通りのお昼、そこから荷物運びとテント設営、奥さんはテントの中で自慢の巣作り、アタシは石油ストーブを活かすため DDの4×4タープを強風と吹雪の中で四苦八苦の七転び八起き(タープほんま苦手ー!)で張り終えたのが16時前のこと、、。ホンマに精魂尽きましたわ。石油ストーブに火を入れ椅子とテーブル、ゴミ入れだけを設置。嗚呼〜ストーブ暖かい!

あたしが風雪の中でタープシェルター設営に四苦八苦している間、暖かなテントの中で巣篭もりしていた奥さんを完成したタープの幕中にご案内。「こんな巣篭もりキャンプしたかったー♪」と奥さんも喜んでおりました。

その後、風雪は激しさを増し、、、

次から次と雪雲が通り過ぎてゆきます。タープの周りを御百度参りの如くぐるぐる回ってガイラインと打ち込んだペグの具合を何度も確認します。どうぞ飛ばされませんように、、と。


しかしのんびりとはしていられません!あたしには日暮れ前までに二つの湯たんぽを熱々のお湯で満タンにしておかなければならないと言う使命があるのです。予定では KELLY KETTLE (写真)と Quechua のステンレスケトルを同時に沸かすはずでしたがこの風では焚き火も危なくて無理と判断。とりあえず火の粉が飛びにくい KELLY KETTLE にほぼ満水の水を入れ点火。点火時は風下に向けていたベースの開口部を点火後に風上に向けると凄まじいトルネード燃焼。たまたま東屋脇に置かれていた真っ赤に錆びたBBQコンロを利用して KELLY KETTLE を稼働させました。風が強くても気温が低くても燃やせば湯が沸く KELLY KETTLE の実力発揮です。

その後、風が弱まったタイミングで予定通り 5" Firebox Stove と Quechua のケトルのコンビネーションで湯沸かしを始めました、が再び風が強まり危険な状態に、、

この両者、今回の環境条件では圧倒的に KELLY KETTLE が優位でした。FIRE BOX も薪をガンガン放り込んで最大火力を引き出せばお湯を早沸かしするくらい簡単ですが、、この日は風がやばすぎました。雪は降っていましたがあたりは一面の枯野です。下手すれば火災の危険もあります。FIRE BOX は一回目の沸騰後に使用中止し、Trangia のストームクッカー(ガス使用)にあとを任せました。

タープが風で膨らんだり凹んだりすることを考えてストーブを安全な位置に設置し直します。タープはAフレームで片側をほぼクローズ、反対側は換気のために半分だけ開放しました。日没とともに気温は急降下しましたがタープの幕中はポッカポカでありました。


午後7時前から予定通り『すき焼き』の開始です。Trangia ガスバーナーと TR-23 五徳、ストームクッカーのベースを逆さまに組み合わせずっしりと重い鉄製のすき鍋をのせ、いざ!すき焼き!

前回の正月キャンプの際に安い海外産牛肉を買い失敗だったとリベンジを誓う奥さんが国産牛肉で挑む!舵取りのあたしはガスバーナーの火力を調整しつつ食っては「旨い!」を連発。奥さんと温燗で乾杯しながら吹雪の夜を『すき焼き』で乗り切る。
たらふく食って二人でさささっと洗い物を済ませ歯磨きしたあと奥さんは巣に戻った。あたしは道具箱から二つのランタンを取り出し『おひとり様』時間がスタート。

まっこと小さな灯りではあるがテーブルの片隅に置いておくだけでなんとなく落ち着くUCO改装のオイルランタン。

もちろん忘れておりませんフュアハンドランタンの灯。今回は石油ストーブと燃料共用。


すき焼きシステムをそのまま使って石油ストーブにかけたばかりのケトルを再度沸騰させる。ダークラムをたっぷりと注いだ蜂蜜紅茶を啜り夜の吹雪を眺めて過ごす。

夜9時、タープ幕中の温度は15℃。風が一段と強さを増す中もう一度ガイラインの張り具合を点検して回る。このあと更に幕中の温度が下がり出したためここが潮時と石油ストーブを消してペールに入れたゴミ袋を閉じ上から荷物を乗せて小さな野生動物に備えます。最後にタープの出入り口を完全に閉じておきます。

Quechua のポップアップテントの後方は本来大きくオープンできて中のウォールの上半分はメッシュです。穏やかな気候の時はこれを開放することで明るく風通しの良い最高の寝床となるがこの日は予報とは真反対の風がテント後方から吹き付けていたためレインフライを兼ねた外側のキャノピーを閉じて更にペグダウンしても吹き込む風が冷たかった。

そこでいつも予備に持っていくスノーピークのポンタでテント後方を覆いペグダウン、余った裾部分をテントの底に入れておく。更にこれがずれない様にテント前方に長いガイラインを張ってタープのサイドポールに繋いでおいた。


テントの入り口は既に着雪している。わが家の Quechua ポップアップテントは大人ひとりがなんとか横になれる程度の前室があるが床面がブルーシートと同様の素材なので冬場は足や手がつくととても冷たい。そこで今回はこの前室にモコモコのフリースを敷いておいた。靴は前室の両サイドに、暖色の小さなランタンも置いてある。

冬キャンプの「あるある」は夜間のトイレ行脚です。自宅では夜間にトイレに行くことは殆どありませんが、冬キャンプではいつも以上に温かなものを飲んで過ごすため寝る前に行っても必ず一度は行きたくなるのです。あたしは意を決し起きると寝床で温めておいた厚手のウールソックスを履き裏地付きの暖パンとフリース、その上にダウンを羽織りヘッドランプと共に外に出ます。防寒用のライナーが付いた大きめのブーツを前室から持ってファスナーを開けると一面真っ白〜。

Quechua のハーフシェルターは倉庫がわりに使われます。夜間はここにランタンをひとつ置いて寝ます。

午前零時半過ぎ、外は風もおさまり雪も止んでいましたが足跡が残る程度の雪が積もっていました。

朝は6時に起床ス。テントの中で完全防寒して外へ出ると一面真っ白、、帰りやばいかな、、いや、帰れるかな、、と不安がよぎる。夜間の強風に耐えたフルクローズのタープシェルターに移動し最初に石油ストーブに火を入れる。

Quechua のステンレスケトルにウォーターバッグから水を注ぐと、、あら不思議。シャーベットマウンテンの出来上がり。

タープシェルターの出入り口を半分開けて Trangia ガスバーナーに火を点す。ガスは正月キャンプに使った残りのPXガス(キャプテンスタッグ)。缶の表面が半分凍りつきながらも何度もお湯を沸かしてくれました。

ストーブの火が安定したらまだしばらくは寝ている奥さんのブーツを温めておきます(なんて優しいオットセイ!)。沸騰した Quechuaのケトルもストーブの乗せて沸々やっておきます。ストーブの右の端(熱くならない)に置かれたサーモスの保冷缶ホルダーは冬の必需品。専用の蓋をすればそのまま保温タンブラーとして使えます。これに熱々のカフェオレを作り置きしておきます。

お次は1.4LのTrangia ケトルでお湯を沸かします。冬キャンプではお湯はいくらあっても良いので沸かしては保温ボトルにストックを繰り返します。前日に沸かしたお湯をボトルからケトルへ、こうすることで沸騰時間も短くなり燃料も節約できます。保温ボトルは常に満水にしておきストーブの周りに置いておきます。

夜に降り積もった雪はふわふわサラサラのパウダースノーなので風が吹けば多くは吹き飛ばされます。日が昇って少し経つとこの様に残った雪も溶けていきます。





しかしそれも束の間、次の雪雲が新たな雪を降らせます。そして短時間のうちにあたりは真っ白に。


雪が降りしきる中、テントの中でシュラフや毛布を畳んで圧縮するルーティン作業をしていた奥さんが外界に出て参ります。「きゃー!」が第一声。

キャンプの朝飯は家と変わらずパンと卵とコーヒーと決まっております。違うのはバターを染み込ませたパンを炭火で炙り焼きすること、卵やソーセージも炭火で調理することです。そのために炭は熾しておかなければなりません。

風があるので火は焚けませんがFIRE BOX ストーブにアルコール燃料満タンのトランギアバーナーを仕込んで点火、その上でオガ炭を熾します。アルコールバーナーの燃料が尽きる頃にはカンカンに熾た炭の出来上がり。

熾した炭はすかさず用意していた B-6君に移します。さあ、炭火の近火の威力発揮です。パンは油断すると黒焦げになるので付きっきりでこんがり焼きます。

ソーセージと卵はすき鍋で。

朝飯を食う頃にはタープシェルターの中はポッカポカの温室状態です。

それにしても強い風の中よく持ち堪えてくれました。
朝食後は始めボチボチやがてササささっと、最後はバタバタドタバタと正午の撤収に向けて動きまくります。そしていつもの光景といつもの台詞、、
「おかしいなぁ、、なんで帰りの方が荷物がいっぱいになるの?」
要は積み方なんです、わかっとるのです、はい。

帰宅後の奥さんの談
冬キャンプ11年目にして初の焚き火ナッシング、そして初の石油ストーブ使用。もっと早くにすれば、、と思ったでしょ? ずっと考えてはいたんですが、わが家のキャンプスタイルで石油ストーブを活かそうと思えば更にデカいテントに買い替えるか、アタシが苦手とするタープワークで温室を作らなければならず、今日まで青空キャンプだったわけです。
それにしてもアタシのタープ苦手意識なんとかならんものかね。ロープワークはボーイスカウトで習って以来全然苦にならないから良いのだけれど。
ponio でした。

あ、そうそう、、今回のキャンプで真っ黒黒スケになってゴシゴシの刑になったのは Quechua のケトルだけでした。
2025年01月19日
ケリー爺さん(KELLY KETTLE)


KELLY KETTLE についてのブログは 2015年以来です。

さて、どちらを選ぶか、、
方や満水容量 1400ml のスノーピーク TREK 1400(左)、方や満水容量 1300ml の KELLY KETTLE。見るからに差がありすぎるサイズ感。これは KELLY KETTLE という道具がもつ特殊性からきている差でございます。スノーピークのTREK シリーズは純然たるアルミ製のクッカーである。本体容量1400ml、フライパンにもなる蓋は500mlの満水容量となっています。このクッカーを使うためには何らかの熱源が必要なのはあたり前田のクラッカー!です。対する KELLY KETTLE はケトルとウッドストーブが合体した異色の道具です。これ一台で火を焚いてお湯を沸かせます。私は「ケリー爺さん」と呼んでいます。

KELLY KETTLE の目的は湯沸かしオンリーですが、今はボトムの火床を使って調理をするための専用五徳(Hobo Stove)も売り出されています。

私のはそれ以前に販売されていた単なるワイヤータイプのロストルです。凝った作りもなく二分割式です。

二つ合わせてこんな風に。ボトムに溜まった熾を利用して簡単な調理が出来ます。

KELLY KETTLE のボトムには煙突効果の吸気口となる大きなホールが設けられています。アルミ製のボトムはかなりの高温になるので草地などでは直置き厳禁です。またこのホールから長めの枝木を突っ込み先から燃やしていくやり方もあります。

このホールから吸い込まれた空気が燃焼を促進しその炎が煙突状の本体の中を龍の如く立ち昇ります。本体は二重構造になっており煙突をグルリと囲むケトル部が広範囲に熱せられるため非常に短い時間でお湯が沸きます。基本的には追加の枝木、木材は煙突上部からポンポン放り込みますが気をつける点もあります。煙突上部からは長い枝なども構わず放り込めるのですがお湯が沸いた時に本体を持ち上げると中で立った状態で燃焼中の枝がバラバラっと崩れてボトムからこぼれ落ちてしまうのです。こうなると再び本体を被せることが出来ません。長い枝木を入れる時は燃やし始めが良く量は少なめがよろしい。それとボトムのホールは風上に向けると恐ろしく火力が上がるので風向きは要チェックです。

ケトル本体の内側はこんな風に真っ黒になりますが他のクッカーと違い外側は汚れません。なので持ち運ぶ時に他のものを汚しません。また手入れも不要。

ウッドストーブで焼かれたクッカーは一様に真っ黒黒スケになる。これは何かに包むか煤や脂を落としてからパッキングしないと手も道具も真っ黒になる。

KELLY KETTLE は内燃式なので汚れるのは内側だけ。

これは雨で湿気った枝木を燃やしているため白い煙をあげている 。この日は土砂降りの中で炊事棟に籠りせっせと湯を沸かし続けた。

よく乾いた枝木を使えば煙は殆ど見えない。こちらは熊本県人吉市のキャンプ場で、到着後に最初の湯を沸かす。ボトムの熱で下草が焼けない様にユニフレームの五徳の上で燃やしています。

私のものは Scout 呼ばれる1.3Lのモデルで中国製です。注ぎ口のキャップはコルク製です。アイルランド発のKELLY KETTLE ですが他社の例に漏れずここも2000年代になって製造国が中国にシフトしたそうです。ただ、ステンレス製のモデルだけは本国で作られているとのこと。これは私が KELLY KETTLE を買った10数年前に日本の代理店に問い合わせた時にもらった返答です。

私がこの KELLY KETTLE を本社から取り寄せたのは東日本大地震の直後だったと思いますのでかれこれ14年ほど前のことです。

その後スマホが隆盛し始めYouTubeなどで海外のキャンプやらブッシュクラフトやらが手軽に観られるようになるとそれを追う様に新たなウッドストーブたちが日本へと入ってきました。

その後は単に湯沸かしだけではなく調理にも使えるグリルストーブ的なウッドストーブや焚き火台が出始めます。

折り畳み式や様々な形に組み換えられるストーブも出てきました。

一方でわが家は日本の至宝「七輪」を長らく使ってきました。そんな新旧の波に揉まれる様に気がつけばわが家の KELLY KETTLE もいつしか使われなくなりました。ネックになったのはやはりそのサイズ感でした。重量はとても軽いのに持ち運ぶにはデカすぎる、ここです。これは昔なら馬やカヌーにて運ぶ、今なら車。そうでなければひと所に据え置いて使うものだと思うのです。


浜に行けば松ぼっくりに流木と燃やすものはいくらでもある。ケリー爺さんを焚きつけるにはもってこいの場所だね。

ザックをぱんぱんに膨らませて長崎の離島まで持って行ったことがある。朝から湯を沸かしお日様の下で髭を剃り残り湯で焼酎のお湯割りを作る。朝から呑む、これ離島の掟。KELLY KETTLE はそのまま軒下に置きっ放し、そんな使い方が似合うケリー爺さんです。

私の KELLY KETTLE は1.3Lのモデルですが、同じ1300ml のお湯を沸かすならもっとコンパクトなクッカーやケトルとストーブバーナーの組み合わせで良いのです。キャンプでは焚き火台や七輪がありますしね。ではこの KELLY KETTLE に生き残る道はあるのか、、ある!きっとある!
ということで、次のキャンプにはこの「ケリー爺さん」を連れて行こうかと考えております。さて、そのデカい図体に見合った活躍となるか。
2025.02.23


活躍しましたぜぃ!強烈な風と雪の中、焚き火が出来ない状況でも火の粉を飛ばさず次々とお湯を沸かしてくれはった。おーきにケリー爺さん!
2024年11月24日
トランギアとピクニック日和

月に一度の日曜休日、これうちの奥さんの話。アタシは毎週お休みざんす。ただし、緊急の事案(救急搬送の手配や同行など)があれば返上となりますが。アタシが不在の時でも救急搬送だけはできる様に段取りはつけてあります。

さて今日はどこへ行ったかというとお隣の佐賀県は伊万里へと行って参りました。標高330メートル余りの低山はその頂までほぼ車で行かれます。あとは整備された道を数分歩いて登れば広々と気持ちの良い草地の頂が待っていてくれます。


駐車場から直ぐ上の広場は広々とした野天の空間、気持ちいいー!すぐ横にはどデカい屋根付きのベンチ&テーブル。

そこからほんの少し登ればまっこと広い草地の頂です。展望デッキが設けられ他にも二方向に素晴らしい眺望が楽しめるウッドベンチが置かれてあります。

遠く壱岐まで見渡せる北向きのデカい屋根付きベンチスペース。更にこの先にも斜面ギリギリの所に固定されたウッドベンチがあります。周囲の樹々は短く伐採されて展望がきくようになっています。


頂の草地は所々が緩やかな斜面になっておりそこに適当な間隔をあけてお馴染みのテーブルとベンチが備え付けられております。これが全部で5カ所。この日は人っこ一人居ない傍若無人ぶり、あまりの興奮にアタシはあっちに座りこっちに移動しと落ち着かない散歩の犬状態。


素晴らしい眺望と各所に設けられた木製ベンチ。

低山とはいえそこは頂なので風は覚悟してきました。風を覚悟するならストーブ&クッカーはこれしかありません。Trangia のストームクッカー。

今日はアタシと奥さんの分を適度な時間差で調理するためにサイズ25の方をアルコールバーナー、サイズ27の方をガスバーナーにしました。この時間差調理の目的は一度に二人分の調理をバタバタと慌ただしくやらないためです。

アルコールとガスではもちろんガスの方がカロリーは高くお湯も早く沸きますし料理も早く仕上がります。アルコールバーナーの方はこの点で『ゆとり』があります。つまり片方ずつちゃんと手をかけて調理ができるのです。

調理といってもこの程度なんですがね。お湯を沸かして凍ったスープと具材を溶かしつつ煮たたせ凍った麺を入れて解して終わり。今日は最高気温が14℃前後で晴れと予想され低山とはいえ山頂で風の影響も考えられるので身体が温まるものを食べましょうと冷食の『あんかけラーメン』にしました。この『あんかけラーメン』量的に二人分だと調理に時間がかかる上にクッカーの容量がギリギリなので二つに分けて時間差調理という方法にしました。

ガスバーナーのストームクッカーが『あんかけラーメン』を調理し終えたらサラダ用のブロッコリーを茹でます。この時もう一台のストームクッカー(アルコール)が『あんかけラーメン』を仕上げにかかっています。

ポカポカ陽気の小春日和の下で『あんかけラーメン』もまた旨し。

昼飯食ったら昼寝あるのみ!車に積んでいたシートを持ち出し奥さんポカポカの昼寝タイム。山頂に着いてから奥さんの昼寝が終わる頃まで誰ひとり訪れる者なき頂の昼下がりでした。

よく手入れされた草地はほぼ枯れ色でしたがふと目をやると大きなトノサマバッタが跳ね回り野生のリンドウがこっそり咲いていました。



眺望のために伐採された枝木がそのまま残されておりアタシ的には『焚き物収集癖』に火がついてしまいました。

奥さんが昼寝の真っ最中にアタシは『焚き物』集めにあっちウロウロこっちでギコギコやっておりました。

伐採や枝打ちされた枝の中にはまだ柔らかなグリーンウッドもありました。


奥さんがネギを刻みブロッコリーやハムを切り分けるのに使った EKA の Swede88は木製の良くできたワンピースハンドル。バックロック式でスカンジグラインド、調理からウッドクラフトまで多用途に使える軽量なフォールダーです。


本日のスパイダルコはDELICA 4。フェロロッドのスパークとパッケージオープナーとしてのみ使われました。



飯も食ったし昼寝もしたし焚き物拾いも済んだ。バッタを追いかけあちこち駆け回って展望も楽しんだ。何より誰もいない山頂での時間があまりにも気持ちよかったざんす。残るはお茶の時間。お湯を沸かしてコーヒーを淹れ道の駅で買ってきた旨そうな饅頭などと一緒に腹におさめてゆっくりと撤収です。この間ここを訪れたのは数人でいずれもごく短時間で帰っていきました。

今回訪れたのは伊万里の大平山山頂でした。こんなヨカ天気の昼時に誰もいない広い草地の山頂でのんびり過ごせるなんて贅沢な時間でした。

本日のトラブルは長年使って痩せてきていたフェロロッド(Kershaw)がポキン!と折れちまったことざんすよ。アタシの場合これは100%アルコールバーナーや点火装置の付いていない液体燃料系ストーブの点火に使っておりました。今後も使えるかどうかわかりませんがとりあえず瞬着とソニーボンドでガチガチに固めたでやんす。
2024年08月20日
SOLO STOVE を考察する

SOLO STOVE 考察
わたしの SOLO STOVE は現在は “ LITE ”と呼ばれているモデルです。その名の通り完全なるソロ用です。お湯だけなら三人分でも余裕で沸かせますが三人分の調理となるとやはり限界を感じる大きさです。炉内が小さく燃料となる乾燥した枝木や流木なども一度に多く入れられません。わたしは小薪と呼ぶブロック状に割り切りした枝木を使います。握るだけでポキポキ折れる細い枝や木屑などは焚き付けとして点火。これが順調に燃えて火勢がある程度強くなったところで小薪ブロックを2〜3個放り込みます。

これで500ml程度のお湯は確実に沸かせます。更に多くのお湯を沸かす場合には追加で2〜3個のブロックを投入します。小薪ブロックの投入は火勢が強い内に行います。

あとは風防となるものを風上に設置してやれば失敗することなく湯を沸かせますし簡単な調理もできます。燃焼が進んで炎が見えなくなっても熾の状態で十分な熱量を発しますのでお湯はなおも沸々と沸き続けます。ここが液体燃料系のストーブバーナーと違うところです。こんなに小さなウッドストーブでも熾のチカラを感じます。
さて、わたしにとってこの SOLO STOVE とは何でしょう?ある見方をすればこれは『ひとり遊び用のオモチャ』とも言えます。使うのはいつもひとりの時。キャンプに行っても奥さんがテントに作った巣に潜り込んだ後で独りこれに火を灯してお湯を沸かし熱燗やホットラムを作って呑むくらいです。

奥さんにとってこれが活躍したのは一度だけ、真冬のキャンプでSOLO STOVE に炭を入れ自分の足元に置いて暖をとった時くらいです。お湯を沸かしたり何かを調理したり夜の明かりや暖をとるのに使うのは大抵の場合『焚き火台』の役目です。SOLO STOVE の出番はありません。

しかし、これがキャンプではなく休日のドライブで簡単な昼飯に添えるコーヒーやお茶のための湯沸かしにならこの小さなウッドストーブは活躍する機会が十分にあります。勿論、それは火を焚いても問題のない場所でという前提で。
そしてもう一つ。

わたしが何度もこのブログにアップしてきた帰省の際に持って行く『ひとり用湯沸かしストーブ』としての用途です。

それなら、FIRE BOX stove や B-6君でも良いのでは?炉内も大きいし畳めばスリムになるし大きめの枝木でも放り込める。確かにそうですね。
ただ、これらには使う環境上の問題あるのです。それはわたしの場合に限られたことかもしれません。
わたしが毎年お盆に帰省する義兄姉の家がある地区では自宅に焼却炉を作ることは禁じられています。これまで普通に行われてきた野焼きも消防への届出が必要になりました。理由は延焼防止のためです。しかし手のひらに乗るような小さなウッドストーブを庭先で焚いたところで誰も気にも止めません。隣の庭先から白い煙がたなびいてもそこにちゃんと人の姿があれば消防に通報する人もいません。それは人がちゃんと管理できる小さな火というのを周りが皆認知しているからです。
SOLO STOVE は発売当初から『煙まで燃える二次燃焼』と宣伝されていましたが実際には煙は上がります。クッカーやケトルなど上に何も乗せずに燃焼させた場合は伸び上がる美しい二次燃焼が見られ煙も殆ど出ませんが、五徳にクッカーなどを乗せた途端に煙が出始めます。

脂分の多い木材では黒い煙、よく乾燥した木材でも風が吹き込むたびに白い煙が上がります。


話を他のウッドストーブにもどします。FIRE BOX stove や B-6君は今もキャンプでも使っています。 Firebox の Nano の様に特別小さな物は別ですが、わたしの持っているFIRE BOX stove や B-6君は二人でも使えるサイズで炉の大きさからスタミナは抜群です。

しかし、都会の家よりはるかに広々とした敷地や庭先があるとはいえ上の写真にある様な大きな炎は周りの人の不安を煽ります。『火事にならないだろうか』とね。炎は小さい方が良いのです。ここにも SOLO STOVE の良さを感じます。

ガスやアルコール、ガソリンの様な液体燃料系のストーブなら何の心配も要りません。枝木や小薪を用意する必要もありません。煙も出ずパチパチと爆ぜる音もしません。

そしてウッドストーブには灰の問題が付きものです。完全に燃え尽きた後の灰は消火を確認してサササッと集めて捨てれば良いのですが、小さな熾を含む灰は下手に処理すると後々火災の原因となるので特に注意します。お世話になっている人の家をそんなことで失わせるわけにはいきません。



FIRE BOX stove の場合 5" Stove や Freestyle、Nanoについてはストーブ底面から灰がこぼれ落ちることで目詰まりを防ぎ下方からの吸気を妨げない仕組みです。それと風に煽られた際に四方のパネルに開けられた多くのスリットやスロット、ホールから炎が噴き出したり灰も飛び散ります。B-6君も同様です。これらには簡単な灰受けがありますが横風には効果ありません。

SOLO STOVE は底まで1ピース構造であるため据え置いて使っている以上は基本的に熾も灰もストーブの外にはこぼれ落ちません。唯一、灰を捨てずに長時間使い続けた場合に溜まりすぎた灰が吸気口から溢れることがあります。また火が消えた後でストーブを持ち上げ振ったり傾けたりすると側面の吸気口から中の灰がこぼれますがそれも微々たる程度です。ここなのです。SOLO STOVE には使用中の灰の飛散という問題がほぼありません。庭先を汚さない、細かな熾を落とさない、ここにも SOLO STOVE を使う意味があるのです。
まとめると、、
❶ 基本的に熾や灰はこぼれない
❷燃焼中の炎が大きくなり過ぎない
❸燃料となる枝木や流木が現地調達できる
❹アルコールバーナーが使える
こぢんまりと小さな火を焚いてお湯を沸かす。周囲に要らん気を遣わせない。迷惑をかけない。雨の日はアルコールバーナーを使える。と、こんなところでしょうか。

さて、さて、今回の帰省で使ってみて改めてわたしのウッドストーブ第一号がボロボロなのに気づかされました。外見上は変色だけなのですが炉内がボロボロです。まだ使えるレベルですがここらで今後を考えておこうかと。
一つの案は『SOLO STOVE を再生長生きさせる』案です。

焼き切れたニクロムワイヤーの替わりにAmazonなどで販売されているペレット用ロストルを組み込む、またはお得意の100均グッズでロストルを自作する、例えば、、

100均の揚げ物オタマの柄を取ってはめ込む、

こんな風に。ここにリーマーで適当に穴を開けてやることで目詰まりしにくくする。が、

いずれはこうなる。まあ、安い材料費ですから想定内。

この写真は100均の小さな焼き網をカットして端を曲げて作ったロストルです。オリジナルに近い姿でしょ?下方からの吸気と目詰まり防止効果が期待出来ます。が、これもおそらく短命でしょう。焼き網は下から炭火などで炙られるのには耐えられますが焚き火の様な直火や火床として使うと簡単に変形してサビサビになってしまいます。まあ、これも2枚100円の品物なので、、。
もう一つの案は『再度 SOLO STOVE を買う』です。買うとすれば現行の LITE (2024年8月現在¥9.790)でしょう。ワンサイズ上のタイタンでも良いのですがひとり遊びの道具としてはやや大きめなのでやはり LITE でしょう。
三つ目の案は現在手持ちのストーブから代替え機を選ぶというものです。

例えば、以前帰省の際に持って行った WILD STOVE です。ただ、これにはちと問題が、。このウッドガスストーブには底板がありません。つまり灰と細かな熾はそのまま地面に落ちるということです。この問題に対してはオリジナルの発売当初からユーザーが個人的に底板を自作しはめ込むという方法が取られてきました。

わたしは収納ケースを兼ねたステンレス製クッカーの蓋を裏返してはめ込んでいました。ボトムの吸気口が隠れてしまいますが十分に隙間があるため機能的なマイナスにはなりません。

それともう一点、これはWILD STOVE の MARK 2 にのみ言えることですが付属のヘナチョコ五徳の使いづらさです。このヘナチョコ針金五徳は外して畳んで収納可能ですが安定して乗せられるクッカーやケトルが限られてしまうことや、取り外しの際に煤で手が真っ黒になることが嫌で当初からあまり使いませんでした。


一時期は太い針金ハンガーから自作した開閉式の簡易五徳を取り付けていましたが最終的には

こんな中国製のコピーストーブみたいなスタイルに落ち着きました。

たまたま今回 SOLO STOVEのロストル作りに買った2枚100円の焼き網の一つが WILD STOVE にピッタンコ。炭でも入れて何か一品焼くのも良いかもです。
そして候補のもう一つが
FIRE BOX stove の Scout です。

FIRE BOX Scout は単純な箱型ストーブです。SOLO STOVE の様な二次燃焼を作り出す特別な仕掛け構造はありません。底近くに設けられたサイドフィードポートと呼ばれる大きな吸気口兼木材投入口からの吸気によって燃焼が促進されるだけの簡単明瞭なストーブです。空き缶に穴を開けて作るホーボーストーブと変わりありません。他の FIRE BOX stove と異なるのはストーブ本体が折り畳み式ではないことと完全な箱型で底板には灰を落とすホールすら設けられていないことです。更に、

付属する二つの箱型リッドには表と裏があり通常は表面にストーブ本体を乗せてストーブベースとして使います(地面への熱インパクトを抑える)が、このストーブベースとなるリッドをひっくり返すことで先に書いたサイドフィードポートを完全に覆う形にすることができます。これは下方からの吸気を遮断することで燃焼を抑える(小さく長く燃やす)効果があると言われています。そしてこれにはストーブ内に溜まった灰がサイドフィードポートからこぼれ落ちるのを防ぐという効果もあります。

下に設けられたサイドフィードポートからは吸気と燃料補給が行われるが燃え残りの熾や灰も排出される。ここをリッドで塞げば上のスロットやエグゾーストポートからの灰の飛散は僅かだ。

リッドを裏表逆にはめ込むことでストーブトップの高さも低く抑えられる。

このストーブは専用のパーツを組み込んで Trangia のアルコールバーナーを組み込んだり、仮設の底を任意の高さに取り付けられます。そこに各種アルコールバーナーや固形燃料を設置することで木質燃料のみに頼らないストーブに変身します。またガスバーナーも組み込めるのも強みです。ただし、アルコールバーナーにしろガスバーナーにしろそれらを組み込むベースとしてはやや大きいのが考えどころです。
さて、あれこれ後継機を考えている間に先日使ったばかりの SOLO STOVE を手入れしてみました。

炉の底からデブリがゴッソリ剥がれ落ちてきました。手入れはしても洗ったり磨いたりはしません。細かなところまでチェックして適当なロストルがあればまだまだ使えると結論しました。『適当な』とは決してペレット用ロストルではありません。

可能ならオリジナルの SOLO STOVE の様な大きな編み方のワイヤーロストルにしたいのですが、、やはりオリジナルというのは製作者が「これや!(関西人か!)」と答えを出した形でありそこには必ず何らかの理由が存在していると思うからです。

さあ、長々更に長々と書いてきましたがこの SOLO STOVE にしても後継機候補の二機種にしても普段は車載用の非常持ち出し品の中に収められている物です。そこから取り出されて使われるのは例によって年に一度か二度の帰省の時だけです。用途もお湯を沸かすだけで調理することは一切ありません。それならスマートにガスやアルコールバーナーで良いのでは?またまた振り出しに戻ってしまいます。しかし、そんなことがわたしには楽しいのです。暇か?!


SOLO STOVE 復活用術の決めてとなるか?!
尾上製作所の『ミニかまど』のトップと五徳がピッタンコ。これで風防兼五徳となるか。いやいや、吸気はそのままでも排気が十分でないと不完全燃焼になるね。

かと言ってこうはしたくないアタシの捻くれ具合。
2024年05月04日
ソロストーブのための「小薪」作り


先日、長年にわたり忘れていたコールドスチールのナイフを買って男のケジメをつけた(どこがじゃ)アタシですが、実はその使い道について考えなくてはなりませんでした。
焚きつけ拾いを兼ねたデイハイクのお供、デイキャンプ、それと、、帰省。
帰省にボイジャー要らんやろー!
と思うでしょ?ところかが、アタシにとっての帰省とは奥さんの生まれ故郷である長崎の離島に帰ることを意味します。すでに実家はないので奥さんの姉の嫁ぎ先にいつも泊めてもらいます。そこに行くと必ずやるのが前庭でやる朝の湯沸かしと髭剃り、姉のためのコーヒー淹れ。最近はキャンプ用のストーブバーナーでやっていますが以前は小さなウッドストーブ(SOLO STOVEとか)でやっておりました。

2017年 離島の朝に SOLO STOVE でお湯を沸かし髭を剃る。もう一度沸かしてコーヒーを淹れる。離島の朝のルーティンざんす。野鳥の声があたり一面に満ち満ちてなんとも言えず清々しい朝ざんす。
この SOLO STOVE は現行品でいう SOLO STOVE LITE です。これを買ったのが2013年頃ですからもう11年になります。

炉内のワイヤーはすでに焼き切れておりその後100均の天ぷらオタマの柄を取り外して底網として使いそれも現在二代目です。

離島での毎朝の湯沸かしはその後ガスやアルコール燃料といった液体燃料へと変わり手早く汚れず出来るようになりました。たしかに安全で火の始末もその場で終わり煙も灰も出さずにお湯が沸かせるのはとってもイージーなのですが、ここには焚きつけとなる枯れ枝がそこらに沢山落ちています。小さな湯沸かしクッカーと小さなウッドストーブ、ライターさえ持っていけ良いのです。雨が降ったら終わりですが、、。そこで小さく切り割りした燃料をジップロックに詰めて持っていきます。それが「小薪」です。

小薪作りは落ち枝を拾うところから始めます。適当な太さの枝を拾いその場で20〜30cmに切って持ち帰ります。使うのは細い枝でもノコ刃が入りやすい細目のノコです。写真は silky ポケットボーイの細目。

持ち帰る前に樹皮を削ぎ落とすこともありますが人が通るような場所では絶対にしません。

松の枝を拾ってこのくらいにカットします。これは自宅の玄関に座布団敷いてやってます。

それをシースナイフと適当に重さのある枝でコツンコツンと叩いて割っていきます。

木質が詰まったものは無理ですが手に持って軽いものならフォールディングナイフでも叩いて割れます。勿論、叩きには力加減が必要です。割れた木片が左右に飛ぶほど強くは叩きません。

これはキャンプ場での一コマ。木質の詰まった硬い枝を細目のノコで輪切りにします。積み木のようですがこれも小薪としてそのまま焚べます。ただし、SOLO STOVE に使うには少し大きく投入したあと火力が出るまで時間が掛かります。


これくらいになると小さなブロックにするまで暇と時間が掛かります。この後1/4程度まで切り割りして炉の大きな Firebox Stove (5インチやスカウト、フリーなど)に使います。

大きな薪は半分に切るか割るかして焚き火台用として使います。

乾燥した楠の枝をsilkyの細目で短く切る。


それに IZULA を当ててコツコツと加減しながら叩く。

IZULA の小さなフラットグラインドのブレードが乾燥しきった楠の枝を割っていく。食い込んだブレードと楠の枝の間に黒く隙間が出来ている。この厚みでもブレードが楔(クサビ)の効果を発揮している。

この程度の枝にも節はある。節の硬さにもよるがこれに当たるとエッジが潰れる可能性が高い。視認できるほどではないが小さな潰れは必ず起きる。

IZULA のお仕事はここまで。あとは、新入りの出番。

先日届いたばかりのボイジャーがそれらを更に1/4に割る。

このあたりまでは IZULA に比べてブレードと割れ目の隙間は無い。叩き始めはハンドルをやや下向きに、切先をやや上向きにしてコツンコツンと加減しながら打ち込む。叩くのはブレードの背から切先に向かう角の部分。

ここまでくるとクサビ効果が現れてくる。

SOLO STOVE 用の「小薪」の出来上がり。着火後はこのピースだけで長く安定した燃焼が続く。WILD STOVE や Firebox Stove 、B-6君 あたりには小さすぎますが火力が落ちた時にはコレをひとつ二つとマッチ1〜2本を放り込むと火勢が復活します。Firebox Nano ならこれで十分。

「小薪」作りに欠かせない細目のノコギリと小さなナイフ。それにデカいフォールダーが加わりました。

手始めに「小薪」作りに使ってみたボイジャーですが、いくら頑強なロックを持っているとはいえそこはちゃんと加減してやりました。必要以上に瞬間的な負圧をかけないように。

ナイフにとっての負圧とはブレードの背に指を押し当てたり、バトンニングの様にブレードを叩いた時に掛かる上から力のことです。コールドスチールではnegative pressure と呼んでいます。

負圧(緑の↓)に対するものとして正圧(ブルーの↑)positive pressure があります。これはブレードを何かに押し当てた際にその面からブレードに向かって掛かる力です。

アタシがEDCブレードとして日頃から最も愛用している Spyderco のDELICA 4は正圧と負圧の均衡が崩れた瞬間に本来動かないはずのブレードがカクッと微動します。その際にハンドル背面のロックバーが内側に微動するのが確認できます。これは硬い木などを削ろうと力を入れた時によく起こります。最初はこれが気持ち悪く感じたものですが普段使っている分にはこの正負の均衡が崩れることは殆どなくブレードやロックバーのガタツキも見られません。
負圧に限っていえばブレードに指を当てがう際にかかる負圧とバトンの際にかかる負圧には大きな差があります。

バトニングした場合はフィクストブレードならブレードやハンドル、フォールディングナイフの場合はピボットやロックバー、ライナーなどにも瞬間的にかなり強い負荷がかかります。ご注意を。

スリムなマッチ箱ほどの「小薪」は着火用にも使えます。クルクルカール(フェザー)の必要もなく、これ以上細く割る必要もありません。アルコール燃料をほんの数滴垂らしてフェロロッドを一閃させれば一発着火。保管は適当なサイズのジップロックで。

とあるデイキャンプにて、ハチェットで小薪を作る。

こちらは WILD STOVE のために用意した小薪。市販の杉薪から作ったものなので非常に燃えやすい。WILD STOVE にはやや小さめ。
今年の夏も離島に渡るかな?
その時は小薪と SOLO STOVE とボイジャー持っていくかな。
「 IZULA でええやん!」
「え、ああ、、ね」
2024年03月27日
波音かき消す燃焼音

MSR のドラゴンフライです。今から24年ほど前にアタシが初めて買った分離式のガソリンストーブです。 たしか、、雑誌の新製品情報で見かけて店頭にて実際に見て触って買った物です。


ここ2、3日続いた悪天も回復して今日は晴れの一日。あちらこちらでヤマザクラや八重が満開です。この数日の雨の影響で仕事の日程が変更となり、そんなこんなで今日の午前はお休みとなりました。英軍のガスマスクバッグに使い慣れたガソリンストーブとポンプ、フューエルボトルなどを詰め込んで海に向かいます。風は北東4〜5メートル。プレヒートの時から小さなウインドスクリーンを立ててやります。手順はいつも同じ、ボトルにポンプをねじ込んでポンピング。ストーブと接続したらポンプ側のバルブを全開、それからストーブ側のコントロールバルブをチョコっとひねりチュルチュルとホワイトガソリンを染み出させたらライターで点火。あとは放っておく。しばらくはオレンジ色の炎が大きくなったり小さくなったりを繰り返します。

個体差もあると思いますがアタシのドラゴンフライはプレヒートの終わりに本燃焼の音が短く混じります。それが合図。その音が聞こえたらコントロールバルブを少し開いて本燃焼を開始します。

問題はそこからです。ケトルに水を入れてストーブに乗せお湯が沸くのを待つわけですが、、コントロールバルブを全開にすると凄まじい燃焼音が轟きます。有名なドラゴンフライの咆哮です。

ウインドスクリーンによる反響もあってアタシにはかなり刺激的な音に聞こえます。今日は風もあって波音も大きいのですが、その絶え間ない波音よりもはるかに大きな燃焼音をあげるドラゴンフライ。あまりに元気すぎる咆哮にアタシはいつもの如くバルブを絞って徐行運転。風の影響もありましたがたった400mlほどのお湯を沸かすのに10分以上は運転しておりました。あまりに沸騰しないので最後はバルブを全開にしましたら辺りを気にするほどの轟音とともに瞬時に沸騰しました。この激しすぎる燃焼音を抑える専用パーツ(サイレントキャップなど)も販売されていますが価格が見合わないのでいまだに買っていません。

これまでに最大火力までもっていったことは一度だけです。家族で野外ランチをした際にお湯がなかなか沸かず恐る恐るバルブ全開にしたところ、、なーんや!あっという間に沸騰。ただ、その時の燃焼音に近くにいた娘が逃げたほど。秘めた実力は流石の MSR です。

購入から20数年、最後のポンプ交換から10数年、こうして本当にたま〜に持ち出し点火してみても相変わらずの爆音豪火です。ただこの形、もっと小さくならんかったのかねぇ。畳んでもデカい!音もデカい!
春の海音など屁でもなかったドラゴンフライの咆哮でした。
2024年01月20日
キャンピングムーンのグリルベース

*キャンピングムーン・ファイヤーグリルベース 帆布ケース付
こんにちは、ponio です。
アタシはキャンプの際に焚き火台と七輪、それに組み立て式のウッドストーブを持っていきます。そんなに熱源ばかり持っていってもと思われるでしょうね。はい、その通りです。いろいろ手間暇がかかります。ではなぜ?



焚き火台はそのまま焚き火のため。これは火付盗賊と呼ばれるうちの奥さんの焚き火欲を満たすためが最大の理由です。七輪は純粋なる調理用熱源です。残るウッドストーブは、、これはアタシの趣味嗜好です。

このウッドストーブですが、 SOLO STOVE を除いてほぼ全ての機種に灰の問題が付きまといます。底板や底網、吸気口から落ちる灰の中には小さな熾も含まれます。キャンプ場の下草を焼いたり、そこら中に灰が飛散することもあります。ウッドストーブによってはアッシュパンと呼ばれる灰受けを持つ物もありますが、無いよりマシという程度のものばかりです。海外の様に灰をそのまま地面に撒いて火の始末をして埋め戻すことが出来る場所ならその必要も無いのですがね。

そこで以前から考えていたのが金属製の焚き火台ベースです。テンマクさんやキャプテンスタッグさんから出ている様な四方に縁の付いた小さなテーブルです。その殆どの物が脚付きですので地べたよりも少し高い位置で火を扱えます。この地面より少し高いことで腰痛も防げるという一挙両得なアイテムです。

そんな焚き火台ベースの中から実際に使う場面を想定して選んだのが今回ご紹介しますキャンピングムーンさんのファイアグリルベースです。

キャンピングムーンのファイヤーグリルベース MT-6-LT。FIRE BOX Freestyle のフルセットが収まります。


こうして見るとなんだかフライや天ぷらなどの揚げ物に使うステンレスパットと油切りみたい。実際、使えると思う。

見ての通り火床となるロストルから本体の底までは2センチに満たない浅さである。左右の空気の取り入れ口はロストルと同じ高さで七輪の様な下方からの吸気は出来ない。もし、下方からの吸気で火力を上げたければロストルを左右の空気取り入れ口より高くすることだ。
一方で炭を並べた場合、上に置く五徳やスタンドの高さによって遠火から極近火まで使い分けられる。このベースを焚き火台やコンロとして使う場合はクッカーや焼き網を乗せるスタンド(五徳)が必要。

クッカーを乗せる。ユニフレームの旧・タフ五徳は前後左右共に長さが足りません。写真は前後に脚を掛けた状態です。これも安定せず傾く恐れがあります。

グリルベースの脚を畳んで正面から奥に向かってタフ五徳を置くと設置可能です。

灰受けとして使う。G2 /5" Firebox Stove は余裕あり過ぎです。使うなら Firebox Nano やB-6君と並べて使うでしょうね。

笑's の B-6君も余裕のヨッちゃん。このためだけにファイヤーグリルベースを持って行くのは勿体無い使い方なのでやらないと思いますが。

FIRE BOX Freestyle の8パネル 横型。ギリギリ収まります。ひとつだけ、、

8パネル の横型にした場合、ストーブ本体の左右に開いたサイドフィードポートとファイヤーグリルベースの空気の取り込み口がちょうど重なります。灰がこぼれるとしたらここです。そこで、このスタイルの場合はストーブ本体左右のポートを例のステンレス板で塞ごうと思います。

FIRE BOX Freestyle の8パネル ファイアーピット スタイル。わが家ではこのスタイルが一番使われる様なのでこれが収まれば大収穫です。ファイヤーグリルベースの左右に開けられた空気の取り入れ口は直線的なので適当なステンレスかアルミ板ででも塞ぐことが可能です。

このMT-6-LTというグリルベースを単体で使うとすれば、オガ炭(短く切り割った物)を適当に並べて焼き網を乗せ耐熱テーブルの上でBBQコンロの様にして使うか、鍋物でしょう。その場合はテーブルの脚を畳んで低くして使えば高すぎず低すぎずで使えるかもね。
コレ予定は未定ですが次のキャンプ(キャンプ 如月)でデビューさせようと思います。


ウッドストーブの灰問題はこれにて解決!
2024年01月14日
FIRE BOX フリースタイルの実際


『Firebox Freestyle』
2022年5月 Kickstarter キャンペーンにて4パネルストーブ(Ti)の初回ロットを購入。一年後の2023年5月、セールにて4パネルストーブ(T i)と MOD kit を追加購入。基本の4パネルストーブ発売と購入から1年半、追加のストーブと MOD kit 購入から8ヶ月、改めてこのモジュラーストーブの実際と感想を書きます。

サイズ的にはG2 /5" Firebox Stove に比べて一回り小さく基本となる4パネルの状態では使い道もソロ用の域を出ない。という最初の感想。しかし、

このソロ用の域を出ない4パネルストーブが2台揃うと、

別パーツによる連結が可能になる。上は4パネルを2台連結した8パネルの横長スタイル。1.5Lクラスのクッカーなら二つ並べて同時に調理出来る。秋刀魚も焼ける。


この Freestyle はパネルの枚数とパーツの使い方によって様々なスタイルに変型させられる。上はキーホールと呼ばれる8パネルの応用型。

8枚のパネルをフルに使った焚き火台スタイル。わが家ははじめからこのスタイルを選んでいる。

わかりにくいがこの写真の時は6パネルのヘキサゴンスタイル。この日はほぼ一日雨でタープの下で小さな焚き火しかできなかった。このスタイルはケトルを置くのに最適。灰受けは100均のステンレストレー。これでは灰がかなり飛散するので下には焚き火シート必須。
わが家の様な夫婦二人のキャンプでは基本の4パネルストーブは湯沸かしなどのサブであり、アルコールバーナーやガスバーナーを組み込んだ五徳としての要素が多い。

ひとりデイハイクで湯沸かしオンリーの3パネルトライトーチスタイル。

Trangia ガスバーナーを組み込んで湯沸かしと調理。
わが家はキャンプ場以外で焚き火や炭を使うことが無いため他の熱源を組み込めるのはありがたい。

4パネルを2台連結させることについては最初に用途を考えた上でスタイルを決めておくことが大切だと感じる。一旦、火を入れてからでは燃やしている木材や炭、灰の処理をしてからでないと分解も変型も出来ないからだ。わが家の場合、8パネルのファイアーピットスタイルが基本でこれは複数人の調理などに使う場合、大は小を兼ねることが明らかだからだ。
さて、ここからは使ってみてわかったこと、ダス。
【便利さと盲点】
この Freestyle の各パネルには付属のファイアースティックや他のオプションパーツを差し込むスリットや枝木を突っ込むスロットが多数設けられており、一見すると穴だらけという印象だ。

たしかにパネルに開けられたスロットやスリットはこのストーブに拡張性を持たせてくれているが逆に風の影響を受けやすくなったと感じる。

この写真はウインドスクリーン無しで風を受けた時のもの。風上から各スロットに入った風が風下側のスロットに炎を押し出している。まるでストーブ全体が炎上しているかの様だ。これを防ぐには単純に風防、ウインドスクリーンがあれば良い。そしてこの状況は炎上以外にも灰の飛散という面倒くさい事態を引き起こす。この灰の飛散を軽減するためにアタシは自宅にあったステンレス板を切ってある部品を作った。

それは単なるL字型の板であり加工といえばエッジで手を切らない様に面取りをしただけの物だ。これをストーブの炉内に設置するのだ。灰は底網から下に落ちたものと風などによってサイドフィードポートから押し出されるものが殆どを占める。

こうして風下側のサイドフィードポートを塞いでここからの灰の飛散を抑えている。風上側はそのまま開放。

このサイドフィードポートは4パネルで3ヶ所、6パネルでは6ヶ所(全てのパネル)、8パネルも6ヶ所となる。なので、6パネル8パネルの時は4ヶ所を同じ様にして塞ぐ。アタシの様な面倒なことをしたくない人は底網の位置をサイドフィードポートより上に上げる方法をお勧めします。

通常の位置(下)から2つ上のスロットにファイアースティックを通した場合、

上の写真の様にサイドフィードポートより上の位置に底網を置くことが出来る。通常なら底網はサイドフィードポートと同じ高さにあり灰は風によって押し出されやすい。この『底網の底上げ』はそのままクッカーと火床の距離を短くすることとなるため近火の効果が生まれる。大きな焚き火ではなく調理用の炭火を近火で有効に使える。
ただし、底網から下に落ちる灰については別の方法を考えなければならない。

Freestyle にはいわゆる底板が無く代わりに各スタイルに合わせた底網を置く仕様なので組み立てには相応の手間が必要。底網は下方からの空気の取り込みと不必要な灰を落とす役目がある一方で落ちた灰の拡散も意識しなければならない。

とあるキャンプにて。収納ケースはストーブの下に置くことで灰受けにもなるが深さが十分でないため上の写真の様に灰が積もって飛散してしまう。

今年の正月のキャンプではコールマンのファイアーディスクを灰受けとして利用した。この時は強風が吹きつける環境でもあったため横風に弱いファイアーディスクを使わず Freestyle の8パネルで代用した。また二つの収納ケースを並べて立て風防として使った。

Freestyle の6パネル ヘキサゴンと Coleman FIRE DISK ソロのサイズ比較。灰受けとして十分使えそう。

この写真は本来は灰受けに使う収納ケースを風防に使い、更に灰の飛散防止のために同社の Scout エマージェンシーストーブのリッドを下に取り付けてある。
この様に別の灰受けを持つ必要があるのか?それはキャンプ場にもよる。手入れされた美しい芝のキャンプ場では焚き火シートの使用を勧められますし、冬枯れの草地では火事の可能性もありますから。念には念を入れるならば、風除けのウインドスクリーンと完璧でないまでも灰の飛散をある程度防ぐ灰受けを考えることが必要だ。土が剥き出しのピットや竈タイプのピットがある場合はこの限りではありませんが。

竈タイプのピットで使う。灰はそのまま下に落下。
次は【歪みについて】

パネルの合わせ目が微妙にズレている。使用には何ら問題ない。
アタシの場合、Freestyleについてはステンレス製の方ではなくチタン製の方を買ったのだがやはり熱によるある程度の変形は起こった。特にウインドダンパーと呼ばれる可動式のパーツと各パネルの微妙な歪みである。

二台ある内の一台のウインドダンパーが常に開いてしまい戻そうとすると一旦引っかかり閉じなくなった。よく見るとダンパーとパネルのクリアランスが殆ど無い。スムーズな開閉のためにはある程度のクリアランスが必要なのだ。

もう一台の方は明らかにダンパーとパネルの間にクリアランスがある。これはどちらにも歪みが出ている証拠なのだ。クリアランスが無い方は開閉時に下のパネルに引っかかるし、クリアランスが大きい方は逆に緩々なのだ。

上の写真でもわかるように手前の4パネルは畳んだ時にウインドダンパーが起きっ放しになっている。奥の一台は本来なら平らになるはずの本体が開いてしまっている。これは熱による歪みと、もう一つ、分解掃除した際に2台のストーブのいずれかのパネルが入れ替わった可能性がある。歪みについては薄いチタン板ではよく起こることであり他のクッカーでも見られるので想定内である。使用には何ら問題がない。気になるなら慎重に手で歪みを矯正することも出来る。

これは上の2台の4パネルストーブのパネルNo3を入れ替えたもの。(おそらく分解掃除の際に組み間違えたのでしょう)結果、奥のストーブは畳まれた状態で平らになった。手前のストーブはパネルとウインドダンパーを手で曲げ直した。このパネル矯正は FIRE BOX が G2 /5" Stove のチタンバージョンを販売し始めた直後から動画等で紹介しており、この歪みという点においてはステンレス製の物の方が強いこともわかっている。そのかわり重い!
これらはあくまでアタシが使った感想です。
まとめると、、
☆4パネルはサイズ的にソロの域を出ない。
☆各スロットは拡張性のために必要であるが、一方で風の影響を受けやすい。
☆サイドフィードポートも風の影響を受けやすく灰もここから飛散しやすい。
☆底板ではなく底網式なので下には灰受けが必須。
☆4パネルから6パネル、更に8パネルへの連結と変型は用途を考えた上で最初に行う。火を入れてしまってからでは難しい。
☆炭(熾)を使う場合は底網の底上げを行うことで近火の恩恵が得られる。
☆パネルの脚を一本外せば各パネルを横並びに広げられ炉内の掃除も楽に行える。
☆チタン製は熱による変形が起きるが使用上は問題なく曲げ直しで矯正出来る。
それで結局どうなんだ?
もし、あなたがソロのバックパッカーなら基本の4パネル・チタンモデルがミニマルとなるだろう。体力や荷物にゆとりがあるなら6パネルの方が使い勝手にもゆとりが生まれるだろう。もし、あなたが移動に車や単車を使えるなら8パネルのフルセットをあなたなりにエンジョイできるだろう。もし、あなたが家族とキャンプをするなら間違いなく8パネルのフルセットを選ぶべきだ。 ただし、他にも焚き火台とか七輪、ストーブバーナーなど調理に使える熱源を持っていくなら Freestyle はあなたの趣味にとどめておくべきかもしれない。このモジュラーストーブは焚き火台や七輪、ストーブバーナーに比べると色んな意味で少しだけ面倒くさいからだ。組み立て、風対策、灰の飛散、パーツの多さ、様々なギミックも実際に使いこなすには慣れが必要だ。家族のあれこれを見ながらしながらやるには面倒に感じるかもしれない。その辺はソロならまったく苦にならないと思う。気持ちのゆとりが違うからだ。
アタシならどうするか、
もしアタシがソロで歩き旅なら4パネルを持って行くだろう(持っていかないかも)。主となる熱源はたぶん他の液体燃料系のストーブバーナーになるだろう。Freestyle の出番は野営地に着いてから。ストーブバーナーの液体燃料を節約するため拾い集めた枝木を燃やすことになるだろう。撤収を意識した朝と、移動途中の昼間は液体燃料系のストーブバーナーが手早く手軽だ。車を使った移動なら目的地で過ごす時間も長くなるから Freestyle を焚き火台としても使うことだろう。それでも独りなら6パネルで十分な気がする。

6パネルのヘキサゴンスタイルと灰受けのアッシュパン(収納ケース)。6面のパネル全てにサイドフィードポートがある。上の写真では左右の4面はなんとか灰受け可能だが正面と後ろ一面は灰受けが機能しない。やはりここは塞がないと。

同じ6パネルでも横長のスタイルにすれば全てのポートを収納ケースが灰受けしてくれる。またヘキサゴンスタイルでは小さなクッカーを乗せるためには別にロングタイプのファイアースティックが必要だ。この横長のスタイルなら通常のスティックが使える。

しかし、6パネルの本体とそれを組むためのスティックや底網だけで 600g 近い。たかが 600g、これね意外とズシリなんです。夜、野営地でしか使わない物にこれだけのズシリ感はチト気が咎める。車や単車なら何の問題もないが、どうしても『歩き』でこの Freestyle を持っていくならやはり4パネルセット(約450g)しかないか。いやいや、目的(液体燃料節約)の為だけなら Gen2 Firebox Nano のチタンモデルで十分かも。

焚き火台と Freestyle 、これは焚き火は焚き火台、調理用に Freestyle と割り切った贅沢な設定。車移動、二人分の調理、そんな条件が無ければやらないと思う。わが家のキャンプは二人なのでいつもこのパターン。
最後に、Firebox Freestyle はギミック感たっぷりの可変型ウッドストーブである。用途に合わせて焚き火台にもBBQコンロにもソロ用ストーブにも五徳の代わりにもなる。ウッドストーブとしてはとても立ち上がりが早く綺麗に燃える。炭も使えて七輪の様な使い方もできる。撤収前の火や灰の始末が面倒ならアルコールバーナーやガスバーナーを組み込めば事足りる。しかし、一方でギミック故のパーツの多さ、組み立ての難解さ(慣れない人にとって)は面倒だと感じる人もいるだろう。この Freestyle は実用的な反面で趣味嗜好性が強いキャンプ道具とも言えるだろう。
結論! このモジュラーストーブを持って行くなら『車移動!』『単車!』。『歩き』なら迷わず4パネルだがそのかわり他のストーブバーナーは持たない!どうしてもと言うのならサイフォンストーブとアルコール燃料を300mlほど。あたしゃ、そう結論したアル。
ponio
最後に、、(まだあるんかいな!)

現地(キャンプ場)で組み立て組み替えをやると余ったパーツを失くさない様に片付けなければならない。あれこれやることの多い複数人のキャンプでは手間が掛かる組み替えは面倒に感じる。

はじめから好みのスタイルに組み直して可能な限りその状態のまま畳んで持って行く。これで面倒なパネルの入れ替えを現地でやらずに済む。

この基本的な4パネルの状態から各スタイルへの組み替えが最も手間がかかる。その上、それを収納用の袋やケースに収めて持って行くと手間が増えるだけです。

日々飽くなき自由研究は続く(暇か!)
8パネルの『キーホール』スタイル。8パネルの状態で畳んだ状態からパネルを開いて右に4パネル、左に6パネルを作るイメージ。ファイアースティックは 凹 切り欠きのあるものを一本とノーマルを3本使います。底網は6パネルヘキサゴンと4パネルに付属する一番小さなものを使います。

右側のボイリングステーション。手前のポートから枝木を突っ込んで強火でガンガン焚きします。お湯を早く沸かしたい時に便利です。

左にもケトルを置いていますがこちらは沸々沸騰維持のコーナー。ファイアースティックのロングをパネルの上ではなく真ん中より少し上に差し込んでケトルをストーブの内側に沈めてしまいます。大きな火から熾火となったものを近火で息長く使う方法です。風の影響もあまり受けません。

こちらはファイアースティックの位置を少し上げて6.5のスキレットを乗せた状態です。右で湯沸かし左で焼き物、やはりスキレットはパネルの内側に軽く沈めています。実際には焼き物の油はねで横の湯沸かしクッカーが油まみれになると思いますが。

今年二月のキャンプにて。8パネルに組み換えた状態で持って行きました。やはり展開が早く便利でしたよ。
2023年11月12日
Trangia 変わらぬ炎

福岡は本日日差し少なく気温は12〜13℃、沿岸部では風もあって体感温度は10℃を切る肌寒さ。って、こうなると俄然お湯が恋しくなる。こんな日は蒼き炎で湯を沸かしたくなる。ガスでもガソリンでもない、アルコール燃料の蒼き炎。

点火はマッチ一本。
バーナーヘッドに小さな炎が回る。

美しい蒼き炎に赤みがさしてくる。炎は上に上にと伸び上がる。ケトルの底面に当たる炎はまだ小さく局所的だ。

バーナー本体が温まり本燃焼への移行を告げる『ポン!』が起きる。炎が一瞬大きく膨らむ。

燃焼炎が太くなりケトル底面の大部分を覆い出す。

燃焼が最大に、そして安定する。

本燃焼。ケトル底面全面に炎が行き渡る。


五徳は料理屋などで使われる固形燃料用のそれ。Trangiaバーナーと 600mlケトルにピッタンコ。バーナーヘッドからケトル底面までのクリアランスも理想的。
Trangia は変わらない、使い始めて30年。いつもどこでもどんな時でも変わらぬ炎。

11月も中旬、昼間はまだ暑さを感じることもあるが朝晩は寒さを感じる様になった。寒々しい朝にはアルコールバーナーの炎がよく似合う。今朝は奥さんが早い時間から離島に出張。いつもは使わない二人用の三つ穴ドリッパーで一人分のコーヒーを淹れる。今朝の味は『ちょい苦』だった。

















