2016年07月29日
焚き火台あれこれ
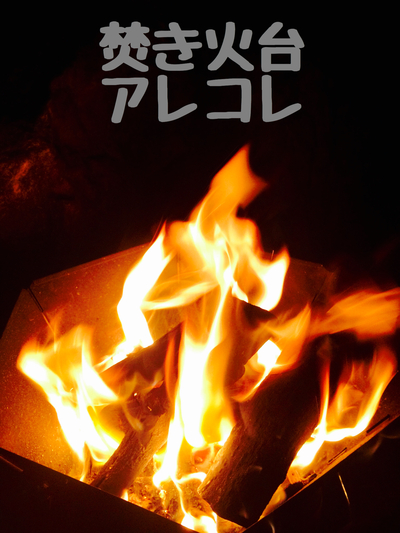
こんにちはponioでございます。

実はこの前の土日で夏キャンプと相成るはずでしたが(奥さんの思いつきで)、目指すキャンプ場の予約状況を尋ねたところほぼ満員御礼で空いてる区画は2つとか、、
そんな時は迷わず《止め!》というわけで夏キャンプは幻と消え、そのかわりに歴史情緒溢れる長崎は平戸の街並みと教会巡りをしてきました。
さて、今回は久々の【 焚き火 】物。と言っても別に目新しくもない道具の寄せ集めですので期待せずに流して流して、、。


わが家の【 焚き火 】番長こと、キャプテンスタッグさんのヘキサゴン ファイアーグリル M 。簡単組み立てでなかなかの燃えっぷり。何よりサイズが夫婦二人には丁度良いのです。本来なら専用の焼き網がパチっとハマっているはずなのですがキャンプ場に忘れて紛失。現在は適当な焼き網乗っけております。わが家のガンガン焚き専用。

これ上のファイアーグリルが登場するまで我が家のメインウエポンだった《七輪》。実はファイアーグリル参入後も七輪専用の風防兼フードを取り付けしぶとく活躍しておりました。


これは私がソロで放浪して歩いていた頃から使っていたファイアーベース(写真は新型)。ただし、焚き火台としてではなく、トランギアバーナーのベース、風防として。その後しばらくお蔵入りしておりましたが見事復活。五徳はユニフレームの旧タフ五徳。これ、構造的に大きく燃やすガンガン焚きには向いておりませんが、程よく長く燃やせる良さが魅力。

これファイアーベース変形応用編。写真はファイアーベース新旧の二枚重ね。下のベースには取り外しのきく脚が付いており下草を焼かずにすみます。


これはKELLY KETTLEのベースにファイアーベース旧型を乗っけた例。下穴からの吸気効果と灰受けを狙った組み合わせ。下の写真はその逆。

上の組み合わせに更にトランギアのバーナー五徳をひっくり返して土台とし、ファイアーベースの中にダッチオーブン用のロストルを組み込んだ例。

上の組み合わせのクローズアップ。一番下の白いのがトランギアのバーナー五徳。若い頃の2年間これとアルコールバーナーで自炊しておりました。

これファイアーベースの下にトランギアのストームクッカー25のベースをひっくり返して組み合わせた例。これも下からの吸気を狙ったもの。

そしてこれが今年の正月キャンプで試したトランギアのストームクッカー・ソースパンとその風防、そこへファイアーベースを組み込んだもの。

内部はこんな感じで、、一番下のソースパンには水を張って、そこへ脚付きのファイアーベースを組み込み、それを少し萎めてストームクッカーの風防をかぶせました。これで風防に付いている三本の五徳がそのまま使え、上に広げればフライパンも。

これ実際に試しましたが、下草を焦がさないように一番下のソースパンに張った水は途中で完全に蒸発。更に下方からの吸気が無いため熾した炭もいまひとつ熱量不足でした。結局、下のソースパンを外してタフ五徳の上にファイアーベースと風防を乗せて使いました。その後、KELLY KETTLEのベースと組み合わせで程よい燃焼を得られる焚き火台へと変身しました。


これ皆さんご存知のKELLY KETTLE。ファイアーベースと組み合わせて焚き火台として、お湯を沸かす時はファイアーベースのかわりにKELLY KETTLEのケトル部分を乗せて使います。お湯を沸かすだけにこのデカさは不要かもしれませんがこれを乗せることで火勢が一気にトルネード!炭だってあっチュー間に熾きます。湯沸しはついでという感じで、、。

そして、、この方。《妻のB-6君》です。
でもね、この方、焚き火台と言うよりはテーブルグリルみたいな使われ方でありまして、もともとそれが目的で作られた製品ではないかと、、。妻も組み立てから火起しまでは焚き火台ぽくやっていますが、後はお決まりの焼き焼きグリル。なので次回からは脚を縮めてロータイプにしたテーブルの上で純粋な調理用グリルとして使おうかと、、。その為に先日、メキシコ製のタイル(1枚120円)を6枚買ってきました。
、、とここまで書いときながら、、
夏=暑い=焚き火する?=大きな焚き火台要らなくない⤴︎=ファイアーグリル持ってく?=考えよう、、となる。(勝手にせい!)
今日も朝から押さえつけられる様な強烈なる陽射しと暑さ、夕立もなく、日の暮れ頃はクラフトテープみたいにベタッとしたしつこい暑さ、、、焚き火?せんせん、、したくもない、、。当分、焚き火のことはクーラーがガンガンに効いた屋内で冷たい飲み物ぐびぐび飲みながら考えましょ。
それでは皆さんサヨオナラ。
2016年07月23日
おさらばさ!

へへーんだ!
とうとう手にしたぜ《トンカチ野郎》を!
新潟・三条市のトンカチだ〜。ベルモントMS054。475g 全長180mm

なんたってアータ、これまではコレですから!焚き火用の薪の残り物。コレが硬いのなんのってアータ!コレでさんざんペグ打ちしたけれどいまだ割れずの堅物野郎。でも、これでオサラバさ!

ウチが必死こいて薪の残り物でペグ打ちしてると、周りから音がするのよ!《キン!カキン!コキン!》って。それに対してウチのテントサイトからは《ガ!ガ!ガッ!》ってな感じで何とも鈍〜い音。まあ、ええねんけど、、、気がつきゃ Amazonから『お荷物でーす』となっていた、嗚〜呼。
これで《ほしいものリスト》を一つ消去!って、欲しかったんかい!
ペグ抜きはどないすんねん?ときたら、いつもビクトリノックスのスイスツールで引っこ抜いてるから!と答えるアタシです。
次回のキャンプは未定ですが、スマした顔してこのピトンヒッターを振るう私がいるでしょう。(実際は狂ったように振るっていた!)
それでは、またのお越しを。
追記

これ先週の土曜日に少し遠出をして長崎の平戸まで行った時の一枚。まぁ〜なんとビンボくさい!ここは平戸の河内峠の見晴らしの良い草原の駐車場。全面アスファルトでペグが打てず、タープが張れずウチの奥さんが起毛シートとオールウェザーブランケットで即席のヒサシを作りました。
2016年07月18日
デイキャンプの道具たち

こんにちは、ponioです。
昨日のデイキャンプ調理関係者をしっかりと手入れし褒め称えベランダに並べてあげました。

手前から
《妻のB-6君》*妻の、、と付くのがミソ。私のウッドストーブ達をストッカーに追いやったのはこいつです。

前回から二度の使用で前面パネルの上が熱により少し歪みました。使用上は何の影響もありません。ただ、焚き火台というより調理機器として使われているので油汚れは免れず、洗って干した後も少し魚臭かったス。


B-6君の子分、グリルプレート(右奥)。これ、昨日はサンマ焼きに使われました。そのままではこびり着くのでこの上に焼き網乗せて使いました。
自宅に戻り魚の脂をマジックリンとお湯で溶かして落とし、ガスレンジの魚焼きグリルで空焼きして油を塗る、少し面倒ですがね。それと現地で片付ける場合に脂で汚れたままのプレートをビニール袋に包んでから畳んだB-6君を組み込んで収納ケースに収める、やはり面倒ス。
小さな焼き網は100均で買った【安心の日本製】。これなかなかいい感じ。
B-6君もこれだけで良さそうなのですが、、。
一番上の写真、右手前はアルミ製のウィンドスクリーン。本来はSOLO STOVE用に用意された背の高い遮風板。その後、WILD STOVE用に転用され、更に他のシングルバーナーにも使われ、砂浜や草地では別に外した2枚分の板を下に敷いて土台にしています。今ではB-6君の子分。
MORAのナイフ(左手前)も妻の手下。キャンプには必ず持って行く調理専用のMORAナイフ。モデルは2010 Forest 。前にも何度か紹介しましたが、ブレードが少し変わったシェープで先端のポイントから1/2程までがカミソリのような薄く鋭い刃付け、残り半分はMORAらしい北欧的刃付け。
 

木を削っても素晴らしい切れ味なのですが、これで食材をカットすると更に素晴らしい切れ味を発揮します。だからウチでは調理用です。

黒鉄皮のフライパン(左奥)は我が家のキャンプには欠かせない道具の一つです。買ってからもう4〜5年になります。勿論とっくにシーズニングも済んで普段から自宅の台所で活躍中の日用品。

鋳鉄製のスキレットではありませんが2.3mm厚で940gと結構なヘビーパン、油もしっかり染み込んで本当に使いやすいフライパンになりました。何よりテフロンなど気にせずゴシゴシ洗えるのかいい!昨日も焼き物の他にまだ冷めやらぬ炭を捨て場まで運ぶのにも使われました。ご苦労さん。
こんにちは、ponioです。
昨日のデイキャンプ調理関係者をしっかりと手入れし褒め称えベランダに並べてあげました。

手前から
《妻のB-6君》*妻の、、と付くのがミソ。私のウッドストーブ達をストッカーに追いやったのはこいつです。

前回から二度の使用で前面パネルの上が熱により少し歪みました。使用上は何の影響もありません。ただ、焚き火台というより調理機器として使われているので油汚れは免れず、洗って干した後も少し魚臭かったス。


B-6君の子分、グリルプレート(右奥)。これ、昨日はサンマ焼きに使われました。そのままではこびり着くのでこの上に焼き網乗せて使いました。
自宅に戻り魚の脂をマジックリンとお湯で溶かして落とし、ガスレンジの魚焼きグリルで空焼きして油を塗る、少し面倒ですがね。それと現地で片付ける場合に脂で汚れたままのプレートをビニール袋に包んでから畳んだB-6君を組み込んで収納ケースに収める、やはり面倒ス。
小さな焼き網は100均で買った【安心の日本製】。これなかなかいい感じ。
B-6君もこれだけで良さそうなのですが、、。
一番上の写真、右手前はアルミ製のウィンドスクリーン。本来はSOLO STOVE用に用意された背の高い遮風板。その後、WILD STOVE用に転用され、更に他のシングルバーナーにも使われ、砂浜や草地では別に外した2枚分の板を下に敷いて土台にしています。今ではB-6君の子分。
MORAのナイフ(左手前)も妻の手下。キャンプには必ず持って行く調理専用のMORAナイフ。モデルは2010 Forest 。前にも何度か紹介しましたが、ブレードが少し変わったシェープで先端のポイントから1/2程までがカミソリのような薄く鋭い刃付け、残り半分はMORAらしい北欧的刃付け。
 
木を削っても素晴らしい切れ味なのですが、これで食材をカットすると更に素晴らしい切れ味を発揮します。だからウチでは調理用です。

黒鉄皮のフライパン(左奥)は我が家のキャンプには欠かせない道具の一つです。買ってからもう4〜5年になります。勿論とっくにシーズニングも済んで普段から自宅の台所で活躍中の日用品。

鋳鉄製のスキレットではありませんが2.3mm厚で940gと結構なヘビーパン、油もしっかり染み込んで本当に使いやすいフライパンになりました。何よりテフロンなど気にせずゴシゴシ洗えるのかいい!昨日も焼き物の他にまだ冷めやらぬ炭を捨て場まで運ぶのにも使われました。ご苦労さん。
2016年07月15日
ナイフに無理をさせる
こんにちは、ponioです。
しばらく《キレモノ》ネタばかり続きましたが、それも今回で一旦終了。『一旦』なのでまたお伝えする事が出来たらやります。今回のお題は《ナイフに無理をさせる》です。

この写真はiphone 5(今だこれ)で撮ったものです。わかりますか?ナイフのブレードです。エッジ(実際に切れる部分)がキラキラしてるでしょ。これ簡単にいうと刃こぼれ、欠けたと言えるレベルではないですが、明らかにエッジが潰れています。光に当てると角度によってこの様に光って見えます。こうなった原因は《バトニング》にあります。

これじゃあ、さぞかし切れないことだろうと思いきや、これがバリバリサクサクと切れるのですよ。切れ味、切れ具合をみるのによくやるペーパーカッティングをしてみてもシャシャーと切れます。しかし、ほんのわずか角度を変えるとパチッと紙に引っかかる、、でもそれでもシャーと切れる。

これ新品のうちはそれはそれはお美しいブレードでありました。ゼロ・スガンディグラインドと呼ばれる刃付けの仕方で造られた北欧のナイフです。

掘削工具のようなバリッとしたエッジが利いたシンプルだけどゾクッとするようなライン。これの主な目的はキャンプなどでの焚き付け作りと加工。それに適した北欧的な刃付けを施されたナイフです。

鋼材は《N690 Co》というオーストリアのステンレス鋼。他にもO1と呼ばれる炭素鋼やD-2と呼ばれるセミステンレス鋼、北欧系のナイフによく使われるステンレス鋼などがブレードバージョンとしてありましたが、自分はこれを選びました。やはり、雨や食材の水分などナイフは水気に晒されることが多いから手入れが楽チンでその辺あまり気にならない物が良かったのです。

この三本のナイフはいずれも一枚物のブレード鋼材を左右2枚のハンドル材で挟んだ構造、いわゆる《フルタング》で造られています。フルタングはハンドル材に差し込まれてネジやカシメなどで固定された物に比べれば頑丈です。ただ、写真中央のナイフは前のブログで紹介しましたがバトニングでハンドルを割ってしまったQueenのナイフです。これはブレードそのものは非常にタフで裸眼で見る限りは刃こぼれも潰れも曲がりもしたことがなかったのですが、天然素材であるハンドル材が見事に割れてしまいました。(ボンドで補修すみ)一番上のスカンディグラインドのナイフはその下のQueen や ESEEのナイフよりブレードの厚みもあっていかにも頑強そうでしたが、硬く太いクスノキの落ち枝をバトニングした際にエッジが最初の写真のようになってしまいました。それでも、シャリシャリと木を削りシャーシャーと薄いペーパーを切っておりました。つまり使える範囲の刃こぼれであったわけです。

中央と下の二本はブレードにもエッジにも変化なく(裸眼で見る限りは)、勿論、顕微鏡などで見たら細かなエッジはボロボロでしょうが、、見た目には何にも変わりません。ペーパーカッティングするとわずかに引っかかったり、紙に食い込まない部分があったりと、やはりバトニング前とは少し切れ味も違っています。そこで、耐水ペーパーでシャラシャラと軽く研いで、革砥の替わりに使ってるスウェーデン軍のレザーショルダーのストラップでシュコシュコ擦ればハイ!元通り。
ペーパーカッティングはあくまでエッジの欠けや潰れを感触で見つけるための試し切りで、これがスムースに出来るナイフが万能で完璧なナイフかといえばそうに非ず。
カッターの様な本当に鋭利で薄いエッジは、ただ切れるだけで刃そのものに耐久性がないのです。だからペーパーカッティングはエッジのわずかな欠けや潰れを発見するための試し切りなのです。
さて、今回お題にしました《ナイフに無理をさせる》はバトニングやチョッピングなどの作業を指します。これには向き不向きが有るのです。その様な作業をやるよりは、やらない方がナイフには良いのです。それらの作業は斧、アックス、鉈に任せれば良いのです。つまり専門分化です。目的にあった道具を使う。これが一番。
では何故やるの?
それは《覚えちまった》からです。
《覚えちまう》とやってみたくなるもんス。ついつい、、。そして無理をさせる。ナイフは物によってはちょっとやそっとじゃ根を上げない頑丈な物もあるから、ついついやっちまうのです。でもね、《覚えちまった》ことをやるならそれに合った物を使った方が絶対いいということです。一つの物で何でもやろうなんてのはアメリカちっくな合理的考え方かも。大工さんも庭師さんもちゃんと目的にあった道具を使いこなしております。まあ、それらが無い時の為に《覚えちまった》ことが役に立つのですが、、普段は要らんということですね。これあくまで私的な考えですので悪しからず。

一番上の写真でボロボロになっていたナイフもその度に研ぎ直されて私なりの癖がついたエッジに変化しつつあります。他のナイフもみんなそうでありやした。そしてそのナイフなりの安定した切れ味に落ち着くのです。メデタシメデタシ。くれぐれも無理は禁物。カロリーオフの糖質オフ。
ponioでした。
またのお越しを。
しばらく《キレモノ》ネタばかり続きましたが、それも今回で一旦終了。『一旦』なのでまたお伝えする事が出来たらやります。今回のお題は《ナイフに無理をさせる》です。

この写真はiphone 5(今だこれ)で撮ったものです。わかりますか?ナイフのブレードです。エッジ(実際に切れる部分)がキラキラしてるでしょ。これ簡単にいうと刃こぼれ、欠けたと言えるレベルではないですが、明らかにエッジが潰れています。光に当てると角度によってこの様に光って見えます。こうなった原因は《バトニング》にあります。

これじゃあ、さぞかし切れないことだろうと思いきや、これがバリバリサクサクと切れるのですよ。切れ味、切れ具合をみるのによくやるペーパーカッティングをしてみてもシャシャーと切れます。しかし、ほんのわずか角度を変えるとパチッと紙に引っかかる、、でもそれでもシャーと切れる。

これ新品のうちはそれはそれはお美しいブレードでありました。ゼロ・スガンディグラインドと呼ばれる刃付けの仕方で造られた北欧のナイフです。

掘削工具のようなバリッとしたエッジが利いたシンプルだけどゾクッとするようなライン。これの主な目的はキャンプなどでの焚き付け作りと加工。それに適した北欧的な刃付けを施されたナイフです。

鋼材は《N690 Co》というオーストリアのステンレス鋼。他にもO1と呼ばれる炭素鋼やD-2と呼ばれるセミステンレス鋼、北欧系のナイフによく使われるステンレス鋼などがブレードバージョンとしてありましたが、自分はこれを選びました。やはり、雨や食材の水分などナイフは水気に晒されることが多いから手入れが楽チンでその辺あまり気にならない物が良かったのです。

この三本のナイフはいずれも一枚物のブレード鋼材を左右2枚のハンドル材で挟んだ構造、いわゆる《フルタング》で造られています。フルタングはハンドル材に差し込まれてネジやカシメなどで固定された物に比べれば頑丈です。ただ、写真中央のナイフは前のブログで紹介しましたがバトニングでハンドルを割ってしまったQueenのナイフです。これはブレードそのものは非常にタフで裸眼で見る限りは刃こぼれも潰れも曲がりもしたことがなかったのですが、天然素材であるハンドル材が見事に割れてしまいました。(ボンドで補修すみ)一番上のスカンディグラインドのナイフはその下のQueen や ESEEのナイフよりブレードの厚みもあっていかにも頑強そうでしたが、硬く太いクスノキの落ち枝をバトニングした際にエッジが最初の写真のようになってしまいました。それでも、シャリシャリと木を削りシャーシャーと薄いペーパーを切っておりました。つまり使える範囲の刃こぼれであったわけです。

中央と下の二本はブレードにもエッジにも変化なく(裸眼で見る限りは)、勿論、顕微鏡などで見たら細かなエッジはボロボロでしょうが、、見た目には何にも変わりません。ペーパーカッティングするとわずかに引っかかったり、紙に食い込まない部分があったりと、やはりバトニング前とは少し切れ味も違っています。そこで、耐水ペーパーでシャラシャラと軽く研いで、革砥の替わりに使ってるスウェーデン軍のレザーショルダーのストラップでシュコシュコ擦ればハイ!元通り。
ペーパーカッティングはあくまでエッジの欠けや潰れを感触で見つけるための試し切りで、これがスムースに出来るナイフが万能で完璧なナイフかといえばそうに非ず。
カッターの様な本当に鋭利で薄いエッジは、ただ切れるだけで刃そのものに耐久性がないのです。だからペーパーカッティングはエッジのわずかな欠けや潰れを発見するための試し切りなのです。
さて、今回お題にしました《ナイフに無理をさせる》はバトニングやチョッピングなどの作業を指します。これには向き不向きが有るのです。その様な作業をやるよりは、やらない方がナイフには良いのです。それらの作業は斧、アックス、鉈に任せれば良いのです。つまり専門分化です。目的にあった道具を使う。これが一番。
では何故やるの?
それは《覚えちまった》からです。
《覚えちまう》とやってみたくなるもんス。ついつい、、。そして無理をさせる。ナイフは物によってはちょっとやそっとじゃ根を上げない頑丈な物もあるから、ついついやっちまうのです。でもね、《覚えちまった》ことをやるならそれに合った物を使った方が絶対いいということです。一つの物で何でもやろうなんてのはアメリカちっくな合理的考え方かも。大工さんも庭師さんもちゃんと目的にあった道具を使いこなしております。まあ、それらが無い時の為に《覚えちまった》ことが役に立つのですが、、普段は要らんということですね。これあくまで私的な考えですので悪しからず。

一番上の写真でボロボロになっていたナイフもその度に研ぎ直されて私なりの癖がついたエッジに変化しつつあります。他のナイフもみんなそうでありやした。そしてそのナイフなりの安定した切れ味に落ち着くのです。メデタシメデタシ。くれぐれも無理は禁物。カロリーオフの糖質オフ。
ponioでした。
またのお越しを。
2016年07月11日
タフなブレード Queen のナイフ


タフで使い良く多くの仕事やキャンプで活躍した一本のシースナイフ。


Queen Cutlery #4180 GMB
ブレード鋼材 : D-2 フラットグラインド
ハンドル材 : グリーンメープルバール

米国のナイフメーカー Queen cutlery(オンタリオ社の姉妹会社)のシースナイフ#4180。セミステンレスとも呼ばれるD-2を鋼材にフルタングで造られたタフな一本。まだ円高花盛りの数年前(1$=70円程)に米国からの送料込みで¥7.000だった。2020年現在、クイーンカトラリー社はその門を閉じ製品の製造は行われていない、残念なことよのぉ。

一時、多くの庭仕事を抱えていた頃に庭師でも造園業者でもない自分がありったけの自前の道具を駆使して素人仕事に精を出していた頃、このQueenのナイフは庭仕事の道具として欠かせない存在だった。

頼まれた庭木を切ってそれを可燃物としてゴミ袋に入れる。その為に細かく切り分ける必要(ゴミ袋を突き破らない様に)があり、ノコで切った太い枝や幹をこのナイフが真っ二つに叩き割ってくれた。細めの枝はプルーナー(剪定ハサミ)が細かくしてくれた。

ゴミとして出す無数の掛け軸の空箱やら廃材をコツンコツンと叩いて割った。刃こぼれを起こす事もなく、雨の日の作業でも錆一つ浮かず、樹液にまみれて帰ってきても水洗いしてサッと研ぎ直し次に備えた。


とにかくタフなブレードで1日を通しかなりハードな作業にもへこたれることなく、良好な切れ味を保ち続けた。はじめ単なるフラットグラインドの粗末な刃付けしかされていなかった如何にもアメリカ的なナイフが使い込むうちに研ぎ直す度に鋭さを増して、最終的にコンベックス(ハマグリ刃風)気味に研ぎ直してからは本当に良く切れるタフで信頼できる一本となった。何でもかんでもコンベックス気味が良いわけではないけれど、この一本は見事に化けました。

頑強なフルタング構造。なれど、、ハンドルは天然の素材だからいつかは割れると意識していた、、。

それが今年の冬に行ったデイキャンプで太い落ち枝を割っていたところ、、、
不用意にハンドルを叩いてしまい、結果、割れてしまった。痛恨の100%完全なミス!

わかりますか?ハンドルのヒビ。実際には補修済みで、方法はソニーボンドで固めただけ、如何にも自分らしい《あり物使いのやっつけ仕事》也。いつまで持つかわからないけれどタフなブレードは健在だから何とか使い続けようと決意も新たに明日へと漕ぎ出すアタシです。

2019年の正月キャンプで太薪をバトンで叩き割る。このタフさと落ちない切れ味こそ、このナイフの真骨頂!


シースにも年季が入りストラップ無しではユルユルに。そこでいつもの技を導入。硬質のウレタンスポンジを切って内部に貼り付け、ついでにストラップは外してしまいます。これだけで十分にナイフを保持出来て抜き差しが簡単になります。
続きを読む
2016年07月10日
コールドスチール SRK

私はコレクターではありません。
買ったものは直ぐに使い出すし、箱も帯も捨ててしまう。だから新しいまま保管している物は一切無し。(避難時の用品は別)
ただし、散々にコキ使われ酷使され(一緒や!)くたびれて、気づけばお蔵入り衆となって久しい道具もあります。
COLD STEEL社のSRK(Survival
Rescue Knife)もそのひとりです。

こいつはかなりの酷使に耐え抜いてきた老兵、ベテランであります。
これを買ったのは20年ほど前のことだったかな、、。
当時、同社のトレイルマスターがその分厚く巨大なコンベックスグラインド(ハマグリ刃)のブレードで話題になっていた頃の事です。とあるお店で見たトレイルマスターは黒いラバーハンドルに赤い紙の帯(錆びるので注意とかかれてあったかな?)が巻き付けられ分厚く重いブレードは錆止めの油がベッタリと塗られていました。その赤い帯が示すのは当時のブレード素材carbon Ⅴの特性に対する注意でした。あの時見たトレイルマスターはRANDALLのスミソニアンボウイに勝るとも劣らない超迫力とゾッとするよな切れ味でした。(お店の人がスラスラスイ〜〜とペーパーカッティングしてくれました)

carbon Ⅴ のブレード。
しかし当時の私が買ったのはバケモノみたいなトレイルマスターではなく、それよりふた回り下のサイズであったSRKでした。これにも赤い紙の帯が巻かれてありました。黒のペイントが施されたブレードにピカピカに研磨された銀色のハマグリ刃がいかにも切れそうな印象を与えておりました。指先で触れてみると、、瞬間的に危ないと感じられる鋭利なエッジ。結局、あの頃の私はこれで何をしたのか?というと何にもしてません。国内のバックパッキングにこんなナイフは必要なかったし、今のようにウッドストーブ持って遊びに出掛けることもなく、日々仕事で使っていたのもBUCKやビクトリノックスのフォールディングナイフです。そうです。使い道など無いくせに買ったのでした。記憶に残ってるのは滋賀県朽木村の河原で同僚と鍋か何か作って食った時にここぞとばかりに持ち出して、、、私は結局何も使わなかったのに、同僚がデカイ流木にまたがってそれをSRKでガシガシ!叩き割っていたくらい、、待てよ!俺が未だ使ってないのに!お前が使うかよ〜〜!そんな記憶です。

かなり使い込まれた後だけどコンベックスグラインドの雰囲気が今も残ってます。

酷使の跡。へこたれず頑張ってくれましたね。ペイントが剥離して鋼材の表面が剥き出しになっていますが錆は浮いていません。

今でも十分に切れるcarbon Ⅴ のブレード。ただ、今の自分には使う機会がありゃしません。キャンプでは MORA のナイフが台頭してるし、時折入る庭仕事も FISKARSのギアプルーナーとノコで十分。バトニングに使うにはブレードが分厚すぎるし、アックスがある今ではチョッピングする事もなし、はて〜?何に使う?
仕事で10メートル以上もある胡桃の木の伐採を頼まれ、隣のマンションに倒れないように枝先を麻縄で引っ張りつつ、上からノコとこのSRKで順に切り倒して最後はSRKで枝打ちと細かく切り割りして軒先に積んだのも、とあるお宅で庭先の柿の木の枝打ちを頼まれレザーマンの小さなノコとこのSRKで枝を山と積んだのも今ではいい思い出ポロポロ。本職(庭師・造園)でもない自分が素人丸出しの《ある物使い》でやったやっつけ仕事。SRKの使い込まれた勇姿はあの頃、新しく始めた仕事に対する自分自身の必死さと重なりますわ、、。
道具は使ってナンボ。SRKもいつかまた使う機会があるのかな?その日までゆっくりお休みなさい。
ponioでした。
2016年07月09日
MORAのナイフ


*Google map より*
MORA は“モーラ”とか“ムーラ”とも呼ばれますが“モラ”と言う方も。日本でいう明治時代から続く北欧スウェーデンの刃物メーカーであり伝統的な刃物のスタイルに近代的な素材や色の組み合わせを施し様々な用途に応じたナイフを生産しています。と、メーカー紹介はさておき、今回は現代版スウェーデニッシュナイフを代表するMORA ナイフをご紹介します。例によってお好きな方だけどうぞ。

MORA 860MG
通称 【コンパニオン】価格は当時で¥2.700ほどでした。なんとお安いナイフなのでしょう!ブレード はSandvik12C27ステンレス鋼
MORAのナイフには基本的に二種類のブレード鋼材が使われています。昔ながらのカーボンスチール(炭素鋼)とステンレス鋼です。
私の MORA 860M はステンレス鋼のブレードで素材の特性から錆びにくいブレードといえます。切れ味ならカーボンスチールと言われますが、MORAの場合、ステンレス鋼でもビックリしゃっくりな素晴らしい切れ味です。そのシミツ(秘密)は北欧的刃付け(スカンディグラインド)にあります。

難しい説明解説は置いといて、、
この北欧的刃付け(スカンディグラインド)は他の一般的なフラット、ホローなどのグラインドに比べて木材に対する当たりが違います。これ感覚の話。まるで削られている木の方が喜んでる様なスムースで気持ちの良い切れ味、その感触はこれまで使ってきた数あるアメリカンナイフ(一部を除く)に比べても明らかな違いをもっています。

ショリショリ、、クリクリ、、スィースィー、、と実に気持ちの良い切れ味です。

軽い! 樹脂製のシースを含めてもわずか130 g前後。ザックに潜り込ませても何の負担にもなりません。

ステンレス鋼のブレードはピッカピカ。鋼材としても錆びにくい特性を持つステンレスですが、このミラーフィニッシュのお陰で更に手入れが楽チンチン。
切れ味が落ちたら水砥石で簡単に研げますし、私はもっぱらセラミックシャープナーで簡単タッチアップ。
私は日用的な道具としてナイフを使いますが自作したり、コレクションしたりはしていません。さらなる切れ味の追求もせず、自分が気持ち良く使える範ちゅうで手入れをし研ぎ直して使い続けています。上には上がある。知っています。さらなる切れ味のある事を。でも、私はノーマルでいいのです。


MORA HI-Q Robust
これ先のコンパニオンのヘビーデューティ版。ブレードの厚みを増して頑強に、グリップもややサイズアップして作られています。ブレードはカーボンスチールでスカンディグラインド。先の860とは鋼材、ブレードの厚みが違いますが、やはり木材に対する当たりも860とは違います。私にはRobustの方が当たりが柔らかく一方で大きく削れるように感じられます。独特のソフトタッチは炭素鋼のなせる技なのか、ハンドルのサイズアップによる力のかかり具合なのか、いずれにせよホンマに良く切れるナイフですわ。ただ、やはり水気には気をつけないと、、以前仕事で突然降り出した雨の中で使った際、帰宅後にシースから抜いてみると見事に錆色吐息。ナイロンたわしで擦ってキレイにしました。今はキャンプの際に大きな落ち枝や流木から細かな焚き付けを作る時の常備ナイフとして活躍中です。

MORA Robust でバターナイフを作る。低山ハイクで拾ってきた落ち枝から削り出しました。実にソフトでスムースな切れ味。気持ちイイー!

MORA 2010 Forest
これはコンパニオンやRobustとは少し違ったブレード形状です。これ木材に対してはやや繊細で切れ味は抜群ですが、どちらかといえば食材のカットに適しているかな。特に先端部がスゥッと食材に吸い込まれていくようで気持ち良く切れます。

とある料理教室にこのMORAナイフを持って行ったウチの奥さん、その切れ味を褒められたそうです。娘にはこれで牡蠣の殻をこじ開けられ刃こぼれ、やはりカーブエッジから先端まではカミソリのような切れ味の反面、欠けやすいので注意です。勿の論、サッと研ぎ直せますがね。

860で目釘を削り出して竹ぼうきを修理する。

ブロック肉切りMORA

とあるキャンプにて。調理全般をMORAでこなす。

仕事先で要らなくなった掛け軸の木箱をバラすRobust。

とある記念日に落ち枝を加工して小さなログハウスを作る。
とにかく使い良くて、食材を切っても木を削っても実に気持ちのよい切れ味を体感できる。そしてこれが肝心、安い!それが MORA のナイフ。最近では調子こいてやや高めのラインナップも出してるけど基本はコンパニオンのようなシンプルなやつ。それで十分なのです。
高価なナイフを持つ。
確かに高いだけの何かはある、かも。
でもね、MORA のお安いナイフを持つと何かが変わる気がする。『これで十分ぜよ!』ってね。十分とは《使えないことはない》の意ではなく、本当にこれで足りる、間に合う、ヤレる、出来た、事が多い。その意を込めて I love MORA !
ponioでした。
続きを読む
2016年07月07日
ナイフの基本 その2
ナイフの基本 PART 2
前回、《ナイフの基本》と題してご紹介したのは主にフォールディング(折りたたみ式)ナイフについてでした。最も基本的で安全な扱いと意識の持ち方を私なりに書かせてもらいました。
今回はその第二弾です。
取り上げるのは《シースナイフ》。
《シースナイフ》とは簡単に言うと《折りたたみ式》ではない鞘に収めるタイプのナイフをさします。シースはそのまま鞘の意。他にもケースとかスキャバード、サックなど呼び方もマチマチです。



この4本のナイフはいずれも《シースナイフ》です。私がこの数年キャンプやデイハイクなどで使ってきた実用品ばかりです。写真の4本のナイフにはいずれも樹脂製のシースが付属しています。樹脂製シースはナイフのブレードやハンドルの一部までを型取りして成型され、差し込むときに僅かに開いて、収まると元に戻る、樹脂の弾性を活かしたロック機構と言えます。他にもホックやベルクロ、突起などによって差し込まれたナイフを固定する仕組みもあります。

上の写真は革製のシースが付属したモデルです。革製シースは古くから存在し飾り気のないプレーンな表革の物や様々な模様や飾りを施した物まであり、使い込むほどに色艶に変化が表れ味が出てきます。一方で使い込むうちに革が伸びたり型が入ったりで全体的に差し込んだ時のホールドが甘くなったりします。また、表面加工されていないカーボンスチールなどの錆びやすい鋼材で造られたブレードを長期間差し込んだままにしていると湿気や革をなめす時の薬品の影響でブレードに錆が浮くこともあります。革製のシースにナイフを収める時は水気を拭き取り、保管は湿気の少ない環境が良いでしょう。中には革製シースからナイフを抜いてブレードには油を薄く引きラップや油紙で包んで別々に保管する方もいらっしゃいます。


上の写真は RANDALL M3-7という米国製のナイフです。01スウェーデン鋼をブレードの鋼材に鍛造(叩いて延ばして鍛える)で造られました。ハンドル材は輪切りの皮を重ねて圧縮し後端をネジ留めしてあります。


この RANDALL のシースナイフはブレードの鋼材が01スチールとかスウェーデン鋼と呼ばれるいわゆる錆びる鋼材で造られています。RANDALLナイフがスウェーデン鋼を使うのには長年の実績に裏打ちされた鋼材としての信頼性があるからです。錆びやすい反面、素晴らしい切れ味と研ぎ易さ、私的には刃持ちもかなり良かった記憶があります。

ただ、それでも革製シースに収めて保管している私は時折ナイフを抜いては薄く油を引いておきます。また、以前にオピネルのナイフの項でも書いたガンブルーによる酸化皮膜をブレードに施してあります。これはもう20年近く前に自分でやりました。それ以来、錆は一切浮いていません。
さて、先にも書きましたが、シースナイフは《折りたたみ式》ではありませんので、構造上は可動するパーツを持ちません。一般的にはブレードとハンドル部が何らかの方法で結合されております。ブレード後端ががハンドルの中まで差し込まれた状態で密着固定された物やブレードとハンドルを兼ねる一枚の鋼材をハンドル材で挟み込んだ物などがそうです。また、鋼材そのものを加工してブレード先端からハンドルまでを一体成型するタイプのナイフもあります。
《折りたたみ式》フォールディングナイフの利点はそのまま《折りたためること》です。《折りたたみ》の理由は単に携行時のサイズダウンだけではなく、刃の付いたブレードを安全に収めて携行できる部分にあります。
ではシースナイフの利点は何でしょう?
*使用の目的に合わせて多くの種類が販売されている。
*基本的に頑丈である。
*比較的ハードな作業にも使える
*シースから抜くだけで使える。
そんなところでしょうか、、
最初の《目的に合わせて多くの種類がある》とはシースナイフには手のひらに隠れそうな特異に小さな物から、もはや鉈や刀と呼ぶにふさわしいかなり大型で刃体長の長い物まで様々な種類があります。刃体長だけではなく、薄刃の物や逆に分厚く重いブレードを持つものもあります。
それぞれに何らかの目的を想定したデザインや造りになっているのが基本ですが、中には単なるデザイン的要素だけの物や映画のイメージそのまま模倣したもの、完全に武器として作られたであろう物まで多彩です。
木を削る、彫るカーヴィングナイフ、魚をおろすフィレナイフ、獲物を解体するハンティングナイフ、トラウト&バード、ダイビング時に携行するダイビングナイフ、投げることを目的にデザインされたスローイングナイフ、軍などの厳しい規格やテストを通った軍用の正式装備品のナイフ(いわゆるサバイバルナイフもこの辺が出どころ)。

正しい使い方とは言えないかもしれないがチョッピング(斧の様に木などに叩きつける)やバトニング(ナイフを木に当て他の何かでナイフの背を叩いて切り割りする)、またブレード先端部を突き刺してこじる、又は近年流行とも言えるブッシュクラフト(自然の中でナイフなどを使用して道具を作り、火を起こし、狩りをして獲物を捌き、シェルターなどの寝床を作る、そういう自然界における昔ながらの知恵と工夫を実践するスタイル、米国流に言うならサバイバルかな?)それら様々な用途目的に合ったナイフ選びができるのもシースナイフならでは。
次の《シースナイフは頑丈である》、は実は必ずしもそうではない。使い方を誤ればシースナイフも欠ける、折れる、曲がる、ハンドルが抜ける、割れる、ガタが出るなどの破損を招きます。先に書いたチョッピングやバトニングは本来ナイフが持つ耐久性を超えた無茶な使い方とも言えます。ただ、やってみたら出来た、何の支障もなく壊れもしなかった、だからそんなハードな使い方でもやってる、きっとそうなのです。そして『おー、、タフなナイフだ!』と満足する。それがチョッピングやバトニング専用に特別な素材や造りの頑強さを持った物なら別ですが。本来その様な作業は斧、アックス、ハチェット、鉈、マシェリ(マチェット)、などが専門としてきた分野なのです。

勿論、ナイフにはその様なハードな作業をこなす能力が備わっているのも事実です。シースナイフの中でも一枚の鋼材でブレード先端からハンドル末端までを造り、それを何らかのハンドル材で挟み込んで造られたシースナイフの構造をを《フルタング》といいます。この単純な構造はブレードが折れない限りは使い続けられるタフさを備えています。《フルタング》=《頑強》と言われるのもわかります。勿論、無茶をさせればブレードがポキン!といくこともありますが。

写真は長年愛用してきた Queen のシースナイフ。ハンドルが割れました。ブレードはフルタングで刃持ちも抜群、1日を通して使い続けても切れ味が落ちないタフな一本でしたが、、無理なバトニングでハンドルを割ってしまいました。勿論、ブレードは何ともないので修理の方法をあれこれと考えております。
《シースナイフはシースから抜くだけで使える》、、当たり前やん!そうですね。当たり前だけどこれもシースナイフの利点なのです。フォールディングナイフは使う時にはナイフを握った利き手とは別のもう片方の手でブレードを開かなければなりません。近年では片手だけでサッとブレードの開閉をすることができる物も多く見られます。マスコミがやたらに騒ぐバタフライナイフもそうです。フォールディングナイフを片手で開閉するのはカッコ良さとは別です。片手で何かを握り、もう片方の手でブレードを開かなければならない状況があるのです。片手が使えない、片手が塞がっている状態です。そんな時にサムスタッドやサムホール、フリッパーやアシストオープンなどワンハンドでブレードの開閉が出来るのは至極便利なことです。
シースナイフはシースから抜くだけで使える、、ブレードを開かなくても良いのです。当たり前だけど大切な利点でもあります。
ではシースナイフの欠点は何でしょう?
それはズバリ、サイズ的な携行性の悪さ、そして携行時やそれを抜いた時の周囲への配慮が必要であるということ。

先に紹介した RANDALL のM3-7はご覧の通りのデザインです。このナイフには本来の目的(ハンティング・獲物の解体)があり、その為のデザインであり決して人を威圧したり恐怖感や不安感を煽る為のデザインではないのです。が、、実際は何も知らない人がこのナイフが抜かれたのを見たら、、間違いなく不安や恐怖といったストレスを感じることでしょう。周囲に子供がいたりすれば 『緊急避難 』『通報』されるかも。それが一般的なキャンプ場でも周囲への配慮なくしてはこの様な大きなシースナイフは持って行けません。ここはアメリカやカナダの広大な自然でもなければ北欧の森林の中でもないからです。勿論、正当な理由がない持ち歩きに関しては銃刀法違反で逮捕の可能性も十分にあるサイズです。【キレモノ】の項でも書きましたが、本人にその気がなく(人を傷つけたり脅したりカッコつけたり)、単純に純粋に木や食材などを切る道具として使う為に持って行ったのに周囲から要らぬ詮索と追求を受け必要のない言い訳をしなければならないのは実に不愉快で腹立たしいことです。私はこれまでその様なトラブルに巻き込まれたことは有りませんが、私の気づかぬところで私を警戒していた人がいたかもしれません。

チョッピングもバトニングもブッシュクラフトも楽しんでやってるうちが花です。理解していない人たちとの要らんトラブルにだけは巻き込まれないように。楽しく安全に場所と周囲を意識してこの便利な道具を使って下さい。



我が家の場合、キャンプ場ではテントサイトに置かれたテーブルにいつもMORAのシースナイフが置かれてあります。それをうちの奥さんがサッと抜いて小さなカッティングボードでトマトや野菜を肉を切り分け何かを作ります。その横では私が小さなハンドアックスで薪を割り、時にはシースナイフやフォールディングナイフで更に細かい焚き付けを作ったりしています。不用意にナイフを抜いたり、手に持ってシゲシゲと眺めたり、必要もなくぶら下げて歩いたり、要もなくあたりの木々を切ったり削ったり、そんなことはしません。必要がないからです。逆にテントサイトを離れる時にはナイフは車載ボックスなどに収納して他人の目には触れないように気をつけます。
シースナイフは目的に合った物を選べばきっと役立ちます。品質にもよりますが多少の無理(チョッピングやバトニング)もきいてくれるでしょう。そのナイフ、ブレード鋼材に合った適当な手入れを怠らず、切れ味が落ちたら自分で研ぎ直す。そうやって使っていくことが愛用への道です。それでも必要を感じなくなったらスイスアーミーナイフ一本でも買えば損はありませんよ。
ponioでした。
前回、《ナイフの基本》と題してご紹介したのは主にフォールディング(折りたたみ式)ナイフについてでした。最も基本的で安全な扱いと意識の持ち方を私なりに書かせてもらいました。
今回はその第二弾です。
取り上げるのは《シースナイフ》。
《シースナイフ》とは簡単に言うと《折りたたみ式》ではない鞘に収めるタイプのナイフをさします。シースはそのまま鞘の意。他にもケースとかスキャバード、サックなど呼び方もマチマチです。



この4本のナイフはいずれも《シースナイフ》です。私がこの数年キャンプやデイハイクなどで使ってきた実用品ばかりです。写真の4本のナイフにはいずれも樹脂製のシースが付属しています。樹脂製シースはナイフのブレードやハンドルの一部までを型取りして成型され、差し込むときに僅かに開いて、収まると元に戻る、樹脂の弾性を活かしたロック機構と言えます。他にもホックやベルクロ、突起などによって差し込まれたナイフを固定する仕組みもあります。


上の写真は革製のシースが付属したモデルです。革製シースは古くから存在し飾り気のないプレーンな表革の物や様々な模様や飾りを施した物まであり、使い込むほどに色艶に変化が表れ味が出てきます。一方で使い込むうちに革が伸びたり型が入ったりで全体的に差し込んだ時のホールドが甘くなったりします。また、表面加工されていないカーボンスチールなどの錆びやすい鋼材で造られたブレードを長期間差し込んだままにしていると湿気や革をなめす時の薬品の影響でブレードに錆が浮くこともあります。革製のシースにナイフを収める時は水気を拭き取り、保管は湿気の少ない環境が良いでしょう。中には革製シースからナイフを抜いてブレードには油を薄く引きラップや油紙で包んで別々に保管する方もいらっしゃいます。



上の写真は RANDALL M3-7という米国製のナイフです。01スウェーデン鋼をブレードの鋼材に鍛造(叩いて延ばして鍛える)で造られました。ハンドル材は輪切りの皮を重ねて圧縮し後端をネジ留めしてあります。


この RANDALL のシースナイフはブレードの鋼材が01スチールとかスウェーデン鋼と呼ばれるいわゆる錆びる鋼材で造られています。RANDALLナイフがスウェーデン鋼を使うのには長年の実績に裏打ちされた鋼材としての信頼性があるからです。錆びやすい反面、素晴らしい切れ味と研ぎ易さ、私的には刃持ちもかなり良かった記憶があります。


ただ、それでも革製シースに収めて保管している私は時折ナイフを抜いては薄く油を引いておきます。また、以前にオピネルのナイフの項でも書いたガンブルーによる酸化皮膜をブレードに施してあります。これはもう20年近く前に自分でやりました。それ以来、錆は一切浮いていません。
さて、先にも書きましたが、シースナイフは《折りたたみ式》ではありませんので、構造上は可動するパーツを持ちません。一般的にはブレードとハンドル部が何らかの方法で結合されております。ブレード後端ががハンドルの中まで差し込まれた状態で密着固定された物やブレードとハンドルを兼ねる一枚の鋼材をハンドル材で挟み込んだ物などがそうです。また、鋼材そのものを加工してブレード先端からハンドルまでを一体成型するタイプのナイフもあります。
《折りたたみ式》フォールディングナイフの利点はそのまま《折りたためること》です。《折りたたみ》の理由は単に携行時のサイズダウンだけではなく、刃の付いたブレードを安全に収めて携行できる部分にあります。
ではシースナイフの利点は何でしょう?
*使用の目的に合わせて多くの種類が販売されている。
*基本的に頑丈である。
*比較的ハードな作業にも使える
*シースから抜くだけで使える。
そんなところでしょうか、、
最初の《目的に合わせて多くの種類がある》とはシースナイフには手のひらに隠れそうな特異に小さな物から、もはや鉈や刀と呼ぶにふさわしいかなり大型で刃体長の長い物まで様々な種類があります。刃体長だけではなく、薄刃の物や逆に分厚く重いブレードを持つものもあります。
それぞれに何らかの目的を想定したデザインや造りになっているのが基本ですが、中には単なるデザイン的要素だけの物や映画のイメージそのまま模倣したもの、完全に武器として作られたであろう物まで多彩です。
木を削る、彫るカーヴィングナイフ、魚をおろすフィレナイフ、獲物を解体するハンティングナイフ、トラウト&バード、ダイビング時に携行するダイビングナイフ、投げることを目的にデザインされたスローイングナイフ、軍などの厳しい規格やテストを通った軍用の正式装備品のナイフ(いわゆるサバイバルナイフもこの辺が出どころ)。

正しい使い方とは言えないかもしれないがチョッピング(斧の様に木などに叩きつける)やバトニング(ナイフを木に当て他の何かでナイフの背を叩いて切り割りする)、またブレード先端部を突き刺してこじる、又は近年流行とも言えるブッシュクラフト(自然の中でナイフなどを使用して道具を作り、火を起こし、狩りをして獲物を捌き、シェルターなどの寝床を作る、そういう自然界における昔ながらの知恵と工夫を実践するスタイル、米国流に言うならサバイバルかな?)それら様々な用途目的に合ったナイフ選びができるのもシースナイフならでは。
次の《シースナイフは頑丈である》、は実は必ずしもそうではない。使い方を誤ればシースナイフも欠ける、折れる、曲がる、ハンドルが抜ける、割れる、ガタが出るなどの破損を招きます。先に書いたチョッピングやバトニングは本来ナイフが持つ耐久性を超えた無茶な使い方とも言えます。ただ、やってみたら出来た、何の支障もなく壊れもしなかった、だからそんなハードな使い方でもやってる、きっとそうなのです。そして『おー、、タフなナイフだ!』と満足する。それがチョッピングやバトニング専用に特別な素材や造りの頑強さを持った物なら別ですが。本来その様な作業は斧、アックス、ハチェット、鉈、マシェリ(マチェット)、などが専門としてきた分野なのです。

勿論、ナイフにはその様なハードな作業をこなす能力が備わっているのも事実です。シースナイフの中でも一枚の鋼材でブレード先端からハンドル末端までを造り、それを何らかのハンドル材で挟み込んで造られたシースナイフの構造をを《フルタング》といいます。この単純な構造はブレードが折れない限りは使い続けられるタフさを備えています。《フルタング》=《頑強》と言われるのもわかります。勿論、無茶をさせればブレードがポキン!といくこともありますが。

写真は長年愛用してきた Queen のシースナイフ。ハンドルが割れました。ブレードはフルタングで刃持ちも抜群、1日を通して使い続けても切れ味が落ちないタフな一本でしたが、、無理なバトニングでハンドルを割ってしまいました。勿論、ブレードは何ともないので修理の方法をあれこれと考えております。
《シースナイフはシースから抜くだけで使える》、、当たり前やん!そうですね。当たり前だけどこれもシースナイフの利点なのです。フォールディングナイフは使う時にはナイフを握った利き手とは別のもう片方の手でブレードを開かなければなりません。近年では片手だけでサッとブレードの開閉をすることができる物も多く見られます。マスコミがやたらに騒ぐバタフライナイフもそうです。フォールディングナイフを片手で開閉するのはカッコ良さとは別です。片手で何かを握り、もう片方の手でブレードを開かなければならない状況があるのです。片手が使えない、片手が塞がっている状態です。そんな時にサムスタッドやサムホール、フリッパーやアシストオープンなどワンハンドでブレードの開閉が出来るのは至極便利なことです。
シースナイフはシースから抜くだけで使える、、ブレードを開かなくても良いのです。当たり前だけど大切な利点でもあります。
ではシースナイフの欠点は何でしょう?
それはズバリ、サイズ的な携行性の悪さ、そして携行時やそれを抜いた時の周囲への配慮が必要であるということ。


先に紹介した RANDALL のM3-7はご覧の通りのデザインです。このナイフには本来の目的(ハンティング・獲物の解体)があり、その為のデザインであり決して人を威圧したり恐怖感や不安感を煽る為のデザインではないのです。が、、実際は何も知らない人がこのナイフが抜かれたのを見たら、、間違いなく不安や恐怖といったストレスを感じることでしょう。周囲に子供がいたりすれば 『緊急避難 』『通報』されるかも。それが一般的なキャンプ場でも周囲への配慮なくしてはこの様な大きなシースナイフは持って行けません。ここはアメリカやカナダの広大な自然でもなければ北欧の森林の中でもないからです。勿論、正当な理由がない持ち歩きに関しては銃刀法違反で逮捕の可能性も十分にあるサイズです。【キレモノ】の項でも書きましたが、本人にその気がなく(人を傷つけたり脅したりカッコつけたり)、単純に純粋に木や食材などを切る道具として使う為に持って行ったのに周囲から要らぬ詮索と追求を受け必要のない言い訳をしなければならないのは実に不愉快で腹立たしいことです。私はこれまでその様なトラブルに巻き込まれたことは有りませんが、私の気づかぬところで私を警戒していた人がいたかもしれません。

チョッピングもバトニングもブッシュクラフトも楽しんでやってるうちが花です。理解していない人たちとの要らんトラブルにだけは巻き込まれないように。楽しく安全に場所と周囲を意識してこの便利な道具を使って下さい。



我が家の場合、キャンプ場ではテントサイトに置かれたテーブルにいつもMORAのシースナイフが置かれてあります。それをうちの奥さんがサッと抜いて小さなカッティングボードでトマトや野菜を肉を切り分け何かを作ります。その横では私が小さなハンドアックスで薪を割り、時にはシースナイフやフォールディングナイフで更に細かい焚き付けを作ったりしています。不用意にナイフを抜いたり、手に持ってシゲシゲと眺めたり、必要もなくぶら下げて歩いたり、要もなくあたりの木々を切ったり削ったり、そんなことはしません。必要がないからです。逆にテントサイトを離れる時にはナイフは車載ボックスなどに収納して他人の目には触れないように気をつけます。
シースナイフは目的に合った物を選べばきっと役立ちます。品質にもよりますが多少の無理(チョッピングやバトニング)もきいてくれるでしょう。そのナイフ、ブレード鋼材に合った適当な手入れを怠らず、切れ味が落ちたら自分で研ぎ直す。そうやって使っていくことが愛用への道です。それでも必要を感じなくなったらスイスアーミーナイフ一本でも買えば損はありませんよ。
ponioでした。
2016年07月04日
B-6君と敗者の弁

キュ、ジャー、ゴシゴシ、、バシャバシャ、、ゴシゴシ、、焚き火のあとは手入れが楽しいなぁ〜って、やっぱりアタシの役目か、、。

昨日、梅雨の晴れ間をついて出かけた佐賀県三瀬村の吉野山キャンプ場で華麗なる普通のデビューを飾った妻の 笑's B-6君(別名・佐藤のB作さん)。アッシが他の作業をしている間に妻がひとりでテキパキと組み立て火起し炭熾し。途中、前面パネルが斜めにはまっていたのを見つけプライヤーで摘んで組み直したくらいで何のコツもなく普通に焚き火から炭火に移行できました。それも妻ひとりで。さすが野生児!さすがB-6さん!

自宅に帰り着き直ぐに焚き火と炭火と焼き物の脂や焦げ付き、雨などでベタベタ状態の B-6さんを台所でゴシゴシと洗ってやりました。新聞紙を敷いてその上に良く水が切れるように立て掛け1〜2時間。やっぱり予想通りグリルプレートとハードロストルに薄っすら錆色の変色有り。これは、、鉄製フライパンやスキレット同様の手入れが要るのだね。グリルプレートはシーズニング要らんのかな?とにかく台所にある油ひきで裏表満遍なく油をひいてあげました。
でもね、、これ油ひくとベタベタになるけど、収納はどないしますの?

すっかり焼きが入ったB-6さん。なかなかええ色になりはって。歪みガタはなし。うーむ、なかぬかの耐久性じゃのう。

油がひかれたグリルプレート。時間が経つとベトつきが出てくるから収納時はビニール袋にでも包もうかしら。

ハードなロストルも所々錆色吐息。
これにも油を引いてあげました。実は昨日のデビュー戦でウチの奥さんこれをチャチャチャと組み立てはしたものの、、撤収間近に炭の後始末をしていたらナント、ロストルが二枚とも本体の底板に密着して乗せられておりました。ハハ〜ん、もしかしたら前後のプレートをはめ込む前にロストルを底に敷いたんじゃないかな?

本来ならロストルは本体内部で宙に浮いた状態でセットされます。これで下方からの空気の取り込みが出来るわけです。
昨日のデビュー戦では特別大きく燃え上がるようなこともなく程々でありながらも十分な熱量と火力で『ええやん!、B-6君』となっておりましたが、ロストルを説明書通りにセットしていたら更に火力が上がったかも、、。

これ焼かれる前のB-6さん。ピッカピカ過ぎて、まるで厨房機器かコンビニのおでんコーナーみたい。サイズ感も我が家の小さなコーヒーカップと比べても如何に小さいかわかります。

『これな〜に〜?』と妻が聞いたのはB-6君のポットサポート(五徳)。昨日は焼き物オンリーだったのでまだ使用されておりません。

これもそのうち煤けて目立たんようになるんやろな。

『あなた〜ハンコと通帳入ってるから失くさないでよ』なぁ〜んて言われそうな事務用品系の収納パウチ。目の付け所が日本的やなぁ〜。

グリルプレートとハードロストルにはオリーブオイルを引きました。燃やしても変な臭いが出ないから。

見れば見るほど不思議なカタチ。いや、これ私の感じ方なので好きな方は気にされないでね。コンビニのおでんコーナーに見えたり馬か牛の胴体にも見える。造り込みは素晴らしく流石は日本製品。ワイルドさには欠けるけど性能は申し分なし。私の持ってるウッドガスストーブと比べても燃料補給に忙しくないし、一気に燃え上がり短時間で燃え尽きる事もない。焚き火台であり、焼き物の調理器具であり、クッカー乗せたり、熱燗つけたり、、【実用的】という言葉が一番よく似合うB-6さんですが、、


問題はこの方たちです。昨日の使い方、使い勝手、妻の満足度からして今後のキャンプ焚き火台選手権はわが家の定番とも言えるキャプテンスタッグのファイアーグリルM かステンレス製ファイアーベース、それに妻のB-6君で決まりかと、、。これまでキャンプからサンデードライブランチまで欠かせなかった存在の SOLO STOVE と WILD STOVE は間違いなくB-6君に取って代わられるでしょう。T_T
でもね、見捨てたり売りに出したりは絶対しないからね、、、と二つの丸っこいストーブを撫で撫でする私です。そうさ!オイラにはソロの時間があるさ!B-6君は妻の手下だからね。二つのストーブの事はこの俺がドンと面倒みる!と敗者の弁。
ponioでした。
2025/03/21 現在 笑's の B-6君はわが家のキャンプに欠かせない道具のひとつになっております。浅い炉が繰り出す炭火の近火が焼き物、煮物、沸々の湯沸かしに最適なのをこれでもか!というくらいB-6君で経験しました。これを持っていかなかったキャンプは何かしら失敗する、遂にジンクスまで生まれました。
2016年07月03日
吉野山キャンプ場にて

ついにこの日がやって参りました。
『アタイのストーブ〜欲しい!』と我が家の火付盗賊改めない方で無類の焚き火好きでもあった(ワテ知らんかった、、)妻が口にしてから苦節1年にもならない7月のとある日曜日、ついに妻の焚き火台に聖火点燈の運びと相成りました。

朝飯腹に詰め込んで車にガソリン食わせて、いつものルートを変えて目移り放題の魅力あるスーパーで新鮮な魚介類と鶏の肝など仕入れていざ行かん!メザシは大好き目指すは吉野山キャンプ場。途中で受付の電話にデイキャンプの申し込みを入れておく。そして、、やって来ました半年ぶりかな?やった〜!本日も無人なり!

避難準備品から時々引っ張り出されるようになった KELTY のタープを張りまして、グッドタイミングでやって来た管理人さんに二人分600万円(関西風)払いまして、、辺りを歩けばピョコンピタンピッタンコ!アマガエルがそこら中に跳ねております。それを狙ってヘビもニョロ〜リとやって来て、オマケに雨雲まで、、。

私がタープやらテーブルやら椅子やらをセッティングしてる間に気がつけばうちの奥さんがチャチャチャと組み立てましたのは本日デビューの笑'sのB-6君。用意していた流木落ち枝をバラバラとぶち込み綿花にアルコール染み込ませて一発点火の天下取り!この間、アタシャ何にも手伝うことなく他の作業に打ち込む姿が逞しい。

今日はデイキャンプで熱源はB-6君のみ。しかもクッカーの類はスノーピークのケトルno1しか持ってきてません。それとてこの暑さでホットドリンク飲むわけもなく目的は無し。バーナーもストームクッカーもない。テントも無いし、薪割りもありまへん。だから道具の展開は至極簡単、直ぐに終わって妻のB-6君の具合をシゲシゲと眺めます。ほほ〜程よい燃え具合じゃのう〜と感心するワタシ。ワイルドストーブやSOLO STOVEみたいな忙しさがないのぉ。ふむふむ。

本当に珍しい事だけど、、ノンアルコールを二缶買ってきまして妻と二人グビグビプハーとやりまして、さっそく焼き物の支度に掛かります。

セットで買ったグリルプレート乗っけてデカい鰆を塩胡椒で、それから鶏のハツ(心臓)、砂肝、ホタテ、最後はチーズ入りのボローニャソーセージを焼き焼きしてハフハフいうてバクバク食ってグビグビ飲んで、『旨いね〜!』と私がほざけば『いいね〜B-6君!』と妻が応える夫婦の絆!

やっとります、やっとります。アタイのB-6君は炭を満載して良い火加減。

すると、、、この日何度目かの気圧傾向インフォメーションのアラームが鳴る。急速な気圧の低下、来るかー?!

来ました〜。パラパラ、ザザーと強弱を繰り返して山間のキャンプ場に雨が降ります。雷は鳴っておらず一先ず安心。いざという時は車に避難です。電波状況がよろしくない中でスマホのXバンドレーダーアプリを開くと南西から小さいが強い雨雲の列が連なって迫りつつあります。

ザザザー!と来たのを良いことにB-6君の中の炭をケトル no1の中に移してB-6君を分解、炭と共に雨の中に晒します。

強い雨が何度か通り過ぎていきます。その雨の止み間に夫婦で片付け機動隊を結成してテキパキと車に積み込みます。最後に雨粒を弾き飛ばして拭き上げ畳んで撤収完了。車に乗り込むとほぼ同時にバラバラバラっと強く大きな雨粒が、、車がキャンプ場を後にする頃にはワイパーも効かないほどの土砂降り降りザエモン。危なかったアル。今度は真上で雷さまが太鼓叩いてらっしゃる。さあ、帰りまひょ!
というわけで、B-6君も無事デビューしまして、あとは妻のB-6君熱がいつまで続くかですね f^_^;)
















