2024年03月22日
記録更新

金曜恒例の射的大会はコロナ明けの2週間ぶりの開催。金曜ロードショーで『魔女の宅急便』が放送されていたので開催が危ぶまれましたが小5の強い念波に動かされて急遽フライパン当ての競技開催となりました。上の写真はアタシの的、キャプテンスタッグの三層ステンレスフライパンです。小5はティファールのパンケーキフライパン(少し大きめ)を射ちます。

映画も終盤に差し掛かった11:00過ぎ、二人並んで一つのフライパンを射つ競技を三度繰り返し遂にこれまでの記録を大幅に更新する39ヒット!

この競技の難しいところはフライパンをぶら下げるのに使っているS字フックがフライパンの向きを左右に変えてしまうことです。

フライパンの右に当たるとフライパンは右を向く、すると右側の射手は射ちやすくなるが左側の射手はフライパンの面が斜めを向いてしまうため吸盤がくっつかないのだ。そこでフライパンが自分の方を向いた射手はここぞとばかりに射ち込みつつ、フライパンが隣の射手の方を向く様に敢えて端っこを射ってフライパンの向きを変えてやるのだ。無駄弾を射ちつつもう一人に正面から射つチャンスを与える、そんなチームプレイが記録を作るのだ。そして同じ場所に当てない努力も必要だ。リファイルと呼ばれる吸盤ダーツは同じ場所に当たると弾き返されてしまう。最悪なのは前に当たってくっついているリファイルを落としてしまうことだ。左右に揺れ動くフライパンの面全体にまんべんなく当てないと良い記録は出せない。マグレ当たりやイレギュラーヒットが出なければ記録は生まれないのである。

次の金曜日に向けて一丁をパワーアップしておく。もう一丁は既に改造済み。これで五分と五分で戦える。ただこの手のオモチャは強度的にバネを強くしたりは出来ないので瞬間的に押し出されるエアーを無駄にしない改良が必要なのだ。分解組み立てに使うのはビクトリノックスのアウトライダー。これの細く長いフィリップスドライバーと缶オープナーが良い仕事をしてくれます。

3丁ある内の残る一丁はサイズも大きく元々パワフルだがシアーの掛かりが甘くコッキングの途中で暴発してしまうため只今調整中。分解時には必ず写メを撮ってパーツの位置関係を記録しておく。

そしてまた金曜がやってきた。仕事の合間にDAISOに立ち寄り吸盤タイプのリファイル30本と今夜の競技に使うカラーボールを仕入れてきた。
2024/03/29 のフライパンシューティングは48発の記録更新。リファイルを30発分増やしたわけだが数が増えれば当たりも増えるとはいかない。先に書いた様に同じ場所に当たれば弾き返されるし、数多く射つほど当たるスペースが無くなってくる。最後はほんの僅かに残る小さなスペースに射ち込まなければならない。それが難しい。計80発ほどのリファイルのうち完全に外したのは10発ほど。これは中央付近は既にリファイルが集弾しており残ったスペースがフライパンの端っこにあることを示している。つまり空いたスペースを狙って外したパターンということだ。残り70発のうち同じ場所に射ち込んでしまい弾き返されたのが20発以上あるのだ。目指せ50発!
2024/05/24
遂に悲願の50発!を大きく超える60発!!の大記録を達成。燃え尽きた、、、。
2024年02月05日
金曜恒例の『遊び』

久しぶりに開催された娘の子(小5)との金曜恒例の射的競技大会。これが開催されるにはいくつか条件がある。先ずは小5の妹(小2)が飯と風呂の後で早々にくたばった(寝た)時に限ること、金曜ロードショーで子供向けの映画などがやっていない、などです。兄の小5がくたばった妹を慎重に覗き込み「寝た」と呟くと即行動開始。奥さんと小5が二人がかりで小2の妹を布団まで搬送する。掛け声は「えっさ!ほっさ!」である。こうなると朝まで妹は起きない。アタシは自室からキャンプ用の折り畳みバケツに入れた遊び道具一式を持ってくる。射的の的となる紙を南向きのベランダのサッシに貼り付ける。全てが粛々と行われる。

ナーフガンは色違いの同じ物。それに吸盤タイプのリファイルを50ほど用意する。簡単なルール説明の後、先ずは練習。

今回はキャプテンスタッグのステンレス三層フライパンやティファールのパンケーキ用フライパンを裏向きに吊るしてそれぞれにナーフピストーレ(勝手に名前つけるな)の癖や射的の感覚を掴むまで練習する。

今回の的はA3の用紙をくり抜いたもので難易度レベル5(わからんわ!)、つまり大きくくり抜かれた的に何発入れるかではなく、リファイルが当たる部分をかなり狭くして当たるか当たらないかを競う的だ。実際にやってみると50発のリファイルを二人で分け分けして25発ずつ射ち『神回』と呼ばれる回でもこのレベル。当たった数でいうと6〜7発が限界だった。左端の最小ポイントに射ち込まれたリファイルに注目!奇跡やー!と一気に盛り上がる。

今回の射的競技大会では『神回!』と呼ばれた回が何度かあった。
狙っても絶対に当たらないレベルのナーフガンでこの結果はまさしく『まぐれ当たり』以外のなんでもない!

これは小5の『神回』。奇跡と呼ばれ二度と起きることはなかった。
左の最も小さな的に見事な『まぐれ当たり』しかもハートマークに5発も当てている。6発目は弾かれ間に挟まっている。

盛り上がった射的競技大会も大詰め。最後のステージではティファールのフライパンを的に50発のナーフダーツ(リファイル)を二人で射ち込む!このフライパンターゲットはそこそこ大きいのだが簡単なのは最初だけ。リファイルが次々と射ち込まれると吸盤がくっ着くスペースが次第に少なくなってくるからだ。まんべんなく散らすのが良いが狙っても当たらないのがナーフガンのオモロいところでもある。更に二人で同じフライパンを射つとS字フックにぶら下げたフライパンが左右に向きを変える。自分が射つ時に斜めになっていると吸盤がくっ着かないことが多いのだ。フライパンの揺れ具合、向きを予測して時には捨て弾を射ち込みフライパンの向きを自分の方に向けたりする。そうやって50発を二人で交互に射ち何発ここに入ったかを見る。ちなみにアタシが1人でこれをやった時は平均20発ほどしかフライパンに残らなかった。当たりは99%だが半数以上は同じ場所に当たって跳ね返されるのだ。同じ感覚でコンスタントに当てられる者ほどこの現象に悩まさせるのだ。

簡単そうで難しい。何度かやってわかったのは50発射っても約20発前後は外す、または同じ場所に当たって弾かれる、そして歯がゆいのは当たってくっ着いたリファイルが突如ポトリと落ちることがあること。原因はリファイルをナーフガンに装填する際に押し込み不足でパワーが足りず吸盤の着きが悪かったり、射手に対してフライパンが斜めを向いていて一時的にくっ着くが直ぐに落ちる、といった具合だ。この競技では小5の『バラつき』加減が不可欠となる。彼の射的のバラつきがフライパン全体にまんべんなくリファイルを射ち込むカギとなるのだ。

そして今回の射的競技大会も大詰め、時刻は23時30分を回っている。小5にとっては限界に近い。そこで、このフライパンターゲットに30発射ち込めたら寝てよし!というルールに変更。小5と二人ソファーに並んで座り目の前のテーブルからリファイルを取っては射ち取っては射つ。1.2.3....6.7.8.9...15.16.17..20..24.25...と二人がかりで射ち込む。そしてここからが一進一退の攻防だ。一発射ち込むと先に射ち込んだリファイルがポトリと落ちる、同じ場所に当たって弾かれる、またはくっ着いたリファイルに当てて落としてしまうを繰り返す。残弾が少なくなって焦り出す。そして最後の一発!をアタシが射つ!恐る恐る二人で当たりの数を数えてみるとジャスト!30個!
「クリアー!! 撤っ収ー!!」
の掛け声と共に小5が散乱したリファイルをかき集めジップロックに入れナーフガンをバケツに戻す、アタシはサッシから紙の的を剥がしフライパンを元の場所に戻して全ての痕跡を消し去る。人呼んで『スイーパー』『掃除人』。このあと、小5は別室の布団へと瞬間移動し瞬間爆睡、それを見届けたアタシはその場に崩れ落ちる。

この『遊び』にはルールがある。射つ瞬間まではトリガーに指は掛けない、まぐれ当たりやスーパーショットが出て歓喜が爆発した時もナーフガンを人に向けない、競技が終わったらナーフガンを触らない、アタシが居ない時にこれで遊ばない、、などルールを徹底している。『遊び』ではあるが事故に繋がる可能性も考えるのが大人の役目だから。このナーフガンの競技を許されているのは小5の彼だけ。中1の兄はつい調子こいてナーフガンを振り回してしまうし、小2の妹は負けず嫌いが昂じて物に当たる。その従兄弟の小2は怖い目にあわない限りまだルールを守れない。これはこれでなかなか難しい遊びだけど小5は大いに盛り上がって毎週楽しみにしている様だ。いつか彼らの父親(娘の旦那たち)と家を代表してナーフピストーレ競技をやろうと計画している。勿論、子供たちは100%観客である。飛び入りは娘たち。子供は「やりたい!やりたい!」と騒ぐだろうがそこは大人の世界だからやらせない。我慢させるのも修行なのだ。
2024/02/09
また金曜がやってきて小5との息詰まる戦いが繰り広げられた。ラストはティファールのフライパンに先週以上(30発以上)のリファイルを射ち込んだら撤収という共同作業。結果は二度目のチャレンジで36発を達成。「撤収ーー!!!」おやすみ。
2023年05月07日
危なかったので

ヤバかったス、これ。『倒木寸前』の朽木です。タープ設営の際に周囲の松にラインを伸ばしていて見つけました。わが家のサイトの正面右側、FIRE PIT の直ぐ右に立っていた枯れ松です。高さは7メートルほどで上部は完全に折れて枝葉もない朽木でした。

手で少し押してやると幹の最下部がミシミシと解れる音がしました。更に根本の土が動くのが確認されました。これが枝葉が広がりもっと高さのある木なら安全のためにサイトの引っ越しをしていたかもしれません。枝葉を広げた高い木は風の影響を受けるからです。しかしこの朽木は枝も葉もなく歪に曲がった丸太の様な姿で風の影響は受けないと判断しました。ただ、このまま倒れるとデッキの正面をかすめる感じで危険と判断。直ぐ隣に生えている太く大きな松に強度の高いロープを渡して上下2箇所を固定しておきました。

撤収日、全ての荷物をリアカーに積んで駐車場に向かう途中でキャンプ場を管理されるスタッフさんに声をかけ倒木の可能性があることを伝えました。ただ、離れた場所から「あそこの、あの木」と指差しても周りは松林、後でどの木か探すうちに事故でも起こったらと考え元いたサイトまでスタッフさんを案内しました。現場に着くとこれは『危険』と判断したスタッフさんが「倒しておきましょう」とその朽木に手をかけ揺らすように押すと例のミシミシという解れるような音と共に幹の最下部が折れて倒れました。ズゴォーん!と倒れた拍子にその朽木は三つに折れてしまいました。根も幹も腐った朽木でしたがドスン!という音からかなりの重量があったと思われます。倒れた方向は予想通りデッキをかすめておりました。
あの時、キャンプ場のスタッフさんが直ぐに確認してくれたのが良かったと思います。「あとで見ておきまーす」では危機感ないですもんね。ワタシも安心して帰れました。ありがとうごさいました。
2021年03月06日
キャンプ場での出来事

これほどまでに人と棲み分けができるキャンプ場をアタシは知らない。これまでにもキャンプ場でアタシひとり、わが家のみということはあったがそれは単に利用した季節や日時の影響、または利用客そのものがたまたま居なかった時に過ぎない。そのいずれもキャンプ場のフィールド自体は決して大きくはなく他に利用する人があればほぼ確実に視野に入ることになる。今回、利用させて頂いたのは南小国町のあの、キャンプ場さんです。

有名ですね、とにかく広くて自然の景観が素晴らしい、必要最低限の設備、ソロでもウチのような夫婦二人でも満喫(ある意味)できる。ヒロシさんも番組で訪れていましたね。

霜ではなく雪が降ったようです。




この風景を探していたんです。冬枯れの草地と青空、ホンマに美しかった!青々とした木立や生い茂る草原よりもアタシはこんな風景が大好きなのです。




だーれもいやしません。管理人さんの話ではこの日は5組くらいだそうで一度腰を落ち着ければ他の方と顔を合わす可能性はかなり低い状況でした。はじめはサイト選択のために車と徒歩であれこれ動き回るのですがそれも途中で諦めました。そう!キリがないのです。何処もかしこもヨカとこばかりで。結局、日当たりよく広々としていて適当な木立があり開放的な場所に落ち着きました。結局、そこは撤収までわが家のみの利用でした。見る人が見れば「あそこね!」とわかるサイトです。

広いサイトにわが家だけ。あれこれ迷って決めた場所にアタシがシートを敷くと、奥さんが Quechua のポップちゃんをビロ〜んと広げます。あとはアタシが外回りのペグダウンと窓の開放、奥さんがマットを敷き詰め自分の羽布団やら毛布、アタシのシュラフなどを持ち込み恒例の巣作りが始まります。

一段落してキャンプ場の散策に出かけましたがあまりに広く30分ほどで帰ってきました。お昼ご飯はいつもの様にカップラーメン。さすがの奥さんも天気の良い昼間から焚き火してとは言いません。ストーブでお湯を沸かしてお終い。これでいいのだ!

前回(昨年初冬)デビューした LOGOS のチェアーはこれで二度目の使用だけど、まるで何年も使ってきたかの様に違和感なく腰かけられてしかも疲れない。

本来、雨が降らないなら冬場のキャンプではタープは張りません。冬の陽射しをたくさん浴びたいからです。しかし、今回は受付で少し高いタープ代を支払っていたので仕方なく張った わけです。目的は風除け。予報などでこの日の風向きを調べて張りましたが山の窪地 は風が巻くので100%の風除けにはなりません。今回は尻尾を内側に畳む張り方でメインのラインは正面の樹から、メインポールの他にポールを2本使って空間を広く取りました。

手前はいつものコールマン銀の皿ことファイアーディスク。今回は珍しく直火OKなフィールドでしたがやはり冬枯れの草地が近いので焚き火台を使いました。管理人のおじさんもこの時期は火事が怖いと言ってたからです。コールマンの焚き火台は脚を畳んで石囲いしました。低い位置で火を焚いた方が足元から温まるからです。この日も翌日も最低気温は零下の予報でした。奥のタープ、内側には裏面防水の多目的シートを敷いて本来はここにシートチェアを置きのんびり夕陽を浴びる予定でしたが、、この後予期せぬ出来事に飛び込むことになります。

ポカポカ陽気の昼間は太陽サンサンでソーラー充電していたスマホもあっという間に100%。翌日は曇りでまったく役に立たず。

さあ今回漸くデビューの七輪二号。中止にした年越しキャンプでデビューする予定でした。使うはオガ炭、めっぽう火がつきにくいが一旦着くとこれが七輪と相まって最高の熱源となりにけり。鳥もも肉は切らずに塊で串焼きに。アスパラと自家製干し芋も旨い美味い!七輪の火力調節は開閉式の風口と焼き面までの高さ調整で行う。今回はオガ炭を多く入れる為に金属製のフードを乗せて遠火に。風口を風上に向けて開閉調整、やっぱり焼き物は七輪に限る!

そして夕食は鍋。これも七輪で煮込む。使うは今回がデビュー戦となった《やぎオジサンのフライパン》。???やぎオジサン?

この鍋、本当はフライパンとして販売されています。正式には FIRE BOX HAA フライパン Large と言います。と、ここまで書くと『わかった!』という方もいらっしゃることでしょう。『やぎオジサン』とは FIRE BOX stove の開発者で同社のオーナーでもある Steve Despain さんのこと。同社の動画には彼と彼のファミリー、その中に2匹のワンコと2頭のヤギが登場します。うちの奥さんはスティーブのことを『やぎオジサン』と呼び、彼らのキャンプを『やぎキャンプ』と呼んでいます。このフライパンはハードアノダイズド加工されたアルミ製で購入者は自分で植物油を薄く塗ってオーブンなどで空焼きするシーズニングを施してやらないといけません。

数度のシーズニングの後はこのような色艶になります。コーヒー色です。表面はガラス質然としており油の浸透も良く不思議な感じ。軽さは完全にアルミのフライパンです。

陽が西に傾き出します。手前で大きく炎をあげているのは SOTO SOD-372。アタシにとってはなかなかの曲者ストーブです。今回は湯たんぽに使う約2.5リットルのお湯を二人分計5リットルのお湯を沸かす役目だけで連れてこられました。そんなもん焚き火台で沸かせばええやん!と考えがちですが、焚き火台は暖を取るために大きな薪をそのまま燃やしています。ケトルは吊り下げられますが容量が足りません。そこで二つのクッカー( GSI デュアリスト1.8L、ソロイスト1.1L )を用意して立て続けに沸かしました。

最初にデュアリスト1.8L で約1.5〜6L、次にソロイスト1.1L で約900〜1Lのお湯を沸かして湯たんぽに注ぎました。これを二人分、面倒くさそうに思えますが《湯たんぽ》の有り難さをしみじみと感じた早春のキャンプでした。

夕食は『誰がこんだけ食うねん!』ってくらいのキムチ鍋。さあ!食うでー!!とこのあたりまではいつもの野営風景でしたが、、この後アタシたち夫婦は思わぬ出会いと寒さの中汗だくの奮闘で夕食はお預けとなります。

それはまだ陽が傾き出す前から聞こえていました。なにやら掛け声の様ですが遠くであり外国語の様にも聞こえました。管理人さんの話では本日は5組、わが家と時同じくしてサイト探しをしていた方がひと組目(この方も後で深く関わります)、わが家よりも下のサイトとさらにその奥に陣取った2組、ウチと残るひと組は、、その残るひと組との出会いが今回のキャンプを印象づける出来事へと発展するのです、、、さあはじまり始まり〜。

その声はわが家がテントを張ったサイトの上から聞こえました。よく見ると冬枯れの草地に白い車輛の一部が見えました。最初は何かの工事車輛かと思いました。キャンプ場は昨年の豪雨で大きな被害が出ていたからです。それにしては言葉が、、わからない、
夕食の前、遠く離れたトイレに車で行く途中のこと、例の白い車輛が上の草地にありました。キャンピングカーでした。周りにはいかにも学生風な若者が数人、どうやら車が草地か泥濘みにはまって抜け出せない様子でした。

アタシがトイレに駆け込む間に奥さんが先程の現場に戻っていました。トイレを済ませアタシが駆けつけると奥さんから「やっぱり外人さんよ、中国の留学生みたい」との報告。見てみるとキャンピングカーの後輪が草地の泥濘みにはまっております。しかもそこは傾斜地で後数メートル下がれば車ごと下のサイトに転落という状況でした。ヤバっ!
しゃーないなぁ、、手伝うしかなさそうやなぁ、、と車でわが家が陣取ったサイトまで下りキャンプ道具の中からランタン、パラコード、薪、アックスなど必要だと思われる道具を持って再び駆けつけました。
現場に戻り焚き火台に使うはずの大きな薪を数本後輪の前に差し込んで動かしてみることにしました。日本語、英語おり混ぜ「 1.2の3ー!!」一人が運転、残りは全員で後ろから押しますがタイヤは煙を発し今にも枯れ草に火がつきそうです。ストッープ!
次にわが家の車で牽引することになりましたがロープもフックもありません。持ってきた550パラコードを二重にして結び今度は「せぇーーーの!」で2台同時にエンジンをふかし、、ウォーリャー!!と押しまくると数十センチではありますが前進、しかし今度はわが家の車の方が斜面にかかり前輪がスリップを始めました。そんな中、お向かいのサイトでソロキャンプしていた方が助っ人に来てくれます。その方は一人のんびりとお酒を飲まれた後だったらしく車は出せないと賢明な判断されていたそうです。しかし、如何ともし難い状況に駆けつけてくれ(助かりました!)うちの車とその方の車(どちらも軽)で引っ張ることに、、。しかし奮闘虚しくデカいキャンピングカーは泥濘みから脱出できません。550パラコードも片方がブチ切れました。あたりは真っ暗。ナイフでも切れない硬い枯れ草を押し分けヘッドランプで照らしながら悪戦苦闘しますが、、結局その夜は留学生たちが借りてきたレンタカー会社を通じてJAFを呼ぶしかないとなり、留学生に代わって助っ人に入ってくれたキャンパーの方が電話で説明してくれました。あの時、トラロープの一巻でもあったら窪地の上から牽引できたでしょう。また大きな四駆でもいれば。タイヤは深くめり込んでおりました。しかも後は下り斜面です。タイヤがスリップするならと薪を埋め込みましたが駄目、次に捨てる予定だった大きな布を差し込みましたがこれも駄目、最後はアタシのカーハートのエプロンならと、、しかしそれも駄目でした。留学生たちは申し訳なさそうに荷物を車外におろし力を合わせますが、、見るからに非力そうで、、。
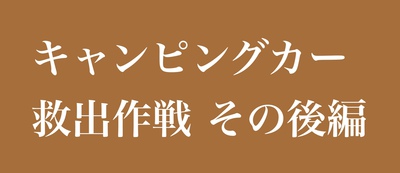
それが解決したのは翌朝のことです。午前9時頃から上の方で掛け声とエンジンを蒸す音が始まりました。JAFさん来たか!と現場に駆けつけると、、管理人さんと従業員のお兄さんが車で牽引しようとしていました。今度はトラロープがガッチリ結んであります。聞くと管理人さんの車は小型ながら四駆だそうで、、これはいけるかもと作戦開始!しかしまたもや激しく煙をあげタイヤの焼ける匂いが鼻をつきます。「ストップ!ストップ!」とアタシが叫び管理人さんも枯れ草への延焼を心配されて用意していたペットボトルの水をかける。再度、管理棟から持ってきた薪を埋め込み試してみますが今度はそれを乗り越えられません。とその時、昨夜は暗くて見えなかった石ころが目にとまります。直火をする際に使う石囲いの石です。『石を埋めてみますか!』と管理人さんと二人で話し合い、従業員のお兄さんが持ってきた石をスリップしている後輪の前に埋め込みます。差し込まれていた板や薪を抜いてかわりに片手で持てる大きな石やコンクリの塊を泥濘みに埋め込みました。これならタイヤが食い込みそうです。そして管理人さんが牽引、従業員の方がキャンピングカーを運転、残りは全員で後ろから押します。「いくよー!!」「せぇーのぉーー!」「うぉりゃーーーー!」
『いったぁー!!』
昨夕から斜面の泥濘みにタイヤを取られ身動きできなかったキャンピングカーは漸く脱出できました。ついでにキャンピングカーが入り込んだ小さな窪地のサイトからも牽引で引き出して作戦終了。歓喜の声をよそに管理人さんとアタシで枯れ草に水撒きして万が一の山野火災に備えました。やれやれ〜。それにしてもあんな大きな車をあんな小さな窪地のサイトに、、もっと広々とした場所はいくらでもあるのに、、管理人さんも苦笑い。小さな窪地、下り斜面、緩い土壌、硬い枯れ草、そして夜という最悪の条件でした。
砂利道を降ってわが家が陣取ったサイトに戻ると「出られた?』と奥さん。それからあらためてゆっくり朝メシを作りそれを食ってお昼過ぎまで掛かって撤収。どっと疲れが込み上げ睡魔と戦いつつ帰った思い出深きキャンプとなりました。

Spyderco と 千切れた550パラコード
大きなキャンピングカーを小さなわが家の軽(一応ターボ)で牽引する際にタープのラインとして持っていた 550 パラコードを二重にして使いました。耐荷重量:約250kgのパラコードを二重にしましたが牽引車の軽は窪地斜面で前輪がスリップ、助っ人に入ってくれたソロキャンパーの方の軽にもパラコードを繋げようとしましたが長さが足りません。車を寄せてなんとか繋ぎましたが3台同時のアクセルワークはタイミングが難しく、結果的に片方のパラコードが切れてしまいました。車間を縮めてパラコードを緩めるとピント張った瞬間に切れる可能性があり、また後ろのキャンピングカーが牽引車に衝突する可能性もあります。パラコードは結び目を解こうにも重い車両で引っ張りあったため固く締まってなかなか解けません。仕方なく出した Spyderco で軽の牽引用ループに固く締まったパラコードの塊を切断しました。
この Spyderco は CPM-S110V というお硬い鋼材で切れ味は抜の群です。これが同じ Spyderco でも DELICA なら、、難しかったかもです。千切れたパラコードを見ると結び目やコードの途中が熱で一部溶けていました。もっと長さがあって三重四重に出来ていたらキャンピングカーでも牽引できたでしょうね。

lionsteel M5 と二度の人助け
今回は自然豊かなフィールドでの野営となるのでいつもより少しばかりタフなキレモノを持っていった。lionsteel の M5 はお硬い鋼材と洒落っ気が融合したキレモノだがこのキレモノを持っていくと何故だか人を助けることに遭遇する。実をいうと今回もそんなことを予想したいた。数年前の一泊キャンプの際は夜遅くに高校生のグループがやってきて焚き火にあたって電気ブランをチビチビやっていたアタシに、「あ、あの、、すみません、、テントの立て方がわからなくて、、」と助けを求められた。夜も遅い時間にライトの一つも持たずスマホや携帯のライトだけで初めてのテントを立てる無鉄砲さと少年らしい考えの浅さに「う、うん、ええよ」と引き受け少し離れたサイトにランタンとフラッシュライトを持って出向くとそれはメチャクチャな立て方で四苦八苦している友人たちが立ち尽くしていた。ポールは一本、ペグも数本足りない。しかもテントも立っていないのにペグを先に打ちつけている。アタシは拾い集めていた焚き付けの枝から適当に数本選んでこの M5 で削り木ペグを作ってこれでその木ペグを打ち込んだ。ポールはどうしようもなかったが、なんとかテントを張ることができた。翌日、管理人から聞いた話では、これから学生だけでキャンプに行くので宜しくお願いしますと母親から連絡が入っていたとか、、。アタシ、管理人じゃないけど、、lionsteel は人助けに繋がるキレモノなのかもしれない。《二度あることは三度ある》さあて、お次は何かな?



夜の救出劇の最中、長さが足りなくなったパラコードを取りにサイトに戻ったアタシは真っ暗なサイトにランタン達を灯して現場に戻りました。その夜の救出が失敗して奥さんと二人でサイトに戻ると寒さの中で LED ランタンはショボい光を放っておりケロシンランタンは真っ黒に煤けていた。点火後に芯の調整をしていったつもりなのだが、、芯の出し過ぎだった様だ。やれやれ、、夜奥さんがテントに潜り込んだ後でひとりフュアハンドランタンからホヤを取り出し磨いて組み立てた。

夜、奥さんが湯たんぽと眠りについた頃アタシはようやく焚き火と向かい合えた。今頃、あの留学生たちは泥濘みにはまったキャンピングカーの中で眠っているだろう。タイヤの後ろには車止めのかわりに大きめの石を置いておく様に言っておいたが、、。それにしてもここは生き物の気配がないなぁ、なんて静かなキャンプ場なのだろう、、などと考えながら朧月を眺めて早春の夜。

湯たんぽでポカポカの夜を過ごし朝は6時にテントを出た。あのキャンピングカーは昨夜と同じ所に見えていた。真っ白になった焚き火台と七輪の灰を始末する際にその中からまだ息のある熾を見つけてそれを全て七輪に移す。風口を全開にするとすぐに息を吹き返す。ここが炭の素晴らしさよのぉ。あとは新たに炭を熾し朝食の準備をする。

昨夜の燃え残りの熾に FIRE BOX stove で熾したオガ炭を加えて七輪が再稼働。本来、撤収の朝は七輪を使わない慣わし(一度火を入れるとなかなか冷めないので)。しかし、このキャンプ場はアウトの時間をフリーとしているので撤収は昼飯を食ってからと考え例外的に七輪に火を入れた。奥さんが起き出す前にやる湯沸かしも七輪の仕事。焚き火台でやらないのはクッカーが汚れるからです。七輪は殆ど汚れない。

『やぎオジサン』のフライパンで定番すぎる朝食。この後、バターを溶かしてライ麦パンを焼いてみたが香ばしくカリカリに焼けて実に美味かったアルよ。卵は双子でした。

*髭を剃るためお湯を沸かす。
本当はタープの下でゆっくり休んで帰りたかったが雨の予報が予定より早くなり、撤収を始める。焚き火台と七輪の火の始末とクールダウン、細かな道具の片付けをやっている間に奥さんが布団やマット、テントを手際よく畳んでくれる。大方の片付けが終わるとタープの下、荷物の夜露避けに使った使い古しのオールウェザーブランケットを敷いてそこでごろ寝した。あのシーンだけを見た人は「なんとチープなキャンプだろー、」と思ったに違いない。奥さんがごろ寝をしている間にアタシはお湯を沸かして髭を剃る。マスクで隠れるからと言われそうだが気持ちの問題。さっぱりしたいのだ。
帰り際にゴミを片付け指定の場所へ。管理人のオジサンと今朝方のキャンピングカー救出のことなど楽しく話をしてこの野趣あふれるキャンプ場を後にしました、とさ。
翌日、全身筋肉痛也!
2020年12月25日
キャンプ中止指令

8年続いた年越しキャンプは今回ついに中止と決定しました。奥さんはどこか近場ででもとそんな感じでしたが、あたしの政治的決断(どこが!)で『えぇーい!やめじゃ!やめじゃー!』となりにけり。
未知のウイルスに対する第一波の時の不安、第二波の拡大をはるかに上回る今回のコロナ禍の中、公的ではないが高齢者に関わる仕事をしているアタシにとっても日々知らず知らずにストレスを抱えているのは感じています。そんな日常を離れせめてキャンプでもと考えていましたが、日々更新される悪い記録と止まる気配すらない感染拡大に九州一の感染者数を出している福岡県民としては一桁少ない感染者数の他県に足を伸ばすことに引け目を感じていました。空いたキャンプ場の片隅で人と接触しなければ、、という考えも脳裏をかすめましたが今時空いているキャンプ場などあるわけなく、最も近場のキャンプ場も最新の情報では年末年始はいっぱいだそうで、、、二年前のガラガラ状態が夢のような現状です。
そのキャンプ場で唯一の年越しキャンプをしていたウチら夫婦に管理人のおばちゃんが笑いながら言った『あんたら好きね〜』という言葉も過去の話。餅や漬け物を差し入れにきてくれた管理人のおばちゃんもこの年末年始は満員御礼で忙しかろう。
というわけで、キャンプモードはガチャ!と音を立てて切り替わり日々召集をかけられ集められたキャンプ道具たちからは極寒の中に連れ出されることなく安堵の声があがっております。キャンプに向けた食材などの買い出しも中止、リストは廃棄。こうなると意外に早いアタシ自身の切り替わり。チェーィンジ!スイッチオン!ワン!ツー!スリー!(わかりますか〜?)
しかし、不完全な良心回路のせいで時折ギルの笛がアタシを狂わすのです、、。わかんねぇだろうなぁ〜。
ponio

2020/12/25
いつも利用させていただいている熊本のキャンプ場に電話を入れて自己判断で移動自粛することを告げキャンセルを申し出ました。ちなみに、これまで3回ほど年越しキャンプをしてきた佐賀県のキャンプ場は年末年始ほとんど埋まっているとか、、やっぱり。『空いてますよ、』と言われましたが元々人の多いキャンプ場は避けてきたので、遂にあそこもか、、と一気にキャンプ熱が冷めて今は自宅のキッチンリビングをキャンプ仕様に変えるべく腰に手を当て頭を捻るアタシです。
2020年10月11日
キャンプよりデイ
キャンプより DAYが楽し
最近、ふとキャンプよりデイ(ハイク・ドライブ・キャンプ)の方が楽しく思えてきた。わが家の場合、キャンプは年に数度。そのほとんどが一泊で年末年始だけは連泊することにしている。対するデイキャンプやデイハイク、サンデードライブは月に3〜4回でほぼ毎週だ。キャンプといえばテントにタープに椅子にテーブル、焚き火台。一泊で三度の食事を作り連泊ではその倍となる。

持って行く道具やファニチャー類もひと頃に比べるとかなり絞ったとはいえ軽に積み込めるギリギリだ。奥さんと二人キャンプをするようになって10年ほど、まだまだ荷物は多いと感じてる。そして、この何年か感じてきたのは一泊キャンプでの《追われる》感覚だ。《追われる》と言っても警察や殺し屋に追われるのではない(わかっとる!)受験勉強に追われるのでも原稿の締め切りに追われるのでもない(それもわかる!)。では何に《追われる》のか?それは 【やること】と【時間】。
【やること】も【時間】に追われることもそれをしないのがキャンプの自由な時間ではないか!と言いたいところだが、、、。実のところ《追われる》感覚が強いのだ、あたしは。
【やること】とは、設営とセッティング、食事と片付け、そして撤収のこと。どれも必要なことなのだが《追われる》のだ。

*ogawa のテントの頃は設営に時間かかったなぁ、、。
設営といっても大したことはない。テントは Quechua のポップちゃんだし、ファニチャーだってリクライニングチェアが二脚、テーブルが二つ、フォールディングベンチくらいだ。一方セッティングは意外と気をつかう。風が強い場所ではテントの向きやタープの張り方、焚き火台の置き場所まで考え抜く。下手すりゃ火の粉でテントやタープに穴が開くし、灰にまみれて飯を食うことになるからだ。かと言ってあまり離しすぎても動線が長くなる。

わが家ではかつて一つのテーブルで調理をして飯を食っていたがテーブルの上が調理用具でいっぱいになって盛り付けた器の置き場所もなかった。そこでテーブルを二つにして片方で調理、もう片方は食卓とした。


ただ、調理用のテーブルにはストーブ、コンロをはじめクッカー他調理用品をどこから取ってどこへ置くかまで考えて使い易く配置しないと直ぐに物で溢れかえる(奥さんの仕業)からそこもセッティング。奥さんの楽しみの一つ、焚き火も焚き火台の置き場所、薪や焚きつけ、着火道具の準備が必要。これらセッティングに追われるのである。

以前、娘一家とデイをやっ時に『あれどこ?』『どれ使えばいいの?』『これどうするの?』と質問攻めにあってバタバタした経験から誰が見てもどこに何があるかわかるようにしておくのがアタシの役目となりました。
さて、もう一つの《追われる》は【時間】。それは飯の時間と撤収の時間のこと。撤収はわかるが、飯の時間とは、、?つまり【日没前に飯を食らう】アタシの習慣にまつわる時間のこと。キャンプ以外の日常生活では夏を除いて晩飯を食うのは暗くなってからだ。午後7時から8時が多い。日常では全く問題ない。煌々たる明かりの下で暮らしているからだ。しかし、キャンプでは日没後はランタンの明かりの下で調理や食事をする。焚き火に向かい旨い飯を食うなんてのはわが家のキャンプシーンには無い。暗くなる前に作り食らう、これがわが家の掟なのです。

それはアタシがソロの頃から続けてきた野営の習慣であり、当時 UCO のキャンドルランタンだけでバックパッキングして歩いていた名残なのである。つまり、暗いと火が通っているかいないかわからない、見た目に旨そうに見えない、魚の骨が見えないなどなど如何に普段の生活が明かりと視覚に頼ったものなのか痛感させられたからだ。

*陽が傾き出した頃。わが家のキャンプ夕飯は明るいうちに済ますのです。
わが家のキャンプでは夕方には調理を済ませ日没前に飯を食う。これはうちの奥さんの習慣にも関係する。うちの奥さんはキャンプでは夕飯済んで片付けが終わると歯を磨いていそいそと寝床に潜り込む。寒い季節にキャンプするのはわが家の家訓だが寒いとそれだけ奥さんの巣篭もりも早くなるのだ。暖かな巣の中でぬくぬくと過ごすためだ。寝入る時間も普段よりかなり早い。晩秋から冬のキャンプでは現地到着から日没までせいぜい6〜7時間だ。【やること】に追われるのだ。

撤収時間もわが家では厳守だ。後に来るキャンパーに迷惑をかけたくないし、近くで待たれると落ち着かないからだ。これは至って普通の感覚だと思う。しかし、その撤収は朝早くから始めないと間に合わないのである。のんびり寝ていたのでは到底間に合わない。だから、一泊キャンプでは日の出と共に起き出し小さな火を起こし朝飯の支度を始める。奥さんは全てが整った時点で狙いすましたかのように起き出してくる。また、わが家の場合、設営より撤収にかかる時間が圧倒的に多いのだ。何故か?それは始末と分別と片付け、そして車への積載順があるからだ。
この《追われる》感覚とその反発で焚き火の世話をする時間が長くなる。結局、終わってみれば何処となく記憶に残らないキャンプとなってしまってる。【やること】に追われてバタバタした記憶、焚き火の世話をした記憶、他はあまり記憶に残らない。これはイカン!

こんな《追われる》感覚を解消するために以前からあれこれ変えてきた。ポップアップテントもその一つだ。これのお陰で設営の時間と手間が大幅に減った。道具も減らした。料理も簡単に済むものにしている。残るはセッティングと撤収。これも目処がついたので次回から試験的にやってみようと考えてる。
一方〜、

デイは気楽だなぁ〜簡単だなぁ〜!
デイキャンプの場合、キャンプ場に入るのが午前中、飯は昼の一回のみ。帰りは夕方、車が混み合う時間の前にさっさと撤収。

大きな道具といえば奥さんの昼寝に使うテントくらい。殆どの場合、ogawa の Stacy-ST のインナーのみを持って行く。組み立て簡単、グラウンドシートのみでペグダウンもしない。これに椅子二脚とテーブル、焚き火台。



更にライトな道具立ての時もある。椅子は一脚、あとはフォールディングベンチ、焚き火台は持たずにストームクッカーと小さなウッドストーブということもある。




晩秋から初冬、春先など虫の少ない時期は Quechua のシェルターに敷物とタープという組み合わせで行くこともある。

わが家のデイハイクは【歩き】と自転車の組み合わせだ。荷物は最小、二人ともバックパックに必要なものを詰め、食糧や敷物、シェルターなどは自転車のカゴに入れて運ぶ。近くのスーパーで買い出しして調理などはせずストーブバーナーで湯を沸かすくらい。


ただし、器とカトラリー、キレモノと小さなカッティングボードくらいは持って行く。加えて一手間。

サンデードライブと称する野外ランチは車での移動とデイキャンプより少ない道具立てとデイハイクよりちょっとだけ手間のかかる(といっても簡単な)調理と飯が付く。焚き火やウッドストーブは使えないことが多いので殆どの場合、ストームクッカーとその仲間たちで間に合わせる。移動が車でも車を横付けできるとは限らないので大きな物は持って行かない。食糧は地産地消のお店で新鮮なものを安く買って簡単な調理で頂くことが多い。炭火や焚き火での調理はしないので焼き物、煮物はやらない。


*お弁当を持って行くのも良し、途中で買い出しして簡単な調理で食うも良し、コーヒーはドリップパックでもスティックでも良し。カップ麺には一品加えて尚良し。拘りを捨てすぎず軽く拘って良し。デイの気楽さよのぉ。

時にはスキレットで魚を焼いたり。

軽のハッチを上げてベンチを置いてカップ麺。こんなライトな時もあり。

太陽の位置と車の向きを考えてやれば軽のハッチは立派な日除けになる。バックシートを倒して平面にしてやればここが奥さんのお座敷に。ここで牢名主の如く君臨するのだ。

デイはロケーションが良ければ海でも山でもどこでも良いのだ。

キャンプにしろハイクにしろドライブにしろデイは道具立てとセッティングが至って簡単。一泊キャンプの様に《追われる》感が全くない。ただ、目的は必要です。うちの場合だいたい言い出しっぺは奥さんで、『あそこに行こうよ』に始まり『火を起こしてあれ焼いて、、』となり『あれも食べたいね〜』となる。ただ単に風景や町並みを楽しむためだけに出掛けることもある。そんな時も『ついでに外でご飯食べて、、』がもれなく付いてくる。外でご飯とは【お金を払ってお店で外食する】ではなく、どこかで野外ランチという意。それによって持ち出す道具も変わります。キャンプでもデイでも準備委員会総合幕僚長兼買い出し係兼積み込み担当兼忘れ物して叱られる係のアタシの出番です。アタシが全て用意するのでアタシがセッティングしないと何も始まりません。一泊キャンプの場合ここが《追われる》感覚にも繋がるのですがね。

先日のサンデードライブは着いて早々に奥さんが娘と調理を始めてしまい(セッティングが終わる前に)あちこちから道具や食品を引っ張り出して使って、、気がつきゃ足の踏み場もない状態に (^_^;) その回だけはちょっとだけ《追われる》感ありました。まあ、そんなことは稀でほぼ毎回楽ちんで小さな時間をたっぷり使えて、あちこち散策して収穫して《追われる》感の無い時間を過ごせます。
次回は CAMP Nov.2020 おそらく一泊。セッティングと撤収を工夫して《追われない》キャンプにしたいと決意を新たに明日に向かって漕ぎ出そうとパドルを忘れて手漕ぎするアタシです。
最近、ふとキャンプよりデイ(ハイク・ドライブ・キャンプ)の方が楽しく思えてきた。わが家の場合、キャンプは年に数度。そのほとんどが一泊で年末年始だけは連泊することにしている。対するデイキャンプやデイハイク、サンデードライブは月に3〜4回でほぼ毎週だ。キャンプといえばテントにタープに椅子にテーブル、焚き火台。一泊で三度の食事を作り連泊ではその倍となる。

持って行く道具やファニチャー類もひと頃に比べるとかなり絞ったとはいえ軽に積み込めるギリギリだ。奥さんと二人キャンプをするようになって10年ほど、まだまだ荷物は多いと感じてる。そして、この何年か感じてきたのは一泊キャンプでの《追われる》感覚だ。《追われる》と言っても警察や殺し屋に追われるのではない(わかっとる!)受験勉強に追われるのでも原稿の締め切りに追われるのでもない(それもわかる!)。では何に《追われる》のか?それは 【やること】と【時間】。
【やること】も【時間】に追われることもそれをしないのがキャンプの自由な時間ではないか!と言いたいところだが、、、。実のところ《追われる》感覚が強いのだ、あたしは。
【やること】とは、設営とセッティング、食事と片付け、そして撤収のこと。どれも必要なことなのだが《追われる》のだ。

*ogawa のテントの頃は設営に時間かかったなぁ、、。
設営といっても大したことはない。テントは Quechua のポップちゃんだし、ファニチャーだってリクライニングチェアが二脚、テーブルが二つ、フォールディングベンチくらいだ。一方セッティングは意外と気をつかう。風が強い場所ではテントの向きやタープの張り方、焚き火台の置き場所まで考え抜く。下手すりゃ火の粉でテントやタープに穴が開くし、灰にまみれて飯を食うことになるからだ。かと言ってあまり離しすぎても動線が長くなる。

わが家ではかつて一つのテーブルで調理をして飯を食っていたがテーブルの上が調理用具でいっぱいになって盛り付けた器の置き場所もなかった。そこでテーブルを二つにして片方で調理、もう片方は食卓とした。


ただ、調理用のテーブルにはストーブ、コンロをはじめクッカー他調理用品をどこから取ってどこへ置くかまで考えて使い易く配置しないと直ぐに物で溢れかえる(奥さんの仕業)からそこもセッティング。奥さんの楽しみの一つ、焚き火も焚き火台の置き場所、薪や焚きつけ、着火道具の準備が必要。これらセッティングに追われるのである。

以前、娘一家とデイをやっ時に『あれどこ?』『どれ使えばいいの?』『これどうするの?』と質問攻めにあってバタバタした経験から誰が見てもどこに何があるかわかるようにしておくのがアタシの役目となりました。
さて、もう一つの《追われる》は【時間】。それは飯の時間と撤収の時間のこと。撤収はわかるが、飯の時間とは、、?つまり【日没前に飯を食らう】アタシの習慣にまつわる時間のこと。キャンプ以外の日常生活では夏を除いて晩飯を食うのは暗くなってからだ。午後7時から8時が多い。日常では全く問題ない。煌々たる明かりの下で暮らしているからだ。しかし、キャンプでは日没後はランタンの明かりの下で調理や食事をする。焚き火に向かい旨い飯を食うなんてのはわが家のキャンプシーンには無い。暗くなる前に作り食らう、これがわが家の掟なのです。

それはアタシがソロの頃から続けてきた野営の習慣であり、当時 UCO のキャンドルランタンだけでバックパッキングして歩いていた名残なのである。つまり、暗いと火が通っているかいないかわからない、見た目に旨そうに見えない、魚の骨が見えないなどなど如何に普段の生活が明かりと視覚に頼ったものなのか痛感させられたからだ。

*陽が傾き出した頃。わが家のキャンプ夕飯は明るいうちに済ますのです。
わが家のキャンプでは夕方には調理を済ませ日没前に飯を食う。これはうちの奥さんの習慣にも関係する。うちの奥さんはキャンプでは夕飯済んで片付けが終わると歯を磨いていそいそと寝床に潜り込む。寒い季節にキャンプするのはわが家の家訓だが寒いとそれだけ奥さんの巣篭もりも早くなるのだ。暖かな巣の中でぬくぬくと過ごすためだ。寝入る時間も普段よりかなり早い。晩秋から冬のキャンプでは現地到着から日没までせいぜい6〜7時間だ。【やること】に追われるのだ。

撤収時間もわが家では厳守だ。後に来るキャンパーに迷惑をかけたくないし、近くで待たれると落ち着かないからだ。これは至って普通の感覚だと思う。しかし、その撤収は朝早くから始めないと間に合わないのである。のんびり寝ていたのでは到底間に合わない。だから、一泊キャンプでは日の出と共に起き出し小さな火を起こし朝飯の支度を始める。奥さんは全てが整った時点で狙いすましたかのように起き出してくる。また、わが家の場合、設営より撤収にかかる時間が圧倒的に多いのだ。何故か?それは始末と分別と片付け、そして車への積載順があるからだ。
この《追われる》感覚とその反発で焚き火の世話をする時間が長くなる。結局、終わってみれば何処となく記憶に残らないキャンプとなってしまってる。【やること】に追われてバタバタした記憶、焚き火の世話をした記憶、他はあまり記憶に残らない。これはイカン!

こんな《追われる》感覚を解消するために以前からあれこれ変えてきた。ポップアップテントもその一つだ。これのお陰で設営の時間と手間が大幅に減った。道具も減らした。料理も簡単に済むものにしている。残るはセッティングと撤収。これも目処がついたので次回から試験的にやってみようと考えてる。
一方〜、

デイは気楽だなぁ〜簡単だなぁ〜!
デイキャンプの場合、キャンプ場に入るのが午前中、飯は昼の一回のみ。帰りは夕方、車が混み合う時間の前にさっさと撤収。

大きな道具といえば奥さんの昼寝に使うテントくらい。殆どの場合、ogawa の Stacy-ST のインナーのみを持って行く。組み立て簡単、グラウンドシートのみでペグダウンもしない。これに椅子二脚とテーブル、焚き火台。



更にライトな道具立ての時もある。椅子は一脚、あとはフォールディングベンチ、焚き火台は持たずにストームクッカーと小さなウッドストーブということもある。




晩秋から初冬、春先など虫の少ない時期は Quechua のシェルターに敷物とタープという組み合わせで行くこともある。

わが家のデイハイクは【歩き】と自転車の組み合わせだ。荷物は最小、二人ともバックパックに必要なものを詰め、食糧や敷物、シェルターなどは自転車のカゴに入れて運ぶ。近くのスーパーで買い出しして調理などはせずストーブバーナーで湯を沸かすくらい。


ただし、器とカトラリー、キレモノと小さなカッティングボードくらいは持って行く。加えて一手間。

サンデードライブと称する野外ランチは車での移動とデイキャンプより少ない道具立てとデイハイクよりちょっとだけ手間のかかる(といっても簡単な)調理と飯が付く。焚き火やウッドストーブは使えないことが多いので殆どの場合、ストームクッカーとその仲間たちで間に合わせる。移動が車でも車を横付けできるとは限らないので大きな物は持って行かない。食糧は地産地消のお店で新鮮なものを安く買って簡単な調理で頂くことが多い。炭火や焚き火での調理はしないので焼き物、煮物はやらない。


*お弁当を持って行くのも良し、途中で買い出しして簡単な調理で食うも良し、コーヒーはドリップパックでもスティックでも良し。カップ麺には一品加えて尚良し。拘りを捨てすぎず軽く拘って良し。デイの気楽さよのぉ。

時にはスキレットで魚を焼いたり。

軽のハッチを上げてベンチを置いてカップ麺。こんなライトな時もあり。

太陽の位置と車の向きを考えてやれば軽のハッチは立派な日除けになる。バックシートを倒して平面にしてやればここが奥さんのお座敷に。ここで牢名主の如く君臨するのだ。

デイはロケーションが良ければ海でも山でもどこでも良いのだ。

キャンプにしろハイクにしろドライブにしろデイは道具立てとセッティングが至って簡単。一泊キャンプの様に《追われる》感が全くない。ただ、目的は必要です。うちの場合だいたい言い出しっぺは奥さんで、『あそこに行こうよ』に始まり『火を起こしてあれ焼いて、、』となり『あれも食べたいね〜』となる。ただ単に風景や町並みを楽しむためだけに出掛けることもある。そんな時も『ついでに外でご飯食べて、、』がもれなく付いてくる。外でご飯とは【お金を払ってお店で外食する】ではなく、どこかで野外ランチという意。それによって持ち出す道具も変わります。キャンプでもデイでも準備委員会総合幕僚長兼買い出し係兼積み込み担当兼忘れ物して叱られる係のアタシの出番です。アタシが全て用意するのでアタシがセッティングしないと何も始まりません。一泊キャンプの場合ここが《追われる》感覚にも繋がるのですがね。

先日のサンデードライブは着いて早々に奥さんが娘と調理を始めてしまい(セッティングが終わる前に)あちこちから道具や食品を引っ張り出して使って、、気がつきゃ足の踏み場もない状態に (^_^;) その回だけはちょっとだけ《追われる》感ありました。まあ、そんなことは稀でほぼ毎回楽ちんで小さな時間をたっぷり使えて、あちこち散策して収穫して《追われる》感の無い時間を過ごせます。
次回は CAMP Nov.2020 おそらく一泊。セッティングと撤収を工夫して《追われない》キャンプにしたいと決意を新たに明日に向かって漕ぎ出そうとパドルを忘れて手漕ぎするアタシです。
2020年08月10日
遊びの時間
こんにちは、ponio です。
コロナコロナでキャンプも行けないし、と言ってもこの時期つまりは暑い季節はわが家にとってのオフシーズン。夏キャンプ、、うちは小さな子供もいないのでとっくに卒業しました。ソロで歩いていた頃は熱中症になってぶっ倒れて怪我しても何度も出掛けていたけど、この数年は日々の仕事で異常な暑さにやられているので休みの日はエアコンの効いた部屋で冷たいものガブ飲みしてお腹こわしてクーラー病になってるのが一番だと悟りました。キャンプ行きたくねぇ〜。そこで、今回は男の子の遊び(失礼、女の子もやるね)飛び道具のオモチャの話です。

バン!バン!と大きな作動音を発して大きなスライドカバーが瞬間的に前後する。屋内ではこの作動音と殆ど時間差なくBB弾が着弾する。5メートル先、着弾は正確だ。

東京マルイの HK USP COMPACT 。発売は2015年春なので既に丸5年が過ぎています。
アタシの USP コンパクトはリセール品でほぼ新品、製造年はわかりません。東京マルイの USP についてはガチャコキ(エアーコッキング)を持っておりました。個人的には本格的なガスブローバックモデルを手にするのは17年ぶりです。なぜこのモデルを選んだか、Jack Bauer に憧れたわけではありませんよ。【 24 -TWENTY FOUR- 】自体殆ど見ていません。アタシはどうも天邪鬼で世間がワーワー騒いでいる時は殆ど見向きもしません。ブームが去って一元さんはお引き取り、本当に好きな人だけが残る頃になって始めることが多いのです。勿論、その逆もあってブームが後で押し寄せることも。しょせん、流行はサイクル、ループなのです。





発売から5年も経っているので今更この製品のレビューなど書くことはありません。実銃についても何ら書くことはありまへ〜ん。ただね、東京マルイさんがこの製品の説明に記している様に本国ドイツ製のパーツを米国で組み立てたヴァリアント 1 というモデルを現地採寸して製造したディテールだと知ると『ほぉ〜、』と実銃見たことないのに感心したりして。それもまた小ちゃな楽しみなのかもしれません。

このシルエットをみると SIG ぽい。いかにも現代ポリマーオート(実銃の話)らしい造形。複雑だがエッジが鋭くなくどこかオモチャ然とした部分があるのも現代銃らしいね。デザイン的には同社(マルイ)の Px4 の方が好みだけど、要はタイミングです。アタシの場合、触手が動いた時に手の届くところにそれがあるか無いか、ただそれだけなのです。この USP コンパクトについても同じです。たまたま、良いなあと思った時期に手の届くところにリセール品が出ていただけです。ついでにガスと弾も買いました(街のおもちゃ屋でPayPayで)

各レバー類(食いもんじゃおまへんで〜)は大きく使い良いね。

短尻尾のブルドックみたいな小さなハンマー。ダウンしている状態で衣服などに引っかからない様指掛けの部分(スパー)が省略されたボブドハンマー。トリガーを絞ればこの小さなハンマーがパチン!と落ちる。そして落ちたハンマーがフレーム内のノッカーと呼ばれるパーツをヒットする。ハンマーに叩かれたノッカーはマガジンの背面のバルブをヒットし発射とブローバックに使われる気化ガスを放出する。

スライドストッパー。マガジン(弾倉)が空になるとマガジンフロアーと呼ばれるパーツと連動してせり上がりスライドカバーをオープン状態で固定する。《弾切れましたぜ〜》的装置。弾の入ったマガジンを再装填したらこのレバーを押し下げる(又はスライドをちょこっと引く)とマガジン最上部の1発がバレル後端のチェンバーに装填される。実銃はともかくメーカー純正品のスライドカバーは樹脂製であり、金属製(亜鉛合金)のスライドストッパーがガシッと食いつき、それをズリっと押し下げることで強度的に弱い樹脂製のスライドが削れてきます。そこでマルイさん、これを解決する為にスライドストップは見せかけ(操作上は本物と同じ)に、実際にはマガジンフロアーと連動する別パーツ(スライドストップベース)をフレーム内に設け、それと噛み合う部分も同じ金属製で作りました。これによりこれまで強度的に弱くめくれ上がって変形していたスライドのノッチ部分が守られる様になりました。

コントロールレバーは水平位置から上に押し上げて安全装置として機能する。水平位置から下げると起き切ったハンマーをハーフコックまで安全に戻すことができる。オートマにおいてはハンマーを指で押さえてトリガーを引き同時にゆっくり戻す、そんな時代は終わりましたね。

コントロールレバーを押し下げハンマーを安全にダウンさせた後、再び射つ場合はそのままトリガーを絞る、これダブルアクション。トリガーを絞ればハンマーがグググっと起きやがてパチンと落ちる。この USPコンパクトのダブルアクションはストローク(引きしろ)が比較的短い。。しかしリボルバーの様なスムースな(重い軽いは別として)ダブルアクションではない。ググーと引いてると突然パチンと落ちる感じ。苦手〜。

対するシングルアクションはオートマチックの真骨頂。ハンマーはフルコック、トリガーは後退しておりストロークはかなり短い。シングルアクション時のトリガーのストローク幅を意識すればトリガーから指を離すことなく最小限のストロークで連射速射が可能です。

上のの写真は日本のオモチャならではの創意工夫です。この USPコンパクトは9mm口径の実銃をモデルアップしたものですが、実際に発射するのはBB弾(6mm +)です。そこで見せかけの樹脂製バレルの中に真鍮製のインナーバレルと呼ばれるものを通しました。9mmから6mmにサイズダウンした分厚いバレルを作ればと思われる方もいるかもしれません。しかし、日本にはオモチャの銃に関する厳しい法律もあり、強度の高い素材をそのまま使ったバレル(銃身)はご法度です。カスタムパーツではアルミ製などの物もありますがそれだと本体価格の上昇に繋がります。そしてギミック。本物では火薬の爆発的な力と圧力による銃の破損を防ぐために瞬間的な爆発力のピークをズラして作動させる機構が組み込まれます。この USPコンパクトにもショートリコイルと呼ばれるバレルの前後運動が取り入れられました(実銃の話)。日本のオモチャメーカーがこのギミックを見逃すはずはありません。このギミックを再現するにあたりBB弾を射出するインナーバレルは固定式に、見せかけのアウターバレルを前後に動かすことで本物みたいなギミックの完成です。そんなオモチャなりの感動も昔の話で今では当たり前となりました。

そして、ホップアップ機構。実銃ではあり得ない原理を利用した《のび〜る弾道》機構です。BB弾という球形弾にバックスピンを掛けて弾に浮力を与え弾道を伸ばす、その創意工夫に感心したのも20年前のこと。今では当たり前のように低パワーでもヒュィーっと遠くまで弾が飛んでくれます。ホームランバッターがバットで球の下を擦る、往年の江川卓や藤川球児の球がバッターの手前で伸びるように浮き上がるように見える、アレです。
これは硬質とはいえ球形のBB弾とガスまたはスプリングのテンションにより押し出されたエアーという低パワー(本物と比べれば)の組み合わせが為せる技なのです。

❶ 直線で到達する距離での弾道。または、ホップアップと弾の重さがマッチした比較的直線的な弾道。
❷ 上向に射った場合の放物線。ホップなしの弾道(遠射の場合)スコープはこれにて合わせる。
❸ ホップアップが効き過ぎまたは弾の重さが軽い場合の弾道。この先でゆるい下降線を辿る。BB弾を最も遠くまで伸ばせる弾道。ただし上げ過ぎはダメ。
❹ 射程距離外から水平に射った時の弾道。自然落下。
オモロイもんです。弾は真っ直ぐ飛ぶのに越したことはありません。しかし機種にもよりますがホップアップ機構なしのオモチャでは5メートル先でも弾道は下降線を描きます。それを弾にバックスピンを掛けることで浮力が得られスイ〜と伸びていく。不思議な感じです。実銃は遠くを撃つ為には銃自体を上向きに微動させますがホップアップ機構の付いたオモチャでは弾の方が伸びてくれるのですから。スコープを使われる方はご存知のようにスコープを付けたからといって弾が勝手にヘアークロスの捉えた所に誘導されるのではありません。あれは距離や風向きを計算してターゲットに弾を落とす様にスコープを調整、その状態でスコープを正しく覗くと銃(銃身)がその方向に微動するような仕組みです。映画『プレデター』に出てくる彼らの武器 Plasma Caster と同じです。狙いを定めると砲身がそちらを向く、一緒です。実銃は山なり弾道の計算ですが、これがホップアップ機構のあるオモチャでは弾はスイ〜と飛んでヒョコっと上がりその先に上から落ちる感じです。計算難しいすね。勿論、BB弾はとても軽く風にも簡単に流されます。弾のバラツキ、ホップアップのバラツキ、オイルの影響、押し出すガスやエアーのバラツキなどで弾道はいとも簡単に乱れます。このホップ弾道の読みはサバゲーを長年やってる人は可能かもしれません。

さて、これもまた日本のオモチャならではの創意工夫から生まれたパーツです。昔風に言うならリキッドチャージ式マガジン。リキッド(液体)状のガスを注入するからそう呼ばれました。最初期のガスガン の中にはリキッドではなくマガジンに対してボンベを下から突き立て気化ガスを入れる物もありました。リキッドチャージではボンベは上下逆さまにして注入しますよね。注入式のガスライターと同じです。

簡単に描くとリキッドチャージ式マガジンの中はこんな具合です。マガジンの底にねじ込まれた注入バルブにガス缶を逆さにして突き立て押し込むと液化ガスが注入されます。マガジンをひっくり返して手に握り温めてやると注入された液化ガスが気化して圧力が上がる。発射もブローバックもこの気化ガスを使う。機構上マガジンの内部にガスの気化スペースを装備したモデルは満タンまで目一杯液化ガスを注入できるが、一般的なマガジンは内部が一気室なので液化ガスを満タンまで入れると上部の気化スペースが殆ど無くなってしまう。発射時に白い生ガスを噴く時はガスの入れ過ぎか、勢いよくGUNをスウィングした際に液化ガスがシリンダーに入ってしまったのかもしれません。百円ライターを思い出して下さい。液化ガスの上に必ず気化スペースを設けてあるます。ガスガン のマガジンも注入口から噴き返すくらいまでガスを入れたら数発でいいので空撃ちをしてガス抜きをした方が良いでしょう。それと気温と使用頻度による冷えはアウトドア用のガスボンベと同じです。ただし、使用するガスの性質上、液体から気化する温度もスピードも違います。夏場以外は使用前にマガジンを手に握ってよく温めて使います。

アウトドア用のガス缶、OD缶や CB缶も可燃性の液化ガスが充填されている。新品の状態で缶を振るとシャカシャカと液体が揺れる音がします。あれは缶の中に気化スペースがある証し。このOD缶に別のガス缶から液化ガスを再充填する時に満タンまで入れると燃焼時に赤火となったり異常燃焼します。あれは液化ガスの入れ過ぎで気化スペースが失われた為に液化ガスがそのまま噴き出し燃焼しているのです。こちらも温めると火力が安定または強くなりますが、あくまで可燃性の液化ガスですので温め過ぎや夏場の保管環境、輻射熱には特別注意が必要です。

さあ、実食ならぬ実射です。
❶ BB弾はチェンバーに装填済み、ハンマーはフルコック状態、トリガーはシングルアクション
❷ トリガーが絞られシアーが外れるとハンマーがスプリングの力でパチンと落ちる
❸ ハンマーに叩かれたノッカーと呼ばれるパーツがマガジンのバルブをヒット、マガジンからガスが放出され最初にBB弾が発射される、その後スライド後端のシリンダー内でバルブが作動し残りのガスの流れを前方(発射)から後方(ブローバック)に切り替える
❹ スライドはさらに後退しハンマーがフルコックまで起こされる
❺ スライドがフルオープンの状態、トリガーバーがスライドに押し下げられシアーがフリーとなる、ノッカーも元の状態に復帰。
❻ スライドがリコイルスプリングの力で復帰、次弾がマガジンからチェンバーに送られる、シアーは再びハンマーをロックし、❶ の状態に戻る。

これは上の連続写真でいう ❺、既にBB弾が発射されガスは後方へと流れブローバックの最中、とそんなところです。この写真の↓↑はこの瞬間のブレを現しています。ん?逆やないのん?そこそこそこです。実銃では発射の後、銃口が上に持ち上がる、いわゆるマズルジャンプが見られます。しかし、その前段階ではこの様な逆のブレをこ起こします。マズル(銃口)側が下へ、スライド後端が上に持ち上がる。生の肉眼ではわかりませんがスロー再生で見れば明らかです。このブレはオモチャであってもブローバックに共通するものです。

発射直後は前下がりの後ろ上がり。現在発売されているガスブローバックはこのブレが起きる一瞬前にBB弾を射出しているので、単発に関して「反動があって当たらなーい」は通用しません。連射や速射の場合はこのブレが精度に大きく関係します。

ガスによるブローバックが完結してリコイルスプリングがスライドを元の状態に復帰させる。この時は前上りで後ろ下がり。これらは実際には始まりから終わりまでコンマ何秒で完結する動きです。
私がこれを知ったのは日本で初めての本格的なガスブローバックモデルを開発した方からその話を直接聞いた時です。その方は「ねじれちゃうんだよね〜前がこうで↓、後がこう↑ 」とそんな言葉で表現されました。それは私がその方が開発したガスブローバックモデルの着弾の癖について尋ねた時のことでした。その方が開発した最初期のガスブローバックは現在のものとはブローバックのプロセスが違っておりました。現在発売されているガスブローバックは基本的にBB弾の発射後にブローバックが起きるというものです。それに対して当時ほぼ30年前のモデルは最初にブローバックの作動が起こりその後ガスは前方に抜けBB弾が発射されるというものでした。勿論、これらのプロセスはほんのコンマ何秒かの間で完結する瞬間的なものです。

当時のガスブローバックに見られた着弾の癖とは狙った所より下方に当たるというものでした。ブレは上の写真の↓↑の通りです。当時のモデルはスライドが動き出しブレが起きてからBB弾が射出される機構でした。これは特に初めて射つ人、グリップが緩めの人、片手で射つ時などはこの現象が顕著に現れました。それを解決するには、はじめから少し上を狙うか、両手でしっかりとグリップしてこの↓↑のブレを極力抑えることでした。
それに比べて現在のガスブローバックはスライドが動きブレを起こす前にBB弾を射出する為、狙点を正確に把握しトリガーを引き絞る瞬間さえ手ブレせず射つことができれば、例え片手でも正確に着弾させられます。もちろん、ガス圧や弾のバラツキは除外して。

当たる当たらないは時の運、いえいえ技量です。オモチャとはいえこれだけ性能の良いモデルが普通になった昨今では射って当たって当たり前なのです。当たるといっても丸いプレートを倒す競技では立っているプレートのどこかにヒットして倒せば当たりです。一方、決められた数を射ってどれだけ点数を稼いだかを競う競技ではど真ん中により多く当てられる人が勝ちです。ど真ん中を狙う競技ではど真ん中以外はたとえ1ミリ外れても、ああ、、惜しい、、となるでしょう。サバゲーでは相手にヒットさえすれば当たりです。ペットボトルや紙コップを射つ人は当たる場所など関係なく的が弾かれ転がれば当たりです。
昔、ある人が私に4〜5メートル先の的を射って見せてほしいと頼んできました。使うのはその人のガスガン でした。特別な改造などしていない市販のものでした。私は紙の的に向かい数発射ちました。続いて彼が射ちました。結果は、私の的には3〜5センチの穴が破れたように開いており、彼の的には射った弾数の分だけ穴が開いていました。
『なんで同じところに当たるんです?』と彼が聞きます。二つの的はボンベの底を押しつけてマジックで描いた円で中心点などないただのサークルです。彼の射った的には射った数だけの穴が開いており、全弾命中です。しかし、彼が求めたのは集弾性でした。そこでもう一度彼に射ってもらいました。彼の質問に対する答えは簡単でした。
『サイト見てますか?』と私
『は?は、はい』と彼
『的見て射ってませんか?』と私
『はあ、え?ダメなんですか?』と彼

*ガチャコキ USP で約5メートル先のサークル(7〜8cmほどの)を射つ。弾は 0.25g 片方に各30発ずつ。ガチャコキでもこれだけ集まれば上等ですわん。これをガスブローバックの USPコンパクトで射つともう少しパターンが広がります。その時の温度でガス圧も変わるし可変(調整式)ホップアップならではの微妙な変化もあるのでしょうね。パワーは断然ガスですがね。
さてさて先ほどの彼ですが、彼はゲーセンとかテレビゲーム流の射ち方をしていたのです。画面だけをみて撃つように的を見て飛んでゆくBB弾の白い弾道と的に開いた小さな穴の場所を見ながら手先だけを動かし一発毎に当たる場所を調整していたのです。彼は両手でしっかりと構えてはいたもののターゲットに目線とピントを合わせて彼の銃のサイト(フロントとリア)は最初の一発目を射つ瞬間まで意識してあとはずっと的の着弾点だけを見て射っていたようです。ロボコップならそれでも当てられるでしょうね (^^)

*ガチャコキUSP(左)とガスブローバックUSPコンパクト(右)どちらも《遊びの時間》にはもってこいのオモチャです。
サバゲーなどフルオートで水撒きする様に弾道を放つ電動ガンならわかります。実銃でいうトレーサー(曳光弾)を目印にするのと同じです。しかし、彼はどうやら小さくまとめたかった様です。出来るなら一発目も十発目も同じところにね。的には全弾当たってるからええやん!と言いたかったのですがそれでは答えになりませんから、ただ一言
『フロントサイトに集中して、』とたけ伝えました。
『え?的は見ないんですか?』
『うーん、、そういうわけじゃないけど射つ瞬間だけはフロントにピント合わせて着弾は見ずに、』と私。
『顔だけ的の方向いて構えた銃が明後日の方向向いてたら当たらないしね、(^^)』とこんな感じで。
もっとラフに射つならフラッシュサイティングという技量があれば複数の的でも次々射てる。オモチャでもね。その後、彼はちゃんと集弾させられるようになりましたとさ。めでたしめでたし。
今日は国民の休日。天気は上々だけど南風。熱風です。日差しはとんでもなく強くて帽子被っていても頭が痛くなる。紫外線で目は疲れるし、だからと言ってマスクにサングラスかけるとコンビに強盗みたいで。こんな日はやっぱクーラーガンガンでキンキン冷えた飲み物グビグビ飲んでアイスをガリガリ食って頭ズキンズキン痛くなってもがき苦しむのが正しい過ごし方だと実践するアタシです。
ponio でした。御機嫌よろしゅう。
続きを読む
コロナコロナでキャンプも行けないし、と言ってもこの時期つまりは暑い季節はわが家にとってのオフシーズン。夏キャンプ、、うちは小さな子供もいないのでとっくに卒業しました。ソロで歩いていた頃は熱中症になってぶっ倒れて怪我しても何度も出掛けていたけど、この数年は日々の仕事で異常な暑さにやられているので休みの日はエアコンの効いた部屋で冷たいものガブ飲みしてお腹こわしてクーラー病になってるのが一番だと悟りました。キャンプ行きたくねぇ〜。そこで、今回は男の子の遊び(失礼、女の子もやるね)飛び道具のオモチャの話です。

バン!バン!と大きな作動音を発して大きなスライドカバーが瞬間的に前後する。屋内ではこの作動音と殆ど時間差なくBB弾が着弾する。5メートル先、着弾は正確だ。

東京マルイの HK USP COMPACT 。発売は2015年春なので既に丸5年が過ぎています。
アタシの USP コンパクトはリセール品でほぼ新品、製造年はわかりません。東京マルイの USP についてはガチャコキ(エアーコッキング)を持っておりました。個人的には本格的なガスブローバックモデルを手にするのは17年ぶりです。なぜこのモデルを選んだか、Jack Bauer に憧れたわけではありませんよ。【 24 -TWENTY FOUR- 】自体殆ど見ていません。アタシはどうも天邪鬼で世間がワーワー騒いでいる時は殆ど見向きもしません。ブームが去って一元さんはお引き取り、本当に好きな人だけが残る頃になって始めることが多いのです。勿論、その逆もあってブームが後で押し寄せることも。しょせん、流行はサイクル、ループなのです。





発売から5年も経っているので今更この製品のレビューなど書くことはありません。実銃についても何ら書くことはありまへ〜ん。ただね、東京マルイさんがこの製品の説明に記している様に本国ドイツ製のパーツを米国で組み立てたヴァリアント 1 というモデルを現地採寸して製造したディテールだと知ると『ほぉ〜、』と実銃見たことないのに感心したりして。それもまた小ちゃな楽しみなのかもしれません。

このシルエットをみると SIG ぽい。いかにも現代ポリマーオート(実銃の話)らしい造形。複雑だがエッジが鋭くなくどこかオモチャ然とした部分があるのも現代銃らしいね。デザイン的には同社(マルイ)の Px4 の方が好みだけど、要はタイミングです。アタシの場合、触手が動いた時に手の届くところにそれがあるか無いか、ただそれだけなのです。この USP コンパクトについても同じです。たまたま、良いなあと思った時期に手の届くところにリセール品が出ていただけです。ついでにガスと弾も買いました(街のおもちゃ屋でPayPayで)

各レバー類(食いもんじゃおまへんで〜)は大きく使い良いね。

短尻尾のブルドックみたいな小さなハンマー。ダウンしている状態で衣服などに引っかからない様指掛けの部分(スパー)が省略されたボブドハンマー。トリガーを絞ればこの小さなハンマーがパチン!と落ちる。そして落ちたハンマーがフレーム内のノッカーと呼ばれるパーツをヒットする。ハンマーに叩かれたノッカーはマガジンの背面のバルブをヒットし発射とブローバックに使われる気化ガスを放出する。

スライドストッパー。マガジン(弾倉)が空になるとマガジンフロアーと呼ばれるパーツと連動してせり上がりスライドカバーをオープン状態で固定する。《弾切れましたぜ〜》的装置。弾の入ったマガジンを再装填したらこのレバーを押し下げる(又はスライドをちょこっと引く)とマガジン最上部の1発がバレル後端のチェンバーに装填される。実銃はともかくメーカー純正品のスライドカバーは樹脂製であり、金属製(亜鉛合金)のスライドストッパーがガシッと食いつき、それをズリっと押し下げることで強度的に弱い樹脂製のスライドが削れてきます。そこでマルイさん、これを解決する為にスライドストップは見せかけ(操作上は本物と同じ)に、実際にはマガジンフロアーと連動する別パーツ(スライドストップベース)をフレーム内に設け、それと噛み合う部分も同じ金属製で作りました。これによりこれまで強度的に弱くめくれ上がって変形していたスライドのノッチ部分が守られる様になりました。

コントロールレバーは水平位置から上に押し上げて安全装置として機能する。水平位置から下げると起き切ったハンマーをハーフコックまで安全に戻すことができる。オートマにおいてはハンマーを指で押さえてトリガーを引き同時にゆっくり戻す、そんな時代は終わりましたね。

コントロールレバーを押し下げハンマーを安全にダウンさせた後、再び射つ場合はそのままトリガーを絞る、これダブルアクション。トリガーを絞ればハンマーがグググっと起きやがてパチンと落ちる。この USPコンパクトのダブルアクションはストローク(引きしろ)が比較的短い。。しかしリボルバーの様なスムースな(重い軽いは別として)ダブルアクションではない。ググーと引いてると突然パチンと落ちる感じ。苦手〜。

対するシングルアクションはオートマチックの真骨頂。ハンマーはフルコック、トリガーは後退しておりストロークはかなり短い。シングルアクション時のトリガーのストローク幅を意識すればトリガーから指を離すことなく最小限のストロークで連射速射が可能です。

上のの写真は日本のオモチャならではの創意工夫です。この USPコンパクトは9mm口径の実銃をモデルアップしたものですが、実際に発射するのはBB弾(6mm +)です。そこで見せかけの樹脂製バレルの中に真鍮製のインナーバレルと呼ばれるものを通しました。9mmから6mmにサイズダウンした分厚いバレルを作ればと思われる方もいるかもしれません。しかし、日本にはオモチャの銃に関する厳しい法律もあり、強度の高い素材をそのまま使ったバレル(銃身)はご法度です。カスタムパーツではアルミ製などの物もありますがそれだと本体価格の上昇に繋がります。そしてギミック。本物では火薬の爆発的な力と圧力による銃の破損を防ぐために瞬間的な爆発力のピークをズラして作動させる機構が組み込まれます。この USPコンパクトにもショートリコイルと呼ばれるバレルの前後運動が取り入れられました(実銃の話)。日本のオモチャメーカーがこのギミックを見逃すはずはありません。このギミックを再現するにあたりBB弾を射出するインナーバレルは固定式に、見せかけのアウターバレルを前後に動かすことで本物みたいなギミックの完成です。そんなオモチャなりの感動も昔の話で今では当たり前となりました。

そして、ホップアップ機構。実銃ではあり得ない原理を利用した《のび〜る弾道》機構です。BB弾という球形弾にバックスピンを掛けて弾に浮力を与え弾道を伸ばす、その創意工夫に感心したのも20年前のこと。今では当たり前のように低パワーでもヒュィーっと遠くまで弾が飛んでくれます。ホームランバッターがバットで球の下を擦る、往年の江川卓や藤川球児の球がバッターの手前で伸びるように浮き上がるように見える、アレです。
これは硬質とはいえ球形のBB弾とガスまたはスプリングのテンションにより押し出されたエアーという低パワー(本物と比べれば)の組み合わせが為せる技なのです。

❶ 直線で到達する距離での弾道。または、ホップアップと弾の重さがマッチした比較的直線的な弾道。
❷ 上向に射った場合の放物線。ホップなしの弾道(遠射の場合)スコープはこれにて合わせる。
❸ ホップアップが効き過ぎまたは弾の重さが軽い場合の弾道。この先でゆるい下降線を辿る。BB弾を最も遠くまで伸ばせる弾道。ただし上げ過ぎはダメ。
❹ 射程距離外から水平に射った時の弾道。自然落下。
オモロイもんです。弾は真っ直ぐ飛ぶのに越したことはありません。しかし機種にもよりますがホップアップ機構なしのオモチャでは5メートル先でも弾道は下降線を描きます。それを弾にバックスピンを掛けることで浮力が得られスイ〜と伸びていく。不思議な感じです。実銃は遠くを撃つ為には銃自体を上向きに微動させますがホップアップ機構の付いたオモチャでは弾の方が伸びてくれるのですから。スコープを使われる方はご存知のようにスコープを付けたからといって弾が勝手にヘアークロスの捉えた所に誘導されるのではありません。あれは距離や風向きを計算してターゲットに弾を落とす様にスコープを調整、その状態でスコープを正しく覗くと銃(銃身)がその方向に微動するような仕組みです。映画『プレデター』に出てくる彼らの武器 Plasma Caster と同じです。狙いを定めると砲身がそちらを向く、一緒です。実銃は山なり弾道の計算ですが、これがホップアップ機構のあるオモチャでは弾はスイ〜と飛んでヒョコっと上がりその先に上から落ちる感じです。計算難しいすね。勿論、BB弾はとても軽く風にも簡単に流されます。弾のバラツキ、ホップアップのバラツキ、オイルの影響、押し出すガスやエアーのバラツキなどで弾道はいとも簡単に乱れます。このホップ弾道の読みはサバゲーを長年やってる人は可能かもしれません。

さて、これもまた日本のオモチャならではの創意工夫から生まれたパーツです。昔風に言うならリキッドチャージ式マガジン。リキッド(液体)状のガスを注入するからそう呼ばれました。最初期のガスガン の中にはリキッドではなくマガジンに対してボンベを下から突き立て気化ガスを入れる物もありました。リキッドチャージではボンベは上下逆さまにして注入しますよね。注入式のガスライターと同じです。

簡単に描くとリキッドチャージ式マガジンの中はこんな具合です。マガジンの底にねじ込まれた注入バルブにガス缶を逆さにして突き立て押し込むと液化ガスが注入されます。マガジンをひっくり返して手に握り温めてやると注入された液化ガスが気化して圧力が上がる。発射もブローバックもこの気化ガスを使う。機構上マガジンの内部にガスの気化スペースを装備したモデルは満タンまで目一杯液化ガスを注入できるが、一般的なマガジンは内部が一気室なので液化ガスを満タンまで入れると上部の気化スペースが殆ど無くなってしまう。発射時に白い生ガスを噴く時はガスの入れ過ぎか、勢いよくGUNをスウィングした際に液化ガスがシリンダーに入ってしまったのかもしれません。百円ライターを思い出して下さい。液化ガスの上に必ず気化スペースを設けてあるます。ガスガン のマガジンも注入口から噴き返すくらいまでガスを入れたら数発でいいので空撃ちをしてガス抜きをした方が良いでしょう。それと気温と使用頻度による冷えはアウトドア用のガスボンベと同じです。ただし、使用するガスの性質上、液体から気化する温度もスピードも違います。夏場以外は使用前にマガジンを手に握ってよく温めて使います。

アウトドア用のガス缶、OD缶や CB缶も可燃性の液化ガスが充填されている。新品の状態で缶を振るとシャカシャカと液体が揺れる音がします。あれは缶の中に気化スペースがある証し。このOD缶に別のガス缶から液化ガスを再充填する時に満タンまで入れると燃焼時に赤火となったり異常燃焼します。あれは液化ガスの入れ過ぎで気化スペースが失われた為に液化ガスがそのまま噴き出し燃焼しているのです。こちらも温めると火力が安定または強くなりますが、あくまで可燃性の液化ガスですので温め過ぎや夏場の保管環境、輻射熱には特別注意が必要です。

さあ、実食ならぬ実射です。
❶ BB弾はチェンバーに装填済み、ハンマーはフルコック状態、トリガーはシングルアクション
❷ トリガーが絞られシアーが外れるとハンマーがスプリングの力でパチンと落ちる
❸ ハンマーに叩かれたノッカーと呼ばれるパーツがマガジンのバルブをヒット、マガジンからガスが放出され最初にBB弾が発射される、その後スライド後端のシリンダー内でバルブが作動し残りのガスの流れを前方(発射)から後方(ブローバック)に切り替える
❹ スライドはさらに後退しハンマーがフルコックまで起こされる
❺ スライドがフルオープンの状態、トリガーバーがスライドに押し下げられシアーがフリーとなる、ノッカーも元の状態に復帰。
❻ スライドがリコイルスプリングの力で復帰、次弾がマガジンからチェンバーに送られる、シアーは再びハンマーをロックし、❶ の状態に戻る。

これは上の連続写真でいう ❺、既にBB弾が発射されガスは後方へと流れブローバックの最中、とそんなところです。この写真の↓↑はこの瞬間のブレを現しています。ん?逆やないのん?そこそこそこです。実銃では発射の後、銃口が上に持ち上がる、いわゆるマズルジャンプが見られます。しかし、その前段階ではこの様な逆のブレをこ起こします。マズル(銃口)側が下へ、スライド後端が上に持ち上がる。生の肉眼ではわかりませんがスロー再生で見れば明らかです。このブレはオモチャであってもブローバックに共通するものです。

発射直後は前下がりの後ろ上がり。現在発売されているガスブローバックはこのブレが起きる一瞬前にBB弾を射出しているので、単発に関して「反動があって当たらなーい」は通用しません。連射や速射の場合はこのブレが精度に大きく関係します。

ガスによるブローバックが完結してリコイルスプリングがスライドを元の状態に復帰させる。この時は前上りで後ろ下がり。これらは実際には始まりから終わりまでコンマ何秒で完結する動きです。
私がこれを知ったのは日本で初めての本格的なガスブローバックモデルを開発した方からその話を直接聞いた時です。その方は「ねじれちゃうんだよね〜前がこうで↓、後がこう↑ 」とそんな言葉で表現されました。それは私がその方が開発したガスブローバックモデルの着弾の癖について尋ねた時のことでした。その方が開発した最初期のガスブローバックは現在のものとはブローバックのプロセスが違っておりました。現在発売されているガスブローバックは基本的にBB弾の発射後にブローバックが起きるというものです。それに対して当時ほぼ30年前のモデルは最初にブローバックの作動が起こりその後ガスは前方に抜けBB弾が発射されるというものでした。勿論、これらのプロセスはほんのコンマ何秒かの間で完結する瞬間的なものです。

当時のガスブローバックに見られた着弾の癖とは狙った所より下方に当たるというものでした。ブレは上の写真の↓↑の通りです。当時のモデルはスライドが動き出しブレが起きてからBB弾が射出される機構でした。これは特に初めて射つ人、グリップが緩めの人、片手で射つ時などはこの現象が顕著に現れました。それを解決するには、はじめから少し上を狙うか、両手でしっかりとグリップしてこの↓↑のブレを極力抑えることでした。
それに比べて現在のガスブローバックはスライドが動きブレを起こす前にBB弾を射出する為、狙点を正確に把握しトリガーを引き絞る瞬間さえ手ブレせず射つことができれば、例え片手でも正確に着弾させられます。もちろん、ガス圧や弾のバラツキは除外して。

当たる当たらないは時の運、いえいえ技量です。オモチャとはいえこれだけ性能の良いモデルが普通になった昨今では射って当たって当たり前なのです。当たるといっても丸いプレートを倒す競技では立っているプレートのどこかにヒットして倒せば当たりです。一方、決められた数を射ってどれだけ点数を稼いだかを競う競技ではど真ん中により多く当てられる人が勝ちです。ど真ん中を狙う競技ではど真ん中以外はたとえ1ミリ外れても、ああ、、惜しい、、となるでしょう。サバゲーでは相手にヒットさえすれば当たりです。ペットボトルや紙コップを射つ人は当たる場所など関係なく的が弾かれ転がれば当たりです。
昔、ある人が私に4〜5メートル先の的を射って見せてほしいと頼んできました。使うのはその人のガスガン でした。特別な改造などしていない市販のものでした。私は紙の的に向かい数発射ちました。続いて彼が射ちました。結果は、私の的には3〜5センチの穴が破れたように開いており、彼の的には射った弾数の分だけ穴が開いていました。
『なんで同じところに当たるんです?』と彼が聞きます。二つの的はボンベの底を押しつけてマジックで描いた円で中心点などないただのサークルです。彼の射った的には射った数だけの穴が開いており、全弾命中です。しかし、彼が求めたのは集弾性でした。そこでもう一度彼に射ってもらいました。彼の質問に対する答えは簡単でした。
『サイト見てますか?』と私
『は?は、はい』と彼
『的見て射ってませんか?』と私
『はあ、え?ダメなんですか?』と彼

*ガチャコキ USP で約5メートル先のサークル(7〜8cmほどの)を射つ。弾は 0.25g 片方に各30発ずつ。ガチャコキでもこれだけ集まれば上等ですわん。これをガスブローバックの USPコンパクトで射つともう少しパターンが広がります。その時の温度でガス圧も変わるし可変(調整式)ホップアップならではの微妙な変化もあるのでしょうね。パワーは断然ガスですがね。
さてさて先ほどの彼ですが、彼はゲーセンとかテレビゲーム流の射ち方をしていたのです。画面だけをみて撃つように的を見て飛んでゆくBB弾の白い弾道と的に開いた小さな穴の場所を見ながら手先だけを動かし一発毎に当たる場所を調整していたのです。彼は両手でしっかりと構えてはいたもののターゲットに目線とピントを合わせて彼の銃のサイト(フロントとリア)は最初の一発目を射つ瞬間まで意識してあとはずっと的の着弾点だけを見て射っていたようです。ロボコップならそれでも当てられるでしょうね (^^)

*ガチャコキUSP(左)とガスブローバックUSPコンパクト(右)どちらも《遊びの時間》にはもってこいのオモチャです。
サバゲーなどフルオートで水撒きする様に弾道を放つ電動ガンならわかります。実銃でいうトレーサー(曳光弾)を目印にするのと同じです。しかし、彼はどうやら小さくまとめたかった様です。出来るなら一発目も十発目も同じところにね。的には全弾当たってるからええやん!と言いたかったのですがそれでは答えになりませんから、ただ一言
『フロントサイトに集中して、』とたけ伝えました。
『え?的は見ないんですか?』
『うーん、、そういうわけじゃないけど射つ瞬間だけはフロントにピント合わせて着弾は見ずに、』と私。
『顔だけ的の方向いて構えた銃が明後日の方向向いてたら当たらないしね、(^^)』とこんな感じで。
もっとラフに射つならフラッシュサイティングという技量があれば複数の的でも次々射てる。オモチャでもね。その後、彼はちゃんと集弾させられるようになりましたとさ。めでたしめでたし。
今日は国民の休日。天気は上々だけど南風。熱風です。日差しはとんでもなく強くて帽子被っていても頭が痛くなる。紫外線で目は疲れるし、だからと言ってマスクにサングラスかけるとコンビに強盗みたいで。こんな日はやっぱクーラーガンガンでキンキン冷えた飲み物グビグビ飲んでアイスをガリガリ食って頭ズキンズキン痛くなってもがき苦しむのが正しい過ごし方だと実践するアタシです。
ponio でした。御機嫌よろしゅう。
続きを読む
2019年07月22日
7月の雑記

おひさしぶりでございます、ponio です。
この2ヶ月、中でも5月中旬から7月上旬までの約ひと月半は一つの仕事に掛かり切りで休みが一日も取れませんでした。アタシは個人で仕事をしているので仕事の苦楽に関係なく全ては自分のモチベーション次第です。今回は昨年に引き続き予断を許さないケースでしたが現在はなんとか《普通》に戻りつつあります。漸く休みがとれるぞー!と思いきや、、遅い梅雨入りと連日の雨、豪雨、大雨で毎日濡れネズミ。凄まじい湿度と高温で体力気力ともに消耗ス。こんな時期はエアコンのきいた部屋で冷たいものガブ飲みして胃腸を弱らせ腹痛めてグッタリするのが一番だー!と実践する日々です。
さて、そんなこんなでアウトドアなんてどこ吹く風、お伝えすることなど何ひとつありまへんが、つい先日、超久しぶりに奥さんとドライブがてらのショートデイキャンプをしました。隣の県のいつものキャンプ場に飛び込んで誰もいない空間をほんの4時間ほど占有させてもらいました。

いつものルート、三瀬峠のループ橋を通りトンネル抜けて目指すは《吉野山》ではなくて、、《八丁キャンプ場》です。

前日予約してはいましたが、最初は空いていなければダム湖周辺に車を停めてと考えておりました。しかし、着いてみると、ご覧の通りの空き具合(ウチだけ〜)。管理棟でいつもの気のいいおじさんに料金を払って案内して頂きました。ここは毎年来ているので勝手はわかっていましたが、来年限りで勇退されるおじさんとのコミュニケーションも楽しく好きな板の間サイトに陣取ります。まずは椅子を二脚置きましたが結局一度も腰掛けることはありませんでした。持ってくるはずの Quechua のポップちゃんも忘れてきたので、板の間サイトにスノーピークのポンタシールドを敷いて銀マット敷いてポール二本でタープを張って奥さんの寝床としました。宿泊しないまでも昼寝用のテントを忘れるなんて、、気合いの入り様がうかがえますね、、。
寝床つくりがおわったとこで、、目的の昼メシ作りに。


ナス科トウガラシ属のピーマンとパプリカを奥さんが切る。

使ったのは スウェーデンの EKA ナイフ(Swede 88)。


いよいよ、蚊取り線香が要る季節になりました。ここはすぐそばに池やダムがあるので、この季節は蚊取り線香は必需品です。板の間サイトの節穴にペグを立てて蚊取り線香をクルリと通しておきます。

ただでさえ蒸し暑いので焚き火なんぞするものかー!と反焚き火運動に身を投じておりましたが、一応燃やしてみるか〜とアッサリ思考転換(弱いヤツ)。持っていった炭の箱に前回切り割りした薪が入っていたのバトンして更に細かく割っていきます。ナイフは ESEE 4 SS。

細かく割った薪を MORA のナイフでクルクルカールして焚きつけにします。

ここのキャンプ場には焚き火や調理のための煉瓦造りのファイアーピットがありますが、使い勝手が今ひとつなのでエンバーリットのパチもんストーブを組み立て小さく燃やしておきます。

小さなウッドストーブを燃やしつつ、イワタニの CB-ODX-1 を点火してスキレットを乗せておきます。スキレットが熱々になる前にオリーブオイルをたっぷりとスライスしたニンニクを入れておきます。

近所のスーパーで買ってきた《特厚》アンガスビーフを半分に切ってレモンソルトと黒胡椒、小麦粉を振って十分に温まったスキレットで焼き始めます。CB-ODX-1 の役目は肉に焼き色をつけるためです。

肉の両面をやや強火でこんがり焼いたら、スキレットに蓋をしてウッドストーブにのせてジックリと火を通します。

肉はある程度火を通してからアルミホイルに包んで寝かせておきます。

肉を焼いたスキレットに厚切りベーコンを入れて火を通しコンビニのカット野菜に乗せて食います。

こんな日はノンアルコールで乾杯ス。THEROS の保温保冷ホルダーに350の缶をはめ込みキンキンに冷えたノンアル飲料をグビグビやります。

肉を焼き終えたらウリ科カボチャ属のズッキーニと残り野菜をスキレットで炒め焼きします。これもウッドストーブで。肉の半分を食ってる内に程よく火が通ります。

今回持っていったキレモノ。左から ESEE 4 SS(薪割り)、ビクトリノックス・アウトライダー(肉切り)、EKA Swede 88(野菜切り)、MORA Classic 2.0(焚きつけ作り)でした。
管理人のおじさんとは18時までと話をしていました、、その後他のキャンパーさんたち三組が来られる予定と聞いておりました。そして、昼飯も食い終わり、蚊取り線香の煙に守られ奥さんの昼寝も済んだ16時頃、先発の一組目が到着、そして『 ◯ X△◇、、、』と聞き覚えのある外国語のイントネーション。そして、隣のサイトへ。奥さんには『早めに撤収すふよー』と一声かけて手際よく片付け二組目の到着と同時に車への積み込みも完了〜。おそらくは、その後すごい賑やかな展開となったことでしょう。『うるさい』とか『マナーが、、』なんて口から出ないうちに、気分が良い内に帰途につきました、、とさ。
ponioでした。
2017年12月06日
続・道具は壊れる

『道具は壊れる』と題した頁をアップしたのは数年前。
道具は使うもの、使わない道具は壊れない、ただし経年による劣化や保管方法や環境によっては自然に壊れることもある、前回といってもかなり前ですが、あれから壊れた道具はというと、、あるある。

たとえばこれ。SKAGEN の薄型 Quartz腕時計。
これは数年前の誕生日にもらった物なのですが、その後
電池式の宿命である電池切れ、電池交換の際にはムーブメントが錆びてるとかで総入れ替え、、とべらぼうな修理代請求され、更にその後またすぐに電池切れ、、そして今回はレザーバンドが付け根からボロっと取れちまった、、。デザイン的には気に入ってたの物だけど、、ひどい壊れっぷりにジャンク扱いとなりました。ちなみにこれ、冠婚葬祭にしか着けてないのですがね。ムーブメントは国産(CITIZENとか)らしいのですが、、濡らした覚えもなく、汗をかく季節にははめてないのに、、モノがダメでしたね。

そして、今回取り上げましたる《こわれもの》はこの方! 三年前の春に買った Black Diamond のヘッドランプ。
製品名は ストーム。旧型で100ルーメン仕様。購入から三年間、毎日ザックのポケットに入れて持ち歩き、年数回のキャンプの際にはうちの奥さんの愛燈としてその頭上に光り輝いておりました。が、、前回の秋キャンプの際に下向きに角度調整しようとしたところ、、まるで椿の花が落ちるようにポロんと落ちてしまいました。

現地はすでに暗くその場で確認することもなく、急遽本体を手持ちのフラッシュライトとして使いました。帰宅してから確認すると、、やはりやっぱり案の定、ヘッドバンドへの取り付け基部、その左右突起がハマる本体側の片方が欠損しておりました。

これがヘッドバンド取り付け基部。このバンド基部には本体の角度調整する際にガチッガチッと何段階かにクリックさせるための板バネ状の加工が施されてあります。
つまりヘッドランプ本体には常に樹脂製の基部からバネのようなテンションが掛かり続けているわけです。これがないと左右から挟み込まれているだけの本体はガクンと下を向いてしまうでしょう。樹脂製の宿命か、常にテンションがかかり続けるハメ込み部分の破損は起こるべくして起こったとも言えますね。

購入から三年、使い道は仕事で暗い場所へ入る時、そして年数回のキャンプでした。誤点灯防止の為のロックアウト機能を備えており、常にそれを機能させておりましたが、これまで何度も電池切れに見舞われました。もちろん、電池は新品でしたが使いたい時に点灯しないことが何度かあり、電池交換すると問題なく使えることから何らかの原因で電池が放電したか、誤点灯していたのかも、、。壊れた部分については修理不能との回答が販売元から届きました。現在はこうして手持ちのフラッシュライトとしても使えるので廃棄にはしませんが、そのうち小さなネジで止めるなど加工してみるつもりです。
続きを読む
2017年08月23日
キャンプと盗難と自衛

キャンプと盗難と自衛
以前からこちらのブログで何度も書かせてもらいましたが私は若い頃にテントと寝袋そして限られた道具を背にあちらこちらと旅する人間でありました。格好つけるとバックパッカーと呼ばれる人種であります。当時はそのほとんどの旅が単独行であり、それ故に独特の警戒心が養われました。

ソロで旅することはとても気ままで誰のペースに合わせる必要もなく、どんなにキツイ旅でも自分と折り合いさえつけばそれで納得できました。たとえ悪天候の中見たかった景色も見られず行きたかった所にも行けず予定していた旅が不完全燃焼に終わってもその道中では自分なりに自分自身とちゃんと折り合いをつけて納得して諦めて気持ちを切り替え旅を続けたものです。
ただ1ついつも気がかりでそれ故にそれなりの警戒と準備をしていたのが天候などの天災と盗難やいたずらなどの人災に対する備えでありました。
今回は後者の人災、盗難への備えについて私なりにやってきた事、今でもやっている事を書きたいと思います。

ソロで旅をし小さなスペースを借りてテントを張り手の届く範囲に道具を置いて小さいけれど自由に野営する。誰にも迷惑はかけないし、何かの邪魔をする気もない。キャンプ場を利用する時もあれば、東屋(四阿)を寝ぐらに一晩明かすこともある。どこかの公園、どこかの岬、どこかの山の中、海辺、、、いつも気にしていたのは人との接触でした。と言っても別に人目を避けて隠れるように野営をしていたわけではありません。有料のキャンプ場ではちゃんと料金は払っていたし(当たり前)、偶然居合わせた他のキャンパーとも関わり過ぎない範囲で旅の話もしました。私の備えの第一はここにあります。人との接触とは不特定多数の人間が行き交う様な場所や目立つ場所で野営をしないということ。仮にそんな所で野営をしていても不特定多数の人間の多くはチラ見してスルーしていきます。が、中には何かしらの興味を持つ人もいるかもしれません。その興味が旅のカタチや会話することにあるのなら問題ありませんが、たとえば使っている道具や所持品に対する興味の中には良からぬ思いが含まれているかもしれない。この部分についてはすべて思い過ごしかもしれませんが。
不特定多数の人間との不用意な接触は場合によっては何かしらのトラブルを招くと考えていました。明るいうちから目立つ場所(キャンプ場以外の)でテントを張りストーブにクッカー乗せて、、なんてことは間違ってもしませんでした。
鹿児島のとある岬の東屋(四阿)にモンベルのステラリッジを張って野営した時も、そこは日中は観光客が行き交う場所で、土産物屋なども並ぶ所でした。夕方近くにそこへ着いて四阿を見つけた時からそこで野営することを決めていました。しかし、観光客や土産物屋の人たちがいる内はテントも寝袋も出さずあくまで歩き旅の途中を装い土産物屋で酒や肴を買い、その土産物屋が閉まり出す頃には一旦目立たない場所に移動して時間を潰しました。この時考えたのが自殺者と間違われない様にということでした。日が沈みかける時間に土産物屋もすべて閉まる頃に独り岬をうろついていたら、、、そう考えたのです。果たして私は土産物屋がすべて閉まった後で四阿にテントを張りそこで一夜を過ごしたのです。勿論、朝一番起き出しテントを撤収し、土産物屋が開く前に野営を引き払いました。人に要らん用心や心配、想像をさせない。それも私流の人との接触なのです。
映画『羊たちの沈黙』でレクター博士が最後に主人公スターリングに与えるヒントの中に “目につくもの、目にするものを切望する”という言葉がありました。そうなのです。目につくことは遭難時などでは助かる可能性が高くなる、一方で不特定多数に目につくことは何か良くない願望を引き寄せることに繋がるかも。若い頃、まだバリバリのヤクザがのし歩いていた頃の大阪ミナミの繁華街を歩く時に身につけた隠れ身の術です。河原でテントを張っていたら石を投げられたと昔読んだことがあります。たぶん、目立ったのでしょうね。
別にコソコソやるのではありません。不用意な接触や目立つことをしないだけです。

ソロで野営していてると突き当たるのがテントを離れる際のことです。瀬戸内のの離島を旅していた時のこと、その日のキャンプ場の近くには離島にしては珍しく温泉がありました。それまで水道で水浴びオンリーだったこともあり、その夜は温泉に行こうと決めましたが問題は荷物です。大きなバックパックに再度荷物を詰め込むなんてバカみたいだしね。結局、夜道を歩く為のフラッシュライトと風呂道具、小銭などを持って、残る荷物のすべてをテントと共に置いていきました。ソロのバックパッキングの途中でテントや寝袋、その他の道具を盗まれたり壊されたりするのは旅の終わりを告げられた様なものです。不安もありましたがテントの中には別に持っていた小さなライトをぶら下げ、外にはUCOのキャンドルランタンを灯して誰か居るように装いました。これは先述した《目につかないように》の逆ですね。誰か居ると思わせる事も時と場合によっては必要なのかも。

時が経って現在、
うちは妻と二人の小さなファミリーキャンプ。
ソロの頃とは違いキャンプ場以外の場所での野営はしていません。東屋泊まりも山の展望台も岬の公園もどこかの海岸での野営も今はもうやりません。歩き旅から車の移動に変わり、荷物も一気に増えました。テントの周りには椅子やテーブル、タープや焚き火台などが所狭しと置かれています。若い頃のソロ旅の癖、習慣から盗難やイタズラへの備えは今でも必ずしています。
キャンプ場から温泉などに行く時は極力二人一緒には行かないようにしている。誰か残らなければならない時は私が残る。買い物もどちらか一人が行く。どうしても二人一緒に出かける時にはストーブなどの備品は車に積む。テントの入り口にサンダルなどを置いておく。これらは利用するキャンプ場とその日の混み具合と雰囲気による。
夜は椅子や大きなランタン類、ストーブや燃料は車に収納(オートキャンプの場合)。特にナイフや斧などのキレモノ類は人目に付かないように収納しておく。カラスやその他の動物の餌になりそうな食料品も車やテントの前室に。
人を疑い出せばキリがない。疑うことは心配や不安を呼び起こし要らん備えをするハメになる。
でもね、若い頃の大阪暮らしで染みついた用心やソロのバックパッカーだった頃に身についた備え、そして今では守るべき家族もいるわけで、用心には用心が私の当たり前になっているのです。
目に付いた物が欲しくて、自分の物にしたくて他
人の物を盗む人に加えて現代では盗んだものを転売する(金に換える)奴もいるようだ。後者は何でもいいから金目と思うものを狙うわけでタチが悪い。盗まれた物はその人にとってとても大切で特別な物かもしれない。また買えばいいさなんてお金に余裕のある人ばかりではない。大阪で商売をしていた頃には病的な万引き常習犯を何人も見てきた。現行犯で捕まえて警察に引き渡しても数日すると何食わぬ顔でまた現れ同じことを繰り返す。『あ、どうも!^_^』なんて挨拶までしてくる。キャンプ場での盗難はそんな病的な万引き常習犯とは違う。金儲けの手段としての窃盗であり、物欲の行き着く果ての窃盗かもしれない。
ただでさえそんなニンゲンが誰かの何かを狙ってるかもしれないのに、盗んで下さいとばかりに道具を並べた無人のサイトはニンゲンに良からぬ欲望を掻き立てさせるのかもしれない。
その気を起こさせないこと、それが何よりの用心であり備えなのかもしれません。
続きを読む

















