2018年12月25日
年末年始キャンプの道具選び その❸
年末年始キャンプの道具選び その❸

薪ー!!今年もまたいつものおじさんから買い付けました。椎の木の薪でかなりゴツい。キャンプ2泊分と伝えて用意していただいた。これで¥2.000也。実は去年の暮れも同じ量を買いましたが、、まだ一、二本残ってます。かなり使ったつもりですが、、。さあ、現地に着いたらまた薪割りしなきゃね。


サーマレストの自膨式マット(フルサイズ)とリッジレスト(下)。上のマットはもう20年ほど前に買ったものです。いまだパンク、エア漏れなし。リッジレストは用途に合わせてカットしたものもあります。

銀マットは分厚いロールタイプ。大判の物を真っ二つにカットして収納しやすくしてあります。冬場はこの上にサーマレスト、ホッカイロ、ボアシーツを重ねて温ぬく仕様にします。

小型のバッグに詰めて持っていく《明かり》。小型の LEDランタンとキャンドルランタン。二人分のヘッドランプ。予備の電池、キャンドル、、など。これに灯油のフュアハンドランタンとジェントスのLEDランタン(エクスプローラー)が加わります。

奥さんの B-6君 と100均の200円商品(折りたたみ椅子とステンレストレー)。B-6君 は熱のインパクトが下方に伝わりにくいためトレーと椅子の間には滑り止めシートが貼ってあります。

あれ?手入れしてたはずなのに、、忘れたか?
B-6君 のハードロストルが錆び錆びに、、。研磨パッドで磨き洗いして魚焼きグリルで軽く焼いてから油を塗って更に焼く、、これでOK。

いい色になりました。


《キレモノ》は悩みましたが、、この3本のシースナイフを持っていきます。3本とも異なるブレードシェイプです。ホロー気味のセイバー、コンベックス気味のフラット、スカンジグラインド。ホントは一本あれば事足りるのに、ゆとりです、心のゆとり。使いたいから持っていく。それも有りです。

テーブルはワンアクションで。これより大きいと単なる道具や食器の置き台になってしまう。夫婦二人ではこれくらいが丁度良い。うちの車(SUZUKIの軽)でも余裕で積み込める。これも全会一致で決定。今回はこれに板を一枚加えて二段式にする予定。

折りたたみバケツは昼間はぶら下げられる道具入れとして、夜は寝る前の足湯に使われます。

Hip flask
スキットルとも呼ばれる。素材はピューター(錫)アルコール濃度の高い蒸留酒専用。
私はこれにラムか、電気ブランを入れる。
冬キャンプの必需品スネ。

薪ー!!今年もまたいつものおじさんから買い付けました。椎の木の薪でかなりゴツい。キャンプ2泊分と伝えて用意していただいた。これで¥2.000也。実は去年の暮れも同じ量を買いましたが、、まだ一、二本残ってます。かなり使ったつもりですが、、。さあ、現地に着いたらまた薪割りしなきゃね。


サーマレストの自膨式マット(フルサイズ)とリッジレスト(下)。上のマットはもう20年ほど前に買ったものです。いまだパンク、エア漏れなし。リッジレストは用途に合わせてカットしたものもあります。

銀マットは分厚いロールタイプ。大判の物を真っ二つにカットして収納しやすくしてあります。冬場はこの上にサーマレスト、ホッカイロ、ボアシーツを重ねて温ぬく仕様にします。

小型のバッグに詰めて持っていく《明かり》。小型の LEDランタンとキャンドルランタン。二人分のヘッドランプ。予備の電池、キャンドル、、など。これに灯油のフュアハンドランタンとジェントスのLEDランタン(エクスプローラー)が加わります。

奥さんの B-6君 と100均の200円商品(折りたたみ椅子とステンレストレー)。B-6君 は熱のインパクトが下方に伝わりにくいためトレーと椅子の間には滑り止めシートが貼ってあります。

あれ?手入れしてたはずなのに、、忘れたか?
B-6君 のハードロストルが錆び錆びに、、。研磨パッドで磨き洗いして魚焼きグリルで軽く焼いてから油を塗って更に焼く、、これでOK。

いい色になりました。


《キレモノ》は悩みましたが、、この3本のシースナイフを持っていきます。3本とも異なるブレードシェイプです。ホロー気味のセイバー、コンベックス気味のフラット、スカンジグラインド。ホントは一本あれば事足りるのに、ゆとりです、心のゆとり。使いたいから持っていく。それも有りです。

テーブルはワンアクションで。これより大きいと単なる道具や食器の置き台になってしまう。夫婦二人ではこれくらいが丁度良い。うちの車(SUZUKIの軽)でも余裕で積み込める。これも全会一致で決定。今回はこれに板を一枚加えて二段式にする予定。

折りたたみバケツは昼間はぶら下げられる道具入れとして、夜は寝る前の足湯に使われます。

Hip flask
スキットルとも呼ばれる。素材はピューター(錫)アルコール濃度の高い蒸留酒専用。
私はこれにラムか、電気ブランを入れる。
冬キャンプの必需品スネ。
2018年12月19日
Trangia グルメフライパン 307260

Trangia GOURMET FLYPAN
Φ 200×75 mm


Trangia のフライパンです。Trangia といえばスウェーデン製ですが、このフライパンは米国のジャクソンビル(フロリダ)からシンシナティ(オハイオ)を経由して日本までやって来ました。品番は 307260で GOURMET FLYPAN と言います。しかし、現物はメーカーのカタログ写真やweb の画像、外箱の写真とは少し異なる部分があります。どこのメーカーも仕様の変更は常ですが。


今から20数年前に一眼で撮った写真です。連れと二人であちこち歩き旅していた頃の写真ですが、当時使っていた Trangia の同型フライパンが写っています。よく見ると何か違いますね。熱源はボルドーバーナーとアルコールバーナーですね。


拡大してみると、、ハンドルが違います。そして、リッド(蓋)です。この写真のリッドにはツマミがありません。つまりこれは、蓋の役目をする皿なのです。そして、ハンドルの形状が違うのは、このお皿を蓋のように被せた状態でハンドルが畳める様ハンドルの付け根部分が長くデザインされています。更にストームクッカーの様にストラップをかける為のループが設けられています。この部分はストームクッカーがベース部分に切り込みを入れて起こしたループなのに対して、フライパンの方は別パーツとなっていました。

20数年前のものは、これですかね(写真は現行カタログより)


それに対して、、今回、米国から送られてきた 307260 という製品は収納時にリッドを裏返した状態でフライパンにはめ込みます。ハンドルはリッドの切り込みにはまり込む形で畳まれます。収納時の高さ(厚み)を抑えた形状です。そしてストラップを通すためのループは設けられておりません。かわりにハンドルが固めに畳まれるので収納時にこれが押さえとなってバラけません。

この関節部が固めに作られておりフライパンを振って使う時にも安心です。以前使っていたモデルはこの部分が緩くフライパンを振ると簡単に折れた状態になって、最悪フライパンが手前にひっくり返ることもありました。

収納時はこんな感じになります。リッドのくぼみに備品が収まりますね。

リッドのツマミはこのような形状になっています。エッジが立っていて手を切りそうでしたが、研磨パッドでひと擦りして解決。

フライパンの底面はこのようなポリッシュ加工になっています。滑り止めと熱の伝達効果ですか。

ノンスティックコーティングは他のものと変わらない様に見えます。金属製のスプーンやフォークなどは使用しないのが鉄則。スプーンなどは出来ればシリコーン製、箸も木製がよろしおすえ〜。それと、強火での空焚きは厳禁です。ノンスティックコーティングが剥離します。炒め物するなら食材を揃えてから、、フライパンを火にかけてから食材をカットしたり、あれこれしてる間にノンスティックコートが傷んでしまうかもしれません。火にかけるなら弱火でね。

同社のストームクッカー25(サイズ L )のフライパンとの比較。外側の大きな方がストームクッカーのもの。GOURMET FLYPAN の直径は200mmです。

そして、深さもこの通り。カタログでは75mmとあります。ストームクッカーのフライパンにグルメフライパンを重ねると深さにこれだけの差が出ます。この深さこそ、このフライパンの強みでもあります。これはフライパンであり、浅型の鍋でもあるのです。ソテーパンみたいな感じかな。水を入れると300ml の計量カップで4杯、満水(縁ギリギリ)まで入れると1300ml は入りそうです。ただ、沸騰時に溢れることを考えて実用満水は900ml〜1000ml位が適当でしょう。ちなみに、ほぼ満水の状態でも注ぎはきれいに出来ました。さすがです。

このフライパンでお湯を沸かしてみると、ノンスティックコートやテフロン加工特有の気泡の立ち方をします。細かな気泡が全体的に広がって、まるで『ポニョ』の世界。アルミの熱伝導の良さも一役かっています。
そして、注ぎは、、本来ならフライパンに注ぎの上手さを求めたりしてはいけないんだけど、、。

この通り、さすがの Trangia !宣伝文句にも載っていない地味な持ち味だけど、小さな湯のみに一滴もこぼさず注ぎ切れるのは巧みな縁加工とコーティングの賜物。だから、これでお湯を沸かしてコーヒー淹れるのはナンセンスでも何でもないのです。

そして、お湯を注ぎ終えたあとは、、この通り水滴も残らず。地味なことですが使い勝手の良さを感じます。

このフライパンて袋入りラーメンを茹でてみます。一袋分なら余裕です。1.5杯分のスープで四つ割りにした麺二袋分を茹でられます。スープが足りないと思うなら先に一袋分を食べてから、残ったスープに少しの水を加えてもう一袋分の麺を茹でます。この時、新しいスープの素はほんのわずか加えるだけです。全部加えると濃すぎて食べられません。


うまかっちゃんバリカタ二袋分をそれぞれに四つ割りにしてグルメフライパンに並べると、、こうして平面状に収まります。このまま沸沸と煮立てて粉末スープは1袋とほんの少しだけ。四つ割りにすることで麺が適当な長さになって取り分けしやすく食べやすいのです。

20数年前の再現。Trangia 純正五徳とアルコールバーナーの組み合わせ(100230 Open spirit stove)をステンレス製のファイアベースで囲むスタイル。五徳とファイアベース、アルコールバーナーは当時の物です。よくぞ生き残っていたもんです。
20数年前の記憶は、、滋賀県の三上山の頂上で連れと二人分のチキンライス(冷凍食品)を作り、琵琶湖の西、比良山の山中でソーセージを焼き、兵庫県のどこかの山中で炒飯を作って食った記憶。当時、Canon の一眼レフで撮った写真には冬、無積雪の山頂でチキンラーメンを2人前作り食ってるものがあります。バーナーはTrangia のアルコールバーナーだったり、エスビットストーブ二個を五徳のかわりにしたボルドーバーナーだったり、、。

あの頃の自分は何をどう考えて Trangia を選びあのフライパンを持ってあちこち旅していたのか、、嵩ばらなかったのか? 重くなかったのか? いまでも同じものを持ち歩くだろうか、、ステンレス製のファイアベースに据え置き型の Trangia の五徳、エスビットストーブ二個とボルドーバーナー、、あの頃はあれしかなかったから、かな? いや、ちがう。あれはあれで、ちゃんと考えて揃え持ち出した道具だったのだ。それにしても、なんでフライパン? なんでボルドーバーナー? あの頃の自分に会って聞いてみたい、そんな気がします。
ponio でした。
2018年12月18日
年末年始キャンプの道具選び その❷
年末年始キャンプの道具立て選考委員会
道具立て選考委員会、毎度のごとく招集されまするキャンプ準備班並びにキャンプ道具選考委員会(共にアタシ一人(^_^;))。近年は道具立ても固定化されて一頃よりは随分と楽になりまして候。小さな車に山のごとく荷物を積み込んで風林火山の旗閃かせ(なんでや!)、、そんな日々は過ぎ去り一時はシンプルを絵に描いたような道具立てで臨んだものの、、何か物足りない!つまらない!と無駄〜な遊び道具を持ち出すユトリを取り戻して候。
今回はその第2回、、
まずは決定者から、、

キャンプブーツ・・弘進ゴムの防寒ラバーブーツ《マックウォーカー》旧型。前回2017年末から2018正月の極寒キャンプの経験を踏まえて今回は Bean Boots ではなくこれを現地で履き替えるキャンプブーツに決定。

ウッドストーブ・・意外や意外!な選考となりました。エンバーリット型のパチモン・ストーブです。Coleman の焚き火台あるやろー!と選考委員会からも怒号がとんだが、そこはアタシの鶴の一声『よかよかー』と西郷どんよろしく押してやり申した。これは昼間の焚き火に使うのでありんす(誰やねん、、)。初日の昼から薪をガンガン焚いては二日目の朝に薪が切れてさぶ〜〜い思いをするのがオチです。だから、昼間はこれを焚き火台の上に据えて薪の節約です。決定。

湯沸かし・・KELLY KETTLE。これまた!意外!ひたすら湯を沸かし続ける為だけのケリー爺さん。薪を有効に使うためです。ただし、これ沸かせるお湯の量が少ないんですよね。

キレモノ・・EKA Swede 88 これは文句なく全員一致で選考。もともとキャンプナイフとして購入したものなので。

燃料その1・・松ぼっくり。着火用として奥さんが大量に消費されますので、、毎回持っていくと言うか、、拾い集める私です。

キッチンナイフ・・MORA 2010 わが家の野営調理兼自宅調理用ナイフ。文句なく選出。

なんとなく使いたいポット・・MSR チタンケトル。単体で湯沸かししても、コーヒーのドリップ用としても、注ぎ上手で容量も問題なし。強権発動で当確。

遊び・・遊びです、遊び。東京マルイさんの18歳エアーコッキング。HOP仕様。

保温効果・・ダブルウォールのカップ(ユニフレームゆのみ)は奥さん用に。アタシは Coleman のステンレスマグ。これで良いでしょう。

カップでもボウルでも・・スウェーデン軍用のカップ。飲み物でもカレーやシチューでも、なんでもござれで選考に外れためしのない常連さん。

いつもの鍋・・Trangia のノンスティックのソースパン。1.75と1.5Lの重ねで持っていく。湯沸かしでも調理でもなんでもござれ。決定。

椅子・・キャンパーズコレクションのリクライニングチェアーは2010年の購入以来、一年365日使ってる完全なる日用品である。一脚は2年ほど前にアタシが座り損ねてパイプが折れ新しく買い直したものです。大きさが違います。それにしても使い続けて8年、いやもうすぐ9年でっせ!しかも365日使っての話、、すごい!
第二回道具選考委員会
ponio でした。
道具立て選考委員会、毎度のごとく招集されまするキャンプ準備班並びにキャンプ道具選考委員会(共にアタシ一人(^_^;))。近年は道具立ても固定化されて一頃よりは随分と楽になりまして候。小さな車に山のごとく荷物を積み込んで風林火山の旗閃かせ(なんでや!)、、そんな日々は過ぎ去り一時はシンプルを絵に描いたような道具立てで臨んだものの、、何か物足りない!つまらない!と無駄〜な遊び道具を持ち出すユトリを取り戻して候。
今回はその第2回、、
まずは決定者から、、

キャンプブーツ・・弘進ゴムの防寒ラバーブーツ《マックウォーカー》旧型。前回2017年末から2018正月の極寒キャンプの経験を踏まえて今回は Bean Boots ではなくこれを現地で履き替えるキャンプブーツに決定。

ウッドストーブ・・意外や意外!な選考となりました。エンバーリット型のパチモン・ストーブです。Coleman の焚き火台あるやろー!と選考委員会からも怒号がとんだが、そこはアタシの鶴の一声『よかよかー』と西郷どんよろしく押してやり申した。これは昼間の焚き火に使うのでありんす(誰やねん、、)。初日の昼から薪をガンガン焚いては二日目の朝に薪が切れてさぶ〜〜い思いをするのがオチです。だから、昼間はこれを焚き火台の上に据えて薪の節約です。決定。

湯沸かし・・KELLY KETTLE。これまた!意外!ひたすら湯を沸かし続ける為だけのケリー爺さん。薪を有効に使うためです。ただし、これ沸かせるお湯の量が少ないんですよね。

キレモノ・・EKA Swede 88 これは文句なく全員一致で選考。もともとキャンプナイフとして購入したものなので。

燃料その1・・松ぼっくり。着火用として奥さんが大量に消費されますので、、毎回持っていくと言うか、、拾い集める私です。

キッチンナイフ・・MORA 2010 わが家の野営調理兼自宅調理用ナイフ。文句なく選出。

なんとなく使いたいポット・・MSR チタンケトル。単体で湯沸かししても、コーヒーのドリップ用としても、注ぎ上手で容量も問題なし。強権発動で当確。

遊び・・遊びです、遊び。東京マルイさんの18歳エアーコッキング。HOP仕様。

保温効果・・ダブルウォールのカップ(ユニフレームゆのみ)は奥さん用に。アタシは Coleman のステンレスマグ。これで良いでしょう。

カップでもボウルでも・・スウェーデン軍用のカップ。飲み物でもカレーやシチューでも、なんでもござれで選考に外れためしのない常連さん。

いつもの鍋・・Trangia のノンスティックのソースパン。1.75と1.5Lの重ねで持っていく。湯沸かしでも調理でもなんでもござれ。決定。

椅子・・キャンパーズコレクションのリクライニングチェアーは2010年の購入以来、一年365日使ってる完全なる日用品である。一脚は2年ほど前にアタシが座り損ねてパイプが折れ新しく買い直したものです。大きさが違います。それにしても使い続けて8年、いやもうすぐ9年でっせ!しかも365日使っての話、、すごい!
第二回道具選考委員会
ponio でした。
Posted by ponio at
14:00
│Comments(0)
2018年12月16日
年末年始キャンプの道具選び その❶
年末年始キャンプ道具立て選考委員会
持ち出し決定の方々〜♪

テント・・Quechua ポップちゃん
もうこれしかねぇべ!ってな感じで満場一致の大喝采。
今年もこれで極寒を乗り切る。設営と撤収の手間と時間を大幅に縮小できたのはこのポップちゃんのおかげです。

タープ・・KELTY Noah's Tarp 12
ポップちゃんとは対照的にいつも苦労して張るタープは雨対策のためだけ也。

タープ・・snowpeak ポンタシールド
KELTY が雨対策なら、ポンタは風対策也。

サブシェルター・・Quechua Arpenaz 0
薪や燃料、夕方から使うランタンなどを置いておく倉庫代わりのシェルター。

焚き火台・・Coleman FIRE DISK
これも、これしかねぇべ!後片付けが超簡単。

七輪は冬の定番。焼き物、煮物、沸かし物どれをとっても柔らかく火が通り、空気の流入を調整し燃焼の具合を長くも、強くもコントロールできる。うちの奥さんがほぼ独り占めします。

テーブルトップ グリル・・笑's B-6君
奥さんの小さな焚き火道具。テーブルトップで灰をまき上げながら何か焼いたりケトルを沸沸させたり。

灯・・ランタン各種
これも満場一致で採択された軍団です。

ノコギリ・・BAHCO 396 & silky POCKET BOY 細目。薪を割る前にこれで短くしておきます。

薪割り・・GransforsBruks ワイルドライフ ハチェット
薪を割るならこれです。今年も椎の木の薪を買う予定なのでこれは必須です。


Klean Kanteen 、サーモス、象印、、など。テーブルトップの水入れとして、沸かしたお湯のストックボトルとして、これまた必須アイテム。文句なく決定。

Trangia メスティンは当然のように飯炊き専用。わが家はキャンプでは白飯をあまり食べません。炊くとしたらこれくらいで十分です。持ち出し許可。

ワークグローブはなくてはなりません。薪や焚き火いじりには特に必要です。

マルチプライヤーも絶対外すことのできないツール。ペグ抜きから焼き網の持ち上げ、炭をカチ割ったり、ハリガネ曲げたりととにかくよく使います。何かを忘れてもこれだけは忘れてはいけない。満場一致で決定。

バウルーは餅を焼くのに使う。これに左右二個ずつの丸餅を挟んで七輪でジンワリと焼くと二つの大きな餅がこんがりと出来上がる。正月キャンプの必須アイテム。アタシの一押し。

シュウ酸両手鍋も冬キャンプの必需品。洒落たクッカーより遠慮なく使える。容量たっぷりで、翌日の分まで作り置きできる。奥さん一押しで即決。


ヘッドランプ・・夫婦それぞれのヘッドランプ。夏場とちがって頭に虫が集まることがないからいいね。予備の電池も揃えた上で忘れずに持っていく。

フライパン・・LODGE スキレット 8 焚き火台で網焼きかホイル焼きするなら要らないかも、しかし、道具立て選考委員会からの圧力に屈して持っていくことに、、。

Java press・・旨いコーヒーや綺麗なお茶を淹れるのに手軽な道具。二人分としてもちょうど良いので持ち出し決定。

調理用ナイフ・・文句なく選ばれました。
第一回選考委員会
ponio でした。
持ち出し決定の方々〜♪

テント・・Quechua ポップちゃん
もうこれしかねぇべ!ってな感じで満場一致の大喝采。
今年もこれで極寒を乗り切る。設営と撤収の手間と時間を大幅に縮小できたのはこのポップちゃんのおかげです。

タープ・・KELTY Noah's Tarp 12
ポップちゃんとは対照的にいつも苦労して張るタープは雨対策のためだけ也。

タープ・・snowpeak ポンタシールド
KELTY が雨対策なら、ポンタは風対策也。

サブシェルター・・Quechua Arpenaz 0
薪や燃料、夕方から使うランタンなどを置いておく倉庫代わりのシェルター。

焚き火台・・Coleman FIRE DISK
これも、これしかねぇべ!後片付けが超簡単。

七輪は冬の定番。焼き物、煮物、沸かし物どれをとっても柔らかく火が通り、空気の流入を調整し燃焼の具合を長くも、強くもコントロールできる。うちの奥さんがほぼ独り占めします。

テーブルトップ グリル・・笑's B-6君
奥さんの小さな焚き火道具。テーブルトップで灰をまき上げながら何か焼いたりケトルを沸沸させたり。

灯・・ランタン各種
これも満場一致で採択された軍団です。

ノコギリ・・BAHCO 396 & silky POCKET BOY 細目。薪を割る前にこれで短くしておきます。

薪割り・・GransforsBruks ワイルドライフ ハチェット
薪を割るならこれです。今年も椎の木の薪を買う予定なのでこれは必須です。


Klean Kanteen 、サーモス、象印、、など。テーブルトップの水入れとして、沸かしたお湯のストックボトルとして、これまた必須アイテム。文句なく決定。

Trangia メスティンは当然のように飯炊き専用。わが家はキャンプでは白飯をあまり食べません。炊くとしたらこれくらいで十分です。持ち出し許可。

ワークグローブはなくてはなりません。薪や焚き火いじりには特に必要です。

マルチプライヤーも絶対外すことのできないツール。ペグ抜きから焼き網の持ち上げ、炭をカチ割ったり、ハリガネ曲げたりととにかくよく使います。何かを忘れてもこれだけは忘れてはいけない。満場一致で決定。

バウルーは餅を焼くのに使う。これに左右二個ずつの丸餅を挟んで七輪でジンワリと焼くと二つの大きな餅がこんがりと出来上がる。正月キャンプの必須アイテム。アタシの一押し。

シュウ酸両手鍋も冬キャンプの必需品。洒落たクッカーより遠慮なく使える。容量たっぷりで、翌日の分まで作り置きできる。奥さん一押しで即決。


ヘッドランプ・・夫婦それぞれのヘッドランプ。夏場とちがって頭に虫が集まることがないからいいね。予備の電池も揃えた上で忘れずに持っていく。

フライパン・・LODGE スキレット 8 焚き火台で網焼きかホイル焼きするなら要らないかも、しかし、道具立て選考委員会からの圧力に屈して持っていくことに、、。

Java press・・旨いコーヒーや綺麗なお茶を淹れるのに手軽な道具。二人分としてもちょうど良いので持ち出し決定。

調理用ナイフ・・文句なく選ばれました。
第一回選考委員会
ponio でした。
2018年12月08日
ハサミの底力 レザーマン RAPTOR


LEATHERMAN RAPTOR ®️
メディカルシザーズ(緊急時の医療用)としてLEATHERMANから販売されているハサミです。日本では2015年の夏くらいからAmazonでも扱われ出しました。折りたたみ可能でメカニカルな構造とストラップカッターなどいくつかの機能を加えてお得意のマルチプライヤー路線から飛び出した製品と言えます。わたしは個人的に高齢者や障がいを持つ方に携わる仕事を長年していますが医療関係者ではありません。病院には毎日のように行っておりますが医療に関する専門的な知識も技術も持ち合わせません。独学では浅く広く勉強しておりますが、目の前の高齢者や障がいを持つ方たちから学ぶことの方が多いのが現実です。

そんな私が医療用のハサミなんて、、実はわたしは若い頃から様々な道具で本来使う目的以外の使い方をしてきました。この医療用のハサミもけっしてケガ人の衣類を切り裂いたりシートベルトをカットしたり(これはあり得るかも?)指輪を切ったり酸素ボンベのバルブを回したりする為に買ったのではありません。それは専門職のお仕事だからです。もちろん、コレクターでもないので何かに使う為にこれを選んだのです。


LEATHERMAN Made in USA

独特の樹脂製ホルスターに収められた RAPTOR 。これを腰につけて、取り出し収めるにはある程度の慣れが必要です。形状が複雑で差し込む方向が決まっているからです。無意識のうちにそれができるようになるまで少しかかるでしょうね。面倒ならホルスターは使わずにポケットクリップを使用する手もあるので便利です。

この独特のホルスターはネジを緩めれば360°の回転式。パドルタイプのベルトクリップは一度差し込むと外すのが一苦労。こっちを外せばあっちが引っかかるといった感じです。ホルスターの角度は人それぞれ、わたしは真下に向けて抜くようにセットしています。写真は真上に抜くようにセットした状態。

この写真の中に、、ポケットクリップ、ランヤードホール、ガラスブレイカーの機能が見て取れます。ランヤードホールは、、私は使わないでしょうね。

カーバイド製のガラス割り。グラス(ガラス)ブレイカーと呼ばれる突起です。車などの分厚いガラスを叩き割るのに使うものですが、、他になにか使い道は、、あるかな?縄文式土器を作る時に模様をつけるとか、、使わん使わん、、ポールペンなら良かったのに。

この写真にはハサミ以外に《切る》機能が見えています。ロック式のストラップカッターです。親指で回転させると開きロックがかかります。



ストラップカッター。V字の片刃です。これで、シートベルトや衣類をカットできます。荒く仕上げられたV字の片刃は薄い紙でもスパッと切れます。紐やコード、ダンボールも切れます。これは使いようですね。

この板状のものがストラップカッターのロックスプリングです。解除はKEYマーク部分を押し込むだけです。

RAPTOR のハサミのとしての生命線でもあるギザ刃。まるでヤスリのような仕上がりです。これが布地などを逃さずカットするのに役立ちます。こうしてアップで見ると紙などをきれいに切る様な繊細な作業は難しいと感じますが、、。

意外とそうでもありません。ギザ刃なので刃を滑らすような裁ちハサミ特有の切り方は無理です。また刃の長さからそれほど多くの部分を一度に切ることはできません。左回りに弧を描くような切り方は簡単にできますがブレードの厚みがあるので右回りはかなり難しく感じます。これは、紙細工をするためのハサミではないからです、それで納得。

こう見ると、、多少メカニカルな文具に見えなくもありません。

ギザギザ〜〜

分厚っー!

この写真の中心部に見える三角形のボタンがハサミのロック解除ボタンです。裏表にあってこれを押してハンドルを片方ずつたたみます。

これがリングカッター。指輪切りです。海外の動画ではキーホルダーのリングを切っていましたね。ワイヤーカッターとしても使えます。

かわいい顔のオウムちゃん。噛む力はすごいものがある。

独特の先端部は衣類と身体の間を傷つけないように動くための形状です。

三種のマルチツールを並べて、、大きさと重さの比較。
一番上(奥)はビクトリノックスの Swiss Tool Sprit (マルチプライヤー)、真ん中が同じビクトリノックスのアウトライダー(ナイフ他)、手前が LEATHERMAN RAPTOR 。大きさ的には RAPTOR が平面的な大きさを感じますが厚みだけならアウトライダーです。オールステンレス製の Swiss Tool Sprit は一番コンパクトながら重量はダントツで重く機能数も一番多い。

結束バンドも簡単に切れます。この結果こそ私がこのハサミに望んだ多様な《切る》作業なのです。


このパドル(クリップ)部分が便利そうで使いづらい。差し込むのも取り外すにも苦労する。米軍の MOLLEシステム対応なので差し込み部分が左右に二分割されており、これがなんとも使いにくい。ベルトやストラップではなくズボンに直にクリップする方が簡単。本体は逆さに向けても落ちることはない。

ポケットクリップを使えばホルスターの煩わしさから解放されるね。

このホルスターからの出し入れに慣れるためなるべく身につけて使っている。そのうち機械的に抜き差しできるようになるだろうね。

さて、届いた翌日にいきなりの本番到来!仕事先で別件として頼まれたカーペットの処分。市の粗大ゴミセンターに確認を取ったところ有料の可燃物用ゴミ袋でも出せますとのこと。ただし、最大45Lの袋に入れて上を結ぶことができること、人が片手で持っても破れない重さであることが条件とのこと。ガッテン!承知の助!これを予期したわけではなかったが、届いたばかりの RAPTOR を試す良い機会だと判断してザックから取り出した。いざ!

1.8m四方で中程度の厚さのカーペットをベランダで三等分に切り分ける。RAPTOR さんはジョリジョリと問題なく切り進むが、、カーペットの毛が凄まじい。一片を切り終わる頃には、、

RAPTORさんもこの通り。この作業、施工の専門家なら何を使うか?オルファのゴツいカッターナイフでしょう。裏面から刃を当てて一気に切り分ける。スマートで効率的。残念ながら、こんな作業が時には舞い込む私の仕事ですが、オルファのゴツいカッターナイフを私は持ちません。(小さいのならある)今回、もし RAPTOR か無ければどうしていたかな?切り分けせずに粗大ゴミ(有料のシールを貼って、指定された日時に指定場所に置いておく)扱いにするか、手持ちの道具、たとえば 常に持ち歩くマルチプライヤーに付いた片刃のナイフで切り裂くでしょうね。でも、以前にも何度かやったことがありますが、カーペットをナイフなどで切ると予想以上に早くエッジが摩耗するのです。以前、表に野ざらしになっていたカーペットを頼まれて切り分けた時は庭木の処理用に持ってきていた カーボンスチール鋼の MORA を使いました。切り分けることは可能でしたが、最後はエッジが摩耗してほとんど丸坊主に、、押しても引いても切れない状態になりました。適材適所、専門的分化はどこの世界でも必要です。

今回いきなりの本番で期待通りの結果を残してくれた RAPTOR 。これまで当たり前のようにナイフでやってきた作業をこれからはコヤツがやるのか?どんな場面で何にどう使うのか、それを前もってシュミレーションしておくことが大切。そうじゃないと、使える場面で瞬時に使う判断ができません。

帰宅して温水シャワーできれいさっぱり丸洗い。ベランダで日光浴と冬の風に当てて自然乾燥させる。


若い頃より様々なシーンでお世話になってきた LEATHERMAN のツール。その LEATHERMAN の造りしハサミ。きっと雑多で多様な作業にも使えるはず。がんばってくだされー、、、。
続きを読む
2018年12月06日
生き残るかストームクッカー


ストームクッカー(Trangia )はわが家のキャンプシーンにはなくてはならない道具として今日まで一軍レギュラーの座に君臨してきました。テントやタープ、車までが変わっていく中でこのアルコールバーナーを核としたクッキングシステムだけは常に生き残りその存在価値を高めてきたのです。しかし、、
ある日、あるキャンプの後でふと、気がついたのです、、
あら? 今回はストームクッカーあまり使わんかったなぁ、、と。

その回は主に焚き火台と小さなウッドストーブ、奥さんのB-6君が熱源としてフル稼働、ストームクッカーは現地に着いてすぐの湯沸かしと、翌朝一番の湯沸かしに使われただけでした。

焚き火台と七輪の存在がソロ時代からの液体燃料系ストーブやバーナーをキャンプの第一線から追い出し始めたのはもう何年も前のこと。それに妻のB-6君が加わり、アタイの小さなウッドストーブも持ち込まれるようになって、、それらはどれも薪や炭を燃やし熾して得られる高い熱量と熾になってからの豊富な余熱を武器にガスやガソリンを燃料とするストーブとバーナーを第一線から追い払っていったのです。そんなストーブとバーナーたちが苦難の時代にあってストームクッカーだけは素知らぬ顔して生き残ってきました。
しかし、あるキャンプでわが家のストームクッカーが湯沸かし専用となっている現状に気づいた時アタシは軽いショックを受けました。

その後も毎回のようにストームクッカーは持ち出されていますが、わが家のキャンプシーズンが夏場を避けるようになって、主なキャンプが秋冬にと変わっていくと熱源も次第に暖をとれる焚き火台と七輪、ウッドストーブへと変化していきました。

ストームクッカーがテーブルの真ん中で湯を沸かし、鍋を煮立て、煮込み、フライパンで炒め物していたのは遠い昔のことのようです。
ただ、焚き火ができない環境や軽めのデイハイクやドライブランチでは相変わらずバリバリの第一線で活躍しているストームクッカーです。しかし、わが家のキャンプシーンを冷静に見つめ返した時、果たしてストームクッカーは持っていくべきかどうかと自問するようになったアタシです。そして、今年、遂にストームクッカーを持ち出さないキャンプを経験しました。奥さんと二人のキャンプを始めて9年余り、、購入以来初めてのストームクッカー無しのキャンプでした。


そして、、
昨年末から正月の年越し極寒キャンプではアルコールバーナーの代わりにガソリンストーブである MSR のウイスパーライトINLが無理矢理ストームクッカーに組み込まれました。アルコール燃料の代わりにホワイトガソリンを燃料とするストーブがストームクッカーの核となって次から次へと湯を沸かし続けたのです。もともと、Trangia はストームクッカー用のガソリンバーナーを販売しています。ガスのユニットを含めるとストームクッカー自体三種類の燃料の使い分けができる仕組みです。ただ、純正のガソリンバーナーが高額なのでなかなか手が出ません。ウイスパーライトINLを無理矢理組み込んでまでストームクッカーをガソリンストーブ化したのは連続燃焼の時間が長くて冬場でも強い火力が保てるからです。予熱作業(プレヒート)という面倒なプロセスも加わったけど、、慣れてることなので苦にはなりませんでした。




七輪に始まった木質燃料を使う熱源たちは、炎の魅力と暖をとれる熱量と有り余る余熱でストーブやバーナーから仕事を奪っていきました、、というか夫婦そろってハマっただけなのですが、、。

すべての液体燃料系ストーブやバーナーは点火と消火、ON と OFF が必要ですよね、、あたりメェーヨー!って、、そうなんですが、、焚き火台も七輪も小さなウッドストーブも熾火になってからの豊富な余熱で湯沸かしをし続けたり煮込み料理やホイル焼きや、バタバタ扇いで火勢を上げてやれば再び強い火力を得られます。その辺の余力というのか、木質燃料の底力ですよね。しかし、その一方で、、七輪や焚き火台の登場で自分自身が焚き火にべったり張り付いて過ごすことが多くなりキャンプの記憶が《焚き火だけ〜》ってことも度々。これはジレンマでした。その点、ストームクッカーを含めたストーブとバーナーは ON と OFF の切り替えが点火と消火だけではなく、キャンプの中の時間の切り替えに繋がっていたのですね、、。反省しきり。

ノンスティックのソースパンとストームクッカーのコンビネーションによる飯炊きもキャンプの定番でしたが、、最近のキャンプでは白飯をあまり食わなくなりましたので、今はメスティン炊飯で足りています。


湯を沸かすだけでも出来れば一度にたくさん沸かしたい。手持ちのクッカーでストームクッカーにフィットして湯を沸かせる最大容量のものは GSIピナクル・デュアリスト(1.8L)です。満水 1.8 なので実用満水は1.6L前後です。せめて2Lあれば余裕なのですが。
今年の暮れに予定されている年越しキャンプでも予想されるのは着いた早々から始まる連続した湯沸かし作業です。何本か持っていく保温ボトルや魔法瓶ににストックしておく為に矢継ぎ早に湯沸かしします。ストックされたお湯は設営中に食べるカップラーメンやコーヒーに使われたり、テントに持ち込む湯たんぽや洗い物にも使われます。ストックした保温ボトルの湯温が下がっても、沸かし直しすることで燃料とかかる時間を節約できます。寒い時ほど早く湯が沸いてほしいからね〜。
いろいろ考えた結果は、、ストームクッカー25(サイズL)には前回の年越しキャンプ同様ウイスパーライトINLを組み込んでいくことに、もう一つのストームクッカー27 はそのままアルコールバーナーで使うことに決めました。

ストームクッカー25にはポットサポート『五徳)を外した状態の Whisper Lite International を組み込む予定です。硬いフューエルラインの影響でバーナー本体が傾くのでステンレス製のボルトとフランジナットで固定します。
さて、ストームクッカーは生き残れるでしょうか、、
続きを読む
2018年12月04日
復活は根気から 三層フライパン

こんにちは、ponioでございます。
今回はアタシのやる気(たまにだけど)と根気(好きなことだけ)と集中力(短いけど)を駆使してキャプテンスタッグさんの三層ステンレス製フライパンを磨きました。

あ〜ぁ、、こんななっちゃって〜だれ〜?こんなんしたの〜!?と聞かれりゃ答えは一つ『はーい(^^)/』アタシです。だってー、、『だってやありません!』



このフライパン、大きさが適当で、手入れが楽だからいろいろ使って、、やらなくていい焦げつきタレ焼きとか、油が焼けてこびりつく目玉焼きとか、、やっちまいまして、、先日なんぞ薄く油を引いて予熱したところ、、目を離したすきに見事にまっ茶々に焦げ付いて、それも油が焼き付いて凄いことに、、。おまけに他の料理で溢れたタレが焼き付いて、、悪魔の手のような模様に、、。


というわけで、、日頃から窓辺にぶら下がったこのフライパンを見るたびに忍び泣く私でしたが、一念発起!(それほどか!)磨くことにしました。いつものボンスターがなかったので、、1200番の耐水ペーパーで水研ぎしてみました。しかし、この焦げつき焼けつきこびりついたヤツってーのはなんとも頑固でして、、店を出したら《頑固オヤジの店》言われるほど。そこでー、、試しに油汚れ専用のマジックリンをシュッとひと吹きして、、ペーパーで磨いてみると、、あれまー!ガッツリ汚れが落ちていくではアーリませんか!
しかし、、ここからが根気とやる気と集中力の見せ場。
薄い汚れはいとも簡単に落ちていきますが、厚くこびりついたヤツがなかなかどうして、、マジックリンをさらにひと吹き、磨くを繰り返し手も泡もフライパンも真っ黒に、、水で洗い更に磨く。ここにアタシは地球温暖化の危機を感じました、、え?温暖化の危機?
こびりついた汚れが周辺部から少しずつ落ちてゆく様はまるで侵食されてゆく海岸線のよう。海面上昇で沈みつつあると言われる島々を思いながらも、、ひたすらに磨く私は『もっと人間磨きなさい』と自分に言い聞かすのでありました。
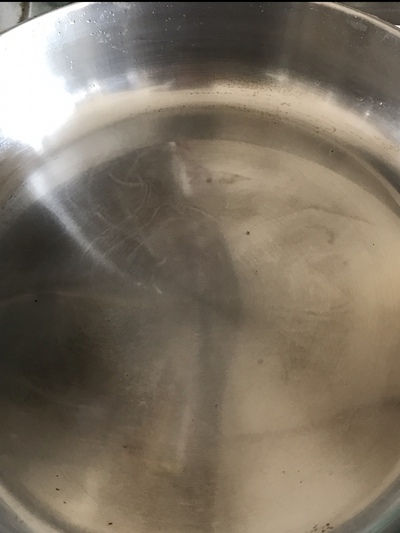

そして、、最後は蛇口からお湯を出して、それを浴びせながらの入魂磨き!(お湯出すのにガス使って、、温暖化に想いを馳せる?)油汚れがお湯で柔らかくなるのか見る見る落ちていきます。そして、、遂に磨き上がりの時を迎えて感慨に浸る私です。(幸せな人)

あとは綺麗に洗って濯ぎ、お湯を沸かして、、そのお湯は他の洗い物に。フライパンは余熱で自然乾燥させます。

ハイ!また美しいお姿となりました〜。
今日は有意義な一日やったわ、、。
幸せなやつ、、ponio でした。





これ何してるかわかりますか?
《煮切りみりん》作って醤油と合わせて調味料つくってます。フライパンにみりんを入れてガスレンジで加熱し、煮えてきたところでフライパンをちょっと傾けると、、揮発したアルコール分に引火して青い炎に覆われます。その炎が燃え尽きたら火を止めて醤油を加えて出来上がり。それを冷ましてビン詰め、冷蔵庫で保管しておきます。カツ丼、親子丼、煮物、、いろいろ使えます。
写真は薄揚げに卵を割り入れ、この調味料でグツグツ煮込むだけの簡単料理。旨い旨い。
続きを読む
2018年12月02日
ブレード別・適材適所《フィクストブレード編》
せっかく治りかけていた腰が、、幼児三匹を抱きかかえたおかげで、、またまたぶり返しました。今はお客さんから頂いたモーラステープを貼って仕事に励むアタシです。こんにちは、ponio です。
さて、今回は先に書かせていただきましたキレモノ、そのブレード別・適材適所のフィクストブレード編です。前回のフォールディングに対して今回のフィクストは折りたたみじゃない、つまり固定式というか、鞘に納めるタイプのシースナイフを示します。
さっそく、いきまっせ〜

はい、先ずはこの方、キャンプなどアウトドアナイフとしては目からウロコ的な安価で素晴らしい切れ味、扱い易いやすい鋼材で伝統と現代技術の融合を見事に製品化したスウェーデンの MORA ナイフ。これはその中でもスタンダード過ぎるほどスタンダードな 860 MG というモデルです。アタシのページでは見飽きるくらい毎回登場する一軍レギュラー的キレモノです。これは860というモデルの中でブレードの鋼材にステンレス鋼を使用したバージョンです。カーボンスチール(鋼)のものと比べてると切れ味というよりはタッチ、つまり手に伝わる感覚に多少の違いを感じますが私的には変わらないと思っています。

木質にもよりますが、これで削ると木の断面がツルツルしています。削られている木が『気持ちよか〜』と言ってるように感じる程スムースなタッチです。勿論、ステンレス鋼ですので、食材を切るのも水まわりで使うのも雨の日も雪の日も、余程でない限りサビが浮く心配もいらず濡れたらサッと一拭きでOK。このメンテナンスフリーに近い扱いの簡単さこそ、ステンレス鋼の最大の利点です。昔は研ぎにくいとか言われてましたが、そんなことありませんよ。切れ味抜群で手入れも簡単、木材から食材まで用途選ばずといった感があるこのブレードですが構造上ブレードとハンドル(グリップ)は差し込まれた形で接合されており無理な使い方、たとえばナイフを叩いて木材を縦割りにするバトニングなどは度を越すとハンドルの付け根からポキンと折れるかもしれません。くれぐれも無理のない範囲でね。

こちらは同じ MORA でもカーボンスチール鋼のブレードをもつ Robust というモデル。少し前にも書きましたので詳しい説明は省きますが、とにかくこれも素晴らしい切れ味です。このモデルは 860MG に比べてブレードの厚みがあって、ハンドルもサイズアップされているので、よりパワフルなカッティングが可能です。これも木を削ると木の断面がツルピカです。
さて、この素晴らしい切れ味のブレードにも難点が一つあります。それはカーボンスチール鋼故のサビです。前に何度も書きましたがこれを使って作業中、突然の雨に濡れながらも使い続け、軽く拭いてシースに収めましたが家に帰り着いた時には見事なまでに茶色く変色しておりました。もちろん、それは表面的なもので目の細かなナイロン研磨パットで軽く擦るときれいに取れましたが、やはりこの手の鋼材は水気は用心しなくてはなりませんね。特に水分の多い食材や酸味のある果物などは使用後のメンテが大事になります。これもブレード厚があって削る作業は効率よくできますが、バトニングなどで目の詰まった硬い木材を叩くとポキンとといくかもしれません。やるなら、木材を選んでね。

MORA 2010 はちょこっと変わったブレードシェイプです。前方と後方でブレードの削られ方(シェイプ)が変化しています。前方は物をスライスなどする時にすうっと入っていきやすい形状、後方は木などを削る際に軽いタッチで押し削りできるような伝統的グラインドです。

これもステンレス鋼で滑らかな切れ味とメンテナンスフリーに近い扱い良さがウリです。我が家では主として食材のカット、スライスに日夜キッチンナイフとして、またキャンプの際の食材カットに使われ続けております。パンもトマトもスラスラスイスイ〜。

Queen #4180 は初めはムラのあるフラットなブレードにホントにお粗末なエッジが付けられただけの酷い製品でした。それをダイアモンドシャープナーで研ぎ直しつつ何年も仕事に使い続けてきました。当時はそれほど鋭利な切れ味ではなかったものの一日を通して使い続けられるエッジのタフさが仕事(当時、仕事の一環でよくやっていた庭木の処理)で役立ちました。時が経ち研ぎ方を変更して軽いコンベックス(ハマグリ刃)風に変えてみたところ、、これが素晴らしく良く切れるタフなブレードに変わりました。

以来、木を削ってもスムースに食い込み、太い落ち枝などをバトンで叩いて割ってもエッジは切れ味を保ち続けます。これは本当に《使える》キレモノになりました。サビず切れ味も落ちることなく一日の作業を終えられる数少ないブレードです。もちろん、食材のカットもOK。

これも先の Queen のブレード同様フラットで粗末なエッジが付けられたモデルでしたが、これも軽いコンベックス風に研ぎ直してやったところ非常によく切れるナイフになりました。

先の MORA 860 とは違ってフルタング構造、つまり一枚の鋼材をハンドル材で挟んだ頑丈な造りなのでガシガシ叩いて木材を割ってもビクともしません。これは1095スチールという錆びる鋼材ですが、デカイ魚(クロ)を捌いたり丸洗いしましたが、MORA のカーボンスチールほどは変色も錆も出ません。もともと生食の食材には使いませんし、ジャガイモなどを切るとブレードの厚みで途中で割れてしまいます。しかし、このブレードは私的には理想のサイズで、ワークナイフとしてとても使いやすく感じます。

上の RAT-3 と同じ1095スチールを鋼材とした小型のシースナイフです。小型ながらフルタング構造とブレードの厚みに物言わせてハードな作業にも従事しております。


楠の太い落ち枝をノコで切り分けた後、バトンで縦割りにする。この枝の太さは IZULA のプレード長ギリギリですが難なく割れました。このナイフは同じ流れをくむ RAT-3 よりも鋭利なエッジが付けられておりましたが、これもごく軽いコンベックス風な研ぎ方に変えて細かな作業にも向くように手直ししました。使用時はシース(鞘)ごと首からぶら下げるネックナイフとして、真下に引き抜く自然な動作でフォールダー並みのブレードを活かした作業に用いられます。台風の前などにベランダの鉢植えなどを固定する為の麻ひものカット作業やキャンプの時の焚付け作りも難なくこなします。

ENZO TRAPPER はMORA と同じスカンジナビアグラインドです。が、ブレード自体の厚みがかなりあり、更にフルタングという構造と相まってバトンにも不安なく使えます。


木を削らせたらスラスラスイスイと気持ちよくカールできます。このブレードの本領発揮です。これぞ北欧系!


このブレードはその厚みを利用してバトン時にはクサビ効果でバリバリと木を割っていきます。エッジの潰れも軽減されます。

lionsteel M 5 は鋼材(Sleipner)の硬さと非常に鋭利な刃つけで箱出しの状態からゾッとするほど良く切れました。幅広のブレードは軽いホローグラインドのようなシェイプです。


そのイカツイ顔つきとは裏腹にブレードの背(峰)のラインは丁寧に丸められたソフトな造りです。この丸みを帯びたブレードの背でもファイアースチールが擦れるから不思議。

ブレードの形状やナイフそのものの大きさ、デザインから食材をカットしたりスライスしたりは普通やりませんが、試しにタマネギをスライスしてみると難なくやれます。ジャガイモのスライスも出来ました。これが先に登場した ENZO では途中からバリッと割れてしまうのです。
米国系のハードユースなサバイバルナイフとは一線を画す鋼材やブレードのシェイプですが、この様にバトンで落ち枝を割っても難なくできます。ただ、 ENZO ほどのクサビ効果はなく割られる木材はそれほど左右に開いてません。しかし、、

実際はかなりハードに使われており、バトニングも数多くこなしてきました。アックスやハチェットがある時にはやる意味がないのでしませんが、椅子に腰掛けてでもできるバトンは焚き付け作りには手軽で良い暇つぶしになります。

COLD STEEL SRK です。すでに引退して引き出しの中で余生を過ごしておりますが、現役時代の酷使されようはこのブレードを見てもわかります。カーボンVと呼ばれる炭素鋼で造られており、刃付けはメーカーサイドが施したコンベックスグラインド(ハマグリ刃)でした。これは非常に鋭利な切れ味でした。錆びる鋼材なので黒のコーティングが施されておりましたが、美しくグラインドされた研ぎ面だけが異様な輝きを放っていたのを覚えています。

コンベックスグラインドの面影見たり。今でもちゃんと切れますよ。サビもあまり浮いていません。

ただ、なんでしょうね、、使いづらく感じてしまったのですね、、このブレードが。たぶん、サイズ。当時、これを使ってやっていた枝払いなども今はギアプルーナー(剪定ハサミ)でチョキンチョキンですし、バトンもフルタングな連中がやりますし、チョッピングはアックスが専門職。これと FISKARS のスライドソーとビクトリノックスを使って高さ10メートルの樫の木を切り倒して更に切り割りして軒下に山積みしたのも今では良い思い出です。静かにお休みくださいね。
さてさて、他にも引退もしくは純粋なコレクション(後にも先にも一本きりの)のフィクストブレードもありますが今回はここまで。
最後に長い考察を、、

これ有名すぎるくらい有名な米国製サバイバルナイフ(この呼び方大嫌い)のステンレスバージョン。上で登場した IZULA Ⅱ と同じ ESEE の ESEE 4 /440 C ステンレス鋼のバージョンです。ESEE 4 は私的にはその全てが完璧なるスタンダード。フルタング、フラットグラインド、マイカルタやG10ハンドルスケール、ランヤードポメル、カイデックスシース、そして、、従来の1095スチールではなく、錆を気にすることなく使える440Cステンレス鋼のバージョンが発売になってしばらく経ちます。これ、、惹かれるんですわ、、強烈に。でもね、、
全てにおけるスタンダードとはつまりオールラウンド的な要素が強いと言うことである、、それは汎用性が高く様々な用途に対応するが、一方ではそれなりの不器用さも持ち合わせている。例えば魚を捌けるか?と聞かれたら『できる』と答える。しかし、魚を捌くことに特化した刃物、例えば出刃包丁や刺身包丁、ナイフと言うならフィレナイフなどが出てきたらそれはもうこのナイフに利は無いのである。木を削れるか?と聞かれたら当然『できる』と答える。しかし、木を削るだけなら MORA のナイフや北欧系のブレードシェイプされた刃物、コンベックス風にシェイプされたブレードの方がはるかに楽でスムースに木は削れる。太い枝木を割れるか?と聞かれたら『できる』と答える。しかし、アックスやナタの方がより効率的に圧倒的なパワーで割ることができる。ウッドカービングはできるか?と聞かれたら『できる』と答えるが、小ぶりなカービングナイフや切り出し、専門的な刃物の前には太刀打ちできない。
それではこのナイフを持つ価値はあるのか?
そのサイズから屋内での作業に使われることはないはずで、となると、屋外での《切る》《削る》《割る》といった作業に使うことになる。より大きな作業は手持ちのアックスやハチェットがやるだろう。より細かな作業はポケットやシースから取り出すフォールダーやネックナイフがやることになる。となると、その中間的な作業といえば、焚付け作りに枝木を割ったり削ったり、枝払いをしたりと、そんなところか。アックスやハチェットは現地で使う見込みがある時のみ持ち出す大物である。だから、その分の作業を頑強なシースナイフが肩代わりしてやるのだ。食材切るのにこんなデカイナイフは必要ないし、ロープやコードを切るのもフォールダーで事足りる。はてさて、本当にこれは必要なものなのか?ですよね。
それなら、、

こちらの方が汎用性が高いんやないかと、、
BRADFORD の Guardian 3 鋼材は M390のバージョン。RAT-3 と同じ3インチのブレードで、より扱いやすいブレードデザインとハンドル材。食材から木材まで幅広く対応できる一番手頃なサイズのブレード長(私には)。
ESEE 4 はキャンプ以外には用途がありませんが、Gurdian 3の方は台所でもデイハイクでも使えそうです。ワークナイフとしてはお高いですが、、いつかは欲しい一本です。もーぅ、こんなの出して!バカバカ!
ponio でした。
さて、今回は先に書かせていただきましたキレモノ、そのブレード別・適材適所のフィクストブレード編です。前回のフォールディングに対して今回のフィクストは折りたたみじゃない、つまり固定式というか、鞘に納めるタイプのシースナイフを示します。
さっそく、いきまっせ〜

はい、先ずはこの方、キャンプなどアウトドアナイフとしては目からウロコ的な安価で素晴らしい切れ味、扱い易いやすい鋼材で伝統と現代技術の融合を見事に製品化したスウェーデンの MORA ナイフ。これはその中でもスタンダード過ぎるほどスタンダードな 860 MG というモデルです。アタシのページでは見飽きるくらい毎回登場する一軍レギュラー的キレモノです。これは860というモデルの中でブレードの鋼材にステンレス鋼を使用したバージョンです。カーボンスチール(鋼)のものと比べてると切れ味というよりはタッチ、つまり手に伝わる感覚に多少の違いを感じますが私的には変わらないと思っています。

木質にもよりますが、これで削ると木の断面がツルツルしています。削られている木が『気持ちよか〜』と言ってるように感じる程スムースなタッチです。勿論、ステンレス鋼ですので、食材を切るのも水まわりで使うのも雨の日も雪の日も、余程でない限りサビが浮く心配もいらず濡れたらサッと一拭きでOK。このメンテナンスフリーに近い扱いの簡単さこそ、ステンレス鋼の最大の利点です。昔は研ぎにくいとか言われてましたが、そんなことありませんよ。切れ味抜群で手入れも簡単、木材から食材まで用途選ばずといった感があるこのブレードですが構造上ブレードとハンドル(グリップ)は差し込まれた形で接合されており無理な使い方、たとえばナイフを叩いて木材を縦割りにするバトニングなどは度を越すとハンドルの付け根からポキンと折れるかもしれません。くれぐれも無理のない範囲でね。

こちらは同じ MORA でもカーボンスチール鋼のブレードをもつ Robust というモデル。少し前にも書きましたので詳しい説明は省きますが、とにかくこれも素晴らしい切れ味です。このモデルは 860MG に比べてブレードの厚みがあって、ハンドルもサイズアップされているので、よりパワフルなカッティングが可能です。これも木を削ると木の断面がツルピカです。

さて、この素晴らしい切れ味のブレードにも難点が一つあります。それはカーボンスチール鋼故のサビです。前に何度も書きましたがこれを使って作業中、突然の雨に濡れながらも使い続け、軽く拭いてシースに収めましたが家に帰り着いた時には見事なまでに茶色く変色しておりました。もちろん、それは表面的なもので目の細かなナイロン研磨パットで軽く擦るときれいに取れましたが、やはりこの手の鋼材は水気は用心しなくてはなりませんね。特に水分の多い食材や酸味のある果物などは使用後のメンテが大事になります。これもブレード厚があって削る作業は効率よくできますが、バトニングなどで目の詰まった硬い木材を叩くとポキンとといくかもしれません。やるなら、木材を選んでね。

MORA 2010 はちょこっと変わったブレードシェイプです。前方と後方でブレードの削られ方(シェイプ)が変化しています。前方は物をスライスなどする時にすうっと入っていきやすい形状、後方は木などを削る際に軽いタッチで押し削りできるような伝統的グラインドです。

これもステンレス鋼で滑らかな切れ味とメンテナンスフリーに近い扱い良さがウリです。我が家では主として食材のカット、スライスに日夜キッチンナイフとして、またキャンプの際の食材カットに使われ続けております。パンもトマトもスラスラスイスイ〜。

Queen #4180 は初めはムラのあるフラットなブレードにホントにお粗末なエッジが付けられただけの酷い製品でした。それをダイアモンドシャープナーで研ぎ直しつつ何年も仕事に使い続けてきました。当時はそれほど鋭利な切れ味ではなかったものの一日を通して使い続けられるエッジのタフさが仕事(当時、仕事の一環でよくやっていた庭木の処理)で役立ちました。時が経ち研ぎ方を変更して軽いコンベックス(ハマグリ刃)風に変えてみたところ、、これが素晴らしく良く切れるタフなブレードに変わりました。

以来、木を削ってもスムースに食い込み、太い落ち枝などをバトンで叩いて割ってもエッジは切れ味を保ち続けます。これは本当に《使える》キレモノになりました。サビず切れ味も落ちることなく一日の作業を終えられる数少ないブレードです。もちろん、食材のカットもOK。

これも先の Queen のブレード同様フラットで粗末なエッジが付けられたモデルでしたが、これも軽いコンベックス風に研ぎ直してやったところ非常によく切れるナイフになりました。

先の MORA 860 とは違ってフルタング構造、つまり一枚の鋼材をハンドル材で挟んだ頑丈な造りなのでガシガシ叩いて木材を割ってもビクともしません。これは1095スチールという錆びる鋼材ですが、デカイ魚(クロ)を捌いたり丸洗いしましたが、MORA のカーボンスチールほどは変色も錆も出ません。もともと生食の食材には使いませんし、ジャガイモなどを切るとブレードの厚みで途中で割れてしまいます。しかし、このブレードは私的には理想のサイズで、ワークナイフとしてとても使いやすく感じます。

上の RAT-3 と同じ1095スチールを鋼材とした小型のシースナイフです。小型ながらフルタング構造とブレードの厚みに物言わせてハードな作業にも従事しております。


楠の太い落ち枝をノコで切り分けた後、バトンで縦割りにする。この枝の太さは IZULA のプレード長ギリギリですが難なく割れました。このナイフは同じ流れをくむ RAT-3 よりも鋭利なエッジが付けられておりましたが、これもごく軽いコンベックス風な研ぎ方に変えて細かな作業にも向くように手直ししました。使用時はシース(鞘)ごと首からぶら下げるネックナイフとして、真下に引き抜く自然な動作でフォールダー並みのブレードを活かした作業に用いられます。台風の前などにベランダの鉢植えなどを固定する為の麻ひものカット作業やキャンプの時の焚付け作りも難なくこなします。

ENZO TRAPPER はMORA と同じスカンジナビアグラインドです。が、ブレード自体の厚みがかなりあり、更にフルタングという構造と相まってバトンにも不安なく使えます。


木を削らせたらスラスラスイスイと気持ちよくカールできます。このブレードの本領発揮です。これぞ北欧系!


このブレードはその厚みを利用してバトン時にはクサビ効果でバリバリと木を割っていきます。エッジの潰れも軽減されます。

lionsteel M 5 は鋼材(Sleipner)の硬さと非常に鋭利な刃つけで箱出しの状態からゾッとするほど良く切れました。幅広のブレードは軽いホローグラインドのようなシェイプです。


そのイカツイ顔つきとは裏腹にブレードの背(峰)のラインは丁寧に丸められたソフトな造りです。この丸みを帯びたブレードの背でもファイアースチールが擦れるから不思議。

ブレードの形状やナイフそのものの大きさ、デザインから食材をカットしたりスライスしたりは普通やりませんが、試しにタマネギをスライスしてみると難なくやれます。ジャガイモのスライスも出来ました。これが先に登場した ENZO では途中からバリッと割れてしまうのです。

米国系のハードユースなサバイバルナイフとは一線を画す鋼材やブレードのシェイプですが、この様にバトンで落ち枝を割っても難なくできます。ただ、 ENZO ほどのクサビ効果はなく割られる木材はそれほど左右に開いてません。しかし、、

実際はかなりハードに使われており、バトニングも数多くこなしてきました。アックスやハチェットがある時にはやる意味がないのでしませんが、椅子に腰掛けてでもできるバトンは焚き付け作りには手軽で良い暇つぶしになります。

COLD STEEL SRK です。すでに引退して引き出しの中で余生を過ごしておりますが、現役時代の酷使されようはこのブレードを見てもわかります。カーボンVと呼ばれる炭素鋼で造られており、刃付けはメーカーサイドが施したコンベックスグラインド(ハマグリ刃)でした。これは非常に鋭利な切れ味でした。錆びる鋼材なので黒のコーティングが施されておりましたが、美しくグラインドされた研ぎ面だけが異様な輝きを放っていたのを覚えています。

コンベックスグラインドの面影見たり。今でもちゃんと切れますよ。サビもあまり浮いていません。

ただ、なんでしょうね、、使いづらく感じてしまったのですね、、このブレードが。たぶん、サイズ。当時、これを使ってやっていた枝払いなども今はギアプルーナー(剪定ハサミ)でチョキンチョキンですし、バトンもフルタングな連中がやりますし、チョッピングはアックスが専門職。これと FISKARS のスライドソーとビクトリノックスを使って高さ10メートルの樫の木を切り倒して更に切り割りして軒下に山積みしたのも今では良い思い出です。静かにお休みくださいね。
さてさて、他にも引退もしくは純粋なコレクション(後にも先にも一本きりの)のフィクストブレードもありますが今回はここまで。
最後に長い考察を、、

これ有名すぎるくらい有名な米国製サバイバルナイフ(この呼び方大嫌い)のステンレスバージョン。上で登場した IZULA Ⅱ と同じ ESEE の ESEE 4 /440 C ステンレス鋼のバージョンです。ESEE 4 は私的にはその全てが完璧なるスタンダード。フルタング、フラットグラインド、マイカルタやG10ハンドルスケール、ランヤードポメル、カイデックスシース、そして、、従来の1095スチールではなく、錆を気にすることなく使える440Cステンレス鋼のバージョンが発売になってしばらく経ちます。これ、、惹かれるんですわ、、強烈に。でもね、、
全てにおけるスタンダードとはつまりオールラウンド的な要素が強いと言うことである、、それは汎用性が高く様々な用途に対応するが、一方ではそれなりの不器用さも持ち合わせている。例えば魚を捌けるか?と聞かれたら『できる』と答える。しかし、魚を捌くことに特化した刃物、例えば出刃包丁や刺身包丁、ナイフと言うならフィレナイフなどが出てきたらそれはもうこのナイフに利は無いのである。木を削れるか?と聞かれたら当然『できる』と答える。しかし、木を削るだけなら MORA のナイフや北欧系のブレードシェイプされた刃物、コンベックス風にシェイプされたブレードの方がはるかに楽でスムースに木は削れる。太い枝木を割れるか?と聞かれたら『できる』と答える。しかし、アックスやナタの方がより効率的に圧倒的なパワーで割ることができる。ウッドカービングはできるか?と聞かれたら『できる』と答えるが、小ぶりなカービングナイフや切り出し、専門的な刃物の前には太刀打ちできない。
それではこのナイフを持つ価値はあるのか?
そのサイズから屋内での作業に使われることはないはずで、となると、屋外での《切る》《削る》《割る》といった作業に使うことになる。より大きな作業は手持ちのアックスやハチェットがやるだろう。より細かな作業はポケットやシースから取り出すフォールダーやネックナイフがやることになる。となると、その中間的な作業といえば、焚付け作りに枝木を割ったり削ったり、枝払いをしたりと、そんなところか。アックスやハチェットは現地で使う見込みがある時のみ持ち出す大物である。だから、その分の作業を頑強なシースナイフが肩代わりしてやるのだ。食材切るのにこんなデカイナイフは必要ないし、ロープやコードを切るのもフォールダーで事足りる。はてさて、本当にこれは必要なものなのか?ですよね。
それなら、、

こちらの方が汎用性が高いんやないかと、、
BRADFORD の Guardian 3 鋼材は M390のバージョン。RAT-3 と同じ3インチのブレードで、より扱いやすいブレードデザインとハンドル材。食材から木材まで幅広く対応できる一番手頃なサイズのブレード長(私には)。
ESEE 4 はキャンプ以外には用途がありませんが、Gurdian 3の方は台所でもデイハイクでも使えそうです。ワークナイフとしてはお高いですが、、いつかは欲しい一本です。もーぅ、こんなの出して!バカバカ!
ponio でした。
















