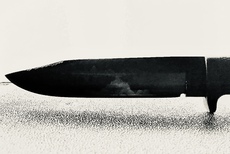2017年03月03日
あの頃トランギアと

こんにちは、ponioです。
今回は《Trangia回顧録》的お話です。

私がTrangiaバーナーを使い出して20年、いやもっとなるかな? 今思い出しても何故それを使い出したのか、何に影響されてのことだったのか、まったく思い出せません。ただ、2枚目の写真(あの頃使っていた一眼で撮った)のようなスタイルで使っていたことだけは記憶に残っています。銀色の囲いは焚き火用のファイアーベースです。当時は今のような小さく折りたためるウッドストーブもSOLO STOVEなどもありませんでしたから持ち歩いたいた熱源はガスかアルコール、少し後になってガソリンを使うバーナーやストーブの類でした。その中でもTrangiaバーナーはかなり早い段階から使い続けており、それはこの20年余りブランクなくずうっと使い続けている唯一の熱源なのです。

あの頃の写真に頻繁に登場するTrangiaバーナーと五徳の組み合わせです。この写真は現在のものですがバーナーも五徳もファイアーベースも当時のもののままです。
五徳は TR23と呼ばれるTrangia 純正品です。白い耐熱ペイントが施されたスチール製の据え置き型五徳で、分解も折りたたみもきかない《そのまんま五徳》です。
当時は今のようなネット社会ではなく、製品は雑誌か店頭で見かけるのが普通の時代、あの頃の自分もこの五徳は店頭で見かけたのでしょうね。以来20年余り、この五徳に関しては何年かブランクがありましたが、使い始めた当時は持ち出す機会も多く(と言うかこれしかなかった)、その後2年以上にわたって自宅のキッチンで炊事に使われ続けました。あの2年間、この組み合わせでちゃんとメシを作り生活していたのだと思うと自分でも笑えるやら呆れるやら。

1990年代の大阪、当時住んでいたマンションの台所での一枚。

この五徳は据え置き型といっても良いデザインと構造です。現在巷にあふれるトランギア関係の周辺パーツとも一線を画すシンプルな使い道を追求した製品といえます。サイズ的には同社のツンドラシリーズの1.5Lソースパンにピッタリ収まるサイズです。このことから基本的には外への持ち出しを考えて作られた物だといえます。
今ならTrangiaバーナーを組み込めるバーゴのヘキサゴンウッドストーブやファイアーボックス系の小型ウッドストーブやメーカー純正品や社外品の五徳関係は山ほど出回っています。選択肢は有り余るほどあるわけです。

しかし、あの頃はこれしかなかったのです。というか、自分が気づかなかっただけなのかな?メーカー純正の五徳やストームクッカーなども販売されていたはずなのですが、、私の目には止まらなかったのでしょうね。
でもね、この白い五徳、今ではペイントも剥がれ汚れて酷い有様ですが、これはこれで非常に使い良い製品なのですよ。分解や折りたたみができない反面、堅牢で五徳としては安定感抜群。バーナーの蓋による火力調整も簡単にできます。下方からの吸気も考えられており中華鍋でもすき焼き鍋でも乗っけられる。だから2年余りも自宅の台所で使われ続けたのですね。ちなみに銀色の囲み、ファイアーベースは多分ですが風対策だったのでしょう。

こうして見ると風対策も完璧とは言い難く、でもストームクッカーを知らなかった当時の私なりに考えたやり方だったのでしょう。自宅ではガスコンロの汁受けの様な役目とバーナーの熱を上方に集中させる為の役目を担っていました。
その後、社外品でチタン製のX型五徳が発売され《チタン》なる言葉の響きに買って使いましたが、、これが荷物としては最小となるものの五徳としては高さが低すぎてイマイチな感じでありました。ご存知のようにTrangiaバーナーの五徳は《高さ》にも向き不向きがあって、炎に近ければ良いとは限らないのです。私の買ったX型五徳(90年代終わり頃)はバーナーに直乗せでしたので炎がクッカーの側面まで回り込んでハンドル焼けを起こしました。
そして使い出したのが、、

Esbitストーブ二つを使った囲い込みです。

二つのEsbitストーブを合わせるとピッタシ!

サイドからは多少の吸気も出来る。

ということで、あの頃の私的には決定打となったスタイルが出来上がりました。これは五徳とTrangiaバーナーには絶対不可欠な風対策を考えてのことでした。

完全な囲い込みでなくても五徳としては機能しました。
ただ、これでは風防としての機能はなく、本当に風の穏やかな日や環境でなければ使えませんでした。

五徳としてみると大きな鍋でも乗せられました。

実際にこのやり方で使ってみると、五徳としては必要にして十分な安定性があり、風防としても効果が高い。
しかし、この上にケトルやクッカーを乗せるとバーナーは完全に箱の中に閉じ込められた状態となり炎はバーナーを包み込んでバーナー本体を過度に加熱することになる。その結果、バーナーは通常の使用時よりも激しく燃焼するが空気の取り込みが極度に制限されるため本来の美しい青火ではなく赤火となってしまう。時としてEsbitストーブに開けられたスリットや二つのストーブの合わせ目から炎が噴き出すこともありました。

そこで考えたのがこのスタイル。風下側をほんの少しオープン。これで適度な空気の取り込みと風対策が可能になります。


さてあらためて、、当時のやり方で試してみると、、
エスビットストーブは20年前の物をそのまま使いました。遮るもののない海岸で風下側をオープンして点火。当時使っていた600mlの紅ケトルより一回り大きな900mlの紅ケトルを乗せます。右に見える木組みは拾って切り分けた松の枝で作った最小限の風除けです。

ちゃんと沸騰します。
Trangiaバーナーを使う時は沸騰時間などは測らない。のんびりと湯が沸くのを待つのみ。いつだったか、京都の宇治の川べりでEsbitストーブによる囲い込みスタイルで湯を沸かしコーヒーでもとなった時のこと、湯が沸くのを待っているといつもの相方から『まだか〜?』と催促のお言葉。確かにガスのシングルバーナーに比べれば沸騰時間も長くかかる。
そこで私は『待ちんしゃい!、男はじっと我慢する!』と言いつつすぐに自分で『それにしても遅いな〜』って呟く。相方には首を絞められましたがそれもいつものこと。その相方も今は三途の川の向こう側です。

今回、あらためて当時のやり方でお湯を沸かしコーヒー淹れて飲んでみました。白い五徳はやはり安定感抜群で使いやすい。Esbit囲い込みは簡単でちゃんと機能する。
Trangiaバーナーに関する多くの周辺パーツの中ではやはり純正品が一番。デザインの好き嫌いはともかく
《Trangiaバーナーを活かす》ことにかけては流石メーカーさん!と言えるだけの機能性能をもっている。
まあ、そこんとこ理解した上で多少の不便を差し置いても社外品を購入し使ってみられるのも Trangia ならでは
の魅力だと思います。
それでは、またのお越しを。

Esbitストーブも本来の固形燃料ストーブとしての役目を終えました。コストの面で割りが合わなくなったからです。しかし、私はこの焼け焦げて歪んだストーブを捨てなかった。何かに使える!そう!何かに役に立つことがあるから! いつか使うからではなく役に立つことがあるから!