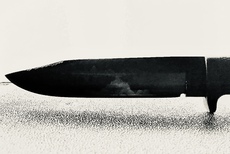2018年12月08日
ハサミの底力 レザーマン RAPTOR


LEATHERMAN RAPTOR ®️
メディカルシザーズ(緊急時の医療用)としてLEATHERMANから販売されているハサミです。日本では2015年の夏くらいからAmazonでも扱われ出しました。折りたたみ可能でメカニカルな構造とストラップカッターなどいくつかの機能を加えてお得意のマルチプライヤー路線から飛び出した製品と言えます。わたしは個人的に高齢者や障がいを持つ方に携わる仕事を長年していますが医療関係者ではありません。病院には毎日のように行っておりますが医療に関する専門的な知識も技術も持ち合わせません。独学では浅く広く勉強しておりますが、目の前の高齢者や障がいを持つ方たちから学ぶことの方が多いのが現実です。

そんな私が医療用のハサミなんて、、実はわたしは若い頃から様々な道具で本来使う目的以外の使い方をしてきました。この医療用のハサミもけっしてケガ人の衣類を切り裂いたりシートベルトをカットしたり(これはあり得るかも?)指輪を切ったり酸素ボンベのバルブを回したりする為に買ったのではありません。それは専門職のお仕事だからです。もちろん、コレクターでもないので何かに使う為にこれを選んだのです。


LEATHERMAN Made in USA

独特の樹脂製ホルスターに収められた RAPTOR 。これを腰につけて、取り出し収めるにはある程度の慣れが必要です。形状が複雑で差し込む方向が決まっているからです。無意識のうちにそれができるようになるまで少しかかるでしょうね。面倒ならホルスターは使わずにポケットクリップを使用する手もあるので便利です。

この独特のホルスターはネジを緩めれば360°の回転式。パドルタイプのベルトクリップは一度差し込むと外すのが一苦労。こっちを外せばあっちが引っかかるといった感じです。ホルスターの角度は人それぞれ、わたしは真下に向けて抜くようにセットしています。写真は真上に抜くようにセットした状態。

この写真の中に、、ポケットクリップ、ランヤードホール、ガラスブレイカーの機能が見て取れます。ランヤードホールは、、私は使わないでしょうね。

カーバイド製のガラス割り。グラス(ガラス)ブレイカーと呼ばれる突起です。車などの分厚いガラスを叩き割るのに使うものですが、、他になにか使い道は、、あるかな?縄文式土器を作る時に模様をつけるとか、、使わん使わん、、ポールペンなら良かったのに。

この写真にはハサミ以外に《切る》機能が見えています。ロック式のストラップカッターです。親指で回転させると開きロックがかかります。



ストラップカッター。V字の片刃です。これで、シートベルトや衣類をカットできます。荒く仕上げられたV字の片刃は薄い紙でもスパッと切れます。紐やコード、ダンボールも切れます。これは使いようですね。

この板状のものがストラップカッターのロックスプリングです。解除はKEYマーク部分を押し込むだけです。

RAPTOR のハサミのとしての生命線でもあるギザ刃。まるでヤスリのような仕上がりです。これが布地などを逃さずカットするのに役立ちます。こうしてアップで見ると紙などをきれいに切る様な繊細な作業は難しいと感じますが、、。

意外とそうでもありません。ギザ刃なので刃を滑らすような裁ちハサミ特有の切り方は無理です。また刃の長さからそれほど多くの部分を一度に切ることはできません。左回りに弧を描くような切り方は簡単にできますがブレードの厚みがあるので右回りはかなり難しく感じます。これは、紙細工をするためのハサミではないからです、それで納得。

こう見ると、、多少メカニカルな文具に見えなくもありません。

ギザギザ〜〜

分厚っー!

この写真の中心部に見える三角形のボタンがハサミのロック解除ボタンです。裏表にあってこれを押してハンドルを片方ずつたたみます。

これがリングカッター。指輪切りです。海外の動画ではキーホルダーのリングを切っていましたね。ワイヤーカッターとしても使えます。

かわいい顔のオウムちゃん。噛む力はすごいものがある。

独特の先端部は衣類と身体の間を傷つけないように動くための形状です。

三種のマルチツールを並べて、、大きさと重さの比較。
一番上(奥)はビクトリノックスの Swiss Tool Sprit (マルチプライヤー)、真ん中が同じビクトリノックスのアウトライダー(ナイフ他)、手前が LEATHERMAN RAPTOR 。大きさ的には RAPTOR が平面的な大きさを感じますが厚みだけならアウトライダーです。オールステンレス製の Swiss Tool Sprit は一番コンパクトながら重量はダントツで重く機能数も一番多い。

結束バンドも簡単に切れます。この結果こそ私がこのハサミに望んだ多様な《切る》作業なのです。


このパドル(クリップ)部分が便利そうで使いづらい。差し込むのも取り外すにも苦労する。米軍の MOLLEシステム対応なので差し込み部分が左右に二分割されており、これがなんとも使いにくい。ベルトやストラップではなくズボンに直にクリップする方が簡単。本体は逆さに向けても落ちることはない。

ポケットクリップを使えばホルスターの煩わしさから解放されるね。

このホルスターからの出し入れに慣れるためなるべく身につけて使っている。そのうち機械的に抜き差しできるようになるだろうね。

さて、届いた翌日にいきなりの本番到来!仕事先で別件として頼まれたカーペットの処分。市の粗大ゴミセンターに確認を取ったところ有料の可燃物用ゴミ袋でも出せますとのこと。ただし、最大45Lの袋に入れて上を結ぶことができること、人が片手で持っても破れない重さであることが条件とのこと。ガッテン!承知の助!これを予期したわけではなかったが、届いたばかりの RAPTOR を試す良い機会だと判断してザックから取り出した。いざ!

1.8m四方で中程度の厚さのカーペットをベランダで三等分に切り分ける。RAPTOR さんはジョリジョリと問題なく切り進むが、、カーペットの毛が凄まじい。一片を切り終わる頃には、、

RAPTORさんもこの通り。この作業、施工の専門家なら何を使うか?オルファのゴツいカッターナイフでしょう。裏面から刃を当てて一気に切り分ける。スマートで効率的。残念ながら、こんな作業が時には舞い込む私の仕事ですが、オルファのゴツいカッターナイフを私は持ちません。(小さいのならある)今回、もし RAPTOR か無ければどうしていたかな?切り分けせずに粗大ゴミ(有料のシールを貼って、指定された日時に指定場所に置いておく)扱いにするか、手持ちの道具、たとえば 常に持ち歩くマルチプライヤーに付いた片刃のナイフで切り裂くでしょうね。でも、以前にも何度かやったことがありますが、カーペットをナイフなどで切ると予想以上に早くエッジが摩耗するのです。以前、表に野ざらしになっていたカーペットを頼まれて切り分けた時は庭木の処理用に持ってきていた カーボンスチール鋼の MORA を使いました。切り分けることは可能でしたが、最後はエッジが摩耗してほとんど丸坊主に、、押しても引いても切れない状態になりました。適材適所、専門的分化はどこの世界でも必要です。

今回いきなりの本番で期待通りの結果を残してくれた RAPTOR 。これまで当たり前のようにナイフでやってきた作業をこれからはコヤツがやるのか?どんな場面で何にどう使うのか、それを前もってシュミレーションしておくことが大切。そうじゃないと、使える場面で瞬時に使う判断ができません。

帰宅して温水シャワーできれいさっぱり丸洗い。ベランダで日光浴と冬の風に当てて自然乾燥させる。


若い頃より様々なシーンでお世話になってきた LEATHERMAN のツール。その LEATHERMAN の造りしハサミ。きっと雑多で多様な作業にも使えるはず。がんばってくだされー、、、。
ハサミついでに、、、追記

とある日曜日、奥さんと二人でサンデードライブランチの一コマ。キンキンに冷やした素麺のつけ汁に添える小ねぎをカットするためにスイスアーミーナイフのハサミを使う。よく切れるし、水洗いしてお終い。サビの心配もなし。

同じスイスアーミーナイフの血を継ぐミニチャンプDXのハサミ。こんな小さなと侮るなかれ。アタシはこれで普通に手の爪を切ってる。20年使い続けても切れ味変わらず。バネは一度も折れたことなし。

Swiss Tool Sprit のハサミ。

よーく見てちょーよ。このハサミは他と逆なんすよ。ハサミの部位だけを見ると、、2枚の刃の合わせが逆です。例えば右利きがこのハサミで紙に書かれた線を正確に切ろうとすると、、切り口が見えないのです。右利きの人は右手にハサミを持って左側から切り口を確認しながら切りますよね。このハサミだと左から見ても切り口が隠れて見えません。左利きの人なら問題なく使えます、、つまりこのハサミは左利き用ということになります。
ただね、これで紙に書いた線を正確に切ること私はありません。どちらかと言えばニッパーみたいに先端部を使ってパチパチと切断する感覚の使い方です。例えば、、結束バンドなどはこれでカットしてます。

上から Swiss Tool Sprit、WENGER バルダン、ミニチャンプDX。やはり Swiss Tool Sprit のハサミだけ合わせが逆ですね。

同じビクトリノックスでも Swiss Tool Sprit(左)は親指で動かす方の刃が下側に、となりのアウトライダーのハサミは親指で動かす方が上に取り付けられています。右利きの人がアウトライダーのハサミで紙に書かれた線を切るとき普段通りに左から切り口を確認しながら正確に切ることができます。
なぜ、同社の製品でありながら左右逆になったのでしょう?実は右も左もなかったりして、、。

アウトライダーのハサミ(左)とレザーマン・ジュースのハサミ(右)こちらは同じ合わせ方。


WENGER バルダンのハサミはギザ十(わかるかな〜)。ギザギザ刃です。ビクトリノックスとの違いでもあります。これ切る対象物を逃さずカットできます。布地、糸、滑りやすいものでも確実にカットできます。ただ、、ハサミの構造に問題あり(個体差)。2枚の刃の接合部(支点)に小さなネジが使われていますがこれがよく緩みます。これが緩むと、ハサミの命である《合わせ》が開いてガタつき全く用をなしません。このバルダンはハサミのネジが緩むたびに付属のピンセットで締め直さなければなりません。

いつも持ち歩くファストエイドキットに入れてある WENGER の小さなナイフ。ビクトリノックスで言うところの《クラシック》ですね。このハサミもやはり WENGER伝統のギザギザ刃。こちらは、、支点ネジの緩みは見られません。やはり個体差があるようです。ガーゼや包帯を切る時に使います。

各ハサミで結束バンドをカットしてみます。
ビクトリノックスのアウトライダーは使いやすいハサミですが結束バンドを切ろうとすると刃先あたりまでスリップしながらも最終的に切ることができました。レザーマンのジュースはスリップしないかわりにアウトライダーのものより切る際の力が必要でした。ハサミも多少のたわみを感じました。WENGERのバルダンは滑りやすい結束バンドも逃さず軽くカットできました。ただ、、このバルダンはハサミの支点ネジが切るたびに緩むのでストレスですね。ミニチャンプDXはサイズ的に一番苦労しました。これは予想できたことです。そして、左利き用のハサミ、Swiss Tool Spritのハサミですがギザギザ刃ではないのに結束バンドも逃さずパチンとカットできました。それと、Sprit のハサミでカットされた切れっ端は、、上に飛びます。他のハサミは全て切れっ端が下に飛びます。やはり逆なのです。

これはこのブログの中では何度も登場してきた FISKARS の剪定用のハサミです。ギアプルーナーという品名です。下刃には刃は付けられておらず、分厚いステンレス鋼の土台です。回転式のグリップを握りこむとSandvic ステンレス鋼の鋭利な刃が上から押し切りします。上の動刃はそれ単体でもナイフとして使えるほど非常に鋭利な刃付けがされています。

とある仕事でブラ製のカゴをギアプルーナーでパチパチと小さく切って捨てる。この剪定用のハサミは動刃(上の刃)がナイフのように鋭い仕上げなのと、静刃(下)に付けられたギアと連動した回転式のハンドルが軽い力で切ることを可能にしています。これを貸してあげると『よう切れる〜』と言われますが、それは上の刃の鋭さだけではなく、回転式のギアハンドルのおかげなのです。

仕事で使った後のギアプルーナーを自宅で分解して水洗い、上の動刃はセラミックシャープナーで軽くタッチアップしておく。これ単体でも下手なナイフより相当切れる。動刃は片刃のため裏面は軽く撫でるだけ。この面を角度をつけた研ぎ方をすると途端にハサミとしての切れ味がガタ落ちします。
やはりハサミは便利です。ナイフとはちがう領域に踏み込める道具ですね。

仕事先のお宅にて柿の収穫を頼まれ。

仕事先のお宅にてプラ板をカット。
他にも入院患者のパジャマの袖ゴムがキツいから切って下さいとお願いされてチョキン。台風で吹き飛ばされ破れた庭先のオーニングの帆布をチョキチョキ、ストラップカッターでザォ〜と切り裂く。使われとりまっせ〜。

とある日曜日、奥さんと二人でサンデードライブランチの一コマ。キンキンに冷やした素麺のつけ汁に添える小ねぎをカットするためにスイスアーミーナイフのハサミを使う。よく切れるし、水洗いしてお終い。サビの心配もなし。

同じスイスアーミーナイフの血を継ぐミニチャンプDXのハサミ。こんな小さなと侮るなかれ。アタシはこれで普通に手の爪を切ってる。20年使い続けても切れ味変わらず。バネは一度も折れたことなし。

Swiss Tool Sprit のハサミ。

よーく見てちょーよ。このハサミは他と逆なんすよ。ハサミの部位だけを見ると、、2枚の刃の合わせが逆です。例えば右利きがこのハサミで紙に書かれた線を正確に切ろうとすると、、切り口が見えないのです。右利きの人は右手にハサミを持って左側から切り口を確認しながら切りますよね。このハサミだと左から見ても切り口が隠れて見えません。左利きの人なら問題なく使えます、、つまりこのハサミは左利き用ということになります。
ただね、これで紙に書いた線を正確に切ること私はありません。どちらかと言えばニッパーみたいに先端部を使ってパチパチと切断する感覚の使い方です。例えば、、結束バンドなどはこれでカットしてます。

上から Swiss Tool Sprit、WENGER バルダン、ミニチャンプDX。やはり Swiss Tool Sprit のハサミだけ合わせが逆ですね。

同じビクトリノックスでも Swiss Tool Sprit(左)は親指で動かす方の刃が下側に、となりのアウトライダーのハサミは親指で動かす方が上に取り付けられています。右利きの人がアウトライダーのハサミで紙に書かれた線を切るとき普段通りに左から切り口を確認しながら正確に切ることができます。
なぜ、同社の製品でありながら左右逆になったのでしょう?実は右も左もなかったりして、、。

アウトライダーのハサミ(左)とレザーマン・ジュースのハサミ(右)こちらは同じ合わせ方。


WENGER バルダンのハサミはギザ十(わかるかな〜)。ギザギザ刃です。ビクトリノックスとの違いでもあります。これ切る対象物を逃さずカットできます。布地、糸、滑りやすいものでも確実にカットできます。ただ、、ハサミの構造に問題あり(個体差)。2枚の刃の接合部(支点)に小さなネジが使われていますがこれがよく緩みます。これが緩むと、ハサミの命である《合わせ》が開いてガタつき全く用をなしません。このバルダンはハサミのネジが緩むたびに付属のピンセットで締め直さなければなりません。

いつも持ち歩くファストエイドキットに入れてある WENGER の小さなナイフ。ビクトリノックスで言うところの《クラシック》ですね。このハサミもやはり WENGER伝統のギザギザ刃。こちらは、、支点ネジの緩みは見られません。やはり個体差があるようです。ガーゼや包帯を切る時に使います。

各ハサミで結束バンドをカットしてみます。
ビクトリノックスのアウトライダーは使いやすいハサミですが結束バンドを切ろうとすると刃先あたりまでスリップしながらも最終的に切ることができました。レザーマンのジュースはスリップしないかわりにアウトライダーのものより切る際の力が必要でした。ハサミも多少のたわみを感じました。WENGERのバルダンは滑りやすい結束バンドも逃さず軽くカットできました。ただ、、このバルダンはハサミの支点ネジが切るたびに緩むのでストレスですね。ミニチャンプDXはサイズ的に一番苦労しました。これは予想できたことです。そして、左利き用のハサミ、Swiss Tool Spritのハサミですがギザギザ刃ではないのに結束バンドも逃さずパチンとカットできました。それと、Sprit のハサミでカットされた切れっ端は、、上に飛びます。他のハサミは全て切れっ端が下に飛びます。やはり逆なのです。

これはこのブログの中では何度も登場してきた FISKARS の剪定用のハサミです。ギアプルーナーという品名です。下刃には刃は付けられておらず、分厚いステンレス鋼の土台です。回転式のグリップを握りこむとSandvic ステンレス鋼の鋭利な刃が上から押し切りします。上の動刃はそれ単体でもナイフとして使えるほど非常に鋭利な刃付けがされています。

とある仕事でブラ製のカゴをギアプルーナーでパチパチと小さく切って捨てる。この剪定用のハサミは動刃(上の刃)がナイフのように鋭い仕上げなのと、静刃(下)に付けられたギアと連動した回転式のハンドルが軽い力で切ることを可能にしています。これを貸してあげると『よう切れる〜』と言われますが、それは上の刃の鋭さだけではなく、回転式のギアハンドルのおかげなのです。

仕事で使った後のギアプルーナーを自宅で分解して水洗い、上の動刃はセラミックシャープナーで軽くタッチアップしておく。これ単体でも下手なナイフより相当切れる。動刃は片刃のため裏面は軽く撫でるだけ。この面を角度をつけた研ぎ方をすると途端にハサミとしての切れ味がガタ落ちします。
やはりハサミは便利です。ナイフとはちがう領域に踏み込める道具ですね。

仕事先のお宅にて柿の収穫を頼まれ。

仕事先のお宅にてプラ板をカット。
他にも入院患者のパジャマの袖ゴムがキツいから切って下さいとお願いされてチョキン。台風で吹き飛ばされ破れた庭先のオーニングの帆布をチョキチョキ、ストラップカッターでザォ〜と切り裂く。使われとりまっせ〜。