2025年04月18日
日々の道具 ビクトリノックス Swiss Tool Sprit 13年目

VICTORINOX Swiss Tool Sprit

あたしが仕事でもキャンプやドライブでも必ず持っていく道具のひとつにビクトリノックスのマルチプライヤー Swiss Tool Sprit があります。過去に何度も紹介してきました。最近ではワンハンドオープン(片手で操作)できる様にナイフブレードに変更が加えられています。あたしのは発売間もない頃の初期モデルです。

このツールの使いやすさは軽く湾曲したハンドルにあると思います。とにかく握って痛くない。

ハンドルの湾曲が絶妙なので畳んだ状態でも幅をとらずスリムなまま。



ハンドルに収納された各ツールはそれぞれに起こした状態でロックが掛かる。ロック解除はハンドル後端の小さなバーをスライドさせて行う。起こすも畳むも軽すぎず重すぎず動きは非常に滑らかだ。

あたしの持っているモデルはナイフブレードがシープフットタイプのもので切先に当たる部分がない。つまり突き刺すことが出来ないデザインである。ブレードは先端がセレイション(波刃)で後端がストレート(直刃)になっている。このブレードは日本流の右利きの片刃で手前からの押し切りに向いたデザインだ。木材を削ると非常に深く食い込み素晴らしい切れ味を示す。もちろん、セレイションの部分でも木を削ることが可能です。扱う上での注意は一つだけ、研ぎ直す際にはブレードの右面(後ろから見て)だけを研ぐこと。左面は研いではいけません。せっかくの片刃が鈍になってしまいます。右面を研いだら左面は軽く擦って目に見えないバリを返してやる程度にします。

プライヤーのジョーの部分は購入から13年使っても狂いがありません。先日は錆びた太い針金を数十本捻じ切ったりワイヤーカッターで切断したり、今日などは枯れて硬くなった柚の鉢植えの鋭い棘を先端部で折り、更に剪定鋏が無かったので枝をプライヤーで捻って折ってナイフブレードで切断、廃棄するという作業に使われました。
マルチプライヤーと言えば LEATHERMAN が代表格ですがあたしは13年前に LEATHERMAN からこのスイスツールに乗り換えました。以来、これはあたしの日々の道具になりました。使っても使わなくても必ず持って行きます。出先での自転車の修理にも何度も使われました。大きく重い専門の道具を持ち歩けないあたしの仕事にはこのコンパクトな道具が必須なのです。

数年前、個人売買のサイトで購入した LEATHERMAN ジュース は購入後ほどなくスプリングが破損、レザーマンJAPAN にて修理交換してもらいましたがそれもすぐに壊れ今はプライヤーのみがかろうじて使える状態です。



仕事では台風で壊れた庭のオーニングを解体したり、プラスチックの保存容器を切ってプラ板を作ったり、枯れた庭木の枝木を切ったりと、その何れもがその日その時に突然依頼されたものばかり。でも、使えるツールを駆使してやってきました。

6年ほど前にあたしのスイスツールを見たお客さんから「私にも買って下さい」と頼まれネット通販にて購入したスイスツールはナイフブレードが不細工にカットされた銃刀法対応のバージョンでした。

そのお客さんのスイスツールで分厚く硬いバスマットを切断し浴室に敷き詰めました。

掴む、抉る、摘む、回す、叩く、折る、捻る、切断する、素手では無理な作業を専門の道具無しでやってきました。今日も明日も明後日もこれぞ日々使う道具の代表です。
2025年04月05日
四月の雑記・時々追記

こんにちは、ponio です。ようやく暖かくなりつつあります。四月は街が華やかに見える、桜のせいかしら(気持ち悪い)。



義父義兄の十三回忌は長崎の離島で。先に潜入している奥さん(特殊部隊か)とは別ルートで今回はひとり筑肥線で西唐津へ。そこからぶらぶらと歩いてフェリーターミナルへ。出航までの時間待ちに水分と糖分を補給しておきましょ。

博多港からと違ってこちらはのんびりゆったり。乗船名簿の記入も無い。航行時間も短いから楽チンです。

カリマーのエピックスキー(45L)は90年代に勤め先のあった心斎橋で買った物。パネルローディングでパッキングがとにかく楽です。2〜3泊旅の定番ザックです。

今回の旅時計は スウォッチ アイロニーのクロノです。




離島のスーパーには魅惑的な商品がズラリと並ぶ。一番下の『川添・木綿豆腐』は壱岐には無くてならないもの。持つとズシリと重く揚げても温めても美味しくいただける。




島の桜は満開。青い海と桜がなんとも言えない美しさ。

義兄姉の自宅の裏にある小さな湧水溝にはカスミサンショウウオの卵塊がとぐろを巻いていた。その周りでオタマジャクシの様な幼生が泳ぎ回っている。

裏の斜面には先人が残した野積みの石垣がある。

シュウ酸鍋は義姉の料理のほとんどを生み出す魔法の鍋である。

ギンヤンマのヤゴが群れなして獲物を待っている。

義兄がすぐ下の海で釣り上げたアジやカサゴを捌くのに使う小さな包丁。

大根の干物が風に揺れる。

アシは「背切り」と呼ばれる裁き方で小骨ごと斜め切りにして食べるか(一晩冷蔵庫で置くと味わい深くなる)、定番のアジフライで。

釣れたてを捌いて一晩寝かせたアジを食う。

義姉が摘んだヨモギは「蓬団子」になる。

フキと筍の煮物もこれまた旨し

法事の時にしか食べられない特別なうどん。

今回の湯沸かしセット。SOTO SOD-310 と TOAKSチタンポット1100。この組み合わせで湯を沸かし庭先で髭を剃る、これ離島での日課也。

コーヒーのドリップに使ったシェラカップ600mlとケトルレスリッド。この組み合わせは問題なく使えました。このリッドは耐熱シリコン製ですがこの素材は色や臭いが着きやすいためコーヒーや紅茶、お茶などを通しているうちに色移り臭い移りが起きます。私は基本的にお湯を通すことにだけ使っています。

「隠居」と呼ばれる家屋の裏に咲いていたヤマブキの美しすぎる黄色。ここには水神様が祀られている。


離島で使ったキレモノ。BENCHMADE 319。


「クロサギ」と思われるこの二匹はさしたる警戒心もなく浅い水面近くを泳いで(漂って)いた。タモを伸ばして簡単に掬い獲れたところを見るとかなり弱っていた個体だったと考えられる。

うじゃうじゃと群がる魚影。手の届きそうな深さをいくつもの魚影が塊になって泳いでいたが、眼に見える魚は釣れないと義兄が言った様に毎日釣り上げたアジで食卓に華を添えてくれる義兄とそれにくっ付いて行った中3が二人がかりでもこの朝はボウズでありました。

今回は一泊旅で朝日を浴びながら庭先で髭を剃る離島の朝のルーティンも一度だけ。TOAKS のチタンポットは満水が 1100ml なので髭剃りに使う蒸しタオル作を使ってもまだお釣りがくる。いつも旅先での髭剃りに使う透明な樹脂製カップは MSR のウインドバーナーに付属のもの。ストーブは SOTO SOD-310 で小さなOD缶やカップと一緒にチタンポットに収納できる。左のシェラカップ600mlとケトルレスリッドは新入りで今回が初めての旅でした。

予定ではチタンポットで沸かしたお湯を予めシェラカップに取り付けておいたリッドの開口部から注ぎ入れて湯温を鎮めコーヒーをドリップするはずでしたが、いざやってみるとここからの湯入れは溢す可能性が大だったのでやめました。結局、いつもの通りリッドを取り付けた状態でストーブに乗せ加熱。

SOTO SOD-310 はコンパクトで風にも強く、、と言いたいところですが、ここ長崎の離島は風が強く屋外ではウインドマスターストーブも燃焼炎が風に大きく流されてドロップダウン寸前までいきました。ストーブを建物の影に移動して冷たくなったOD缶を手で温めようやく沸騰。何度も書きますが、「風に強い、云々」は風に煽られながらも変わらぬ性能を保証する宣伝文句ではありません。あくまでも立ち消えしないで燃焼し続けるというもので、必要以上の燃料消費を防ぐためにも風除け対策はするべきなのです。
2025年4月9日
今朝のwebニュースで福岡市西区を流れる室見川で事件との報道を見た。先日は別の事件事故の報道があったばかり。今回はアタシが仕事の合間に時々昼メシを食う河川敷から3キロ余り下流で対岸にあたる場所。アタシも昼メシ時には人気の無い場所を選ぶがなんとも物騒な世の中になったものだと感じる今日この頃です。以前、やはり昼メシスポットだった場所も殺人事件が起きてから行かなくなった。大きな意味では平和な日本だけど日々の生活は油断できない現状です。
『シェラカップの憂鬱』
わたしはシェラカップをあまり使わない。ソロのバックパッカーだった頃からシェラカップは何故か使わなかった。ハンドルが折り畳めないとか容量が足りないとか、たぶんそんな理由で。でも持ってはいました。使った記憶は殆ど無いが当時一眼レフで写した古い写真にはたしかに二つのシェラカップが写っている。

当時使っていた二つのシェラカップ。手前250mlの「ロッキーカップ」、その奥400mlの「カスケードカップ」ともに使った記憶なし。

バックパッキングをやっていた頃は飯といえば荷物の軽量化から殆どがフリーズドライの山飯でアルミ製のクッカー(コッヘル)でお湯を沸かしそこへ山飯をぶち込むスタイル。たまに旅先の食堂でまともな飯を食べたりしたけど多くは「お湯さえあれば」作れるフリーズドライ食品だった。
シェラカップはそんな私には容量不足だったろうしハンドルが邪魔でコッヘルに収まらないとか、合う蓋がないとか、そんな理由で旅の道具に加えられなかったのだと今は思う。カスケードカップやロッキーカップは今も持っている。しかし、、、

カスケードカップは蚊取り線香の灰受けになっているし、

ロッキーカップに至ってはワイヤーハンドルを無理矢理切断されてただの湯呑みに成り果てています。しかも使われていない。

マッコリカップ大小
取っ手つきの大きな方は大阪系ホームセンターで、小さなカップは千日前道具屋筋にて。アルミ製アルマイト仕様。

買って使っても記憶に残らないシェラカップたちとは対照的に100均のシェラモドキやマッコリカップは自宅のキッチンで主にミキシングボウルとして溶き卵やタレ作りなどに使われています。底面積が小さく左右に注ぎ口が設けられていてシェラカップというより完全に調理器具だね。

SUZUKIの景品シェラカップも自宅キッチンでミキシングボウルや刻んだ食材入れとして使われている。こちらは普遍のシェラ型。

こちらは加熱できない樹脂製シェラカップ。ユニフレームの「カラシェラ300」です。加熱できないのでこれは100%「食器」としてキャンプなどで使われています。金属製のシェラカップを『器』としても使わないのには多分口当たりもあるのだと思います。冬場が主戦場となるわが家のキャンプシーンでは冷めやすく口当たりが強い(熱くても冷たくても)シェラカップはどうしても敬遠されがちになる。

こちらはシェラカップではないが私的には同類のスノーピーク トレック1400 のフライパン兼リッド(容量500ml)。容量500mlで軽量(104.5g実測)、神経質なドリップ は無理だがこの広口にして溢さずカップにお湯を注げるのはお見事。うちではスティックコーヒーなど一杯分の湯沸かしに使われること多し。コレとにかく沸騰が早い!

今回「必要に迫られ」買った(言わせて!)キャンピングムーンのシェラカップ600mlと360mlはどちらも頑強そうな造りで少なくともぺコンペコンな薄造りではない。重さも実測で600ml が159.5g、ケトルレスリッドを付けると205g、360ml の方が128.5g だった。今はもうミニマム、ミニマル、軽量化を目指すことが無くなった私ですがそんな私でもキャンピングムーンのシェラはどちらも重く感じる。

シェラカップは使わないんじゃなかったっけ?
これからは心入れ替えて少しずつ使うように心がけたいと思いまするぅ〜。(ホンマかいな)

今年度初蛾

大阪に住む妹から『お兄様ご生誕のお祝い』にと届いた品々。懐かしやー!昭和世代のある地域にしかわからない懐かしさよ。わかる〜?わかんねーだろうなぁ、、。食品添加物世代にはこたえられない旨さよのぉ妹よ!



大阪に住む妹から届いたる誕生日プレゼントの第二弾はこれまた懐かしい!『コアップ・ガラナ』。北の大地ではごく普通に売られていた。記憶に残るのはドクターペッパー並みの癖のある味と回収再利用され擦れて印地がかすれた茶色の瓶。クレイジーケンバンドの横山 剣兄いもご愛飲とか。これをキンキンに冷やして王冠(現在はスクリューキャップ)をシュポッと開けクピクピ飲んでブハァーゲボッとやるのが正しい作法也。

昨日届いた “ブツ” を食す。
うーん、、とってもチープな味わい。昭和の味、どこか未完成な味と風味ざんす。ソースはあと混ぜではなく麺に練り込まれている。お決まりの沸騰したお湯に麺を漬けて片面ずつ煮込み水気がなくなったら出来上がり、、なのだがこれがなかなかのパサパサ感。高校の下宿時代に一緒だった貧乏大学生が言っていた「即席麺には何も加えるべからず」の掟を破り思わず胡麻油を回しかけてしまった。おまけにカットネギと胡椒も、、。それでも尚お口に広がるチープな味と香りに懐かしの昭和を感じた。

2025/04/15
ダブルラーメンを一個だけ作って食った。何十年かぶりに食った。これもチープな味を期待して(?)いたが普通に美味かった。実をいうと当時の味はまったく覚えていない。世はまさにインスタント時代だった。「今日のお昼は即席ラーメンよ〜♪ 」なんて時代さ。マルちゃんのダブルラーメン、一個でも今の袋麺より量が多い(食ってみてそう感じた)。これを一度に二つ作ってひとりで食うと最後は “バリ柔” 麺になっちまう。それもまた当時食ってたラーメンらしくていいんじゃない? 〆はガラナをラッパ飲みしてブハァーゲポっとやればアイムソーハッピー!

今日は自転車に乗る手に手袋が必要だった。mont-bell の暖かいインナーの上に Tシャツ、その上にウインドブレイカーを羽織って強風をしのいだ。夜、お風呂に入ろうとしたが入浴剤が切れていることに気づいた。「ヨモギを煮出す?」と奥さんが言った。昨年のGWに糸島の山で摘んで乾燥させ保存していたヨモギの葉を煮出す。使うは SOTO ST-310 と MSR のストアウェイポットの1.1L。ヨモギの様に濃い色が出る煮出しにはステンレス製のクックウエアが最適なのだ。この煮汁を濾して沸かしたお風呂に投入する。カラダはぽっかぽか。


うーむ、惜しいね〜とは SOTOさんのミニマル角型クッカー ST-3108 ではなく、それに付属するポットハンドル(リフター)の方です。この角型クッカーはご存知の通りアルミ製でハードアノダイズドなど表面を保護する加工は施されておりません。それは別に構わないのですが、ハンドルレスであるこのクッカーを持ち上げるために付属しているポットハンドル(ステンレス製)を使用すると、、上の写真の様にクッカーの縁がギザギザになってくるのです。

これは無垢のアルミの柔らかさに対してそれよりも硬いステンレス製のポットハンドルの噛み込み部分の加工が荒いためです。そこでこのポットハンドルを分解してクッカーの縁に噛み込む部分をヤスリと研磨パットで均してやります。これで新たな傷がつくことが無くなりました。もともとクッカーなんて使ってナンボの物、多少の傷や凹みなど屁でもないのですがこのクッカーに関しては洗う際に指先が引っ掛かるようになりました。キャンプより自宅で使われる方が多いので怪我をしないための改良です。


今日は暑かったー!とは昨日に比べての話です。ただ陽射しは初夏のそれでしたね。さて本日は気温が上がった午後から個人宅の広いバルコニーでの仕事(作業)がありました。亡くなられたご主人が作ったアサガオのグリーンカーテンを解体する作業です。碁盤の目に組まれた大小様々な園芸用の支柱とそれをつなぐ錆びた針金、更にグリーンカーテン用のネット他をマルチプライヤー(Swiss Tool Sprit)とスリップジョイントのナイフを使って解体し支柱は金属用のノコで切れ目を入れて80センチほどの長さにへし折り不燃物として搬出しました。各支柱をつないだ針金はすでに錆びて腐食が進んでおりプライヤーのワイヤーカッターを使うまでもなく挟んで抉って切断しました。グリーンカーテン用のネットも廃棄するとのことでこれも遠慮なくナイフにて切り離しました。カットした錆びた針金はあとで家人が怪我をしない様に空き缶に詰め込みました。

2025/04/16 マンションの六階バルコニーでの仕事の最中に突如上空を通過した三機の自衛隊ヘリの一機。AH-64D と見られるこのヘリに先行する二機(UH-1 か UH-2 かわからない)が福岡市西区の海上をぐるぐるぐるぐる旋回飛行しておりました。もちろん訓練なのでしょうが時間にして 30分以上はバルコニーから見える海上や陸地上空を旋回しておりました。


大阪の妹から東洋水産のダブルラーメン、SBのホンコン焼きそば、コアップガラナが送られてきたのは先週のこと。そしてトドメが奥さんからのプレゼントであたしが日夜欲しい欲しいと訴えてきた『鯨の大和煮缶詰』が届きました。しかも今年は2缶多い38缶!!さっそく食糧ストッカーに隠しました。

日曜日、地域の清掃活動を終えて帰りシャワー浴びて遅い朝飯を食った。さささっと道具をまとめて海に向かった。どんよりとした曇り空、時折り霧雨が通り過ぎる中で砂浜にシートを広げお湯を沸かし甘いスティックコーヒーを飲む。砂浜では座る前にお尻の部分だけ少し凹ませておく。逆にストーブなどを置く場合は平面を作り出すことが大切だ。

グラウンドシートの四隅に打ち込む枝ペグはこの方が削ってくれました。


仕事の合間に口にする行動食を買いに行った帰り道、ふと海の方を見ると不思議な低い雲が海岸線に迫っていた。それは雲のようでもあり霧のように見えた。この薄気味悪い白い靄の正体は「海霧」だったと夕方のニュースでわかった。昨日も訪れた浜に自転車を走らせると途中の松林の中を白い靄が流れ抜けているのを見た。松林を抜け浜に出ると今まさに白い靄が海から浜へと這い上がる瞬間だった。急いでその中に突入すると、、ヒンヤリとした体感と湿り気に包まれた。暫くそこに留まっていたがやがて松の葉先から冷たい雫がポタポタと落ち始め体を濡らし出したので靄の外に撤収。実に不思議な体験だった。


能古島も玄界島も今津の海岸線もまったく見えない。この「海霧」はこの後内陸に入り込み高台の住宅地はすっぽりとこの冷たい霧に包まれた。この海霧の中を突っ切った翌日、自転車は全体的に真っ白な黄砂状の塵に覆われていました。やっぱり、って感じ。

花々が美しく咲き乱れる季節となりました。

おっと忘れていました、今年もムッシーたちの季節となりました。

「材料高いんだから」と言いながらも今年も『ケークサレ』が焼き上がりました。旨し。

やはりシェラカップは外より内で活躍する。カップ一杯分、二杯分の湯を沸かす、つけ添えの野菜を茹でる、コーヒーを煮出す、マカロニを茹でる、など家でやるちょっとした茹でものに使われる日々。これはもう立派な家用調理器具です。


今月のムッシーたち

廃屋に咲く藤の花も山なりです。季節が移りゆきます。
2025年03月24日
菜の花とトランギアとクピルカと。

毎年この時期になると「今年はどこ行く?」と同じやり取りのわが家。どこ、とはお花見のことだが今年は桜にはまだ早いので菜の花にする。

いつもの里山に行く。ここは最初に菜の花、そして桃と桜が咲き乱れる人気のスポットだがそれもある年の春に地元のテレビで取り上げられたからで、それ以前は渓谷歩きにきた人たちや混んでも駐車場が満車になることなど殆ど無かった。あの年のテレビ以降ここは桜の開花時期には人と車で混み合う残念な場所になっている。

ひと通り菜の花を愛でてからいつもの草地にシートを広げランチにする。クレイジークリークのシートチェアはパッと開くだけ。フルオープンすればマットの代わりに、左右のストラップを絞れば絶妙なバランスで座れる座椅子になる。


途中の地産物産市場で買ってきた苺とバナナ、缶詰のパイナップルでホイップクリームたっぷりのフルーツサンドを奥さんが作る。


アタシはお湯を沸かしてブロッコリーを茹で、ハムと自宅で作ってきたゆで卵、そしてケールでたっぷりのサラダを作る。



ブロッコリーを茹でたあとはアルコールバーナーを弱火にする。これは調理の間に沸騰してしまわない様にするため。コーヒーはドリップパック。豆ゴリドリップは家だけで十分。気が向いたらまたやるかもだけどアタシのむらっ気あるドリップより今はこちらの方がよほど手軽で安定してる。ケトルはトランギアの600ml、これでクピルカ21 のカップ2杯分には十分。


苺は有名な品種ではないが実に美味かった。ホイップも甘ったるくなくてムチョムチョ食えました、食べ終えたら奥さんは得意の「昼寝」に入る。木漏れ日を浴びて気持ちよさそうに眠ってる奥さんの横でアタシは余ったお湯で食器やカトラリーを濯いで拭き取る。

片付けが終わったら BAHCO396と EKA のナイフを持ってあちこちに落ちている枝木を物色して歩く。スプーンカービングに使う太めのグリーンウッドや焚き火用の吊り下げハンガーを作るための二股の枝を収穫しました。

帰りはいつもの無人販売所で野菜を買って帰りました。
2025年03月11日
続・クッカー烈伝

『続・クッカー烈伝』
「私的にクッカー列伝」(2018年01月25日)から7年、待望の(待ってへんって?)『続』編です。
超暇な方のみ見ないふりして見ていってつかぁーさい。
先ずはこの方から、、

マルタマ「ケットル」1.5L
完全自宅用湯沸かしケトル
18-8ステンレスの鏡面仕上げ
使い心地抜群の美しい日本製ケトル。品名の「ケットル」ですが何故“ケットル”としたのかは製造販売元の株式会社 玉虎堂製作所さんでもわからないとのこと。購入から数年、毎日使っているが変色なども一切無し。沸騰すると蓋がカタカタいって教えてくれる。日々使う物はこうありありたい。

こちらも日本が誇る『しゅう酸』鍋。自宅では煮物、汁物、その他様々な調理に使われている。キャンプに持ち出すこともあり。昔から変わらぬ安定安心の使い心地。

ユニフレームの小さなダッチオーブン。普通に洗えて手入れも楽チン。Trangia のストームクッカー27にも使えるのでデイキャンプやドライブランチにも持ち出される。自宅では卓上での天ぷらやフライ、長時間のコトコト煮込みに使われている。蓋の重さが旨さのポイント。

LODGE の小さな鋳鉄製サーバー。
朝のソーセージ&エッグ他、キャンプでも二つ並べて同時調理が可能。市販のアルミ板から作った即席のリッド(蓋)のおかげて蒸し焼きもできる。手入れも楽。

大阪の雑貨屋さんで買ったフランス軍のアルミソースパン。パスタを茹でたりカレーやシチューを作るのにも使いやすい。オールアルミ製なのでハンドルまで熱くなるのは承知の助。

キャプテンスタッグの三層フライパン。ハンドルは取り外しできる。ステンレスの熱伝導の偏りをラミネートされた軟鉄が補っている。パスタから揚げ物まで使えるが食材を動かさずに焼く様な調理には向かない。料理の仕上がりがどうこうではなく食材を置いていない部分の油が頑固な焦げつきとなる。食材をかき混ぜながらフライパン全体を使って炒める調理や揚げ物などに向いている。

上の三層フライパンの頑固な焦げつきをコーティングとして利用するのがこのFIRE BOX H.A.A フライパンだ。ハードアノダイズド加工されたアルミの素地にアマニ油やオリーブオイルを塗ってオーブンで焼き付ける作業を何度も繰り返し初めて使える状態になる。この頑固なコーティングは何度でもやり直せる。空焚きも大丈夫。アルミ製なので火の通りが早くダッチオーブンの様な使い方も可能。ただし、蓄熱性はアルミのそれで良いとは言えない。

アウトドアで使うことを前提に作られた小さな鉄製中華鍋。自宅では揚げ物や焼き飯、オムレツなどに使われキャンプでは鍋物にも使われる。専用の蓋があるので蒸し物にも使える。ハンドルは取り外しがきき、鍋、ハンドル、蓋を収納できる専用の袋が付いている。ストームクッカー25でも使用可能。

直火、電子レンジ、オーブン加熱が出来、そのまま冷蔵庫で保存もできる。鍋物、麺類、蒸し物、煮物、オーブン料理までこなす。汚れたら細かな研磨パットで簡単に落とせるのも魅力。いつかキャンプでも使いたい万能調理器。それなりの重さがあり底面がツルツルなので滑らない五徳が必須。いろいろ試してみたが一番安定していたのが MSR のドラゴンフライだった。

ストームクッカー27 DUOSSAL 用に買い替えた同サイズのノンスティックフライパン。DUOSSAL (ステンレスとアルミの積層)フライパンは火加減が難しく油を多めに使わないとこびり着くのでこちらに替えた。調理がやりやすくなったのは言うまでもないが、そのかわりにノンスティックのコーティングを傷めないように長時間の強火や空焚き、金属製のカトラリーを使わないなど気をつけるポイントもある。

お馴染み Trangia のケトルで容量は1400ml。わが家は『冬キャンプ』がメインなのでお湯はいくらあっても余ることはなく、ケトルはこの程度の容量が理想的。中にたくさん物を詰め込めるのでそこも便利なところ。

ストームクッカー27用のケトルで最小。コーヒーなどはマグ2杯分。容量が少ないためすぐにお湯が沸く。

トランギアが復刻させたステンレスとアルミの積層クッカー。アタシのは 1.0Lのアウターとインナーソースパンです。 Duossal はトランギアの造語で外側に0.5mm厚のアルミニウム、内側に0.3mm厚のステンレスを積層した0.8mm厚のソースパンとフライパンを指します。外のアルミが熱を素早く均等に伝え内側のステンレス層は腐食や変色、大きな傷からクッカーを保護してくれます。UL(ウルトラライト)や HA(ハードアノダイズド)と比べると重量は増えたが DUOSSAL のソースパンやフライパンにはリムが無いため洗った後も水残りがない。更に注ぎがめちゃくちゃ上手なのです。ただし、フライパンは炒め物や焼き物をする際に火加減(弱火から中火)と油の量がこびり着かせないコツ也。

品番は 307260で GOURMET FLYPAN と申しまする〜。単品販売の物で米国Amazonからの取り寄せだったと記憶しております。キャンプに持ち出すことは殆ど無く主に自宅でチョットした調理に使われることが多いフライパンです。フライパンの割に深さがあって袋入りラーメンも四つ割りにすれば重ねず一度に二袋まで茹でられます。ブロッコリーを茹でたりリゾットを作ったりするにもこれを良く使います。ソーセージや卵を焼くならスキレットの方がフンワリカリカリに仕上がります。また、お湯を沸かして注ぐ技にも長けています。わが家に現存する二つのコーティングフライパンの一つであります。

しばらく行方不明だったトレック1400のフライパン(蓋)。販売店を通じて取り寄せたがその後偶然に前の物が発見される。コーヒーなど一杯分はこれが一番早くお湯を沸かせる。ミニトランギアの丸型クッカーと重ねることも出来る。

わが家ではあまりやらない「すき焼き」用に買った物だが買ってからはキャンプに持ち出し夜は鍋物、朝はスキレットのかわりに焼き物に活躍している。焚き火の煤が着くとなかなか落ちにくいので基本は七輪かガスを熱源としている。

SOTO ST-3108 分厚いアルミ製の角いクッカーで作りはシンプルそのもの。もともと分厚い造りなので鍋の蓋には強度をもたせるためのリムも無い。蓋は乗せるだけで適度な重さがあり炊飯時には程よく圧が掛かる。トングにもなるステンレス製のハンドルが付属する。分厚いがそこはアルミ製なので傷は入りやすい。角型だけあり注ぎもお上手。

mont-bell のスクエアクッカー900ml。角いクッカーの使い良さはバックパッキングに明け暮れていた頃から実感していた。注ぎのしやすさ、パッキングのしやすさなどアタシ的には丸より角となる。

TOAKS のチタンポットシリーズ。容量1100mlだがギリギリ 1Lまで入れても溢さずに注ぎ切れる。チタン製は軽いことが1番の売りだが使用後は本体が冷めるのが早いので撤収も時間がかからない。ただ、チタン製故の薄造りなため剛性は期待できず特に開口部は変形に注意。1100mlという満水容量はソロには十分、デュオには丁度良し。

おっと忘れていました Quechua のステンレスケトル 1.0L。キャンプで焚き火に焼かれ自宅でガスに焼かれかなり使われましたが気づくと内部にポツポツと点状のサビや腐食が見られるようになりました。新品の頃は注ぎがめちゃくちゃストレスでまるでポンピングブレーキにつんのめる感じでした。原因は蓋に空気穴が無いためでアタシ頑張ってゴリゴリ穴を開けました。これで注ぎは一気に解決。ただ、最近お湯を注ぐ際に何処からか漏れ伝うことがありもっか鋭意探索中。

おっと、おっと、こちらも忘れてたアタシの寵愛用ステンレスケトル GSI グレイシャーステンレスケトル。これの最大の売りは何といってもどデカい開口部。この開口部のデカさこそがこのケトルを超使いやすくしている。水を注ぐ際には兎に角わかりやすくその気になれば茹でものも出来る。現行モデルはハンドルデザインが変わってしまい更にはコピー品が出始めてますね。このケトルは空焚きして底が変形した今でも自宅やキャンプで使われ続けているウルトラサブケトルです。
ponio
番外編

あたしの Trangia ストームクッカー27は DUOSSAL 2.0 、二つのソースパンとフライパンはそれぞれ外側がアルミで内側がステンレスの積層です。他のバージョンに比べると重量は少し重いけれど水道水による変色も無いし気をつかうコーティングも無いので使った後はガシガシ擦って洗える。ただね、火加減と食材によってはこびり着くのが玉に瑕。ソースパンは湯沸かしや煮物、汁物などに使うことが多くこびり着きは殆ど気になりません。ただしフライパンはね、、炒め物、焼き物が多いので「こびり着き」がよく起きます。こびり着いてもガシガシ擦り洗いすれば良いのですがね。そこである時、アタシはこの DUOSSAL のフライパンを同社の別売のノンスティックフライパンに替えたのです。

ストラップ通しが付いたフライパン サイズS TR-662818 が品番です。

Trangia お馴染みのノンスティック・サーフェイス(サーフェス)。使用する際にはコーティング面に傷をつけない、熱によるコーティング劣化に気をつけることが長持ちさせるコツです。金属製のカトラリーなどは極力使わずシリコン製の物にする、収納時には角のある物を重ねない、ガス、アルコール共に強火では使わない、空炊きしないなどアタシなりに気を遣ってきました。

しかし、いつの頃からかこの買い替えたノンスティックフライパンが「こびり着き」出したんです。よく見ると剥離は無いのですが明らかに健全なコーティング面とは違う劣化があちらこちらに見られます。何度やっても油を多く使ってもその部分だけ見事にこびり着きます。2025年の春の時点でまだ2年しか使っていないのですが、、特別何かやらかした覚えはないのに、、うーむ、当たり外れ? Trangia の製品は30年以上使ってきたけど「当たり外れ」はこれまで一度も無かった。とにかく油を引いても卵がこびり着くようになったので使用をやめることにしました。

10数年前に買って今も現役のストームクッカー25やミニトランギア、グルメフライパンのノンスティックは今も健全なサーフェイスを維持しています。

左が「こびり着き」100%のノンスティックフライパン S、右が DUOSSAL フライパン。DUOSSAL の方は油を塗った上で意識的にオーブンで空焼きをしてコゲ茶色の新油性コーティング(まだ一回目)を施したもの

FIRE BOX H.A.Aフライパン(上)と同じですがあの美しい茶色になるまではまだまだ長い道のりです。それでも今の時点では「こびり着き」ノンスティックよりこびり着かずに使えるので再登板させるつもりです。あとは均一な茶色になるまで気長に油焼きを繰り返すつもりです。

似たもの同士な三つの深型クッカー(ポット)は手前からスノーピーク・トレック1400、MSR ・アルパインティーケトル、TOAKS・チタン1100ポット。この三つは自宅でもデイハイクでもよく持ち出される満水容量850〜1400mlの深型クッカーです。今回は「ハンドル」を考える、です。

こちらスノーピークのトレック 1400、本体はアルミ製でハンドルはステンレス製。形は下が膨らんだ逆蝶々型。意識して握ると親指以外の四本の指がハンドル内に収まるが無意識に握ると親指がハンドルの上、順に三本がハンドルの中、小指がハンドルを下から支える格好になります。アタシ個人はこのハンドルがチョイと使いにくい。容量がある分、いっぱいに入れると本体が前傾する感じになるからです。もう少し大きくても良かったとは、あくまでアタシ個人の意見です。

こちら MSR のチタン製ポット。長年(30年近く)使ってきた今やクッカーの中では長老クラスの愛用品。こちらのハンドルは容量の割にかなり大きく形状はスノーピークと同じ逆蝶々型。このハンドル、ずっと前から「なんとなく使いにくい」と感じていた。それはハンドル下部の膨らみが大き過ぎること、そのため本体から離れた場所を握るため容量の割に重く感じられることです。ちなみに現行品はハンドルの形状が変更されており、耐熱のチューブまで付いております。

こちら TOAKS のチタン製ポット。MSR の物より容量は大きいのにハンドルは小さめ。上下の膨らみは同じで下部に小指を置くチョイルが設けられている。この三つの中では一番しっくり握れる。そのかわり熱源に近く位置するため熱くなりやすい。ただ、チタンは冷めやすいので屋外ではよほどの強火で加熱しない限りは気にならないと思います。

この三つの中で一番持ち出される回数が多い MSR のポットのハンドルを購入以来初めて上下をシックリ返す(江戸っ子か)ことにしました。逆蝶々型から正蝶々型へ。

畳んでももちろん普通。

実際に持ってみると、、やはりこちらが握りやすく感じます。早くやらんかい!とアタシ自身に言っときました。
2025年03月05日
弥生の雑記・時々追記

弥生三月は雨から始まり。
写真は2024年度版の新富士バーナーカタログ、新年度直前だというのに、、これについてはのちほど。

三月最初の日曜は予報通りの雨・雨・雨。毎年訪れる太宰府政庁跡から『歴史の道』を散策。今年はほぼ一日雨でした。雨やどりをしながら約7時間の散策を終え奥さんと合流したのが16時すぎ。春になったらまた来まひょ。

TOAKS TITAN POT 1100

軽い以外は取り立てて特筆することが無さそうな普通のクッカーです。TOAKS といえばアメリカのブランドですが製造は中国。今や雨後の筍か無限分身の如く出現し続ける China made TITAN の先駆け的な存在でした。現在市場に溢れる類似製品と比べると価格的にもワンランク高かったのですがここにきてほぼ同価格となってきました。やはりネームバリューだけでは売れないということでしょうね。

この三つ、すべて1100ml、1.1Lの満水容量です。
左から MSR(seagull)のストアウェイポット、真ん中が GSI ソロイスト、右 TOAKS です。この1.1Lという満水容量は現実的に沸騰時の吹きこぼれや溢さず注げる限界を考慮すると約2割減の 800〜900ml あたりが最大適量とわかります。MSR のストアウェイポットは調理上手で注ぎ下手、GSI のソロイストは三層のコーティングで抜群の水切れと注ぎ上手、

では TOAKSは? それは無垢の強さでしょう。コーティングが施されていないので金属製のカップやカトラリー、ストーブバーナーなどをそのままガチャ入れてきるし、水道水による変色や傷も気にならない。ただ、一点気をつけるべきはその薄さと剛性です。持ち運ぶ際には他の荷物で潰されない様に注意すべきです。チタンは丈夫だからはあくまで素材のお話で、この薄さとなると蓋が収まる開口部は簡単に変形します。中にスタッキングできるものを詰め込むのも策です。

TITAN POT 1100 に付属のリッドはあたしが9年前に買った同社のチタンリッドと同一のもの。9年前に買ったリッドは GSI ソロイスト用として無理矢理使われています。今回のチタンは水がシミにならず玉のようになります。EPIのチタンは水分が表面に広がるようにしみていました。

KUPILKA のカップ。ティーパックを淹れる時はこの様にハンドルの穴に紙タグを通しておきます。



3年前の今日(3/6)はあるお宅の橙を収穫していた様です。FISKARS のギアプルーナーで切り落とし収穫のあとは余った橙を Queen のナイフで半分に切って庭木の枝先に突き刺してメジロやヒヨドリの餌にしていました。今はもうこのお宅も庭も橙もありません。
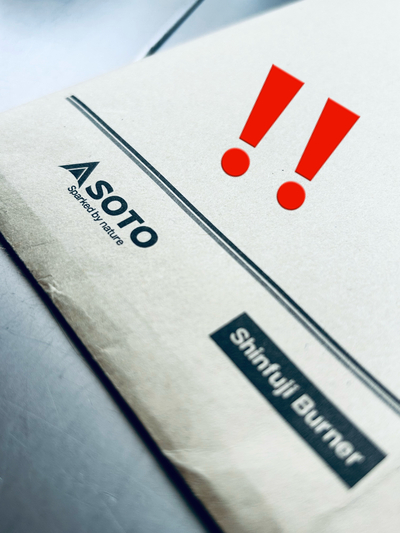
「これか?!」とはアタシの内なる叫び、、
先月二度にわたって見知らぬ市外局番からの着信がありその番号を調べてみると、、なんと新富士バーナーさんからではないか!アタシが日頃から家でも出先でもキャンプやドライブでも持ち出して使っている【SOTO 】さんからの着信。結局こちらから問い合わせてみたところ「間違いだと思います。」との返答。それがだ、またもや同じ番号から着信があり今度は「モスモス?」と出まして候。すると〜「当社のホームページから無料カタログの送付をご希望されておりますが宛先に訪ねあたりませんと戻ってまいりました」ちゅーことで、こりやぁーアタシが忘れていただけ?なーーぁんだ!そうだったのかー!こりゃまた失礼こきました!

来月、法事のため長崎の離島に行くにあたっていつもの毎度お馴染みの湯沸かしセットを考察中です。上の写真は Trangia のストームクッカー 27(DUOSSAL)からフライパンとソースパン(インナー)を抜いたセットアップです。目的は朝のひげ剃りと義姉に淹れるコーヒーのためです。離島は風が強い日が多く昨年正月と夏の訪問時は風を遮るのにひと苦労しました。今回は一泊なので MSR のウインドバーナーが最有力ですがあれこれと考えるのも好きなアタシです。現実的にはこれにアルコール燃料を加えると重量増しとなるのでたぶんウインドバーナーになるでしょう。ただね、ストームクッカーの安心感に勝るもの無しと実感もしております。

身近な道具たち
SOTO SOD-331 は南向きの窓に面して置かれたキャンプテーブルの脇にいつもある。気が向いた時に OD缶をつなぎ適当なクッカーやケトルを乗っけて湯沸かしをする。小さなケトルやクッカーの場合は常に OD缶と接続されている SOD-310 がサッとお湯を沸かしてくれる。

珈琲一杯ならこれで済む。SOTO SOD-310。

身近な道具たち。Trangia の『グルメフライパン』。わが家にたった二つだけ残るノンスティックフライパンのひとつ。もう一つはティファールのパンケーキ用。Trangia の方はアタシしか使わない。奥さんは「強火魔王」なのでコーティングがぶっ飛んでしまうから。一人分のパスタやリゾット、写真の様にパンを軽く炙り焼きする時などに登場する。

身近な道具たち。100均のメモ帳とボールペン、そして革製のシースに収められた CASE 社のナイフ(Sowbelly)。南向きに置かれたキャンプテーブルの右の隅にいつもあって仕事の電話もここで取るし、書き物や読み物もここでする。キレモノはズボンの右ポケットにクリップされているが目の前にあるこちらを使うことも多い。身近に置いておく物ほど愛着があって使いやすい。

母親の月命日にご飯を炊く。一合の米をたく。

アルコールバーナーははじめ強火でのち弱火

分厚いアルミの蓋が微かに持ちあがりパフゥ〜と蒸気を吐き出す。耳をすませ沸々と米が炊ける音に集中する。おおよその時間がきたらバーナーを強火に戻して10秒ほど炊く。

10分蒸らして出来上がり。仏様にあげたら残りはおむすびにしておく。

三月第二日曜はすっきりと晴れ渡り風が吹けばほんのちょっぴり肌寒いだけのお出かけ日和。寒さも緩んだせいか街にはどっと人が出ている。東西にのびる主要な幹線道路は軒並み長い車列ができている。

アタシはというと本日仕事の奥さんに頼まれ野菜の買い出しに自転車走らせる。買い物を済ませ仕事で時折訪れる近くの昼飯スポットに立ち寄る。と言っても飲食店でもカフェでもない。ここはアタシが外飯を食う場所の一つで河川敷。朽ちたベンチが置かれ景観は冬枯れの雑木と緩〜く流れる川面だけ。そのせいかあまり人とバッティングせずのんびりできる。先ずは湯沸かし、Trangia トライアングルに TOAKS のアルコールストーブ、小さなウインドスクリーン、そして500ml の水を入れた mont-bell のクッカー。

TOAKS のアルコールストーブは燃料を燃やし尽くさなければ消火できないのでアルコール燃料は多過ぎず少な過ぎずの目分量。今日の気温を考えれば 500ml の湯が沸くまで6〜7分、それだけ燃えてくれれば良い。時間を測ったわけではないが沸騰後10秒ほどで火が消えたのでそんなとこだろう。

朝握ったおむすびとカップで食べるチキンラーメンが今日の昼飯。

コーヒーはドリップパックで湯が沸いたら最初に淹れておく。保温タンブラーは作り置きができるので外飯には最適だ。飯の後でも熱々を啜れる。塩ミルクキャラメルはコーヒーのお供。これを一粒口に入れてコーヒーを飲むとなんとも言えない香ばしさ。


自宅に戻り買ってきた野菜から先ずはブロッコリーを茹でる。カリフラワーはレンジで3分チンしておく。

今夜はイワシのフライ、つけ添えにブロッコリーとカリフラワー、これに半熟ゆで卵を加えてサラダにする。

仏様のご飯を炊いた SOTO の角いクッカー。他のアルミクッカーと違い分厚く作られているので炊飯時の火加減はやや強め、時間もやや多めにとる。シンプルで何かと使えるクッカーです。

先月末の厳冬キャンプで一瞬だけ使われた G2 /5" Firebox Stove 。このウッドストーブはチタン製で軽く扱い易いが使用しているうちに熱による軽微な変形を起こす。もう一つあるステンレス製の方は奥さんのガンガン焚きにもびくともしない強さを誇っている。今日はこのチタン製の FIRE BOX STOVE を手曲げで矯正してやりました。

本日もいつもの河岸にて昼メシざんす。天気は上々、陽射しがジリジリと熱い。この時期にこの暑さは夏が思いやられる。

引退箱で暮らすこと10年余り、Esbit 585 ポットの再登城(家臣か)です。今の仕事を始めたばかりの頃に買って仕事先にてこれで湯を沸かしカップラーメン作ったりコーヒー淹れたり。蓋が外れて手に火傷をしたのもいまや昔の話。今日はカップ一杯分の湯を沸かすだけなので久しぶりにこれを持ち出しました。ポンコツな蓋は使わず TOAKS のチタンリッドを代用しています。

熱源はこの方、SOTO SOD-310 Wind Master stove です。ポットが小さいので付属のトライフレックスできました。風は微風でしたが吹くたびに燃焼炎が流される音がします。“風に強い” は立ち消えしないというだけでそのまま風防要らずではありません。たとえ Wind Master stove といえど風のある環境下では何らかの風防は必要だと思います。風に煽られて必要以上に燃料を消費するのは明らかですから。

お湯が沸くまで2分ほど、ポンコツ蓋の代わりに持ってきた TOAKS なチタンリッドを外してニョロニョロとドリップパックに注ぎます。

本日は自宅で作ってきた蒸しパンをシートゥーサミットのデルタボウルに密封してきました。食べ終えたらこれにゴミを入れて密封して帰ります。デルタボウルは蓋をちゃんと閉めると水の運搬も可能です。

Esbit のポットと共に引退箱に押し込まれていた A&F のチタンカップです。これも長いこと使われてきました。しかし何を飲んでも美味く感じない、甘いもの苦いもの、コーヒーもカフェオレもココアもただのフレーバーなお湯にしか感じられない不思議なカップです。今日もドリップパックのコーヒーがコーヒー風味のお湯に感じられました。

「カップで食べるチキンラーメン」を二つ食べる。二つと言ってもこの量だから満腹にはならない。ただね、スープが濃いので後味は満腹です。外で食べる時は殆どの場合、それは仕事の合間なので後の仕事を考え満腹を避けています。


今日も外メシ、いつもの河川敷、しかし寒かったー!
風もあって体感温度は10℃を下回っていました、これには流石に鼻水出ましたわ。ウインドスクリーンは 360度囲い、それでも 600ml の水が沸騰するまでかなりかかりました。

アタシのお気に入りパン(6個入り)も小さくなっちまって、、くぅー泣けてきます。

いつも持ち歩くシリアル。100均で買った何種類かをミックスしてある。これも大切な行動食。


雨の福岡、人の気配無き総合図書館で気になっていた本を読み終える。外は雨、雨、夕方からは「呑み会」ざんす。

アタシは新しい道具(焚き火台やテント・タープ以外)を手に入れたら先ずは自宅で使ってみる。それからキャンプやデイハイク、日常で実際に使って一応の結論を出す。自分の中で結論が出るとそれからは滅多に実験などしない。しかし、実際に使っても「うーむ、、いまひとつわからん」という物もある。その一つが SOTO SOD-331 フュージョントレックなのです。


SOTO SOD-331 は主に湯沸かしを担当しています。ちゃんと使ってるんです。自宅でも外でも。キャンプにも持ち出して。その都度ちゃんと働いてくれるんです。数年前の極寒キャンプで湯たんぽ用のお湯を沸かそうとして沸かしきれず(あまりの寒さに待ちきれず)同社の SOD-372 にバトンタッチしたことを除けば持ち出した先では「普通」に使えてるんです、コレ。

ただね、このストーブの売りである低温下や連続使用に効果を発揮するマイクロレギュレーター機能や風に強いすり鉢型バーナーヘッド、安定感のある分離型(最近はリモートというらしい)、冬季用ガスなども豊富なOD缶仕様、とこれだけ聞けば「完璧やん!」と言いたくなりますが、、実はアタシこのストーブの実力を実感したことがありません。
かと言って「え?ホンマは大したことない?」とはならない摩訶不思議なストーブなのです。購入から数年、実際に使っての感想は、春夏は当たり前に調子が良く、では秋冬は寒さに強いかと言えば「強い、かな?うーむ、普通」とそんな感じ。アタシにとってこの SOD-331 は『普通』なのです。同じ OD缶+マイクロレギュレーター機能を持った SOD-310(Wind Master stove)ほどのコンパクトさも無く、SOD-372 の様なギミックやガソリンモードの癖や力強さも無く、自宅で2L以上の湯沸かしを担当している ST-310 ほどの盤石性も感じられず、、果たしてこれ(SOD-331)ってどうなの?とモヤモヤしとりました。

今日は雨でとても寒い、福岡は北の風6メートル前後で気温8℃、ガスキャニスターストーブにとっては一番悪い条件ざんす。そこで滅多にやらない実験をSOTO SOD-331 にやらせてみました。風は建物の反対方向から回り込むような吹き方で2〜3メートルくらいか。アルミの風防を風上側に立てます。エバニューの2.8L満水クッカーに2.5Lの水を入れお湯を沸かして麦茶を煮出します。

ガスは純正のトリプルミックスではなく冬季用として長年使っているキャプテンスタッグのPX。今回実際に使ったのは昨年末からの年越しキャンプと2月末の厳冬キャンプの2回に持ち出してかなりのお湯を沸かした「使いかけ」です。

点火直後からバルブ全開。豪快な燃焼音をたてて最大火力を発揮。社外品のチタン風防は真っ赤っかです。クッカーの中の水も短時間で沸々し出しました。

結果からいうと点火から12分ほどで2.5Lが沸騰状態になりました。これは室温20℃の屋内で ST-310を使って沸かす時にかかる時間とほぼ同じです。ちなみに自宅キッチンのガスレンジでは火力をやや絞って10分です。低い気温、風防越しの横風という条件の悪さを加味しても室内での沸騰時間と変わりない、これってやはり凄いのか。これが ST-310 なら更に多くの時間を要したでしょう。

更に細かくみると、点火から3分半ほどで力強い燃焼音がやや落ち着き気味に。その後は時間をを追う毎に更に燃焼音は小さく、赤化したチタン風防の色もやや薄くなりました。点火から5分ほどでOD缶の表面が曇り始め8分が経つころには結露が霜って白くなり出します。そこから沸騰までが長くかかった印象です。10分を回る頃でもクッカーの中は比較的おとなしく直ぐには沸騰しそうにありませんでした。

点火から12分ほどで蓋の隙間から白い蒸気が出始めその後ちょっとで沸騰状態に。ただ、グツグツ煮立ってる感じはなく大人しく沸騰している感じでした。OD缶は白く冷たく結露ってこれ以上はちょっと無理な状態でした。
さて、麦茶沸かしという名目で行った今回の実験では気温8℃、風2〜3メートルで風防ありという条件で2.5Lの水を12分で沸騰させてくれました。

今回使ったOD缶が未使用の純正トリプルミックスの新品だったらもう少し最大火力が続いたかもしれません。逆に風防無しでは更に多くの時間がかかり沸かしきれなかった可能性もあります。風に強いは「立ち消え」しにくいだけで風をまともに浴びても常に同じ性能を発揮できるわけではないことを理解しなければなりません。
気温8℃ 横風3メートル前後、この条件下で使いかけのガスを使い点火から最大火力が3分半ほど続くなら一人分、たとえば500ml程度の湯沸かしは楽勝だと思います。

実際に同日のほぼ同じ条件でやった500mlの湯沸かし(クッカーはmont-bell スクエア900ml)では上の数値でした。燃焼音を聞いた感じでは点火から沸騰まで落ちることなくほぼ最大火力でした。

外に持ち出しては毎回一人分5〜600ml(多くても900ml程度)の湯沸かしを火力の低下無く済ませてしまう SOD-331 の当たり前さ、それこそアタシがこのストーブに感じる『普通』なのかもしれません。

友人とSNSでコーシー談義しつつ『煮出し』コッシーを淹れる。350ml ほどの湯を沸かし残り豆を挽いたミルを蒸気に晒す。わかる人はわかるよね。静電気防止ね。それから挽いた豆をぶち込み煮立てるが時折りケトルを持ち上げ沸々を落ち着かせる。最後に蓋をして一瞬強火に。あとは忘れるくらい放っておき気がついたらケトルをコンコン叩いて上澄をカップに注ぐ。結果は「うーん、、なんともビミョーな旨さ也」


春のお彼岸、中日に奥さんが「ぼたもち」を作る。
仏様に供え翌日にはそれすら食い尽くされた、わたしに。

サァーと雨が降った後の晴天下、久しぶりのドライブランチはわが家がよく行く菜の花と桜の名所。流石に殆どの桜はまだ咲いていなかったけど菜の花は満開、桜の開花前なので人もおらずほぼ貸し切り也。

ひと通り菜の花を愛でた後、いつもの草地にシートを広げランチを食う。コーヒーはドリップパック、豆ゴリドリップは家だけで十分だ。これに奥さん手作りのフルーツサンドとアタシ作のサラダを加えてモリモリ食う。

昨日買ってきた菜の花はお決まりの「菜の花パスタ」になりました。




今から20年近く前に中古で買った RICOH GR1/35mm。最後に使ったのは16年前の身内の結婚式。これが流石の写り具合で我ながらスンバラスィー出来でした。その後、フィルムと電池を抜かれた状態で壁に飾られ今は玄関の置き物になっています。果たしてまだ使えるか。液晶が生きていればまた写してみたいカメラです。

キャンピングムーンのシェラリッド・ケトルレスを GSI ソロイストに取り付ける。少し前に自宅使いのシェラカップに TOAKS のチタンリッド 110mmを乗せたら微妙に大きく使えなくはないがフィットせずだった。??これって、、アタシの GSI ソロイスト と同じやん!純正のリッドを失くしてからずっと微妙に大きな TOAKS のリッドを乗せていたソロイストとサイズ感同じ。ということは一般的なシェラカップとソロイストは同じ径か?とケトルレスリッドを取り付けたら見事にフィットいたしました。ただね、GSI ソロイストはこのリッドを取り付けなくてもニョロニョロ注ぎが出来るのであまり意味がないかも知れませんが、、ちょっと多めのコーヒーを淹れる時などは良いかも。それと、アタシの持っている TOAKS のチタンポット1100 にもピッタンコでありました。

一気に咲きました




ほんと思い出した様に巻いてみる時計。大阪時代に仕事で渡韓する友人に買ってきてもらった中古のオメガ・シーマスター。オートマチックで手巻きもOK。デイ・デイトとも呼ばれる曜日付きカレンダーモデル。70年代の代物と思われざっと考えても50年は経っているかも。現在は手巻きにて正確に駆動している。放ったらかしだったが思い出した様に引っ張り出して3Mのスーパーファイン研磨パッドで磨いておく。アタシは何につけてもコレクターではないし転売など考えもしないので使って磨いてを繰り返してきた。これを中古で買ったのが90年代だからそれからでも30年以上にはなる。防水性など無いに等しくいずれは動かなくなる機械式時計、その日まで使ってあげましょう。
三月も今日で終わりざんす。ここ福岡は花冷えなれど桜満開ざんす。
またのお越しを。
2025年03月02日
雨の太宰府 散策 テーマは「雨やどり」


雨の日曜、雨の太宰府都府楼、雨の政庁跡は人の気配がまったくない。坂本八幡宮も平成の頃みたいにすっかり静かになっている。あの『令和』改元の後の喧騒はなんだったのか。日本人はブームに煽られすぎやね。

久しぶりの『歴史の道』散策は雨の中。先ずは予定通り目当ての東屋で荷物を下ろし途中で買ってきた食糧を「行動食」「昼メシ」「おやつ」に分けて行動食はスイス軍のPVCバッグに、残りはザックに収納する。

「行動食」のビスケットは外袋から取り出し個別包装の状態でPVCバッグに。キットカットも外箱を畳んでビスケットと同様 PVCバッグに入れておく。

手前のスイス軍SM74ガスマスクバッグはPVC(ポリ塩化ビニル)素材で雨の日でも安心。開閉はホック式。ショルダーストラップはグレゴリーのものを使用している。今回はこれに「行動食」と小さなキレモノ、iPhone 用のAirPodsを入れて歩いた。

椿の花も雨に散り濡れ。

本日の防水ブーツは HI-TEC の V-LITE ALTITUDE MAX WPI 約7時間の雨天散策でもソックスは全く濡れず。


あたしの大好きな道、舗装されておらず地道である。春は桜咲く道となる。

戒壇院も、

観世音寺も人の気配なし。
*今回のテーマは「雨やどり」。
腰をおろしてのんびりできるかはどうでもよく、荷物を下ろして一休みできる、降りしきる雨を眺めて立ちんぼできる場所を渡り歩こうというのものだ。

観世音寺にある苔と礎石の上にザックを下ろす。傘をさしてザックを「雨やどり」させてやる。

こちらは政庁跡に面した東屋にて強い雨をやり過ごす。

戒壇院の境内にて「雨やどり」


『歴史の道』の雨やどりスポットNo. 1 は観世音寺の軒の下。雨の雫と波紋をボォーと眺めてすごす時間のなんと平和なことか。

昼下がりようやく雨があがる。水溜まりの中の青空が美しかった。

桜の道の向こうにも青空が顔をのぞかす。

昼メシは最初に荷物を下ろした東屋にて。先ずはレインパンツの裾をたくし上げブーツを脱ぐ。カットして座布団のかわりにしているウレタンマットを敷いて足を下ろす。日本人はやっぱり靴を脱ぐ時間が必要なんだ。リラックス度が断然ちがう。

昼メシの湯沸かしは MSR の WIND
BURNER 。

SIGG ボトルの600mlが短時間で爆沸騰。

昼メシはカップヌードル・ミニと途中で買ったカレーコロッケ、ドーナツ一個と、

歩きのあとはスティックカフェオレ。カップはスウェーデン軍用の Kăsa Cup。

カップヌードルの容器は半分に切って重ねて袋に入れます。


今年は梅の花もまだチラホラ、昨日今日の暖かさで蕾が膨らむかな?
ponio
2025年02月27日
道具立てと結果
今回の二月キャンプに向けた道具立てとその結果を厳しく評価します。この結果を先に見越していたなら荷物をかなり減らせたかもしれません。


Quechua のテントは導入から8年を経て今なお暖かな寝床を提供してくれています。風雨に耐え雪にもめげずに結露もほぼ無し。わが家にとっては唯一無二の寝床也。今回のキャンプでもサイドのファスナーをちょっと開け電源を引っ張り込んでホットカーペットと小さな温風ヒーターを稼働させフカフカのシュラフと毛布を加えて巣作りしてくれた奥さんにも感謝。


DD4×4とスノーピークの『ポンタ』はアタシたちを予想以上に強い風雪から守ってくれました。

コールマンのフカフカ布団シュラフは二分割して使いました。フカフカすぎて車に積み込む際には大きな圧縮袋が必須ですが安心の寝心地にはかえられません。


Quechua Arpenaz 0 は既にカタログ落ちした製品ですが使い道は実に広く単なるハーフシェルターにとどまりません。わが家の場合は地面に直に置きたくない又は放射冷却による霜降に晒されたくない荷物を置く「倉庫」として使われます。今回も強い風雪から荷物を守ってくれました。

今回テントの前室に置いて使うために持っていったクレイジークリークのシートチェアは到着直後の昼メシの時に奥さんが使った後、夜間に前室の隙間から強い風雪が入るのを防いでくれました。

Trangia ストームクッカーは過去のほんの一時期焚き火に押されて使われなかったこともありましたが、その後返り咲き今やキャンプ道具のトップをひた走る存在です。今回もガスバーナー仕様で湯沸かしから調理までここぞのシーンで使われました。

TR-23 五徳は購入から使い続けて30年になる最も古いトランギアのアクセサリーです。今回は鋳鉄製の重い『すき鍋』を乗せてタープシェルター内の「すき焼き」を演出してくれました。

前回焚き火で調理したためその後の手入れに苦労した(煤を落とすのに何度も洗った)経験から今回はガスバーナーを使うと決めていました。夜は「すき焼き」、朝は炭火で卵とソーセージの調理に使われました。ストームクッカーの底に重ねられるのも魅力です。


強い風と雪の中で焚き火が出来ない状況でも火の粉を飛ばさず強い火力で次々とお湯を沸かした強者。ケリー爺さんの面目躍如!

キャンプの朝は炭火のバタートーストと卵、ソーセージと決まっているわが家の必需品。今回はアルコールバーナーで熾した炭を使ってお得意の近火調理に、湯沸かしに活躍しました。


前々回の残り炭(オガ炭)は焚き火ではなくアルコールバーナーで熾されました。火力が強く息も長い。調理用熱源として最高だとあたしは感じています。

今回はトランギアのケトルはガスと石油ストーブ、炭火によってのみ使われました。湯たんぽのお湯を沸かす冬場はわが家のメインケトルになりました。

Quechua のステンレスケトルは内部に軽い腐食が見られますが今回は焚き火用ケトルとして持って行きました。強風のため焚き火ケトルとしての出番は一度だけでしたが幕中ではストーブトップ、ストームクッカー、B-6君と三つの熱源を渡り歩いてお湯を沸かしてくれました。

最大火力をもって湯たんぽ用のお湯を沸かすのが使命だった G2 /5" Firebox Stove 。今回のキャンプでは強風雪のため稼働は一瞬のみ。そのかわりに翌朝の炭熾しの際にはこれにアルコールバーナーを仕込んで下から炭に着火、燃料が尽きるまで燃やし続けてオガ炭全てをカンカンに熾してくれました。

撤収日の朝に 5" Firebox Stove とのコンビでオガ炭を熾してくれました。燃料ほぼ満タンで燃料切れまで燃焼させました。

前回かなりの量のお湯を沸かしてくれたキャプテンスタッグのPXガスですが今回は流石にスタミナ切れぽかったので最後は PRIMUS のTガスにバトンタッチ。新品ガスのチカラを見せつけてくれました。

パナソニックのマルチライトはわが家のキャンプ照明の主役です。合計三個のマルチライトを各所に配置して使います。照度調整とライト、ランタンモードの切り替え、常夜灯としても使える便利な明かりです。今回は不覚にも電池を忘れ一個のみの使用でしたがテント内ランタンとして活躍してくれました。

ヘッドランプは必需品。いつも直ぐに目につく場所にぶら下げておきます。今回も勿論使いました。

フュアハンドランタン、今回は持って行こうかどうか迷いましたが(どうしたこっちゃ?)、幕中での灯りとしてひとりの時間を演出してくれました。風が強かったため点灯中にひっくり返る恐れがあったため外には置いておけませんでした。


保温ボトルは冬場のキャンプの必需品。ケトルで沸かしたお湯を常にストックしておくためです。お湯はある程度冷めても洗い物や歯磨きなんかに使えますし、沸かし直せば直ぐに沸騰するので燃料の節約にもなります。

サーモスの保冷缶ホルダーは蓋をつけりゃ保温タンブラーに早変わり。幕中でこれに熱々のドリンクを作り置きしておけば気がついた時にいつでも温かい飲み物を口にできます。食事の前にこれにコーヒーなどを作り置きしてゆっくり飯を食い食後に口をつけてもまだ熱々です。

イワタニのウォーターバッグ(ジャグ)は水を入れた状態でぶら下げられます。冬場は凍ることもありますが今回はシャーベット状になっておりました。

MORA 860M は奥さんが調理用として使いました。「あれ?これ、いつものと違う?」といつもの MORA 2010 と違うことに気づいたようです。評価は「これ良く切れる〜!」でした。

この小さなネックナイフが今回のメインキレモノでした。が、焚き火のために薪を割ったり削ったりすることもなく、食材をカットしたり電池のパックを開けたりとそんな使われ方でした。帰宅後に見てみるとカッティングエッジにいくつか錆が浮いていました。ただ、ネックナイフの使いやすさは改めて実感できました。

仕事でもキャンプでも必ず携行する EDC ツール。今回は焚き火をしなかったのであまり出番がなかったが撤収の際にペグ抜きに使われました。

これ無くしてわが家の冬キャンプは成立しません!というくらい頼りに頼っている『湯たんぽ』。ひとつが満タン2.5Lなので二つで5Lのお湯を沸かさなければなりません。今回は KELLY KETTLE とストームクッカーが同時作業で次々とお湯を沸かして夕食前にはテント内のシュラフの中に放り込まれました。

NT BOX はサイズ13が4つとパーツボックスがひとつの組み合わせ。サイズ13には食器やカトラリー、クッカーや調理道具などをわかりやすく分けて収納してあります。パーツボックスには乾電池やライター、ファイアースターター、予備のキレモノ、自動巻きの腕時計、ヘッドランプ、小型のビノキュラーなどが入っています。準備も展開も楽チンです。

クピルカの食器たちは今やわが家のメイン器です。欠かせません。

今回の厳冬キャンプで最大の威力を発揮したのが古いトヨトミの石油ストーブです。灯油はフュアハンドランタン用に買ってあった10Lの残り。これで当日の夕方から夜寝るまで、翌朝から撤収の直前までタープシェルター内を暖かくしてくれました。洒落たデザインでも対流式でもないけれど反射式ならではの正直な暖かさを感じました。これ、わが家の冬キャンプの転換点となるかもしれませんね。

おっと忘れちゃいけねぇ!自宅の布団軍団。落ちつきますわ〜。

大阪時代に買ってから20数年着ているmont-bell のアウター。柄が示す様に冬用で3レイヤーです。表地はフリース、裏地は布滑りの良いナイロン素材、そしてその間に『GORE-WIND STOPPER』が入れられ風を効果的に防いでくれます。ポケットは左右がトンネル状に貫通しておりどちらの手でも中の物が取り出せます。今回はインナーを2枚(mont-bell とユニクロ)、中間着も mont-bell のクリマエアーフリース、そしてアウターをこれにしました。このアウターはプルオーバータイプでスルスルっと脱ぎ着が出来ます。ゆったりとしていますがドローコードで裾を絞れるため下からの風の侵入も防いでくれます。今回はかなりの寒さでしたが少なくともアタシは寒さを殆ど感じませんでした。

今回持って行った薪の中にはアタシの腕より太い伐採枝の丸太がありました。これを割って燃やすには小さくてもアックスが必要だと判断しましたが、、焚き火自体できませんでしたからまったく活躍の場ナッシングでした。

焚き付け作りにと完全引退状態だったところを持ち出された COLDSTEEL SRK 。こちらも同じく使い道ナッシングでした。

こちらの方が一番ガッカリされていることでしょう。キャプテンスタッグのヘキサ・ファイアグリル Mです。今回何年かぶりに焼き網とロストルを買い替え第一線に返り咲こう!と意気込んでおられましたが、、焚き火自体が出来ない状況ではドナイモコナイモアリマヘン。今頃気を落とされていることでしょうから慰めてあげまひょ。
今回は この焚き火台といいコールドスチールのSRKといい復活をかけた舞台でまさかの不使用とは、、。これもキャンプの醍醐味ですかね。


Quechua のテントは導入から8年を経て今なお暖かな寝床を提供してくれています。風雨に耐え雪にもめげずに結露もほぼ無し。わが家にとっては唯一無二の寝床也。今回のキャンプでもサイドのファスナーをちょっと開け電源を引っ張り込んでホットカーペットと小さな温風ヒーターを稼働させフカフカのシュラフと毛布を加えて巣作りしてくれた奥さんにも感謝。


DD4×4とスノーピークの『ポンタ』はアタシたちを予想以上に強い風雪から守ってくれました。

コールマンのフカフカ布団シュラフは二分割して使いました。フカフカすぎて車に積み込む際には大きな圧縮袋が必須ですが安心の寝心地にはかえられません。


Quechua Arpenaz 0 は既にカタログ落ちした製品ですが使い道は実に広く単なるハーフシェルターにとどまりません。わが家の場合は地面に直に置きたくない又は放射冷却による霜降に晒されたくない荷物を置く「倉庫」として使われます。今回も強い風雪から荷物を守ってくれました。

今回テントの前室に置いて使うために持っていったクレイジークリークのシートチェアは到着直後の昼メシの時に奥さんが使った後、夜間に前室の隙間から強い風雪が入るのを防いでくれました。

Trangia ストームクッカーは過去のほんの一時期焚き火に押されて使われなかったこともありましたが、その後返り咲き今やキャンプ道具のトップをひた走る存在です。今回もガスバーナー仕様で湯沸かしから調理までここぞのシーンで使われました。

TR-23 五徳は購入から使い続けて30年になる最も古いトランギアのアクセサリーです。今回は鋳鉄製の重い『すき鍋』を乗せてタープシェルター内の「すき焼き」を演出してくれました。

前回焚き火で調理したためその後の手入れに苦労した(煤を落とすのに何度も洗った)経験から今回はガスバーナーを使うと決めていました。夜は「すき焼き」、朝は炭火で卵とソーセージの調理に使われました。ストームクッカーの底に重ねられるのも魅力です。


強い風と雪の中で焚き火が出来ない状況でも火の粉を飛ばさず強い火力で次々とお湯を沸かした強者。ケリー爺さんの面目躍如!

キャンプの朝は炭火のバタートーストと卵、ソーセージと決まっているわが家の必需品。今回はアルコールバーナーで熾した炭を使ってお得意の近火調理に、湯沸かしに活躍しました。


前々回の残り炭(オガ炭)は焚き火ではなくアルコールバーナーで熾されました。火力が強く息も長い。調理用熱源として最高だとあたしは感じています。

今回はトランギアのケトルはガスと石油ストーブ、炭火によってのみ使われました。湯たんぽのお湯を沸かす冬場はわが家のメインケトルになりました。

Quechua のステンレスケトルは内部に軽い腐食が見られますが今回は焚き火用ケトルとして持って行きました。強風のため焚き火ケトルとしての出番は一度だけでしたが幕中ではストーブトップ、ストームクッカー、B-6君と三つの熱源を渡り歩いてお湯を沸かしてくれました。

最大火力をもって湯たんぽ用のお湯を沸かすのが使命だった G2 /5" Firebox Stove 。今回のキャンプでは強風雪のため稼働は一瞬のみ。そのかわりに翌朝の炭熾しの際にはこれにアルコールバーナーを仕込んで下から炭に着火、燃料が尽きるまで燃やし続けてオガ炭全てをカンカンに熾してくれました。

撤収日の朝に 5" Firebox Stove とのコンビでオガ炭を熾してくれました。燃料ほぼ満タンで燃料切れまで燃焼させました。

前回かなりの量のお湯を沸かしてくれたキャプテンスタッグのPXガスですが今回は流石にスタミナ切れぽかったので最後は PRIMUS のTガスにバトンタッチ。新品ガスのチカラを見せつけてくれました。

パナソニックのマルチライトはわが家のキャンプ照明の主役です。合計三個のマルチライトを各所に配置して使います。照度調整とライト、ランタンモードの切り替え、常夜灯としても使える便利な明かりです。今回は不覚にも電池を忘れ一個のみの使用でしたがテント内ランタンとして活躍してくれました。

ヘッドランプは必需品。いつも直ぐに目につく場所にぶら下げておきます。今回も勿論使いました。

フュアハンドランタン、今回は持って行こうかどうか迷いましたが(どうしたこっちゃ?)、幕中での灯りとしてひとりの時間を演出してくれました。風が強かったため点灯中にひっくり返る恐れがあったため外には置いておけませんでした。


保温ボトルは冬場のキャンプの必需品。ケトルで沸かしたお湯を常にストックしておくためです。お湯はある程度冷めても洗い物や歯磨きなんかに使えますし、沸かし直せば直ぐに沸騰するので燃料の節約にもなります。

サーモスの保冷缶ホルダーは蓋をつけりゃ保温タンブラーに早変わり。幕中でこれに熱々のドリンクを作り置きしておけば気がついた時にいつでも温かい飲み物を口にできます。食事の前にこれにコーヒーなどを作り置きしてゆっくり飯を食い食後に口をつけてもまだ熱々です。

イワタニのウォーターバッグ(ジャグ)は水を入れた状態でぶら下げられます。冬場は凍ることもありますが今回はシャーベット状になっておりました。

MORA 860M は奥さんが調理用として使いました。「あれ?これ、いつものと違う?」といつもの MORA 2010 と違うことに気づいたようです。評価は「これ良く切れる〜!」でした。

この小さなネックナイフが今回のメインキレモノでした。が、焚き火のために薪を割ったり削ったりすることもなく、食材をカットしたり電池のパックを開けたりとそんな使われ方でした。帰宅後に見てみるとカッティングエッジにいくつか錆が浮いていました。ただ、ネックナイフの使いやすさは改めて実感できました。

仕事でもキャンプでも必ず携行する EDC ツール。今回は焚き火をしなかったのであまり出番がなかったが撤収の際にペグ抜きに使われました。

これ無くしてわが家の冬キャンプは成立しません!というくらい頼りに頼っている『湯たんぽ』。ひとつが満タン2.5Lなので二つで5Lのお湯を沸かさなければなりません。今回は KELLY KETTLE とストームクッカーが同時作業で次々とお湯を沸かして夕食前にはテント内のシュラフの中に放り込まれました。

NT BOX はサイズ13が4つとパーツボックスがひとつの組み合わせ。サイズ13には食器やカトラリー、クッカーや調理道具などをわかりやすく分けて収納してあります。パーツボックスには乾電池やライター、ファイアースターター、予備のキレモノ、自動巻きの腕時計、ヘッドランプ、小型のビノキュラーなどが入っています。準備も展開も楽チンです。

クピルカの食器たちは今やわが家のメイン器です。欠かせません。

今回の厳冬キャンプで最大の威力を発揮したのが古いトヨトミの石油ストーブです。灯油はフュアハンドランタン用に買ってあった10Lの残り。これで当日の夕方から夜寝るまで、翌朝から撤収の直前までタープシェルター内を暖かくしてくれました。洒落たデザインでも対流式でもないけれど反射式ならではの正直な暖かさを感じました。これ、わが家の冬キャンプの転換点となるかもしれませんね。

おっと忘れちゃいけねぇ!自宅の布団軍団。落ちつきますわ〜。

大阪時代に買ってから20数年着ているmont-bell のアウター。柄が示す様に冬用で3レイヤーです。表地はフリース、裏地は布滑りの良いナイロン素材、そしてその間に『GORE-WIND STOPPER』が入れられ風を効果的に防いでくれます。ポケットは左右がトンネル状に貫通しておりどちらの手でも中の物が取り出せます。今回はインナーを2枚(mont-bell とユニクロ)、中間着も mont-bell のクリマエアーフリース、そしてアウターをこれにしました。このアウターはプルオーバータイプでスルスルっと脱ぎ着が出来ます。ゆったりとしていますがドローコードで裾を絞れるため下からの風の侵入も防いでくれます。今回はかなりの寒さでしたが少なくともアタシは寒さを殆ど感じませんでした。

今回持って行った薪の中にはアタシの腕より太い伐採枝の丸太がありました。これを割って燃やすには小さくてもアックスが必要だと判断しましたが、、焚き火自体できませんでしたからまったく活躍の場ナッシングでした。

焚き付け作りにと完全引退状態だったところを持ち出された COLDSTEEL SRK 。こちらも同じく使い道ナッシングでした。

こちらの方が一番ガッカリされていることでしょう。キャプテンスタッグのヘキサ・ファイアグリル Mです。今回何年かぶりに焼き網とロストルを買い替え第一線に返り咲こう!と意気込んでおられましたが、、焚き火自体が出来ない状況ではドナイモコナイモアリマヘン。今頃気を落とされていることでしょうから慰めてあげまひょ。
今回は この焚き火台といいコールドスチールのSRKといい復活をかけた舞台でまさかの不使用とは、、。これもキャンプの醍醐味ですかね。
2025年02月26日
厳冬キャンプ 2025年 2月





これらの写真が今回のキャンプを如実に物語っています。今年度最後(?)の「雪景色」。予報(北西)に反して反対方向(南東)からビュービューと吹きつける強い風と大粒の雪にこれはとても焚き火ができる状況ではないと早々に判断、冬キャンプを始めて11年、初めて焚き火を諦め、初めて石油ストーブに頼りました。

結局、こうなりまして候。今回は自宅で廃棄寸前だった古いトヨトミの石油ストーブをメンテナンスし直して持ち込んでいました。キャンプ場に着いたのが予定通りのお昼、そこから荷物運びとテント設営、奥さんはテントの中で自慢の巣作り、アタシは石油ストーブを活かすため DDの4×4タープを強風と吹雪の中で四苦八苦の七転び八起き(タープほんま苦手ー!)で張り終えたのが16時前のこと、、。ホンマに精魂尽きましたわ。石油ストーブに火を入れ椅子とテーブル、ゴミ入れだけを設置。嗚呼〜ストーブ暖かい!

あたしが風雪の中でタープシェルター設営に四苦八苦している間、暖かなテントの中で巣篭もりしていた奥さんを完成したタープの幕中にご案内。「こんな巣篭もりキャンプしたかったー♪」と奥さんも喜んでおりました。

その後、風雪は激しさを増し、、、

次から次と雪雲が通り過ぎてゆきます。タープの周りを御百度参りの如くぐるぐる回ってガイラインと打ち込んだペグの具合を何度も確認します。どうぞ飛ばされませんように、、と。


しかしのんびりとはしていられません!あたしには日暮れ前までに二つの湯たんぽを熱々のお湯で満タンにしておかなければならないと言う使命があるのです。予定では KELLY KETTLE (写真)と Quechua のステンレスケトルを同時に沸かすはずでしたがこの風では焚き火も危なくて無理と判断。とりあえず火の粉が飛びにくい KELLY KETTLE にほぼ満水の水を入れ点火。点火時は風下に向けていたベースの開口部を点火後に風上に向けると凄まじいトルネード燃焼。たまたま東屋脇に置かれていた真っ赤に錆びたBBQコンロを利用して KELLY KETTLE を稼働させました。風が強くても気温が低くても燃やせば湯が沸く KELLY KETTLE の実力発揮です。

その後、風が弱まったタイミングで予定通り 5" Firebox Stove と Quechua のケトルのコンビネーションで湯沸かしを始めました、が再び風が強まり危険な状態に、、

この両者、今回の環境条件では圧倒的に KELLY KETTLE が優位でした。FIRE BOX も薪をガンガン放り込んで最大火力を引き出せばお湯を早沸かしするくらい簡単ですが、、この日は風がやばすぎました。雪は降っていましたがあたりは一面の枯野です。下手すれば火災の危険もあります。FIRE BOX は一回目の沸騰後に使用中止し、Trangia のストームクッカー(ガス使用)にあとを任せました。

タープが風で膨らんだり凹んだりすることを考えてストーブを安全な位置に設置し直します。タープはAフレームで片側をほぼクローズ、反対側は換気のために半分だけ開放しました。日没とともに気温は急降下しましたがタープの幕中はポッカポカでありました。


午後7時前から予定通り『すき焼き』の開始です。Trangia ガスバーナーと TR-23 五徳、ストームクッカーのベースを逆さまに組み合わせずっしりと重い鉄製のすき鍋をのせ、いざ!すき焼き!

前回の正月キャンプの際に安い海外産牛肉を買い失敗だったとリベンジを誓う奥さんが国産牛肉で挑む!舵取りのあたしはガスバーナーの火力を調整しつつ食っては「旨い!」を連発。奥さんと温燗で乾杯しながら吹雪の夜を『すき焼き』で乗り切る。
たらふく食って二人でさささっと洗い物を済ませ歯磨きしたあと奥さんは巣に戻った。あたしは道具箱から二つのランタンを取り出し『おひとり様』時間がスタート。

まっこと小さな灯りではあるがテーブルの片隅に置いておくだけでなんとなく落ち着くUCO改装のオイルランタン。

もちろん忘れておりませんフュアハンドランタンの灯。今回は石油ストーブと燃料共用。


すき焼きシステムをそのまま使って石油ストーブにかけたばかりのケトルを再度沸騰させる。ダークラムをたっぷりと注いだ蜂蜜紅茶を啜り夜の吹雪を眺めて過ごす。

夜9時、タープ幕中の温度は15℃。風が一段と強さを増す中もう一度ガイラインの張り具合を点検して回る。このあと更に幕中の温度が下がり出したためここが潮時と石油ストーブを消してペールに入れたゴミ袋を閉じ上から荷物を乗せて小さな野生動物に備えます。最後にタープの出入り口を完全に閉じておきます。

Quechua のポップアップテントの後方は本来大きくオープンできて中のウォールの上半分はメッシュです。穏やかな気候の時はこれを開放することで明るく風通しの良い最高の寝床となるがこの日は予報とは真反対の風がテント後方から吹き付けていたためレインフライを兼ねた外側のキャノピーを閉じて更にペグダウンしても吹き込む風が冷たかった。

そこでいつも予備に持っていくスノーピークのポンタでテント後方を覆いペグダウン、余った裾部分をテントの底に入れておく。更にこれがずれない様にテント前方に長いガイラインを張ってタープのサイドポールに繋いでおいた。


テントの入り口は既に着雪している。わが家の Quechua ポップアップテントは大人ひとりがなんとか横になれる程度の前室があるが床面がブルーシートと同様の素材なので冬場は足や手がつくととても冷たい。そこで今回はこの前室にモコモコのフリースを敷いておいた。靴は前室の両サイドに、暖色の小さなランタンも置いてある。

冬キャンプの「あるある」は夜間のトイレ行脚です。自宅では夜間にトイレに行くことは殆どありませんが、冬キャンプではいつも以上に温かなものを飲んで過ごすため寝る前に行っても必ず一度は行きたくなるのです。あたしは意を決し起きると寝床で温めておいた厚手のウールソックスを履き裏地付きの暖パンとフリース、その上にダウンを羽織りヘッドランプと共に外に出ます。防寒用のライナーが付いた大きめのブーツを前室から持ってファスナーを開けると一面真っ白〜。

Quechua のハーフシェルターは倉庫がわりに使われます。夜間はここにランタンをひとつ置いて寝ます。

午前零時半過ぎ、外は風もおさまり雪も止んでいましたが足跡が残る程度の雪が積もっていました。

朝は6時に起床ス。テントの中で完全防寒して外へ出ると一面真っ白、、帰りやばいかな、、いや、帰れるかな、、と不安がよぎる。夜間の強風に耐えたフルクローズのタープシェルターに移動し最初に石油ストーブに火を入れる。

Quechua のステンレスケトルにウォーターバッグから水を注ぐと、、あら不思議。シャーベットマウンテンの出来上がり。

タープシェルターの出入り口を半分開けて Trangia ガスバーナーに火を点す。ガスは正月キャンプに使った残りのPXガス(キャプテンスタッグ)。缶の表面が半分凍りつきながらも何度もお湯を沸かしてくれました。

ストーブの火が安定したらまだしばらくは寝ている奥さんのブーツを温めておきます(なんて優しいオットセイ!)。沸騰した Quechuaのケトルもストーブの乗せて沸々やっておきます。ストーブの右の端(熱くならない)に置かれたサーモスの保冷缶ホルダーは冬の必需品。専用の蓋をすればそのまま保温タンブラーとして使えます。これに熱々のカフェオレを作り置きしておきます。

お次は1.4LのTrangia ケトルでお湯を沸かします。冬キャンプではお湯はいくらあっても良いので沸かしては保温ボトルにストックを繰り返します。前日に沸かしたお湯をボトルからケトルへ、こうすることで沸騰時間も短くなり燃料も節約できます。保温ボトルは常に満水にしておきストーブの周りに置いておきます。

夜に降り積もった雪はふわふわサラサラのパウダースノーなので風が吹けば多くは吹き飛ばされます。日が昇って少し経つとこの様に残った雪も溶けていきます。





しかしそれも束の間、次の雪雲が新たな雪を降らせます。そして短時間のうちにあたりは真っ白に。


雪が降りしきる中、テントの中でシュラフや毛布を畳んで圧縮するルーティン作業をしていた奥さんが外界に出て参ります。「きゃー!」が第一声。

キャンプの朝飯は家と変わらずパンと卵とコーヒーと決まっております。違うのはバターを染み込ませたパンを炭火で炙り焼きすること、卵やソーセージも炭火で調理することです。そのために炭は熾しておかなければなりません。

風があるので火は焚けませんがFIRE BOX ストーブにアルコール燃料満タンのトランギアバーナーを仕込んで点火、その上でオガ炭を熾します。アルコールバーナーの燃料が尽きる頃にはカンカンに熾た炭の出来上がり。

熾した炭はすかさず用意していた B-6君に移します。さあ、炭火の近火の威力発揮です。パンは油断すると黒焦げになるので付きっきりでこんがり焼きます。

ソーセージと卵はすき鍋で。

朝飯を食う頃にはタープシェルターの中はポッカポカの温室状態です。

それにしても強い風の中よく持ち堪えてくれました。
朝食後は始めボチボチやがてササささっと、最後はバタバタドタバタと正午の撤収に向けて動きまくります。そしていつもの光景といつもの台詞、、
「おかしいなぁ、、なんで帰りの方が荷物がいっぱいになるの?」
要は積み方なんです、わかっとるのです、はい。

帰宅後の奥さんの談
冬キャンプ11年目にして初の焚き火ナッシング、そして初の石油ストーブ使用。もっと早くにすれば、、と思ったでしょ? ずっと考えてはいたんですが、わが家のキャンプスタイルで石油ストーブを活かそうと思えば更にデカいテントに買い替えるか、アタシが苦手とするタープワークで温室を作らなければならず、今日まで青空キャンプだったわけです。
それにしてもアタシのタープ苦手意識なんとかならんものかね。ロープワークはボーイスカウトで習って以来全然苦にならないから良いのだけれど。
ponio でした。

あ、そうそう、、今回のキャンプで真っ黒黒スケになってゴシゴシの刑になったのは Quechua のケトルだけでした。
2025年02月16日
俺たちゃ時代遅れなのか

「俺たちゃ時代おくれなのか?」と道具箱で冷たく眠るキレモノたちに柔らかな冬の陽射しを浴びせてあげる。今日はそんな日。ついでに『ピカール』で磨いてあげる。

CASE P10051L パッカーとはバックパッキングを共に楽しんだ間柄。90年代の米国製らしい粗雑さとスタイリングの良さが入り混じっている。


手前から CASE P10051L 、真ん中が GERBER FS Ⅱ、一番奥が Kershaw 1056。どれも磨けば光るブラスのハンドルやボルスターで身を固めている。ブレードは FS-Ⅱ を除けばよくあるステンレス鋼。彼らが店頭に並んでいたのは現代のようなスーパースチールが一般的ではなかった時代だからね。


ズシリと重い質感は手にした瞬間なぜか安心するんよね。手に馴染むというのかね。そのかわりポケットなんかに入れると重くてゴロゴロして何とも落ち着かない。これらを身につけるにはシース(鞘)が一番なのだ。ロックはどれもオーソドックスなバックロック。

kershaw 1056 の美しさは何といってもこのハンドル部。ブラスのボルスターとベークライトのハンドル材が見事に波長を合わせてうねっている。手にすると「これしかねぇべ!」というくらいにフィットする。重く固く使い良さは微塵も感じないが手離せない一本になっている。

思わず「カッコいい〜!」と言ってしまうイケメン。古き良き時代の GERBER の面影を残した一本。これも90年代の米国らしく作りは粗雑でブレードにも左右にガタがある。切れ味は素晴らしい。

コンパクトでバランスのとれたスタイリングの CASE のパッカーは数ある CASE のフォールダーの中ではどちらかといえば地味〜なモデル。現在は廃盤。これもブレードに左右のガタあり。ホローグラインドのブレードは良く切れるが刃持ちは特別良くはない。
「俺たちゃ時代おくれなのか?」と彼らに問われたら「君らは君らでいい」と答えてあげよう(その前に病院いけ!)。
追記

GERBER の FS Ⅱ はいつもメシを食う南向きのキャンプテーブルに常駐することになりました(その後キッチンの棚に異動、そのブレードレングスを活かして食材のカットという意外な職に就きました)。CASE P10051L は同社の COPPER LOCK と一緒にコーヒー豆の封切りに従事することになりました。

プラスではなくニッケルボルスター組の面々は言う、「美しければ生き残れるわよ」と。チっ!

あたしゃフォルムだけで生き残る!
2025年02月01日
2025・2月の雑記 時々追記

今年も早二月。来週は今季一番の寒気襲来とか。
このところ休み無く日曜まで仕事が入って少々お疲れ気味なアタシです。


2台の FIRE BOX FREE STYLE ストーブを矯正する。購入以来キャンプやデイハイクで毎回のように持ち出され4〜3、4〜6、6〜8 とパネルの枚数を足したり引いたりしながら使ってきました。気がつくと2台のストーブのパネルが入れ替わっていたり、熱変形による歪みが出ていたり、ここらで少し手直ししてやろうかと全てのパネルを外してじっくりと観察。パネルの焼け具合などから各ストーブを構成していた4枚のパネルを特定し組み直しました。

この2台の FREE STYLE ストーブは購入時期が異なっており使用時間にも差があります。それぞれのストーブを構成する 4枚のにチタン製パネルの焼け具合や変形の度合いも違っています。実際のところ使用には全く問題ないレベルですが収納の際にパネルが少しずつ浮いて反発するようになっていました。使用時間が異なる 2台のストーブのパネル(計8枚)が分解掃除や組み替えの際に入れ替わってしまったのが原因でした。パネルを特定して組み直すとほほ平らに畳めるようになります。残る熱変形による歪みは 2台のストーブそれぞれに手で曲げ直します。

ほぼ平らに畳めるようになりました。

パネルの入れ替えと矯正が済んだ 2台のストーブ。パネルの変形などで脚も微妙に緩くなっていたのでほんの少し曲げてやりました。

二月最初の日は本降りの雨。今日は仕事で靴を脱ぐことがないためレースアップの Bean Boots を履いていきました。かなりの雨の中を自転車走らせましたが浸水は無し。専用のウールソックスがフカフカで履き心地は最高です。足元が守られている感じがなんとも言えない安心感があります。


昨日、仕事から帰った奥さんが車に積みっぱなしだったキャンプ道具をバタバタと降ろし出した。なんでも日曜に友人を何人か乗せて走らないといけないらしくバックスペースを空けておくためだとか。降り頻る雨の中をドタバタと降ろした道具の中にはダウンのシュラフやジャケットが含まれておりいずれも雨に濡れてしまった。自宅の暖房とサーキュレーターをフル稼働させ乾かすはめに。マーモットのダウンジャケットは大阪時代に買ったものだから20年以上、モンベルのダウンハガーは福岡に来てからだからそれでも20年近く経つ。マーモットのダウンジャケットは引っ掛けたり焚き火の火にトロけて補修跡だらけ。それでもいまだフカフカモコモコ。モンベルのダウンハガーもいまだ現役。長く使える道具というのはこういうものなんだね。

2月最初の日曜日はお仕事ざんす。ご主人の見舞いに通うお客様の付き添い。往復のタクシーの手配と移動介助、安全確保、観察と声掛け、タクシーに往復のコースを告げてあとは運転手さんの判断に任せる。車椅子や荷物の積み下ろしもアタシの仕事。病院ではアタシは入院病棟には入らず一階の超豪華なラウンジ、いやロビーにて3時間の待機。外来がなく見舞い客だけが時折り通る静かで暖かいロビーにて次のキャンプのことなど書き留めて過ごす。これも仕事也。

CAPTAIN STAG
ヘキサ ステンレス ファイアグリル M用
バーベキューアミ (No.UG-2021)購入。佐賀県の北山キャンプ場がまだ無料だった頃に一泊して見事に置き忘れ焼き網無しで4年ほど使っていました。今回、12年ぶりに復活しました。パチパチパチパチ〜。

CAPTAIN STAG
ヘキサ ステンレス ファイアグリル M用
目皿(No.UG-2028 )、こちらは買い替え。リニューアル。


約4年使ってもおボロボロです。使えないことはありませんがちょっと触れるだけでポロポロと表面が剥がれ落ちる状態なのでそのうち焼き切れるでしょうね。

底板はまだまだ使えるのでそのままです。

きゃー❤️ ピッカピカだぜ!おっかさん!

ウヒョー!さあ、復活してもらいまひょ!「わが家の焚き火台1号」
しかし、、これ薪を追加する度に網を外さないといけないんですよね。以前に使っていた時はスイスツールのプライヤーで持ち上げていました。これは焼き物など調理をする際にだけ使う物、そういうことで納得。

これはファイアグリルを使う上で欠かせなかったアイテムです。上の五徳はユニフレームのタフ五徳(旧品名)、下は大阪時代に買って Trangia バーナーの風防として使っていたメーカー不詳のファイアベースです。これと同じデザインの CAPTAIN STAG イージーファイアベースも持っていましたが呆気なくバラバラになって廃棄されました。このメーカー不詳のファイアベースは購入からかれこれ30年近く経ちますがまだまだ使えそうです。ユニのタフ五徳は置き忘れた焼き網の代わりに使われてきました。その名の通りダッチオーブンも乗せられるタフな五徳です。ファイアベースは開いて焚き火台の下に設置、吸気口から排出される灰を受けるのに使われてきました。

やられました、、これが夏ならゲリラ豪雨だったでしょうね。まさしく猛吹雪でした。この写真の雲の仕業です。福岡市早良区での仕事の帰りに凄まじい風と雪で目を開けていられず一旦自転車を止めます。ザックのサイドポケットからモンベルの折りたたみサングラスを取り出しそれをかけて向かい風の吹雪の中を突破。西区に入った途端にパタっと雪も風も止んで「なんじゃぁーこりゃああー!」となりましたわ。暫く走ってふと今さっき走ってきた方向を見るとデッカい雪雲の塊がありました。

ガチガチ震えながら自宅に戻りかじかんだ手でストーブをつけ生姜湯を作ります。この数日はこんな楽しいことばかり!(楽しーんかい!)

激しい雲の流れの隙間に真っ青な空が顔を出す。しかし、風が、、スゲーーー!体感は零度を遥かに下回る。くぅー、、しばれるねぇー。

わが家でほぼ毎日の様に使われている SOTO ST-310 とミニマルワークトップ(旧ST-3107)。いつも持ち上げ移動する際に脚が外れそうになる。一時期細引と輪ゴムと何かしらの金属片でストッパーを作って取り付けていたが一度持ち出した際に失くしてしまった。

現在はST-3107S なるストッパーが別売されており現行のミニマルワークトップ(ST-3401)には標準装備されている。


自称『ある物使い』の達人であるアタシは自宅にあった金属クリップを分解して新たなストッパーを作り取り付けました。シンプルながら効果覿面です。あとは二つの金具を適当な細引で緩〜く繋ぐだけ。

本日は霙のち大雪のち猛吹雪のち寒暴風でした。両眼涙溢れ鼻水滝の如し。寒かったー!

ここ福岡でも気温零度を下回る朝が年に何度かはある。今朝がそれ。ベランダのメダカ鉢は見事に凍りついておりました。雲は相変わらずの崩れかたで耐え切れなくなった部分から地上へ雨や霙、雪を降らせます。今朝はケトル三頭体制です。「大きな薬缶でええやん!」てな感じですがこれらにはそれぞれ役目があるのです。手前の マルタマ・ケットル 1.5 L はわが家のメインケトルで火から下ろした後も湯温を保ってくれるスグレモノ。美しくこの数年毎日使っても変色一つしない流石の日本職人芸。コーヒーのドリップはこれでやります。一つとんで三番目はキャンプでもかなり使われて今は自宅のサブケトルとして日々活躍している GSI グレイシャーステンレスケトルです。空焚きして底が何変形したけどまだまだ現役。現行品とはデザインが異なりますが何よりこの開口部のデカさは他のケトルには無い使い良さです。普段は最近「白湯」ブームの奥さん用に沸かしたての状態で蓋を開けて置いておいてあげます。またお湯のストックに使う Klean Kanteen の容量とピッタリなので重宝してます。最後に真ん中は新入りでいきなり焚き火の洗礼を受け真っ黒に焼かれて帰ってきた Trangia 1.4 L ケトルです。いつもはキャンプでしか使われませんが今朝はお湯がいつもより多く必要でしたので持ち出されました。この中で唯一のアルミケトルで容量の割に早く沸騰する便利なケトルです。

今年も長崎の離島に暮らす義理の姉から搾りたての「つばき油」が届きました。人が放して野生化したタイワンリスに食い荒らされながらも果敢に石つぶてで追い払いカテシと呼ばれる椿の種を守る義姉の姿が思い起こされます。熱したフライパンに垂らすとなんとも言えない甘い香りがします。



はるか異国の国おフランス ARCOFRAM の耐熱ガラス鍋はあたしが小さなリサイクルショップで見つけ千円も出さずに買ったものです。わが家のキッチンではしばらく姿を見せませんでしたが昨日鋭意捜索の末に発見。無事現場に復帰しました。復帰後初の仕事はゆで卵でした。

娘の誕生日に奥さんが焼いたキッシュ。パイ生地の縁がまるで阿蘇の外輪山の様です。昨日はその誕生会の食事を奥さんと二人で次から次と作り食わせて片付けるを『あうん』の連携技で乗り越えました。

今夜のおかずはクロムツの丸干しをじっくりと焼いたもの。これに三日目の豚汁に新鮮な小葱を足して汁物とし、細かく刻んだきんぴらごぼうと万能ネギを加えて焼いた卵焼きでした。




本日建国記念日は奥さんと八女市の福島町に行ってきました。これがまた皆さんしっかり休んではって観光客も殆どおりませんでした。うちはと言うと行きつけの食器屋さんでお酒を呑むための小さなグラスを買って昼飯も食わずに帰りました。


うちは耐熱ガラスのサーバーをよく壊します。というか、よく割れるのです。殆どが使用中ではなく洗い物の際に他の食器に当てて割ってしまいます。そして今回は奥さんが勤め先のフリマにてパイレックスのコーヒーサーバーを射止めてきました。どうぞ今回は割れませんように。

蕾菜の季節になりました。茹でて酢味噌でいただきます。


今朝米国のナイフディーラーからのメールを開いたら GERBER L.S.T のニューモデルが新発売されているのに気がついた。いつもならサササッと流し見して終わるメールだけど L.S.T とくれゃ見ないわけにはいかないアタシです。むむむ、、相変わらずの超低価格(日本円で¥3.800ほど)、鋼材は 440A となってワイヤータイプのポケットクリップが付いている。1980年代初頭の初代(ブラッキー・コリンズのデザイン)から何代目になるのかいな?日本で発売されるのは少し先になるだろうが価格は¥5.000台かな。果たしてこれにあ¥5.000出す価値はあるのか? やっぱり L.S.T は米国のスーパーあたりで棚の上に置かれた日用品的価格じゃないとね。長年 L.S.T を愛用してきたアタシには気になるニュースだが。

このモデルには Gerber LST Ultra という製品名がつけられている。上のワンハンドオープニングモデルとはブレードのデザインが違っている。鋼材は前作までの 420HC となっていて価格も少しだけ高い。

自宅で日々使うキレモノはいくつかあるけどそれらはある条件で自然淘汰されて生き残ったものばかりだ。その条件とは、軽いこと、扱いやすいこと、切れ味を簡単に回復できること。鋼材は440C だろうが420HCだろうが良く切れる状態であれば全く問題ない。少なくともアタシの日常では今流行りのスーパースチールである必要など全然ないのだ。上の写真は安価な鋼材を使った GERBER のキレモノだが研ぎやすくいつでも良く切れる状態にしておける。操作感は快適で軽快。切れ味は滑らかで癖が無い。製品自体は90年台後半の物だけど今なおバリバリの現役ッス。

新鮮なイワシが手に入ったので今夜はこれの煮付けにしましょう。リサイクルショップでタダ同然で手に入れた『無水鍋』にイワシを並べ酒、醤油、砂糖、梅干しでコトコト煮詰めます。無水鍋は蒸気を逃しつつシーリング効果で適度な圧力を掛けられる調理器です。うちのは分厚いアルミ製なので熱も均等に回ります。「おいしゅうなぁれ」


かれこれ10数年は使っているスウェーデン軍のカップ。ラーメン食ったり鍋を取り分けたり雑炊よそったり勿論コーヒーやお茶もね。いつもちゃんと洗ってはいたんだけどいわゆる茶渋みたいなものが着くんよね。今日は気が向いたのでちょこっと気合い入れて茶渋を落としてあげました。

こんな偶然って、、あるのか
本日、午前と午後にそれぞれ一度全く100%完全に心当たりのない電話番号からアタシのスマホに着信があった。たまたま電話をとることができなかったのだが相手は市外局番で愛知県豊橋市となっていた。「ふん、どーーーせ間違い電話やろね」と全く気にも留めずに仕事の準備をしていた。すると今度は午後になってまた同じ局番から着信があった。今度は一旦意識的に無視して電話が切れると同時にその番号をネットで検索すると、、、ぬわぁーーんと!
『新富士バーナー』と出た。新富士バーナー営業部出荷チーム。むむむ、、なんやなんや!豪華景品でも当たったか?そんなもん応募してしたことない。就職の面談の話か?そんなもん願書送った覚えもない。それともホワイトガソリンが充填されたOD缶でも発売になるのか?いやいやそれはアタシの妄想だった。むむむ、、、クレーム、注文、問い合わせ、それも出した記憶はない。アタシ自身は新富士バーナーさんのストーブを長年愛用してきてつい先日もこちらのブログでミニマルワークトップの脚抜け落ち防止策を書いたばかり。なんだか気になってきましたので意を決して(それほどのものか?!)着信にリダイヤルしてみると、、

「はい、新富士バーナーです」と若い女性の声。カクカクシカジカと着信があった件を伝えると直ぐに調べてくれまして結果「おそらく、、まちがいではなかろうかと、」とのこと。そこでアタシから「新富士バーナーさんってSOTO さんですよね?」と問い直すと電話の向こうからでもわかる笑顔で「はい!そうです!」と電話対応の方。アタシ自身、「新富士バーナーさんのストーブを何年も使っております!」「ありがとうございます!」などという明るいやりとりで電話を切ったのだが、なんとまあ〜こんな偶然あるのか?

6年前の今頃、仕事先のお宅での一枚。このお宅では毎年ちょうど今時期に庭の橙の収穫をする。収穫した橙はスロージューサーで搾って蜂蜜を加えさらに薄めてジュースにする。残りは写真のように半分に切って庭木に突き刺し鳥たちにあげる。このお宅も今は家主が亡くなり二軒の新築が建っている。

梅が咲き出しました、さあ二月も終盤です。

ハリャ〜〜!ぬわぁーんと!行方知れずだったスノーピーク TREK 1400 の蓋(フライパン)が出てまいりました。ここ何年か着ていない冬用のアウターを引っ張り出したところその下に隠れておりました。何年振りの再会でしょう!

一年前(2024年1月)に販売店を通じて取り寄せた二代目との刻印比較。さて、どちらが新しい方でしょう?答えは刻印が消えそうに薄い方ざんす。行方知れずだった蓋は今から10年ほど前に買った TREK 本体に付いていたやつです。古い方が刻印がハッキリ!クッキリ!とは。メーカーさんの盛衰を感じます。

「すんばれるねぇー」→「しばれるねぇー」→「めっっちゃ冷え込むわー」と三段活用が飛び出るほどに凍れたキャンプでした。山を甘くみてはいけない!

テントから顔を出した奥さんが思わず叫ぶほど雪が降りました。風も強く吹雪の中、冬キャンプ11年目にして初の焚き火ナッシングなキャンプでした。

二月の厳冬キャンプでは焚き火をすることもなかったためキレモノはパックを開けたり食材をスライスしたりとそんな使われ方。ESEE の IZULA Ⅱ はキャンプの間中ずっとネックナイフとして首からぶら下げたシースに収めて使いました。普段はこの IZULA の様な炭素鋼のキレモノでは食材を切ることは無いのですが今回はネギや他の食材を刻みました。帰宅後にチェックすると、、やはり錆が浮いていました。とはいっても切れ味が変わるわけで無し何の支障もありませんが気分の問題なので研ぎ直しました。

研ぐと言ってもいつもの1000番から2000番くらいの使い古しの耐水ペーパーでシャカシャカとストロッピングするだけです。

はい、5分ほどで元通り。

果てしなき宇宙に散らばる無数の星々、、ではありません。これ今回のキャンプで使った Trangia のアルミケトルの内部です。利用させて頂いたキャンプ場は水場が地下水です。この水を沸かすとアルミケトルはこうなります。もちろん、人畜無害ざんす。

でも、これも気分の問題なのでいつもの様にレモンのスライスをコトコト煮込んで綺麗にしました。そのあとはお決まりの米の研ぎ汁コーティングです。

昨年購入し年末年始と今回の二月キャンプを経たトランギアケトルは既に古びたアルミヤカンの雰囲気です。あたしは焚き火で焼かれ真っ黒になれば必ず磨き直して使います。そうやって長年やってきました。このトランギアケトルは今や古い登山用品店の片隅に凹んだりくすんだりして埃を被った古き良きアルミ製品の面影すら漂っています。


先日のキャンプで使った FIRE BOX ストーブを手入れする。いつもは帰宅後直ぐに勢いそのままで手入れをしますが今回は荷運びをひとりでやったのでアタシ自身がバッテリー切れでした。この FIRE BOX ストーブは強風のため火を焚いたのは一度だけ、翌朝にアルコールバーナーを組み込んでオガ炭を熾すのに使っただけです。炭を熾した際にファイアーグレートと呼ばれるオプションの中板(チタン製)が熱変形しました。ストーブ本体もチタン製ですがチタン製品と熱変形はつきものです。丈夫なので薄く造れる、軽くて丈夫がうたい文句のチタン製品ですがこの程度の変形は普通に起きます。使用に差し支え無いのでこれもまた味なのでしょう。


















